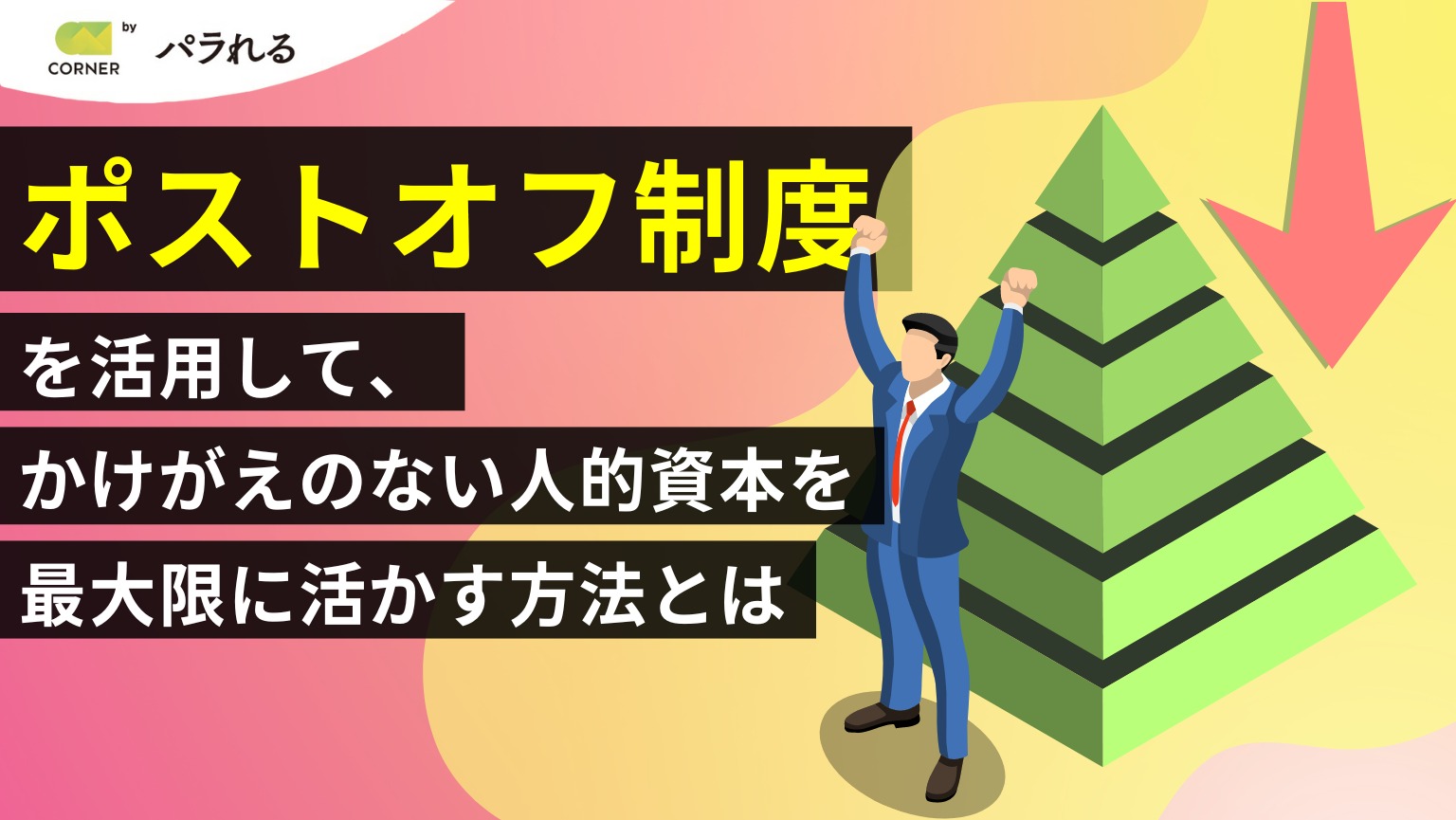
「ポストオフ」制度を活用して、かけがえのない人的資本を最大限に活かす方法とは
組織活性化と若手人材の起用戦略のひとつである「ポストオフ」制度。近年ではミドル・シニア人材活用の観点からもその有
2022.08.30

「セルフ・キャリアドック」で従業員のキャリア自律を促進し、組織成長につなげるには
従業員が主体的にキャリア形成できるよう企業がサポートする「セルフ・キャリアドック」。2016年の職業能力開発促進
2022.08.25
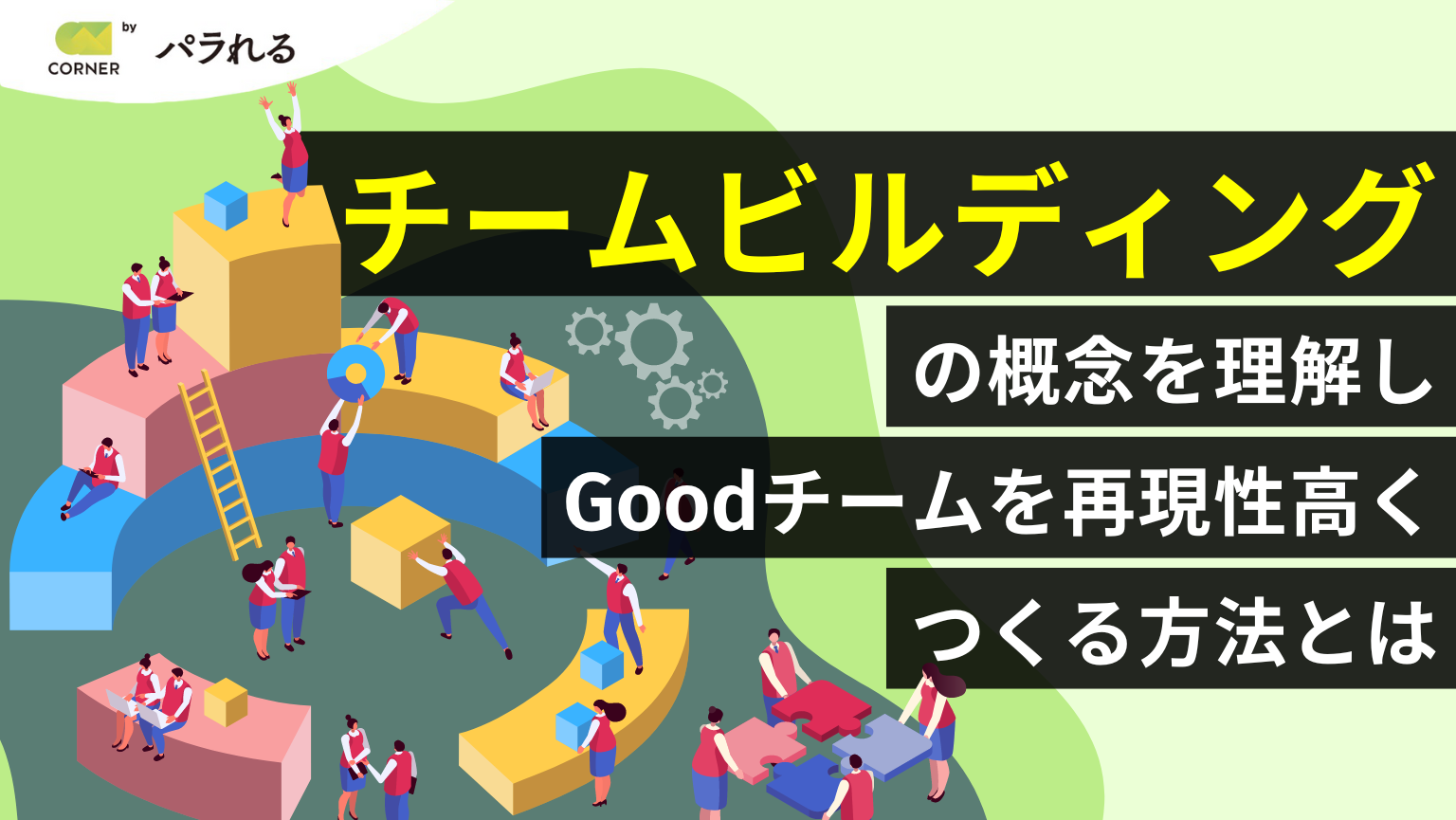
「チームビルディング」の概念を理解し、再現性高くGoodチームをつくる方法とは
時代の変化やグローバルな環境変化が要因となり、個々の多様な価値観や働き方の変化に対して組織としての順応力が求めら
2022.08.18



「イクボス」「イクボス宣言」単なる男性育児参加ではない組織成長戦略
コロナ禍でリモートワークが浸透し、家庭で過ごす時間が増加し、これまでの働き方を見直すビジネスパーソンが増える一方
2022.07.12
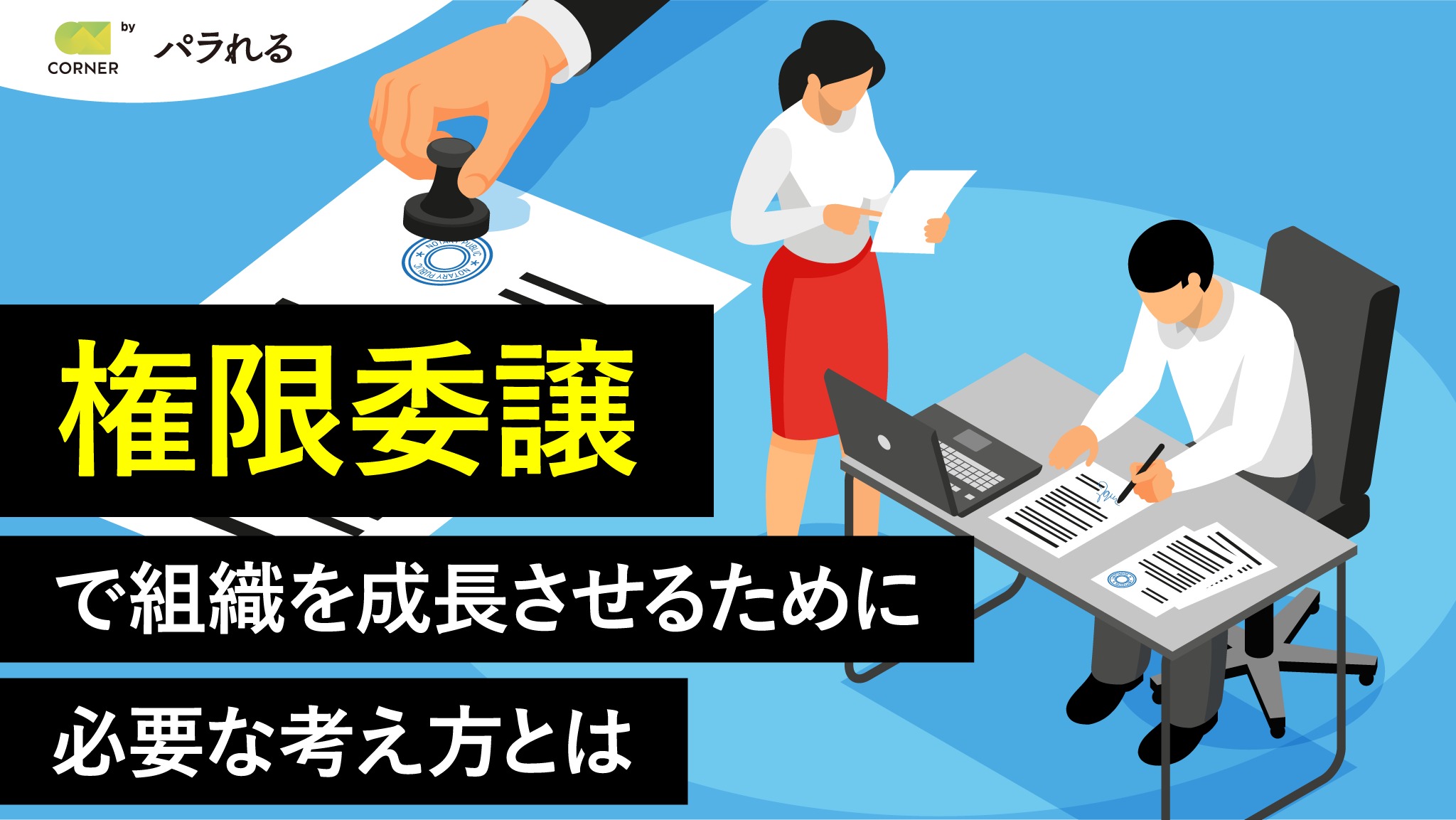

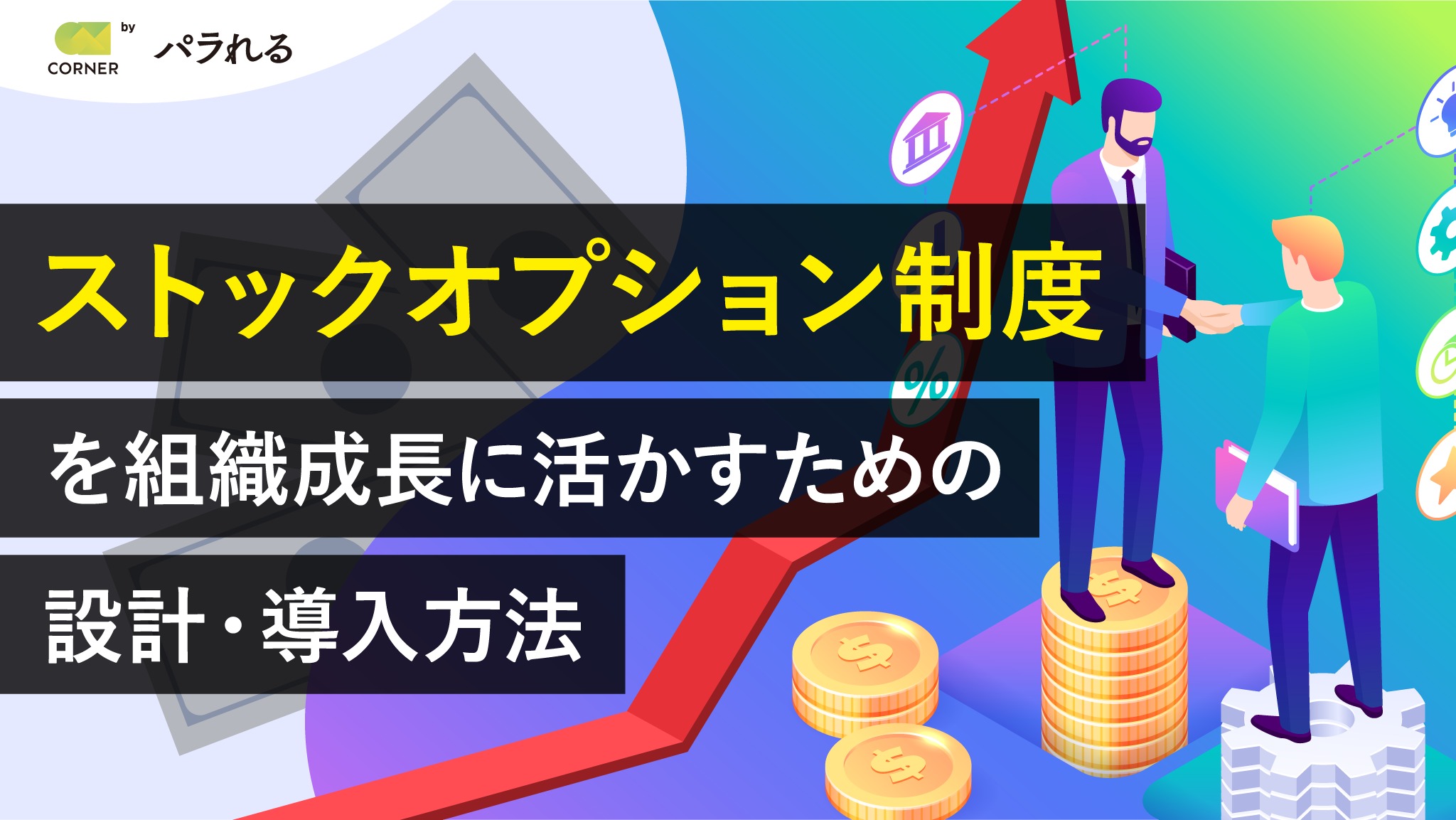
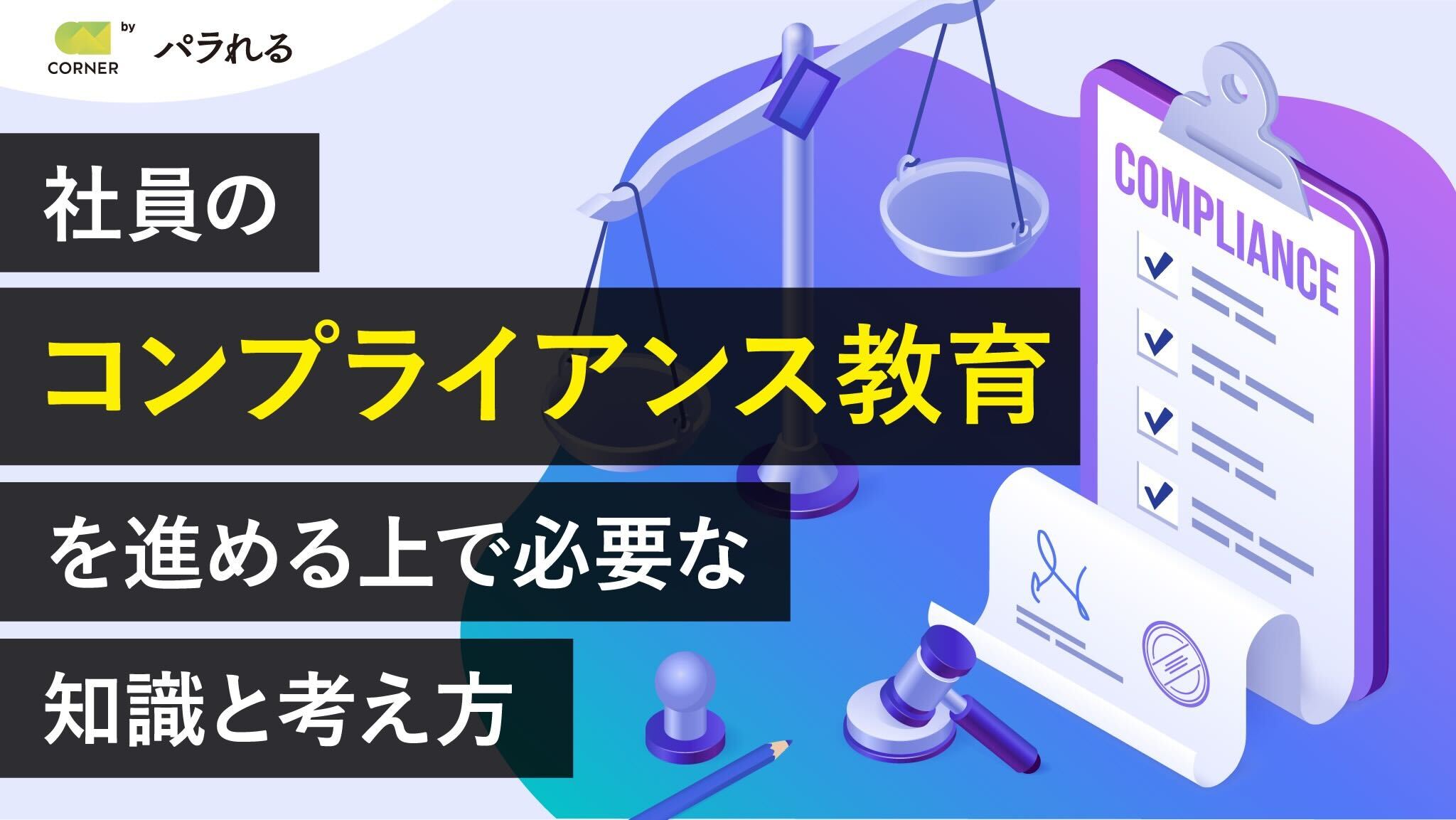

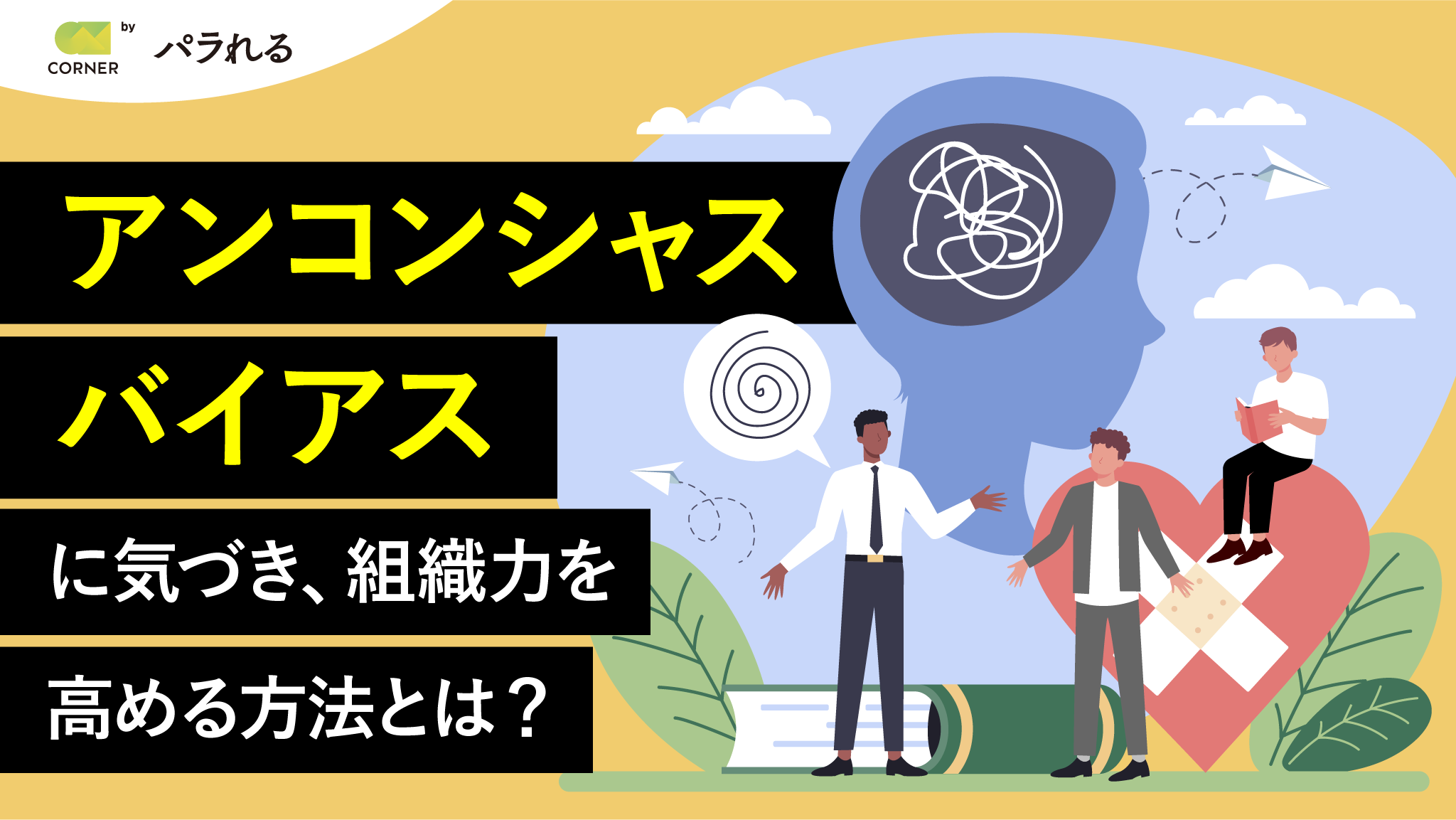
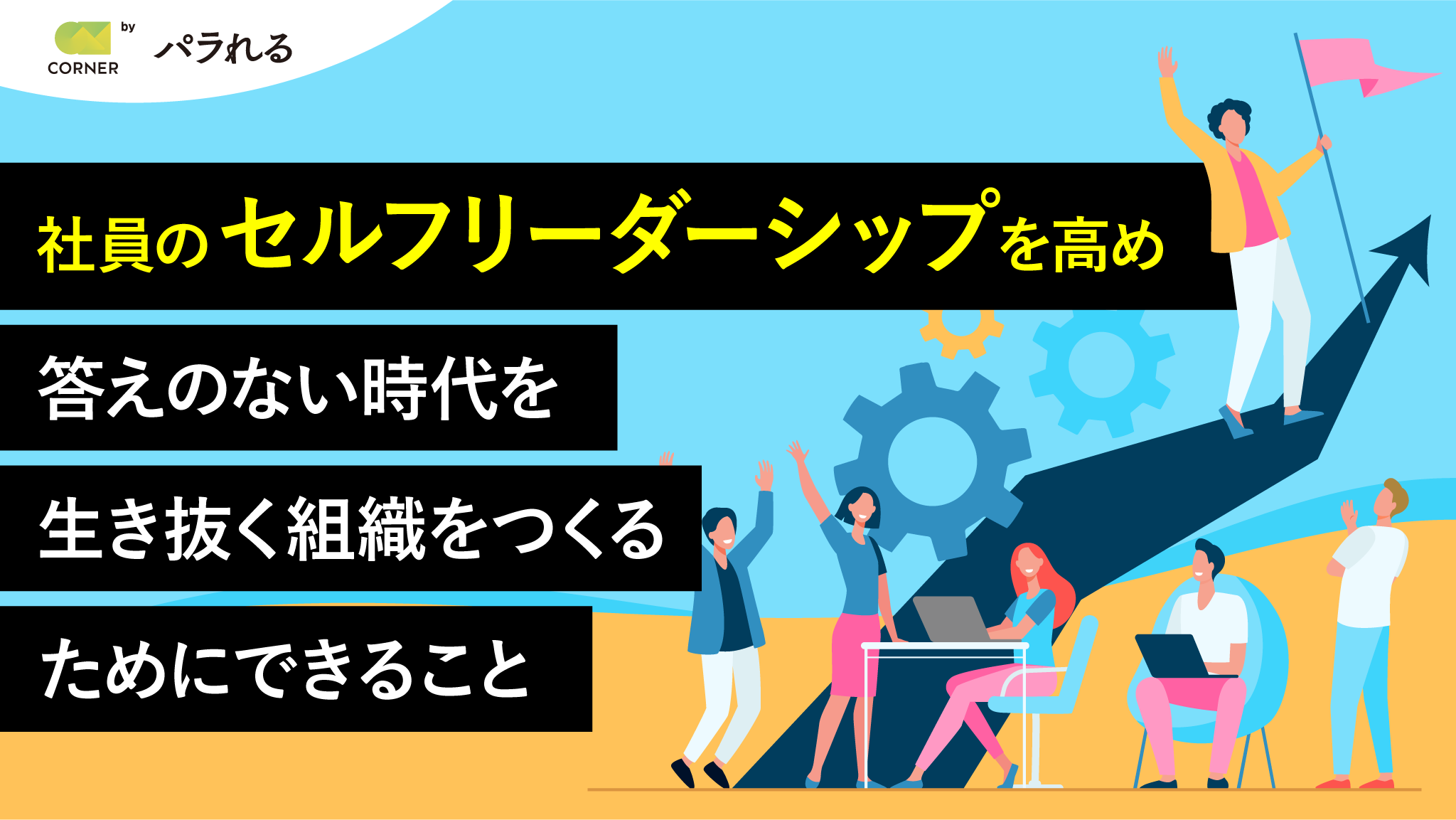
社員のセルフリーダーシップを高め、答えのない時代を生き抜く組織をつくるためにできること
セルフリーダーシップとは、その文字通り「自分自身を導く力」のことを指します。昨今の働き方の変化や、「個」の力が求
2022.06.07
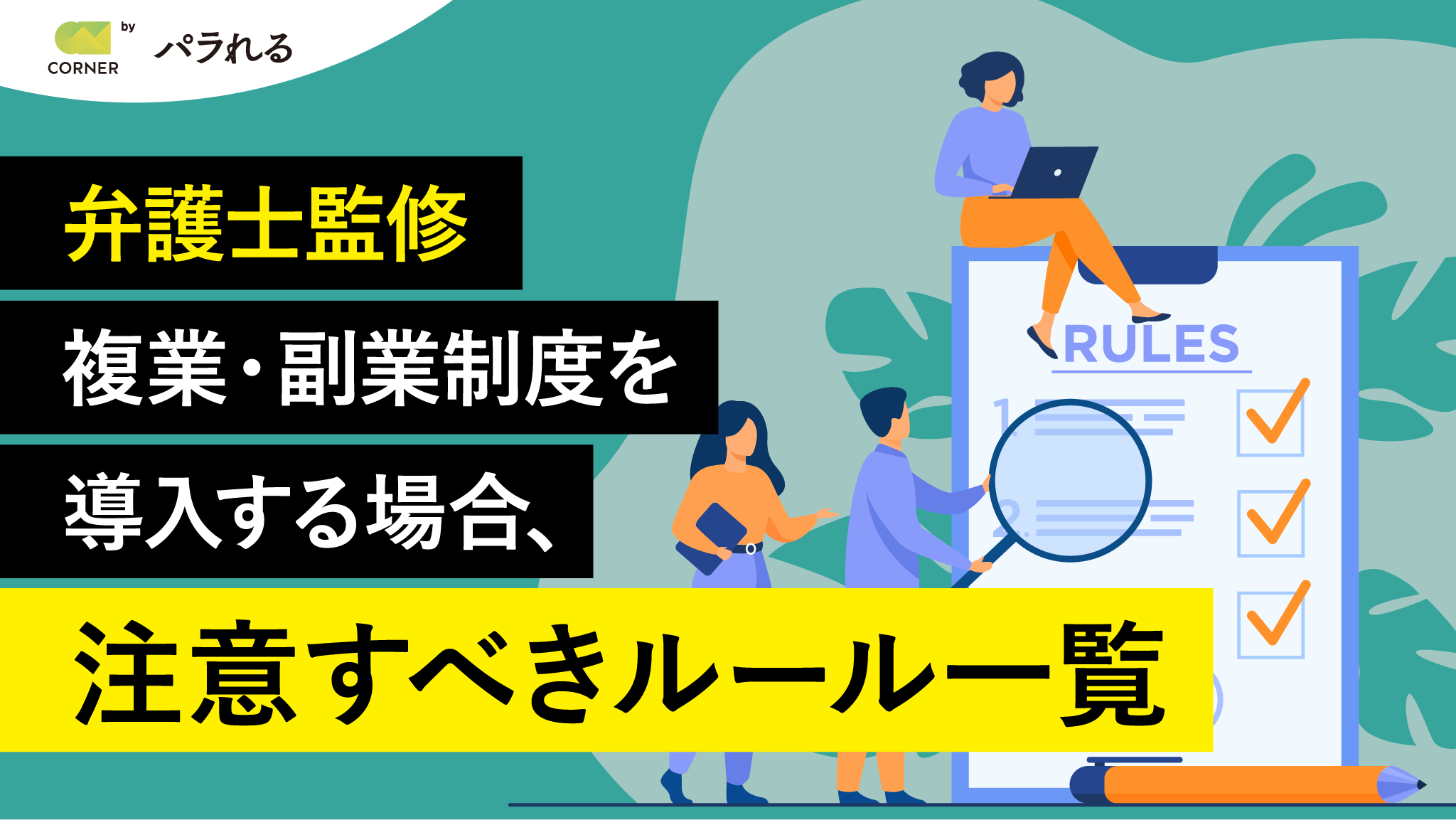
【弁護士監修】複業・副業制度を導入する場合、注意すべきルール一覧
働き方改革の推進や、人材不足の解消に対するアプローチのひとつとして、副業・複業(以下、副業と記載)を解禁する企業
2022.06.02
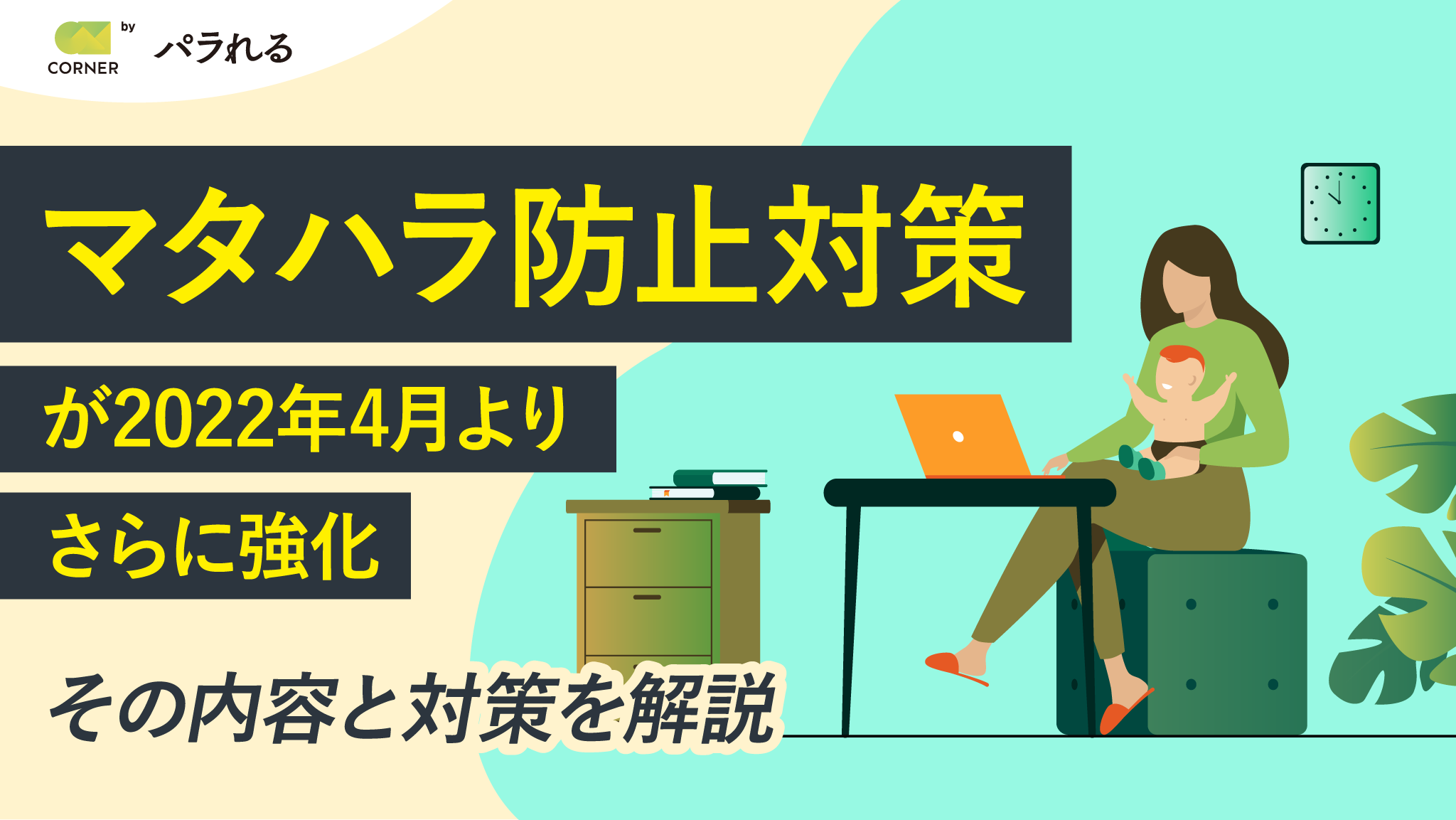
「マタハラ防止対策」が2022年4月よりさらに強化。その内容と対策を解説
2017年1月施行の『男女雇用機会均等法』『育児・介護休業法』によって義務付けられたマタニティーハラスメント(以
2022.05.26

「成人発達理論」を活用して、多様化する人材をマネジメントする方法とは
大人になっても人間は成長をし続けることが可能だと考える「成人発達理論」。VUCA時代と例えられる急激な社会の変化
2022.05.24

人や組織の「バーンアウト」を防ぐために、企業や人事ができる予防・対策とは
リモートワークが普及し、社内外の対面コミュニケーション機会が激減しました。こうした環境変化の影響か、昨今では優秀
2022.05.12

「改正育児・介護休業法」(2022年4月1日より順次施行)の内容と対応ポイント解説
2022年4月1日から3段階に分けて施行される「改正育児・介護休業法」。今回の改正では、出産・育児などによる労働
2022.05.11
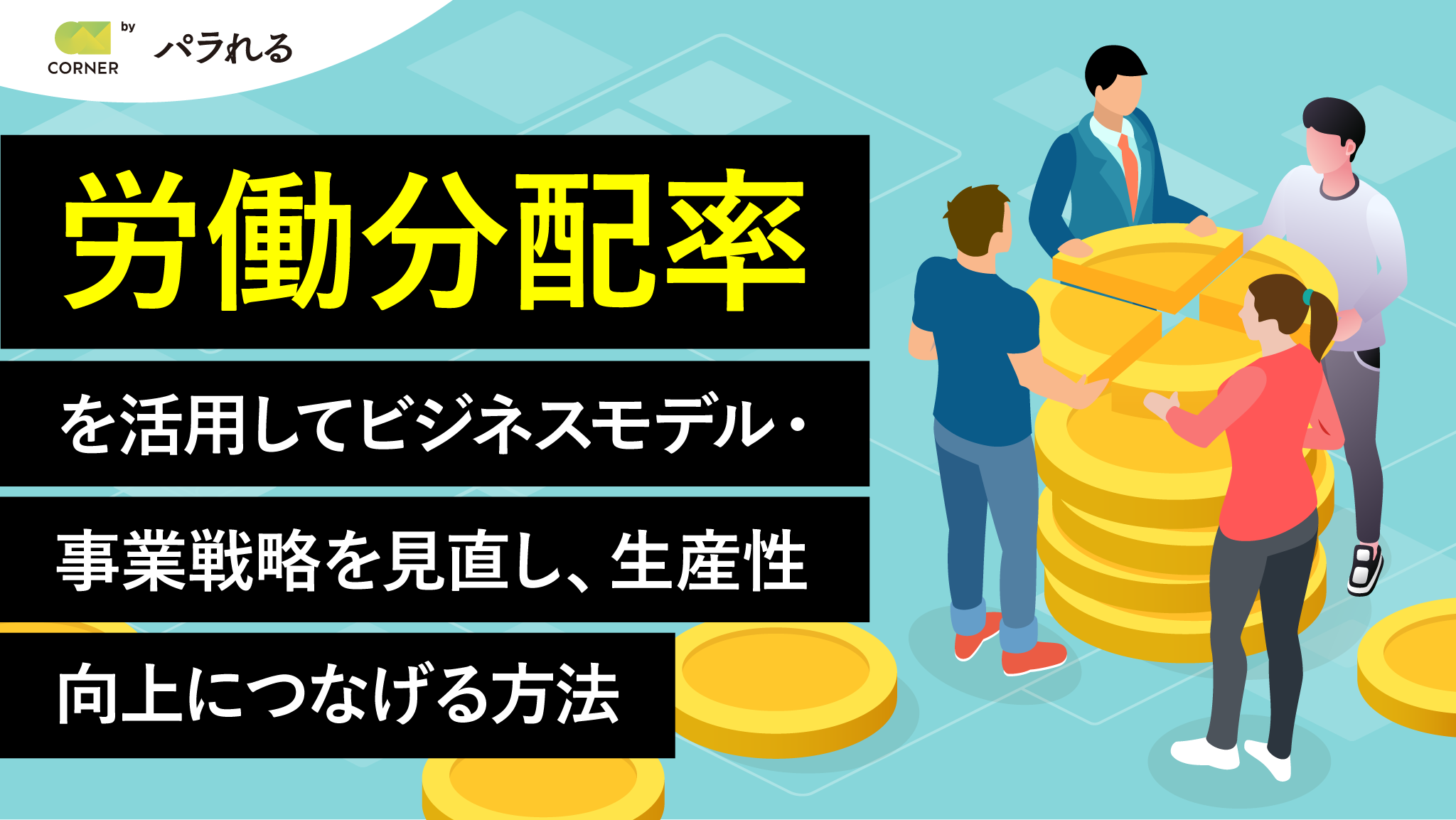
「労働分配率」を活用してビジネスモデル・事業戦略を見直し、生産性向上につなげる方法
会社にとって大きな割合を占める人件費。それが適正かどうか判断する上で活用されるのが「労働分配率」です。基本的には
2022.05.02

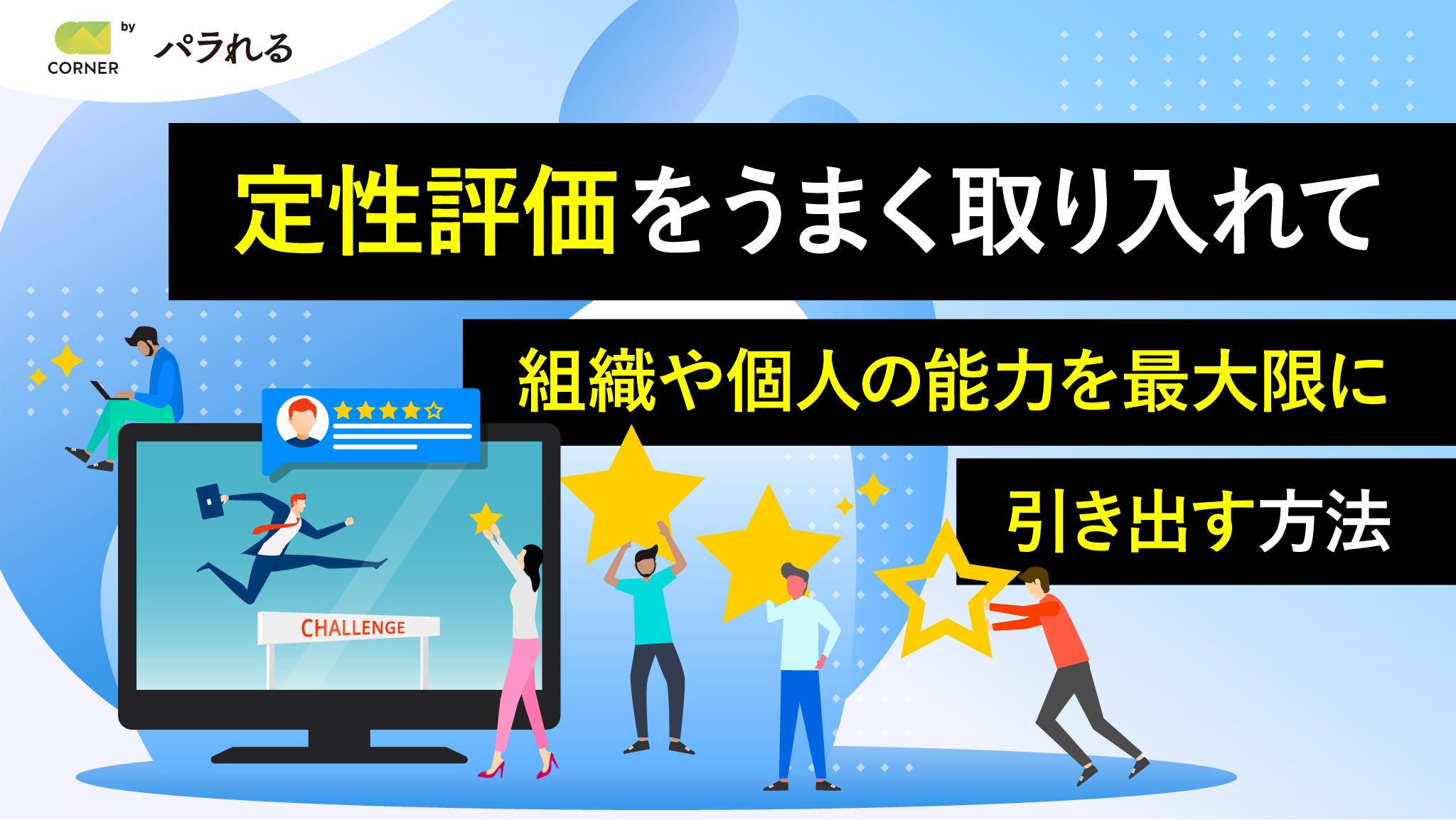
「定性評価」をうまく取り入れて、組織や個人の能力を最大限に引き出す方法
組織への貢献度合いや個人の能力を待遇に反映する人事評価。うまく活用することができれば、組織・個人の成長促進に繋が
2022.04.26

「不活性人材」を生まない組織の在り方と、具体的な人事施策について
もともとは熱心に仕事に向き合って活躍していたのに、いつしか成果もやる気も低下してしまった──そんな人材を「不活性
2022.04.19
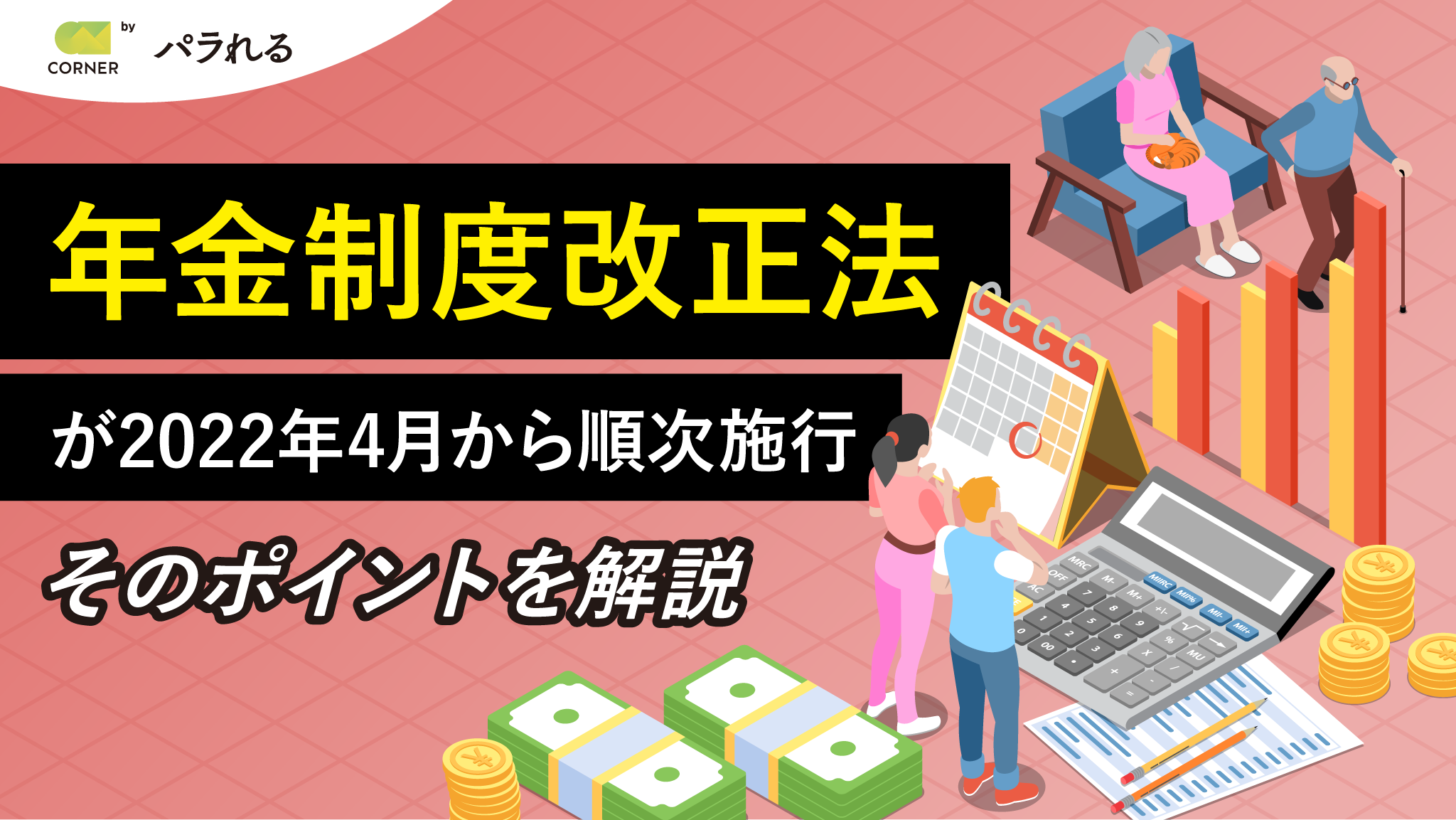
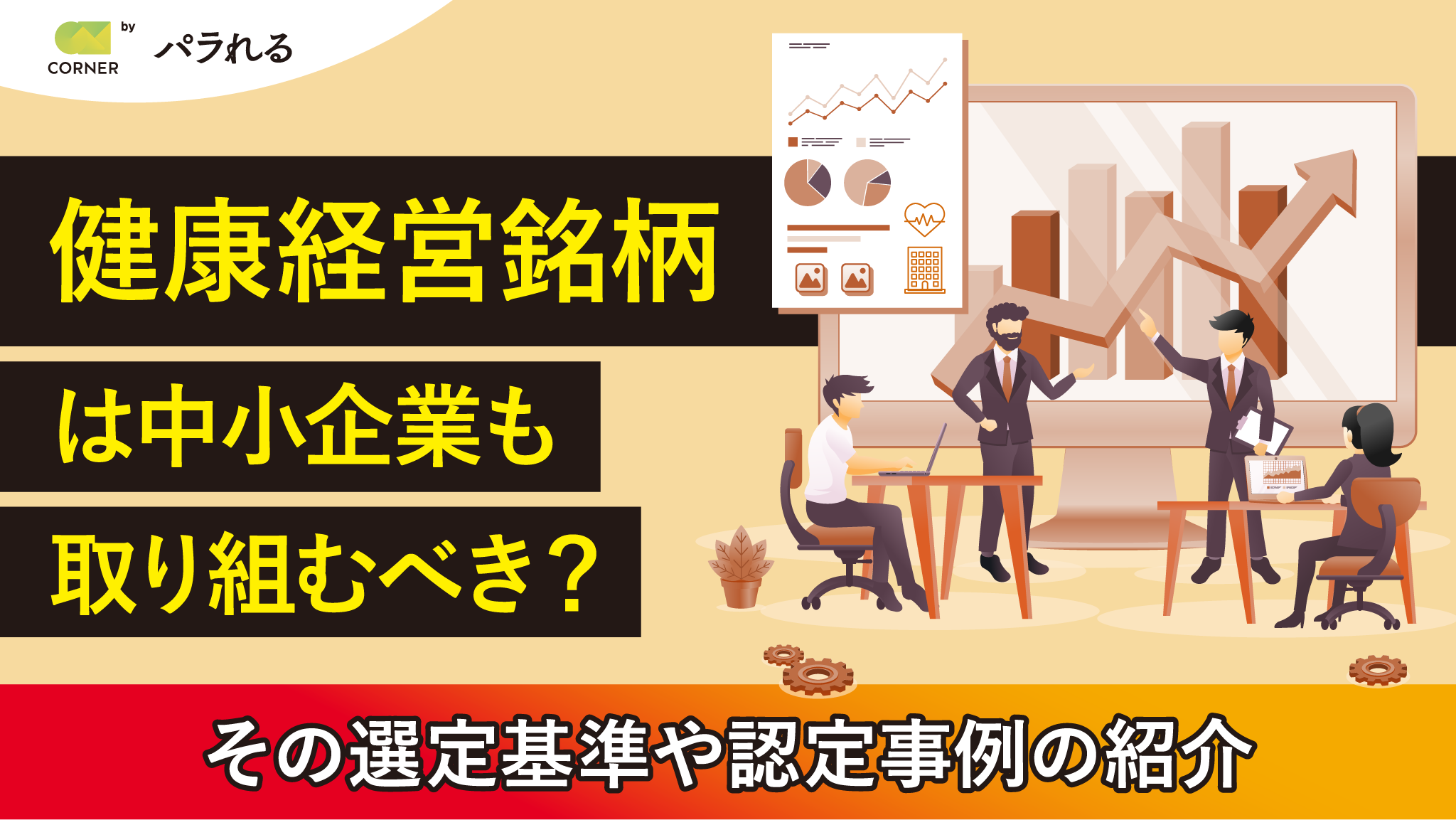
「健康経営銘柄」は中小企業も取り組むべき?その選定基準や認定事例の紹介
従業員の健康管理を経営的な視点で考えて戦略的に実践する健康経営。昨今の働き方改革の流れもあり、より注目度が高まっ
2022.04.05

2023年4月に施行の「法定割増賃金率」の引上げとは?中小企業が準備すべきポイント
法定労働時間を超えて従業員を働かせた際、企業は割増賃金を支払う必要があります。労働基準法では月60時間以内の時間
2022.03.31

「チェンジマネジメント」で変革の好循環を生み、強くしなやかな組織を作る方法
昨今の激しい外部環境変化に対応するべく、新しい組織体制や社内システムを導入する機会が増えています。しかしながら、
2022.03.15

「インターナルコミュニケーション」で、社員と会社を繋ぎ、事業成長を加速させる方法
「インターナルコミュニケーション」とは、組織内における広報活動のことを指します。社内広報やインナーコミュニケーシ
2022.03.03
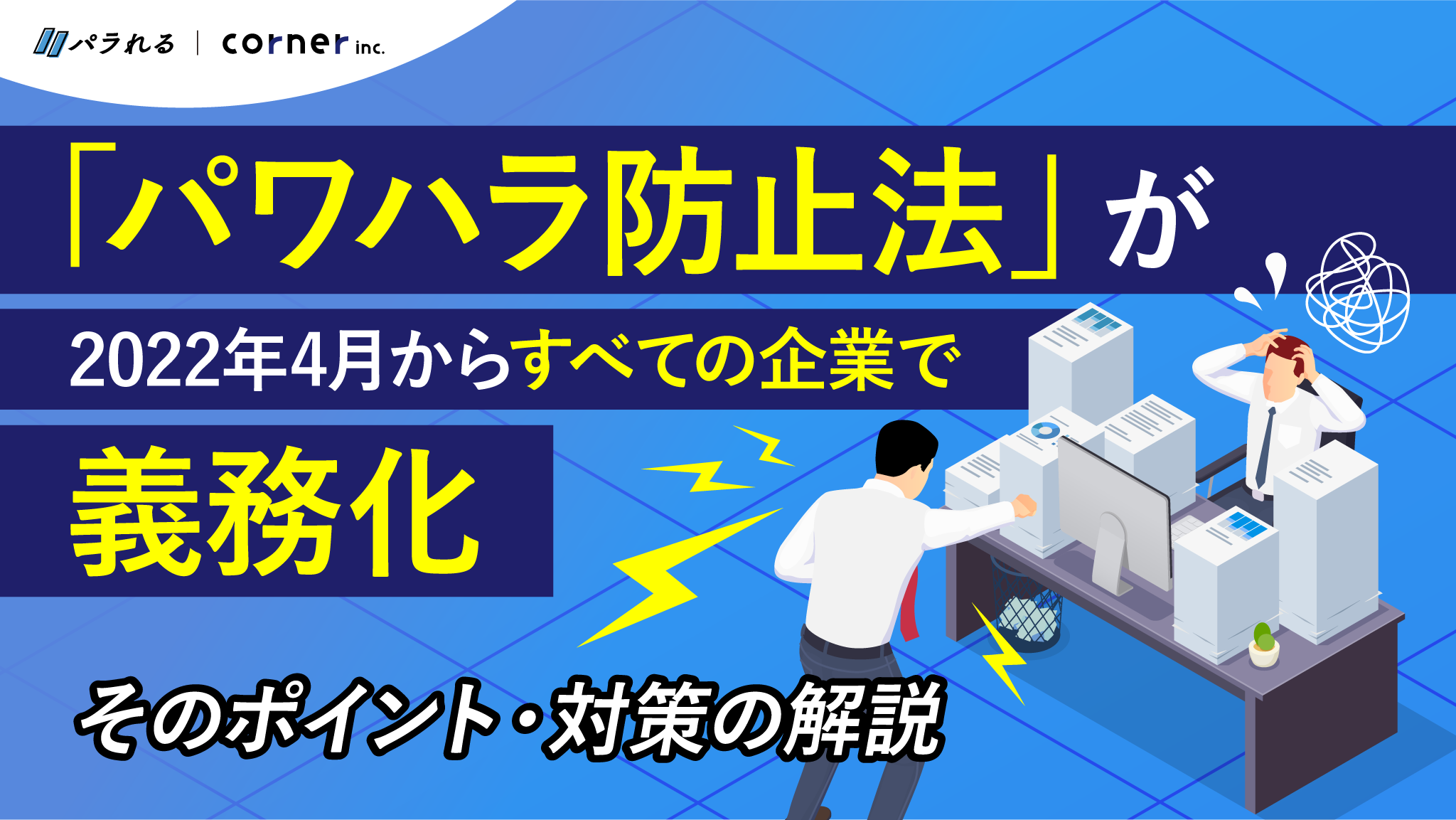
「パワハラ防止法」が2022年4月からすべての企業で義務化。そのポイント・対策の解説
いよいよ2022年4月1日からすべての企業を対象に施行される「パワハラ防止法」。同法には、職場内のパワーハラスメ
2022.03.01
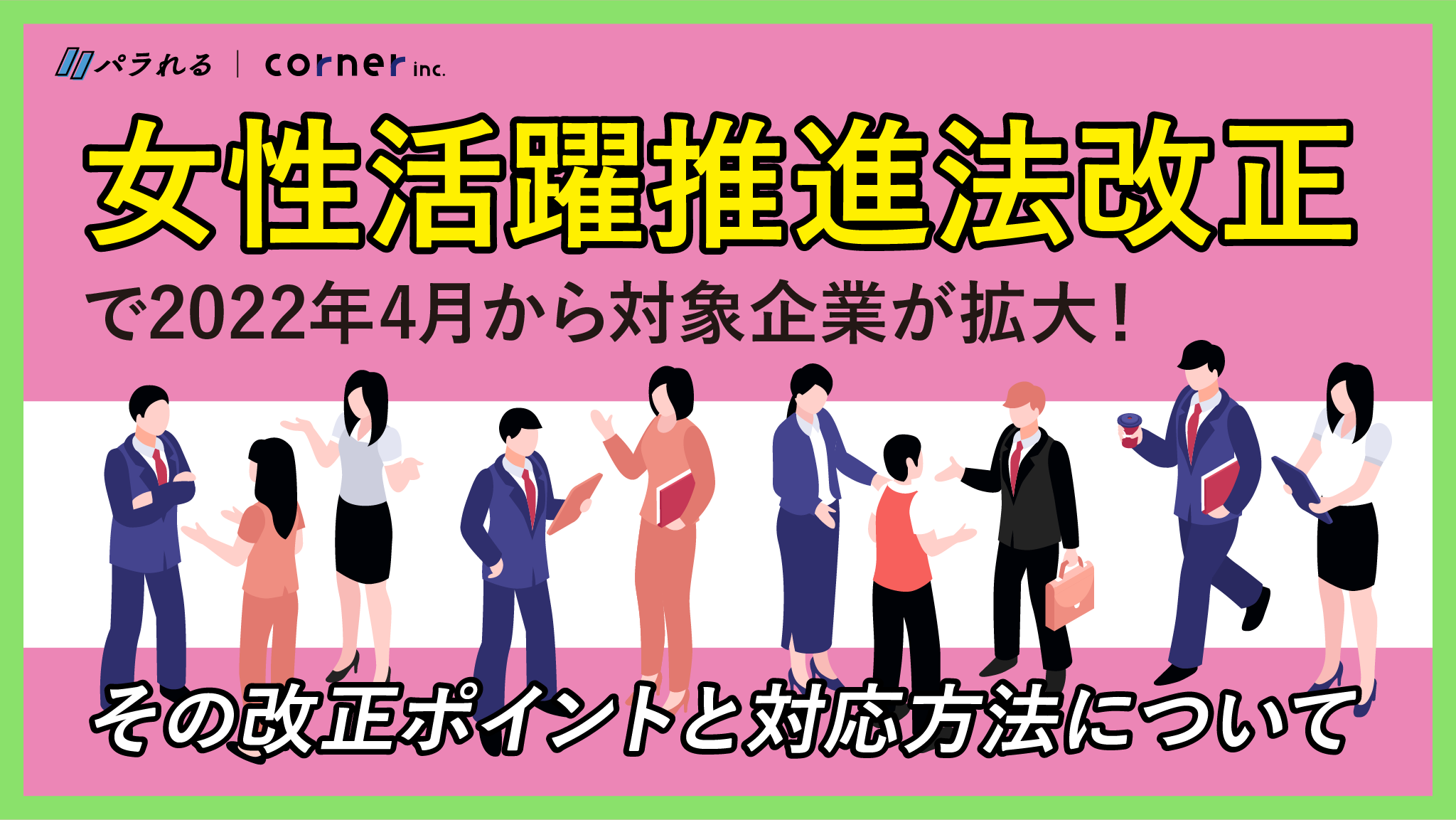
「女性活躍推進法改正」で2022年4月から対象企業が拡大。その改正ポイントと対応方法について
広く耳にするようになった「女性活躍推進法」。働き方改革・ダイバーシティ推進・人材不足解消など、さまざまなテーマに
2022.02.08

「人事PMI」とは。企業統合後の組織風土をつくり、社員のモチベーションを守る
事業拡大、後継者問題の解決、人材・ノウハウの吸収などを目的に行われるM&A(Mergers and Ac
2022.01.25

「データドリブン人事(HR)」人事データを取得・活用して採用や配置に活かす方法とは
ビジネスなどで得られたあらゆるデータを総合的に分析し、意思決定の判断材料とする「データドリブン」。すでにいろいろ
2022.01.18

オンライン化するだけではダメ。ニューノーマル時代の「オンラインインターンシップ」とは
就職活動のスタンダードとなっているインターンシップ。しかし、2020年からの新型コロナウイルスの影響やテクノロジ
2022.01.13
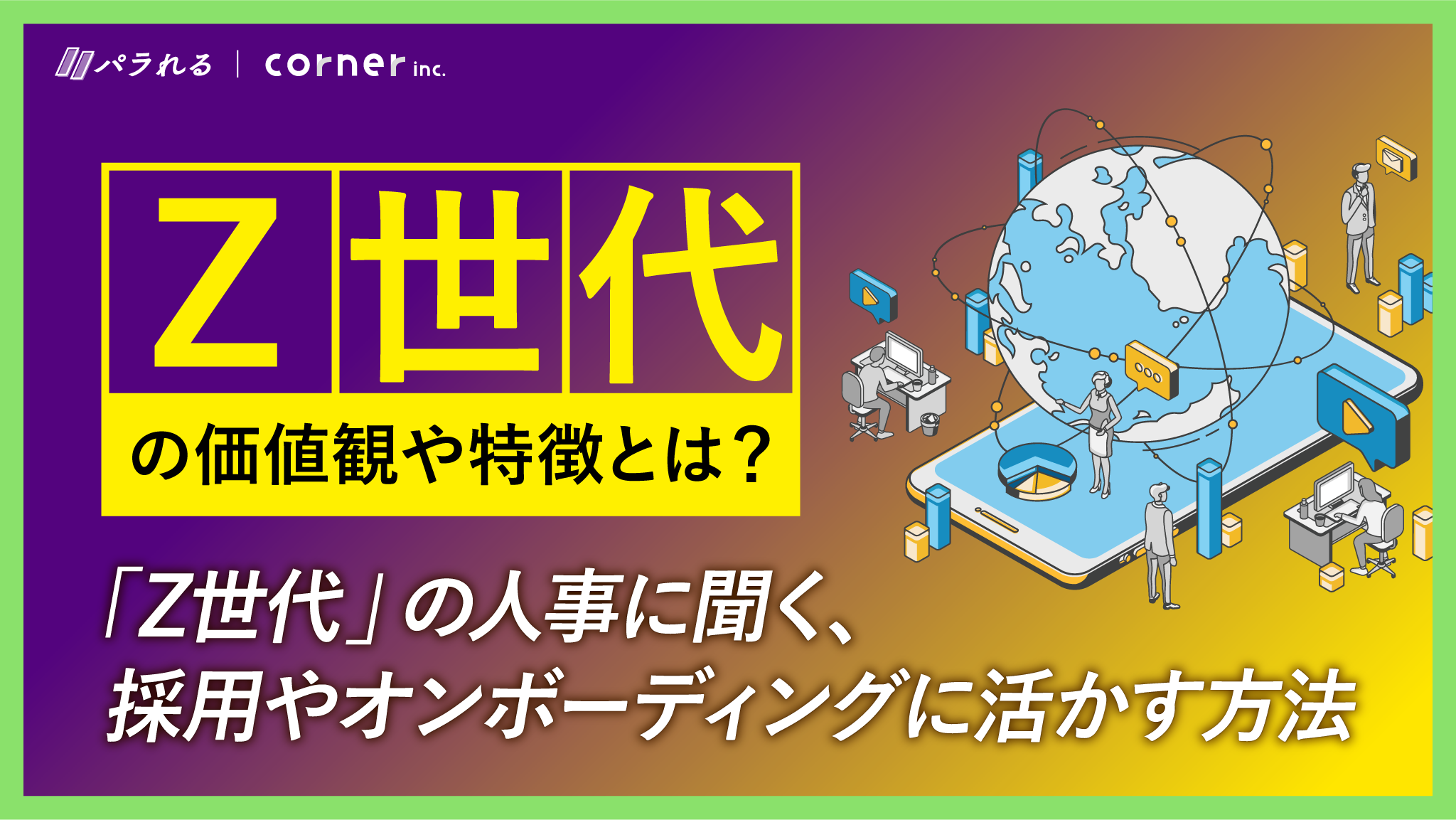
Z世代の採用手法は違う?Z世代人事に聞く、採用やオンボーディングに活かす方法
世代を表す言葉はこれまでさまざまありましたが、最近ではX世代・Y世代・Z世代、という言葉を聞くことが増えたのでは
2022.01.06
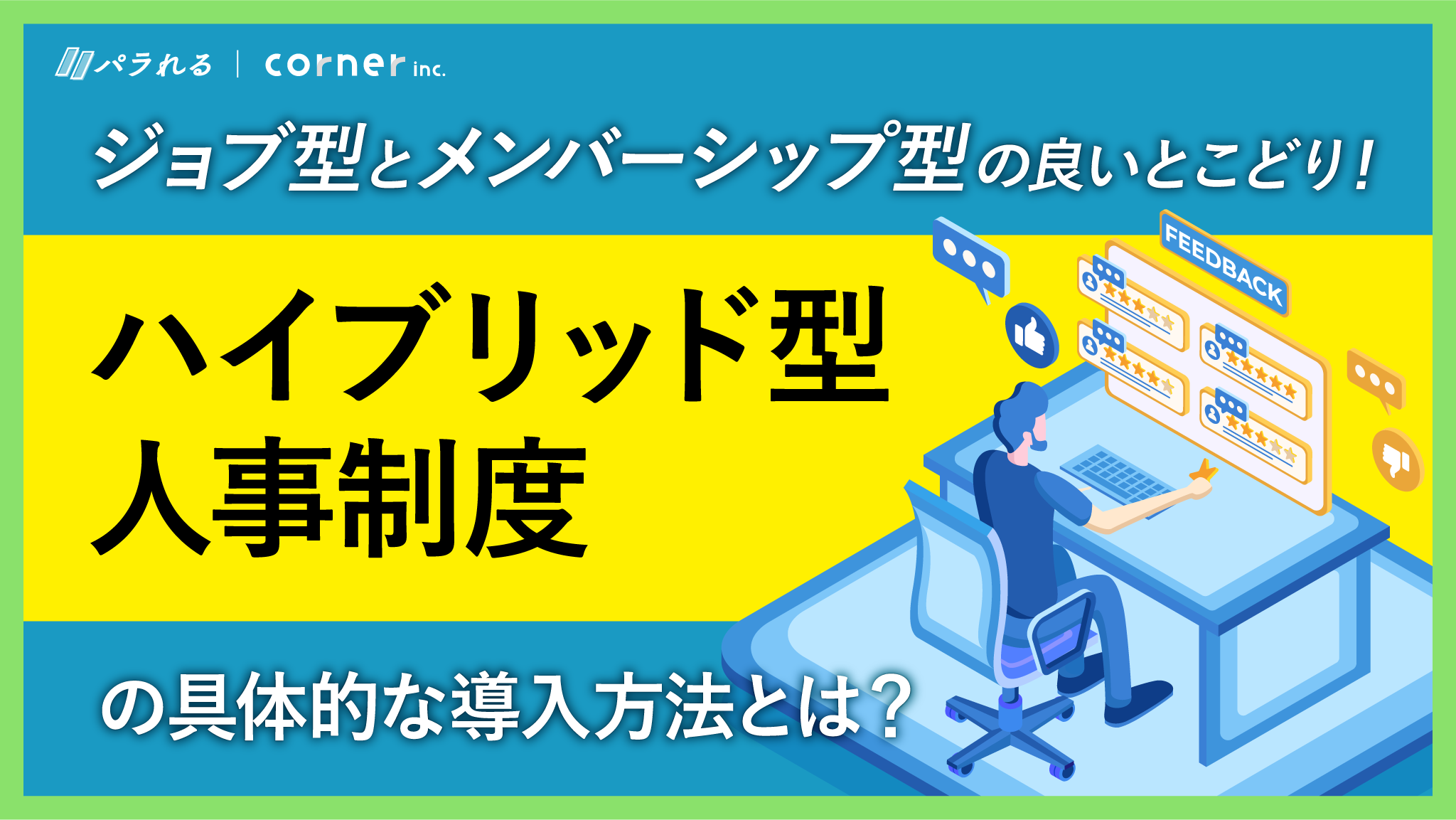
「ハイブリッド型人事制度」で、ジョブ型とメンバーシップ型の良いとこどり!具体的な導入方法とは?
これまで多くの日本企業が導入してきた、新卒一括採用・年功序列をベースとした「メンバーシップ型」雇用から、昨今のリ
2021.12.23
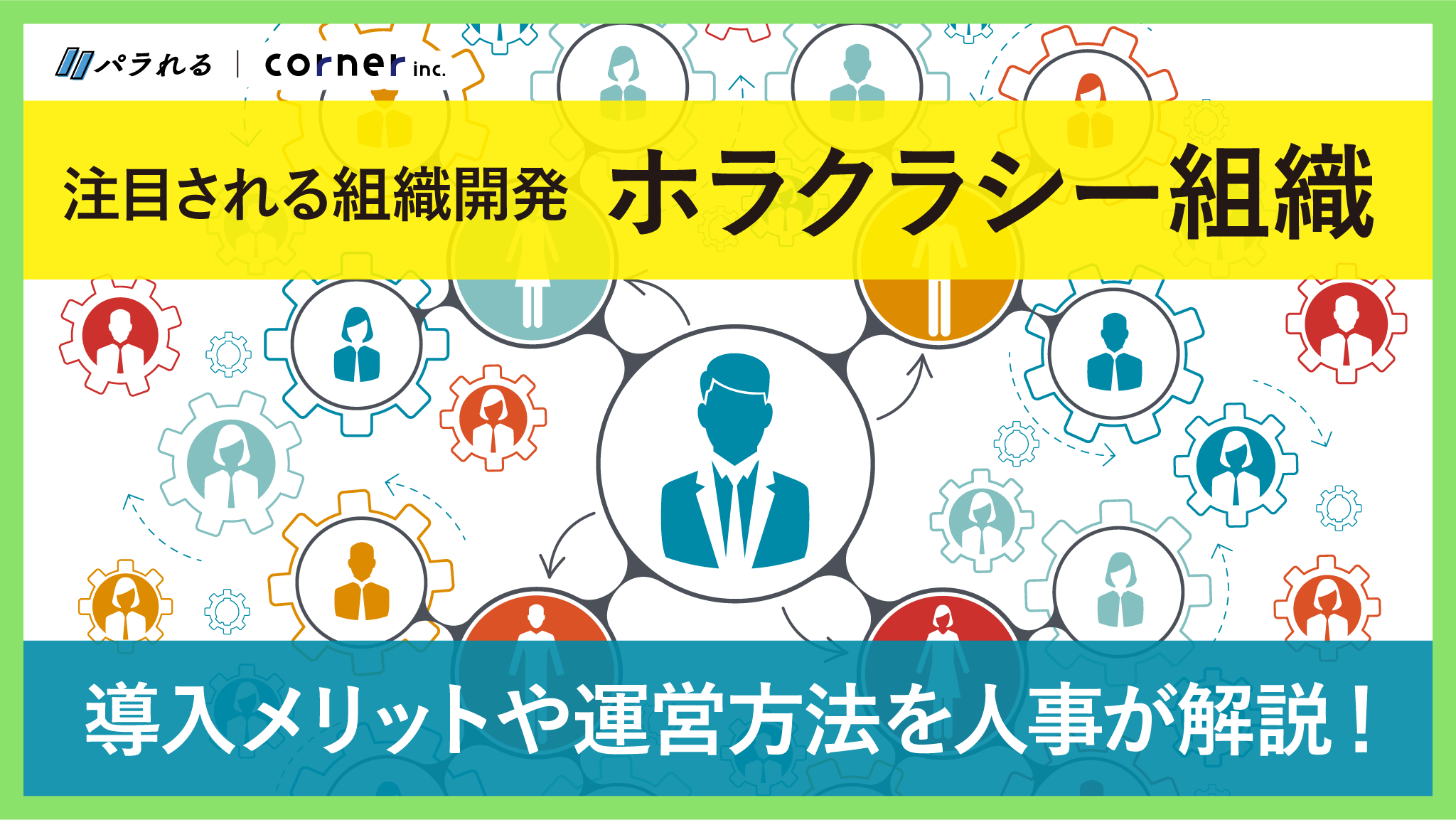
注目される組織開発「ホラクラシー組織」。導入メリットや運営方法を人事が解説!
組織開発の文脈で聞くことが増えた「ホラクラシー組織」。従来の組織管理体制や経営手法に代わる新しい組織の1つとして
2021.12.21
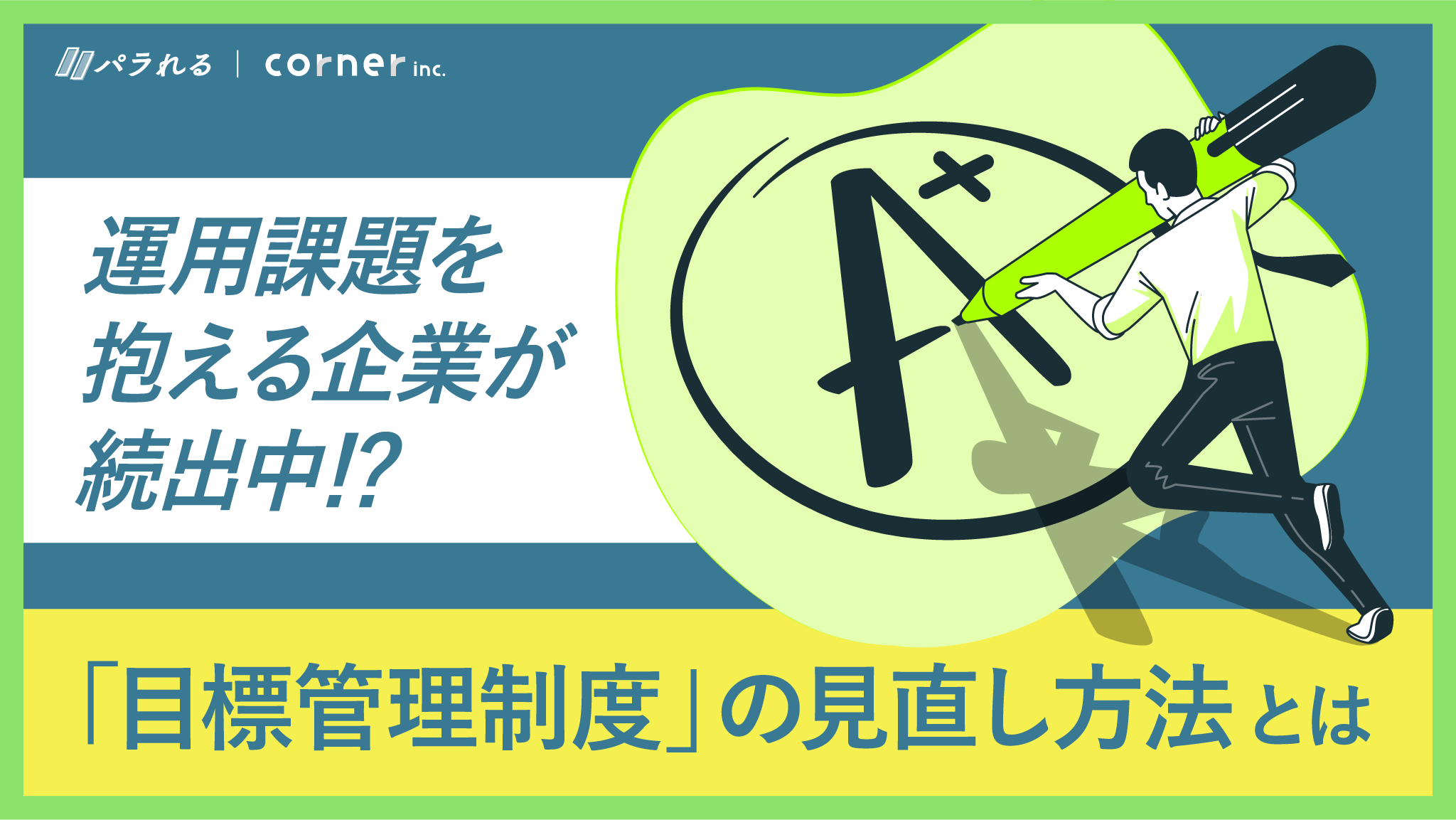
「目標管理制度」の運用うまくできてる?今だからこそ目標管理制度の見直すべき点とは?
今や多くの企業が導入している「目標管理制度」。しかしながら働き方の多様化や急激な就業環境変化の影響からか、その運
2021.12.14
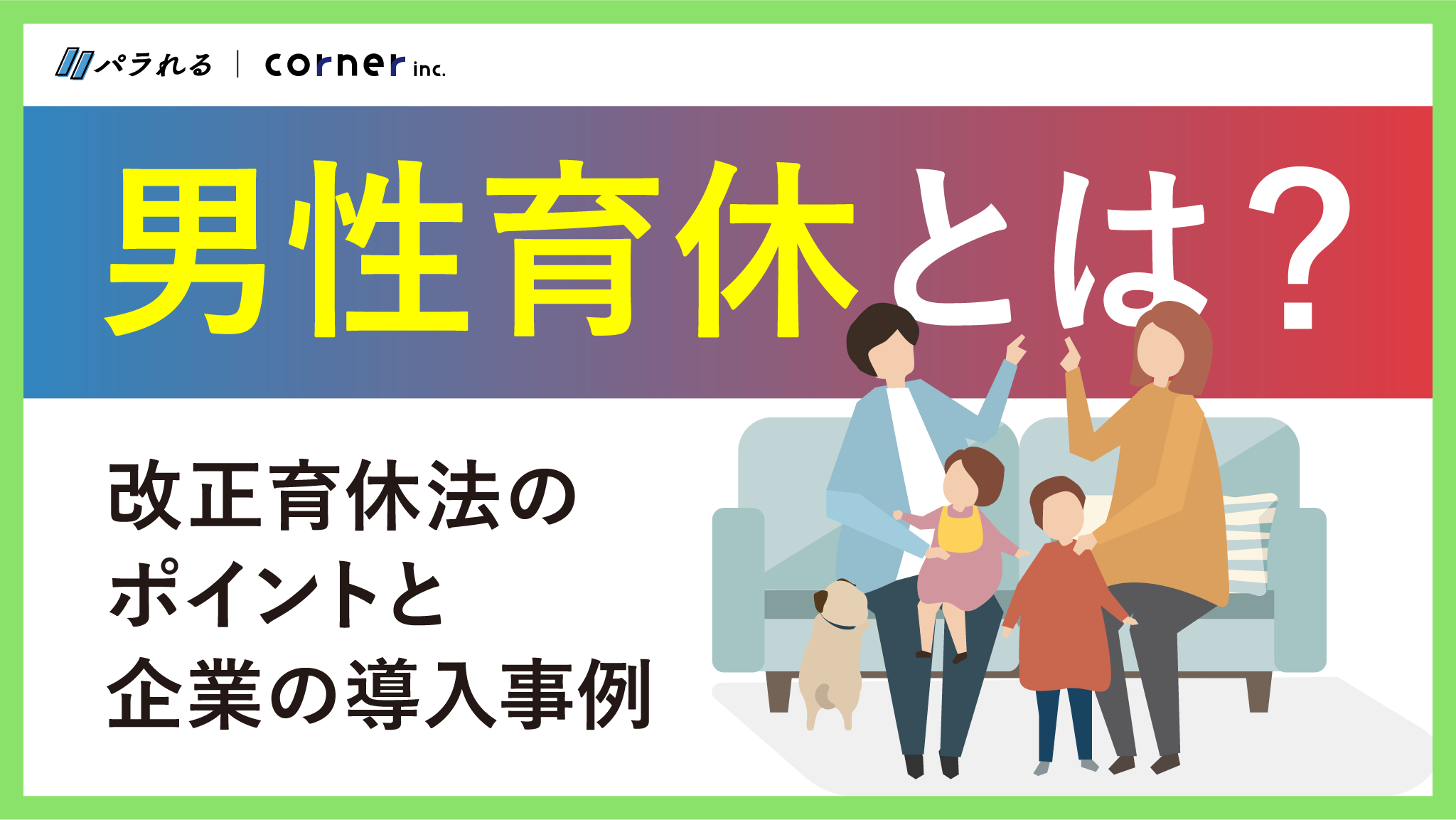
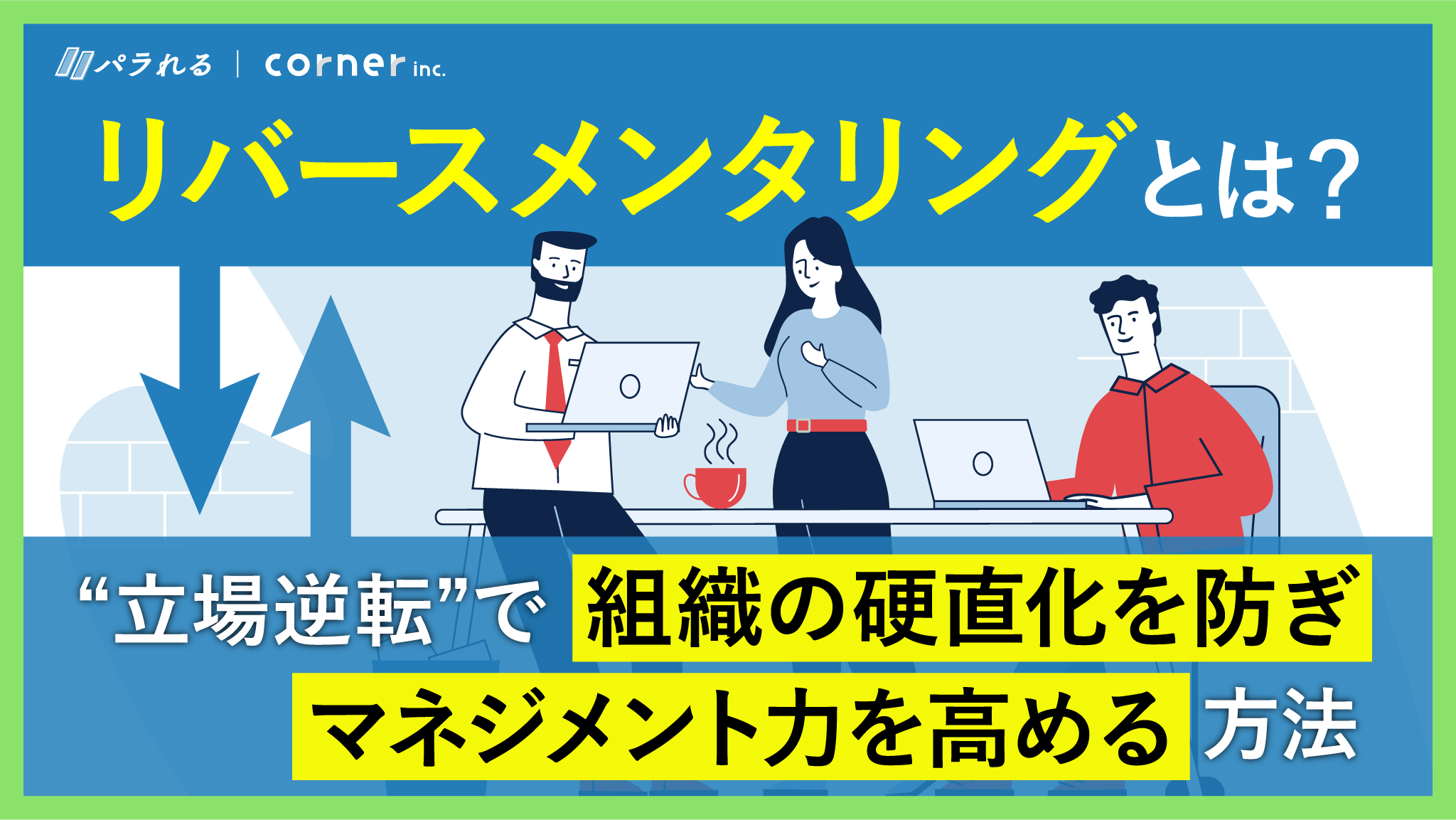
「リバースメンタリング」とは。“立場逆転”で組織の硬直化を防ぎマネジメント力を高める方法。
社員の自主的・自律的な成長を促進するための取り組みに「メンタリング」があります。これは上司や先輩社員がメンター(
2021.12.07
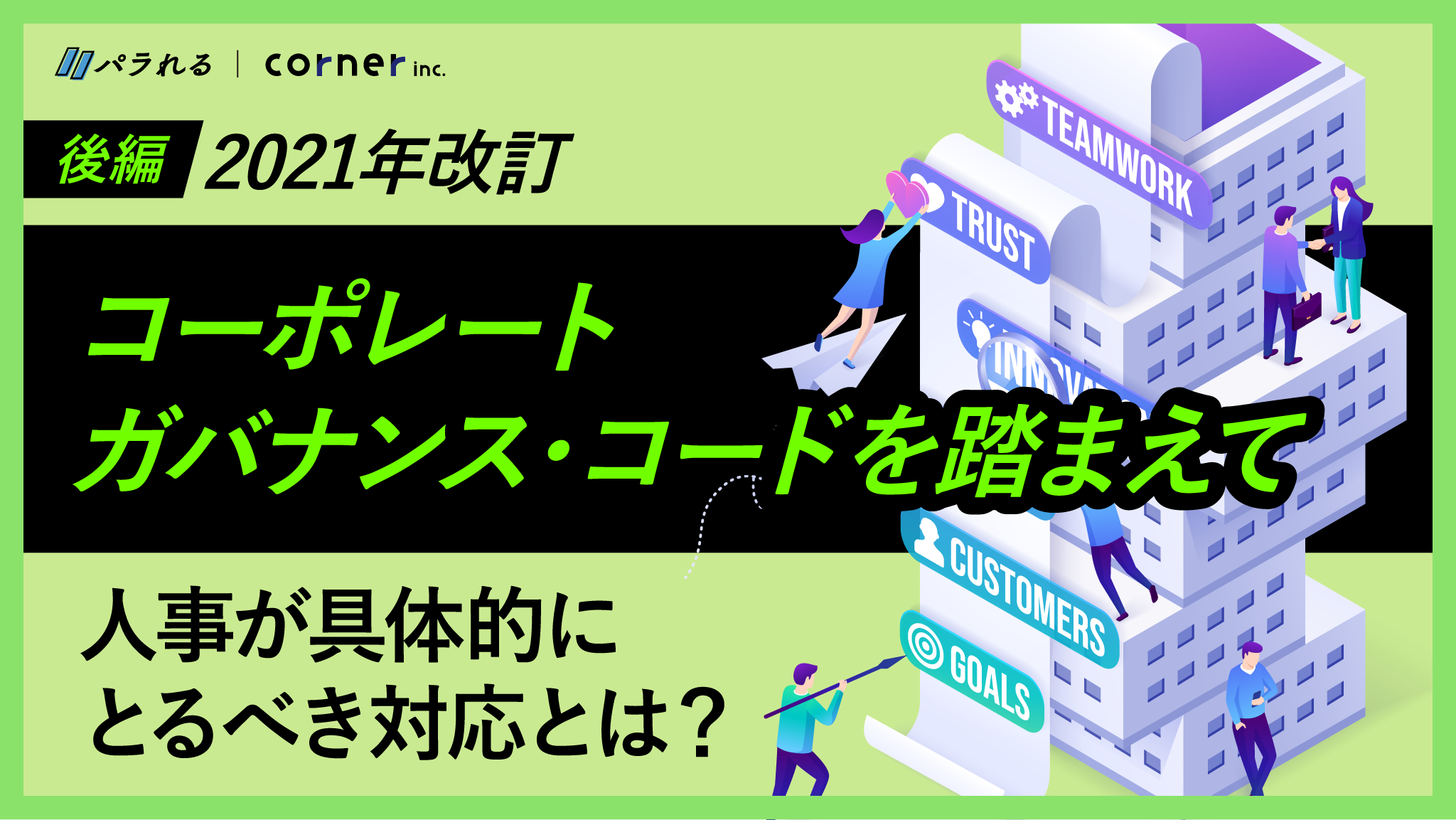
2021年改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、人事が具体的にとるべき対応とは?
2021年6月にコーポレートガバナンス・コードが改訂されました。今回の改訂では、取締役会が備えるべきスキルと実態
2021.12.02
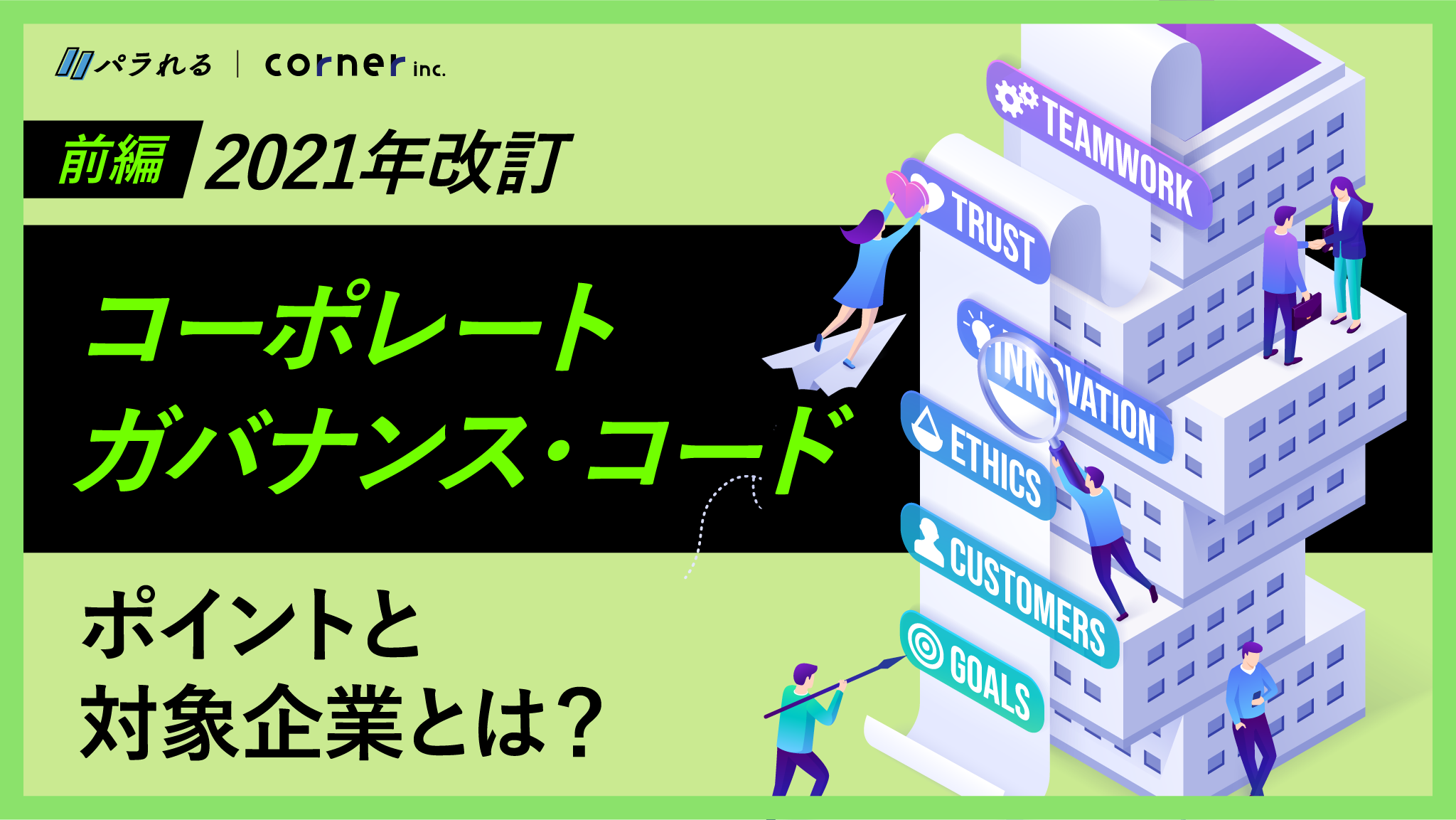
2021年改訂コーポレートガバナンス・コードのポイントと対象企業とは?
2021年6月にコーポレートガバナンス・コードが改訂されました。今回の改訂では、取締役会が備えるべきスキルと実態
2021.11.30
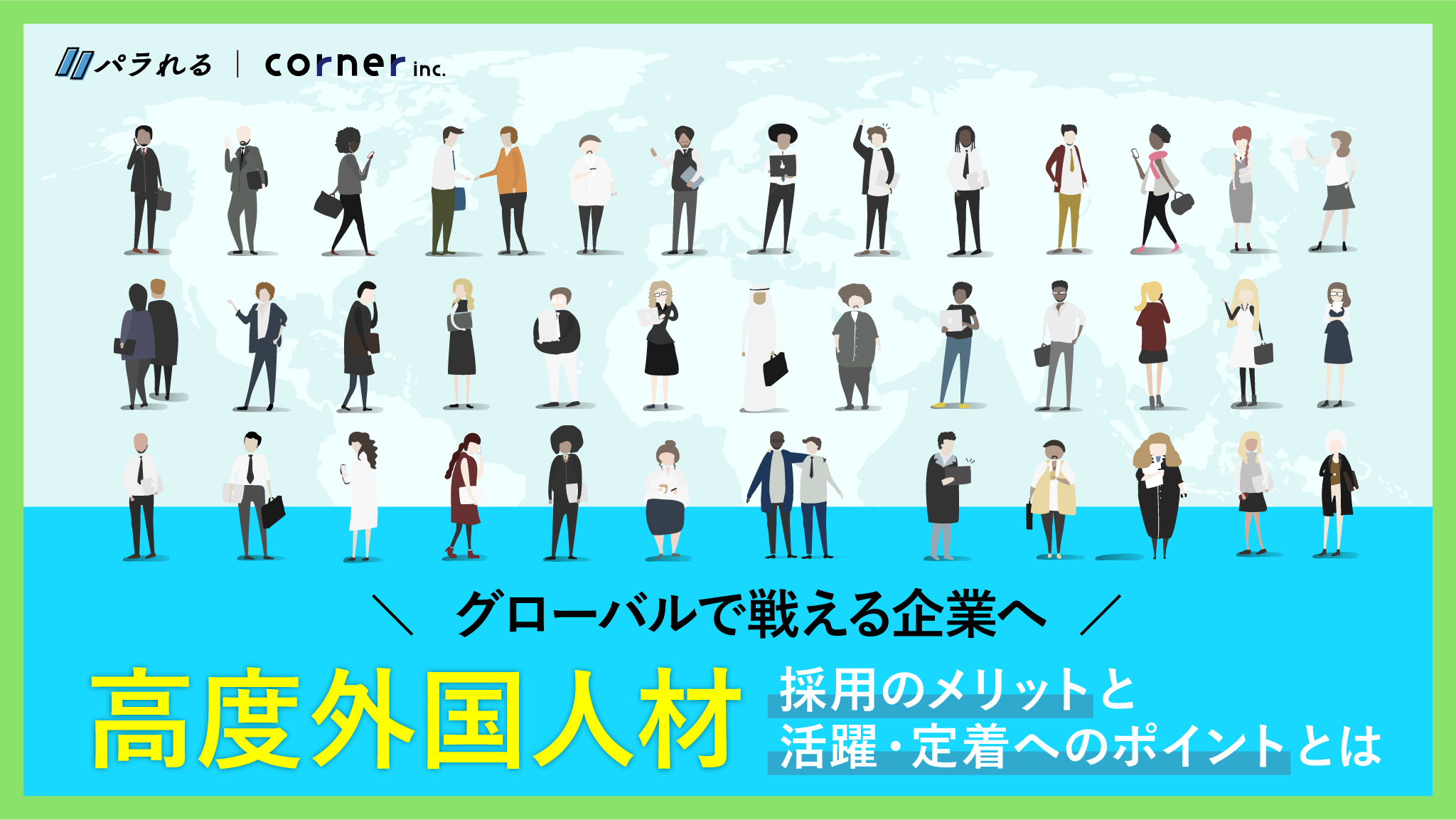
グローバルで戦える企業へ。「高度外国人材」採用のメリットと活躍・定着へのポイントとは
優秀な人材を採用し働き続けてもらうことは、企業にとって非常に重要です。そのために、国内だけでなく海外在住者や外国
2021.11.09
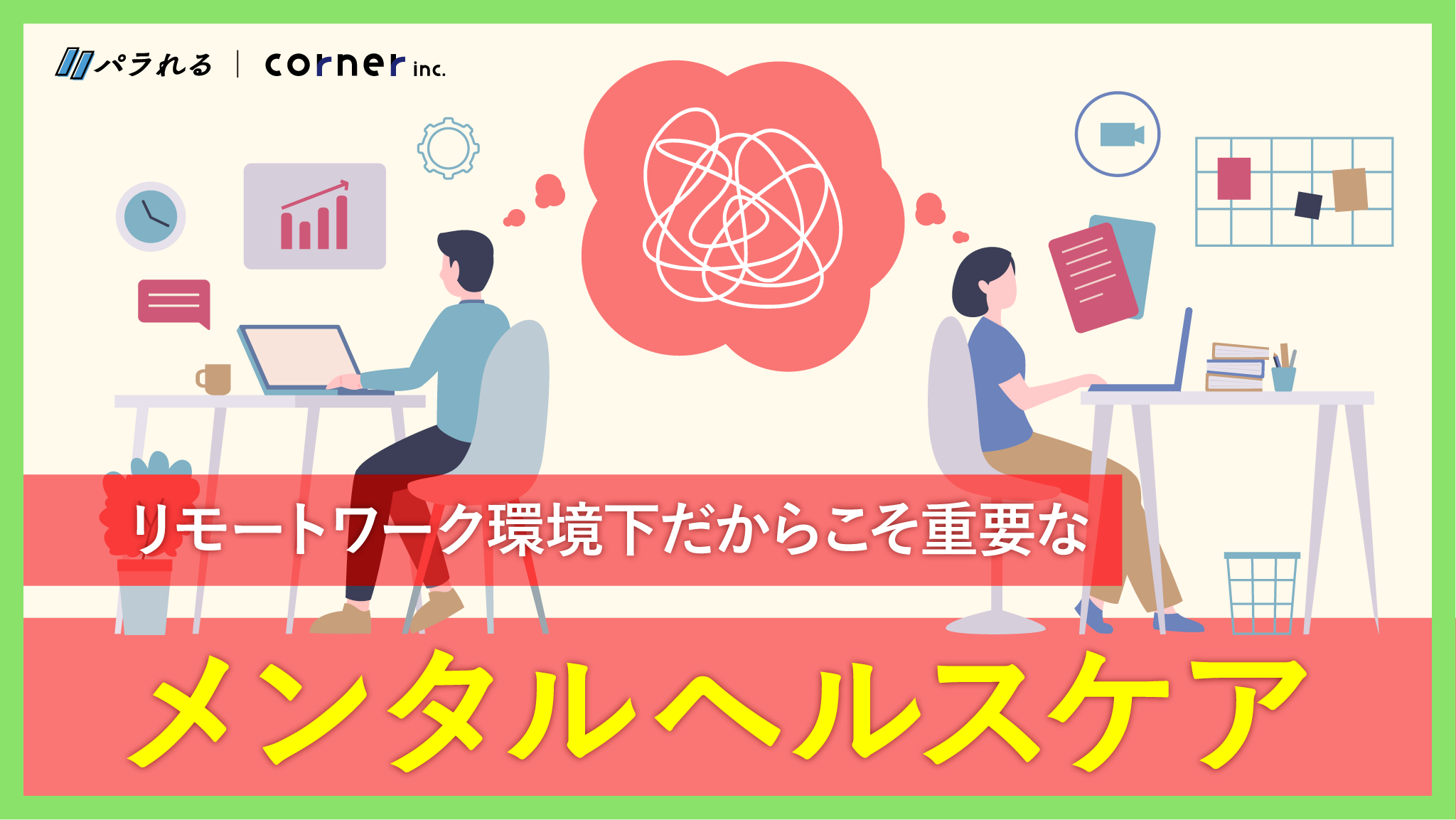

注目が高まる「DEI(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」とは
近年注目され、さまざまなところで聞くようになった「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I
2021.10.12
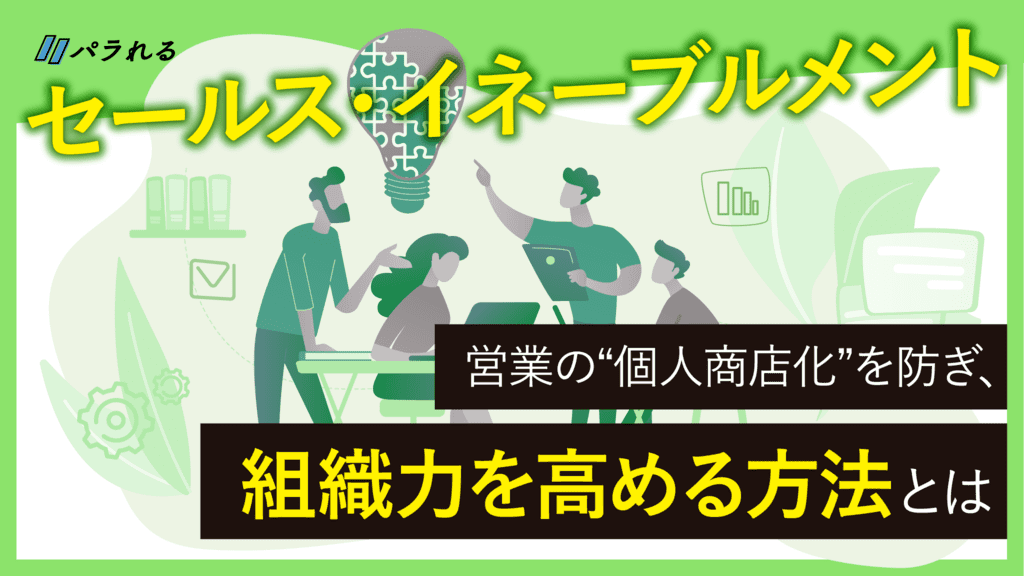
「セールス・イネーブルメント」で営業の“個人商店化”を防ぎ、組織力を高める方法とは
営業組織の強化を目的に、アマゾン、セールスフォース、マイクロソフト、ツイッター、SAPなどの欧米企業が導入し注目
2021.10.07

グローバル企業が多く導入する「職務等級制度」がハマる組織とハマらない組織
以前、このパラれるのメディアにて「等級制度」についての記事を掲載しました。 前回の記事はこちら「普遍性とフレキシ
2021.09.14

コンディション変化を察知!「パルスサーベイ」を形骸化させず、エンゲージメント向上につなげる方法
昨今、従業員エンゲージメントの向上に取り組む企業が増え、それに伴い各種サーベイが導入されるようになりました。しか
2021.09.09


キャリアの多様化に対応する「複線型人事制度」とは?メリット・デメリットと導入ステップ
多様な専門性をもった人材が組織に必要となり、統一された一つの人事制度では対応できなくなってきことを受け、複数のキ
2021.09.02

「ビジネスレジリエンス」を高めて環境変化に強い組織づくりを行う方法
昨今の激しい環境変化を受け、「レジリエンス」という言葉を耳にする機会が増えました。一般的には「変化にうまく適応で
2021.08.26


VUCA時代に求められる「オーセンティック・リーダーシップ」とは
時代の変遷と共に、求められるリーダー像は変化・多様化してきました。その中の1つに「オーセンティック・リーダーシッ
2021.08.17

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定背景と、企業・人事が注意するべきポイント
2021年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働け
2021.08.05



会社と個人のWillを重ねる「エンプロイーサクセス」の本質的な実践方法とは
複数社で働くことが少しずつ一般的になる中で、「個人の限られた時間やリソースを、いかに自社にコミットしてもらえるか
2021.07.20

「ワークフォース・プランニング」で感覚的な経営から脱却し、戦略的に人員計画を立てる方法
「データドリブン経営」という言葉が一般的になってきている昨今。その波は人事業務においても同様で、「ワークフォース
2021.07.15

人材育成術としての「メンタリング」。メンター・メンティー共に大きく成長する方法・手順
これまでも若手メンバーに対して先輩社員が手厚くフォローする形を取る企業はたくさんありました。そして最近では、若手
2021.07.08

「FFS理論」により人や組織の可能性を引き出し、他社がマネできない強い組織土壌を作る方法
採用や組織開発において適性検査や性格診断が用いられることはありますが、最近「FFS理論」が人事の間で話題に上がる
2021.07.01
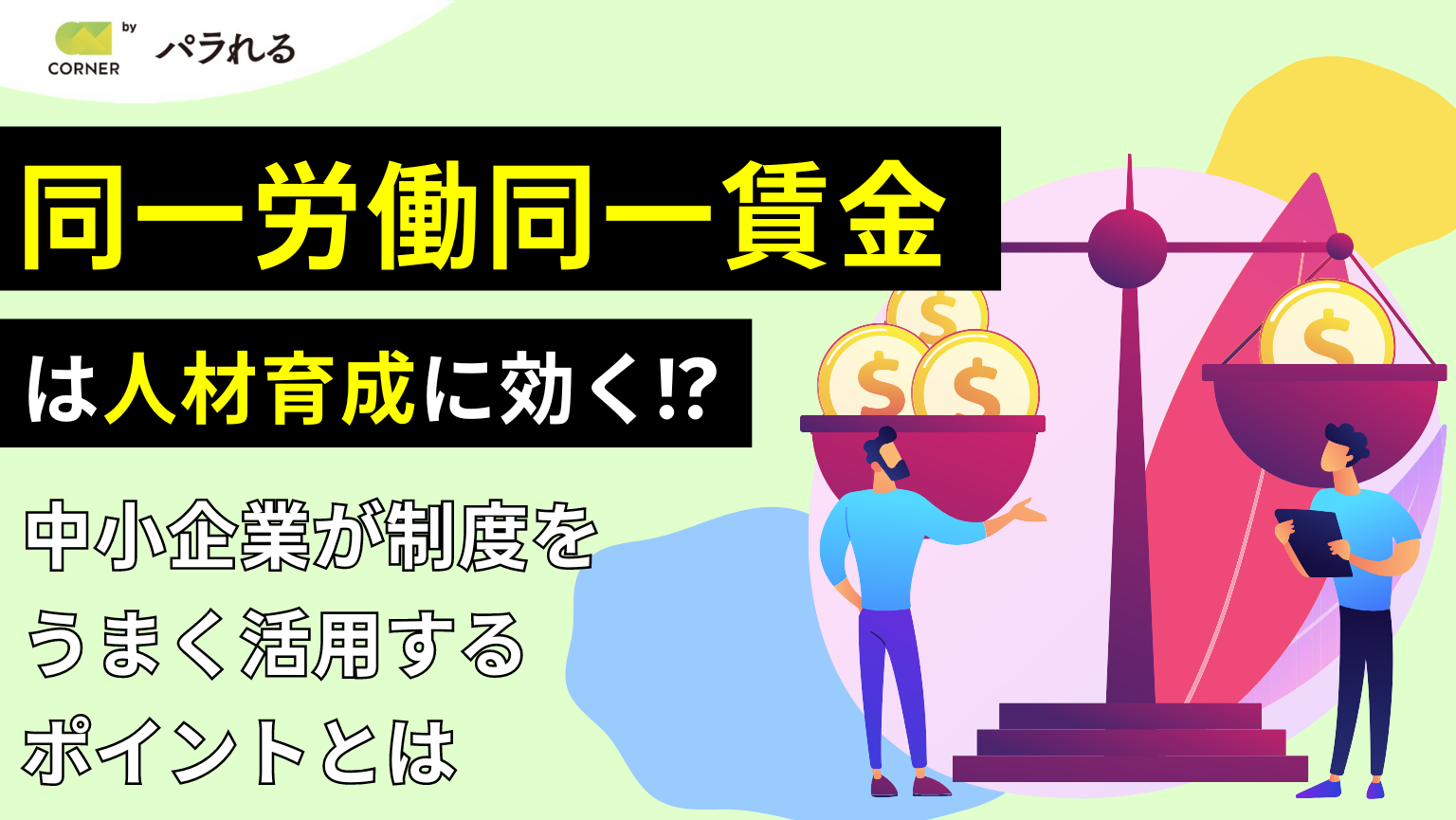
「同一労働同一賃金」は“人材育成”に効く⁉︎ 中小企業が制度をうまく活用するポイントとは
2020年4月に大企業を対象に施行された「同一労働同一賃金」が、1年の猶予期間を経ていよいよ2021年4月より中
2021.06.17

スタートアップでの採用を限られた経営資源の中で進めるための採用戦略・手法
採用難易度が年々上がるマーケット感の中、スタートアップ企業から「思うように採用ができない」という声が多く聞かれま
2021.06.15
