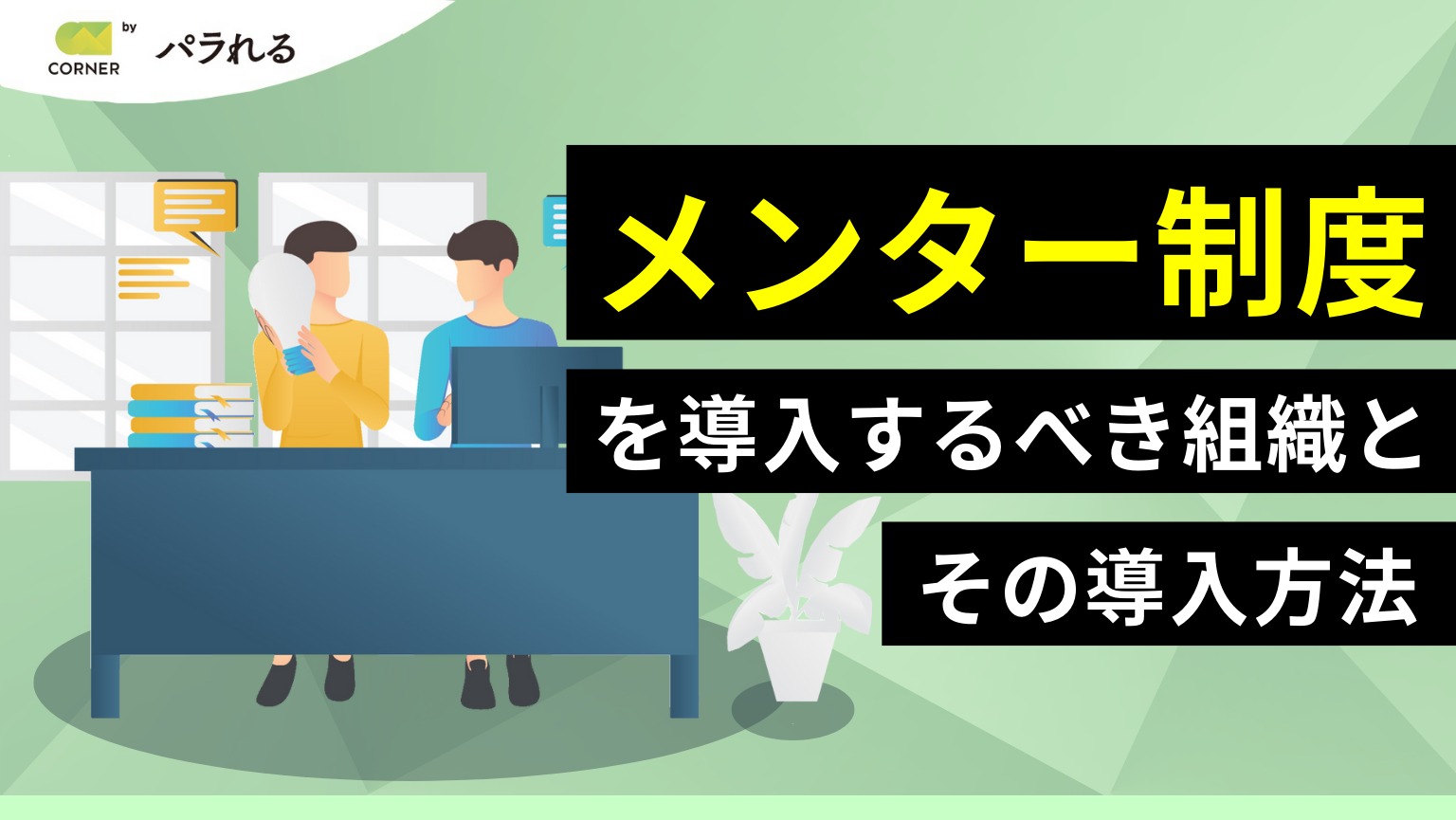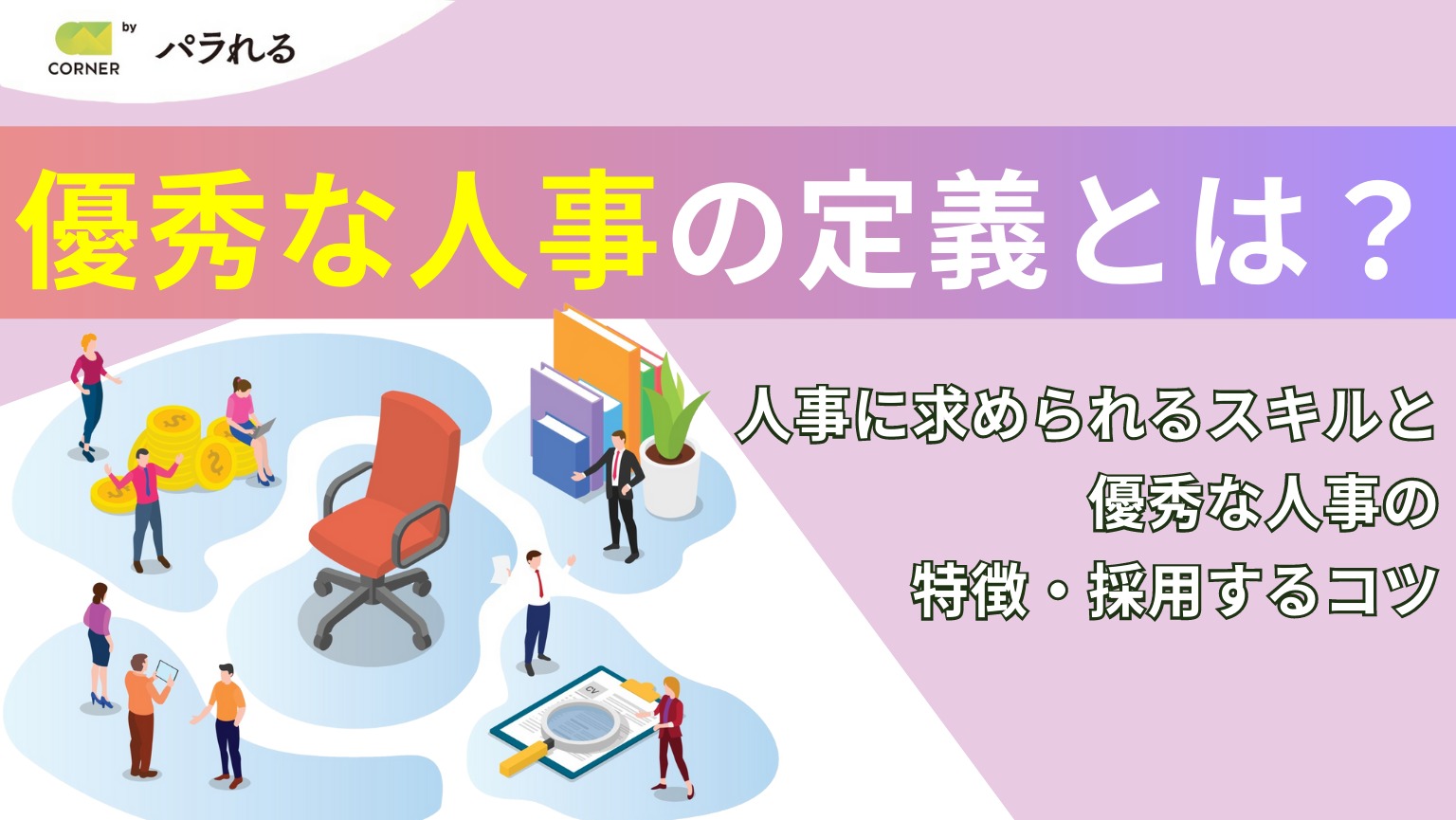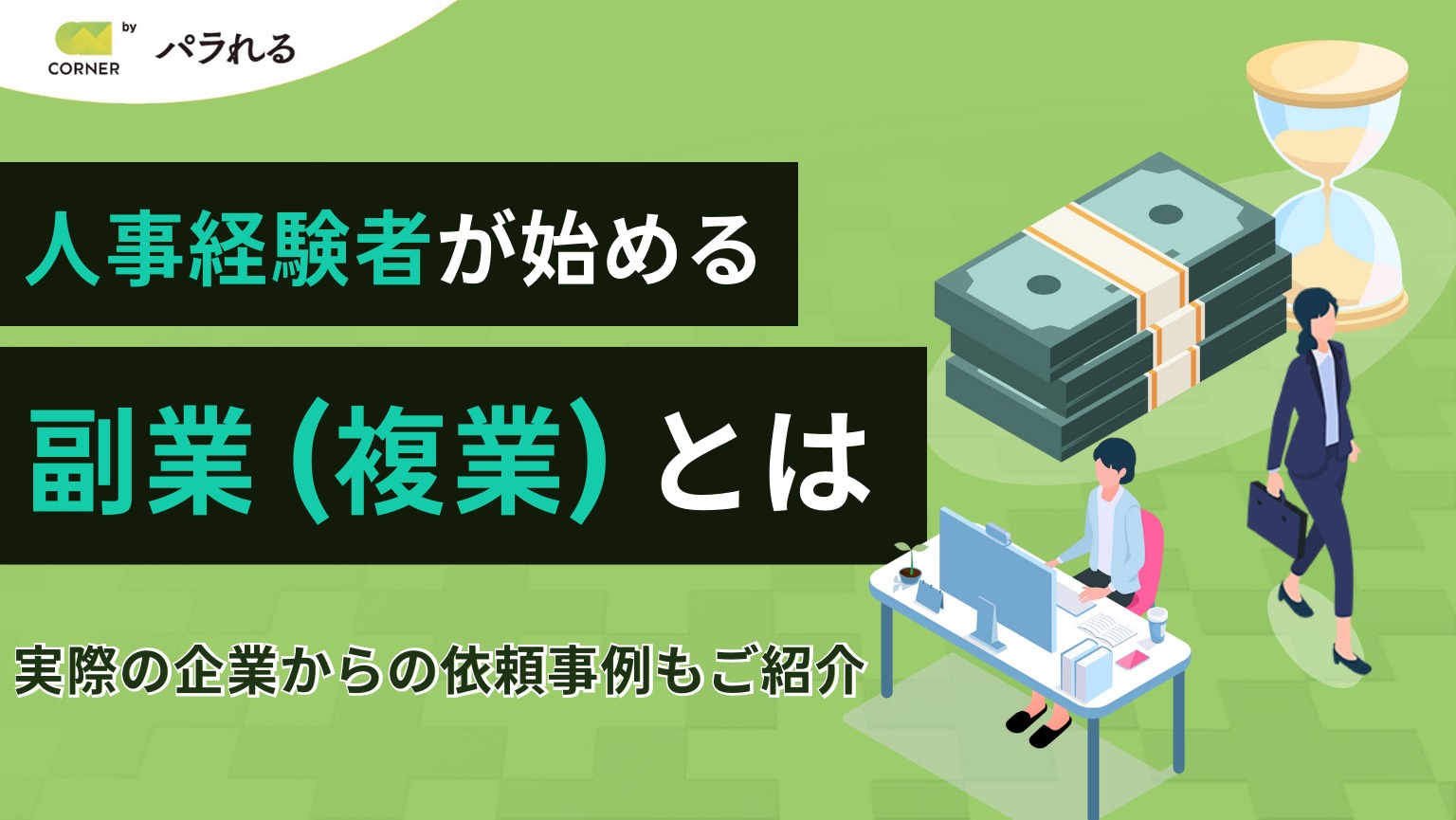変化の波を乗りこなし成果を導く力「キャリア・アダプタビリティ」の高め方
近年「終身雇用の崩壊」が進んできたことで、一人ひとりのキャリア自律の重要性が叫ばれるようになりました。そんな中「
2021.06.08


「コンピテンシー」に基づく人材開発で組織のパフォーマンスを高める方法
「コンピテンシー」と聞くと、高い業績を残している社員(ハイ・パフォーマー)に共通する行動特性を探し出し、それを組
2021.05.20
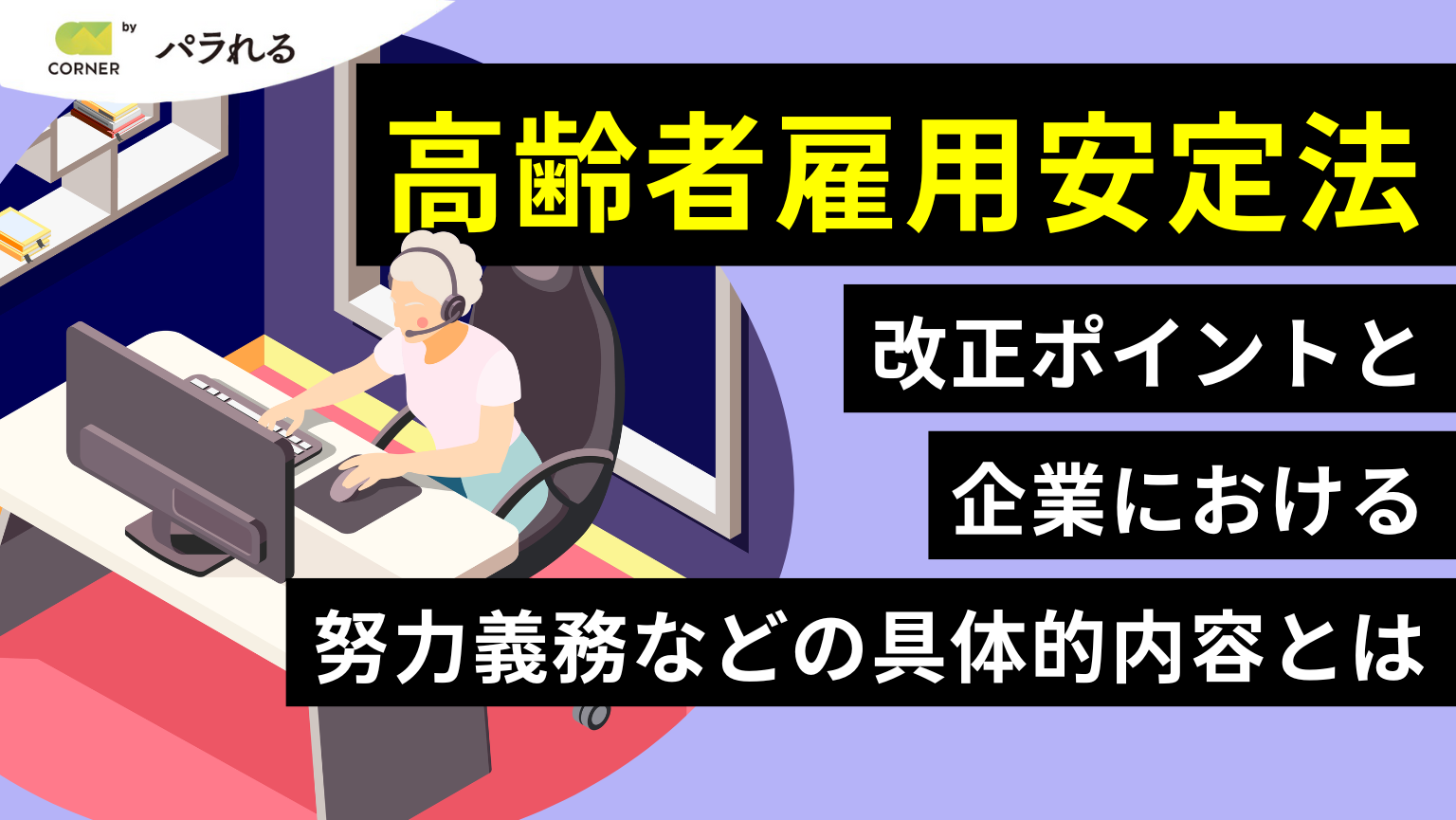
2021年4月施行「高年齢者雇用安定法」の改正ポイントと、企業における努力義務などの具体的内容とは
「高年齢者雇用安定法」の改正法が2021年4月に施行されました。「65歳までの雇用確保」からさらに一歩進み、「7
2021.05.13
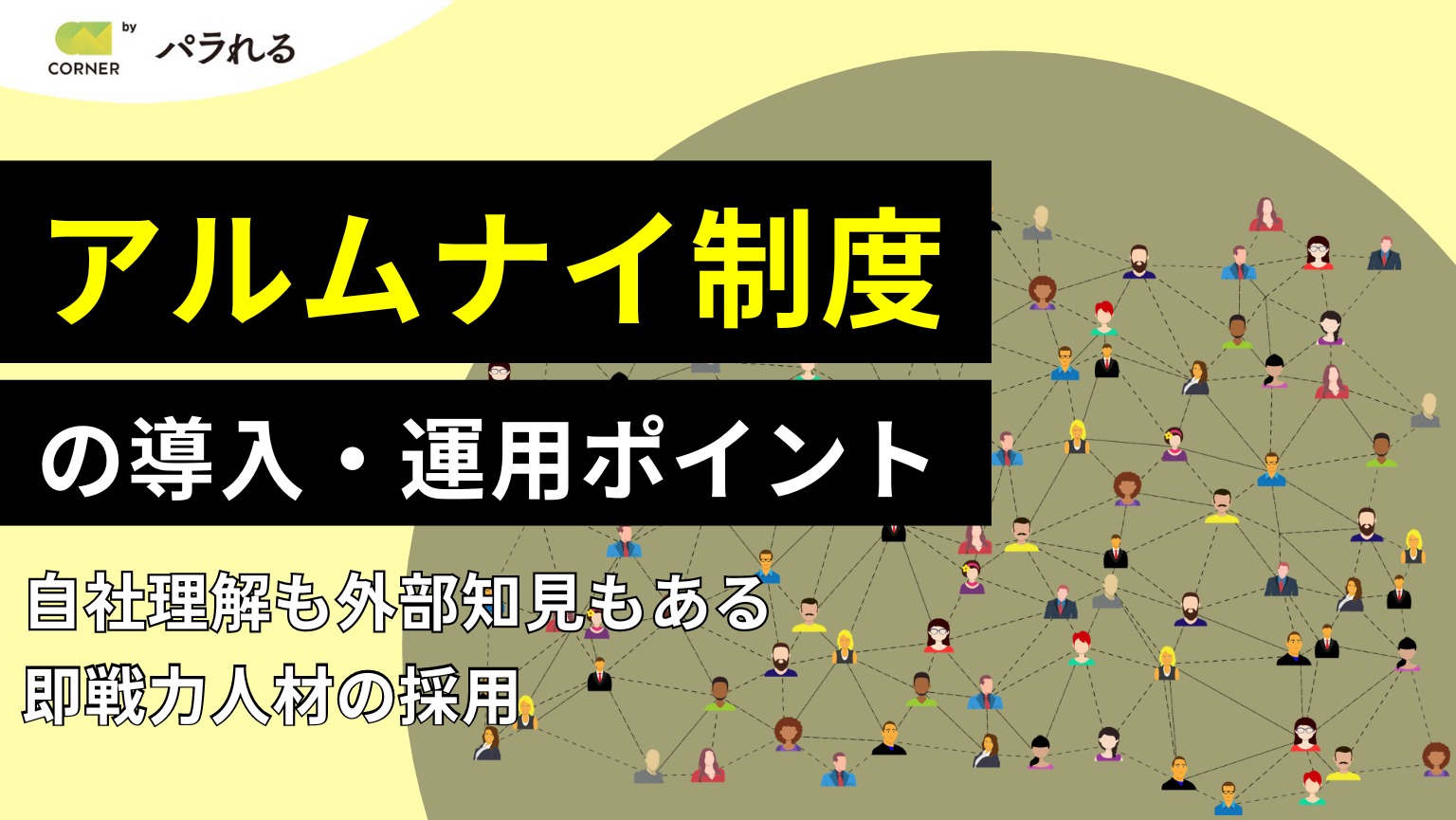
「アルムナイ制度」の導入・運用ポイント。自社理解も外部知見もある即戦力人材の採用
企業の“卒業生”との関係性を離職・退職後も保っておくことで、一度退職したメンバーを再び雇用する手法である「アルム
2021.04.13

「ノーレイティング」導入は社員の成長のため。新たな評価制度から3年経ったフィードフォースのこれまで
社員をランク付けしない人事評価「ノーレイティング」。従来の年度単位の評価やランク付けでは昨今の目まぐるしい変化に
2021.04.06

ジョブ・クラフティングを企業で実践し、社員の働きがいを高める方法とは
仕事に働きがいを求める人が増える中、「ジョブ・クラフティング」が近年注目を集めています。仕事を「やらされているも
2021.04.01


弁護士に聞いた「副業/兼業ガイドライン」の改訂背景と、人事が注意するべきポイント
副業/兼業ガイドラインの改訂が2020年9月になされました(策定は2018年1月)。その背景には「より企業人事が
2021.03.25
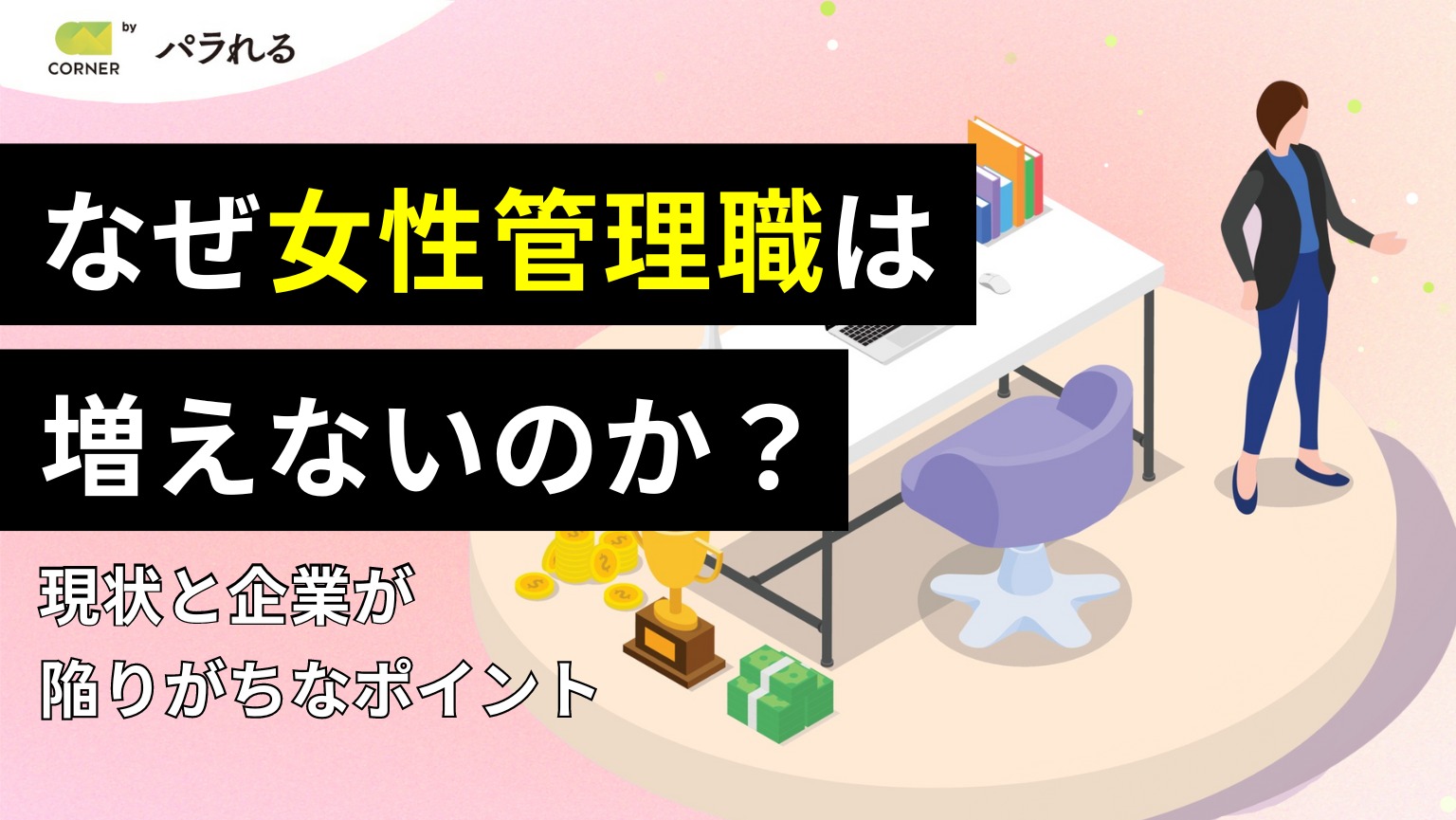

「EAP(従業員支援プログラム)」とは?定義・目的から実践方法まで解説。
「EAP」とはEmployee Assistance Programの頭文字をとったもので「従業員支援プログラム
2021.03.09

テレワーク・リモートワーク下でも機能する「BEI」による評価コミュニケーションとは
テレワーク・リモートワークへの急激な移行を受け、各社さまざまな対応を迫られている中、社員のケアやコミュニケーショ
2021.03.04

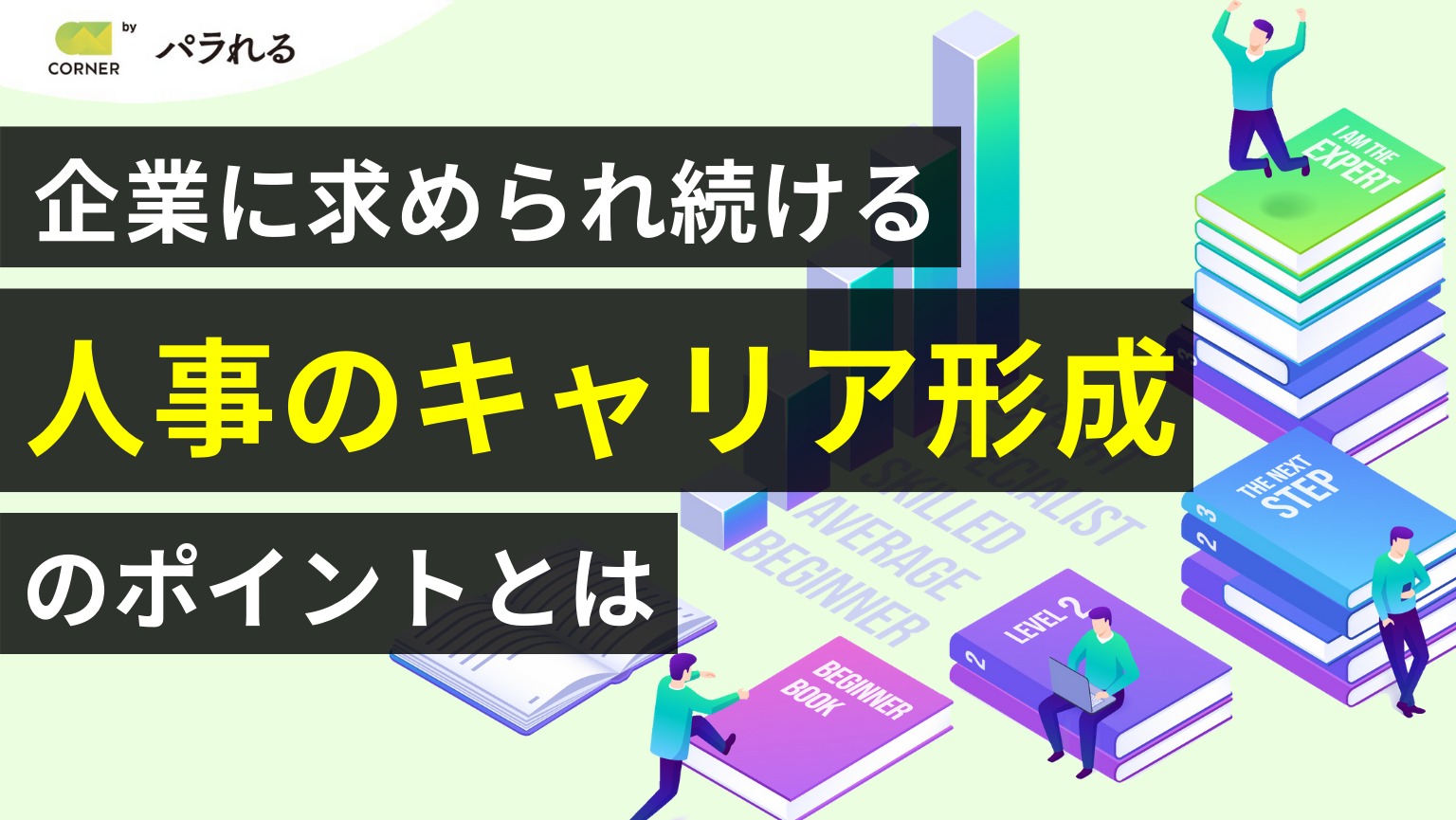
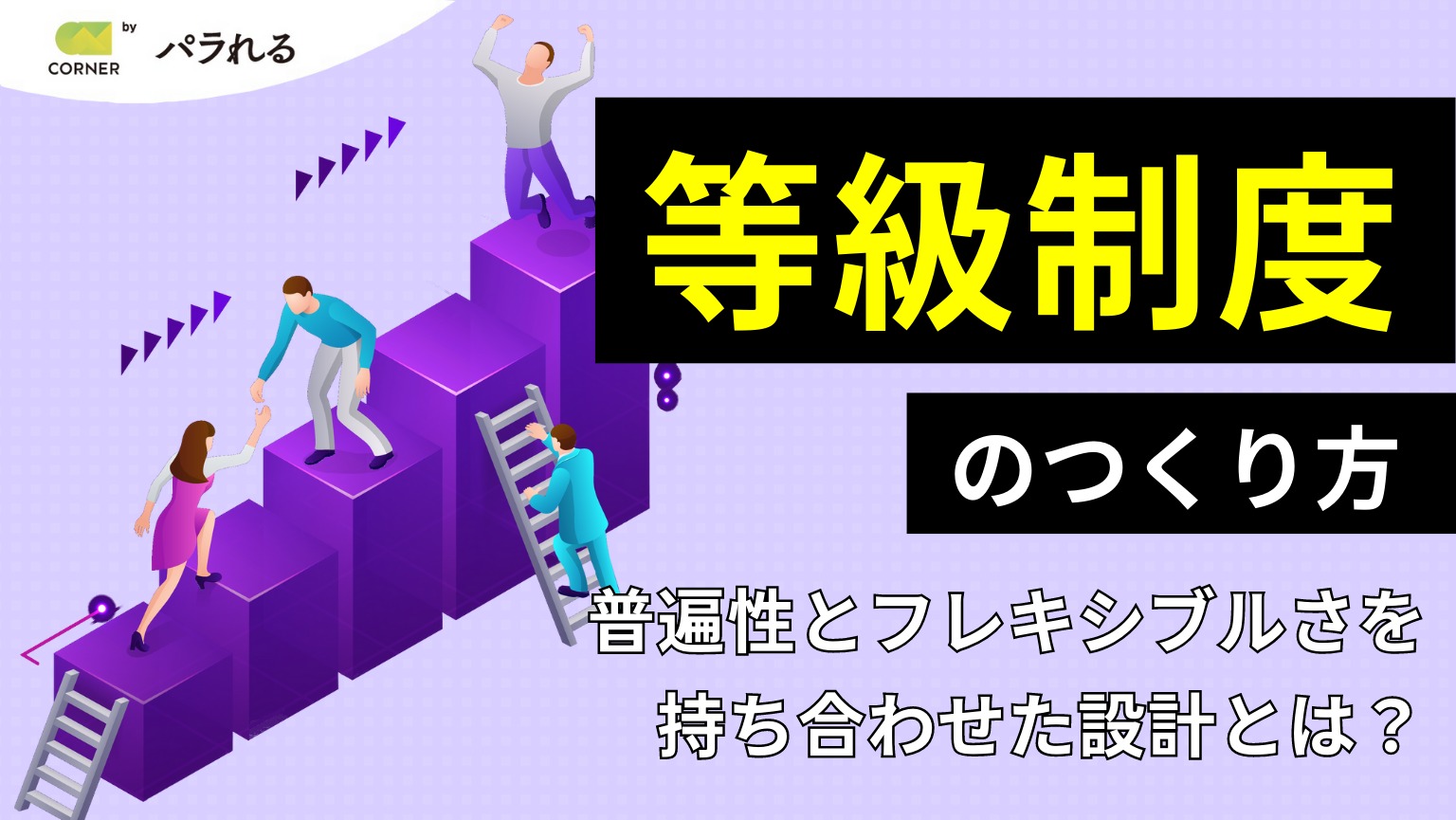
等級制度のつくり方。普遍性とフレキシブルさを持ち合わせた設計とは?
人事制度全体の骨格とも言える「等級制度」。ここが明確であればあるほど、社員はキャリアイメージを描きやすくなり、企
2021.02.16

ハイブリッドワークとは?リモートワークの先に生まれた組織の生産性を上げる方法
新型コロナウイルスの影響で導入が急ピッチに進んだリモートワーク。昨年度の緊急事態宣言が明けてからは、リモートワー
2021.01.12


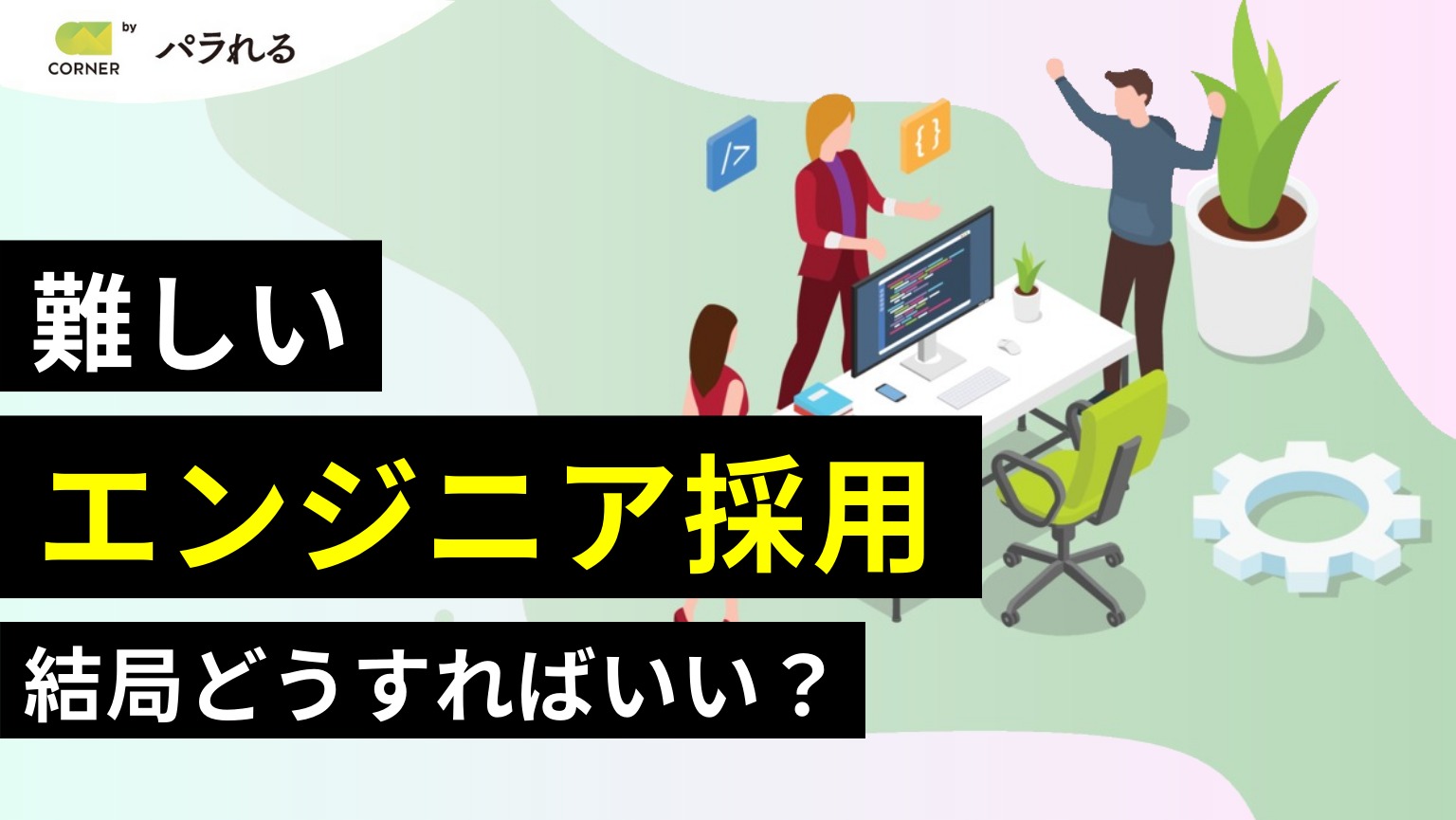
難しいエンジニア採用、動向と手法を解説。エンジニア採用に強い媒体12サービスも紹介。
「ITエンジニアの採用は難しい」 実際に求人倍率が高まり続ける中、あらゆる採用ツールを使っても狙った層からの応募
2020.12.03

社員の能力を最大限引き出す、オンライン/オフラインでの階層別研修の在り方
「新入社員研修」や「管理職研修」など多くの企業で導入されている階層別研修ですが、本来の目的やメリット・デメリット
2020.12.01
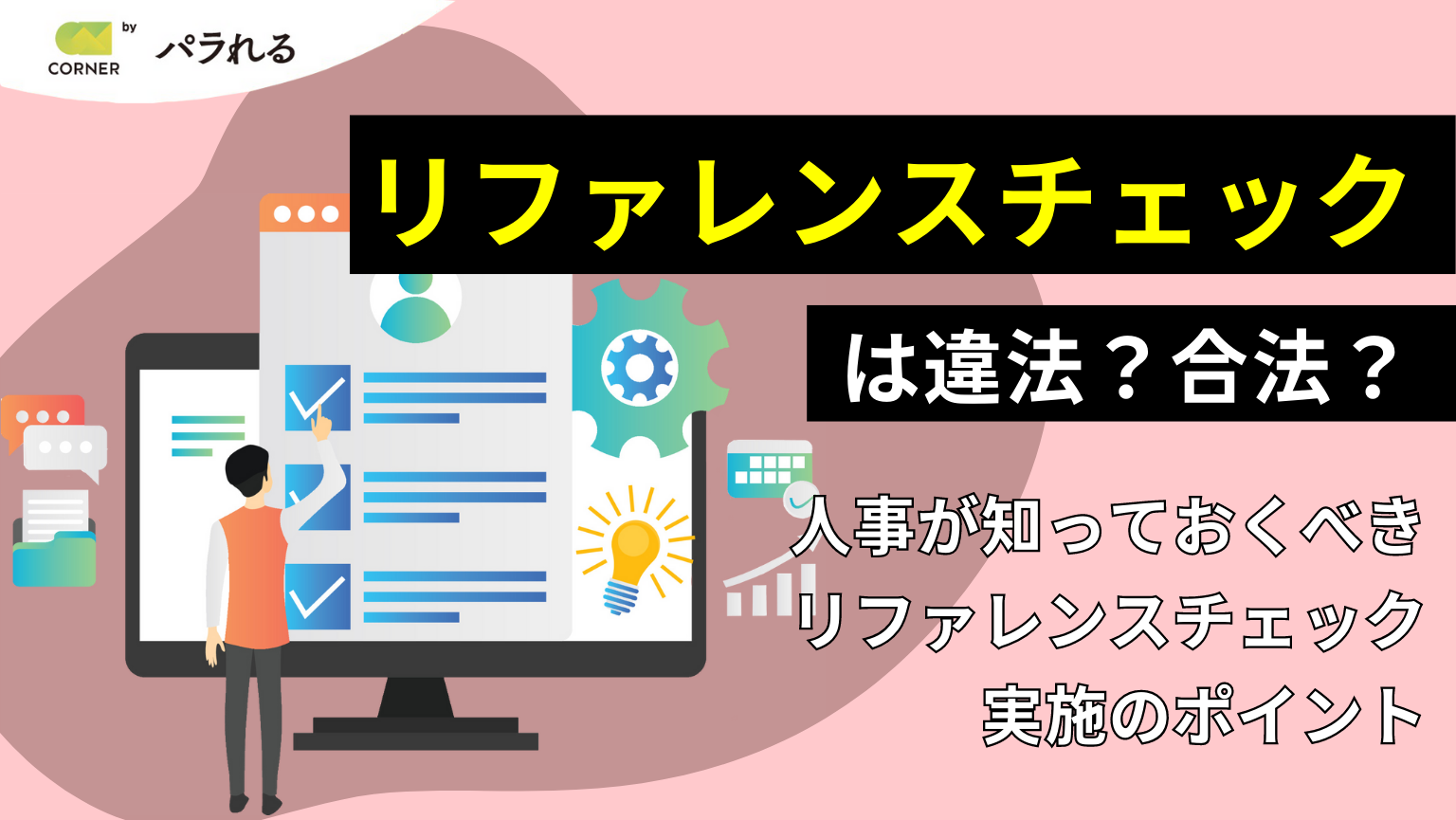
リファレンスチェックは違法?合法?人事が知っておくべきリファレンスチェック実施のポイントとは
外資系企業では当たり前のように実施されてきたリファレンスチェック。日本でも早期離職やミスマッチを防ぐ方法として徐
2020.11.26

戦略的タレントマネジメントとは?決して「従業員を管理する」だけの手法ではない。
従業員の持つ能力(タレント)に着目し、戦略的な人材配置や育成などを行う人事マネジメントを総称して「タレントマネジ
2020.11.24
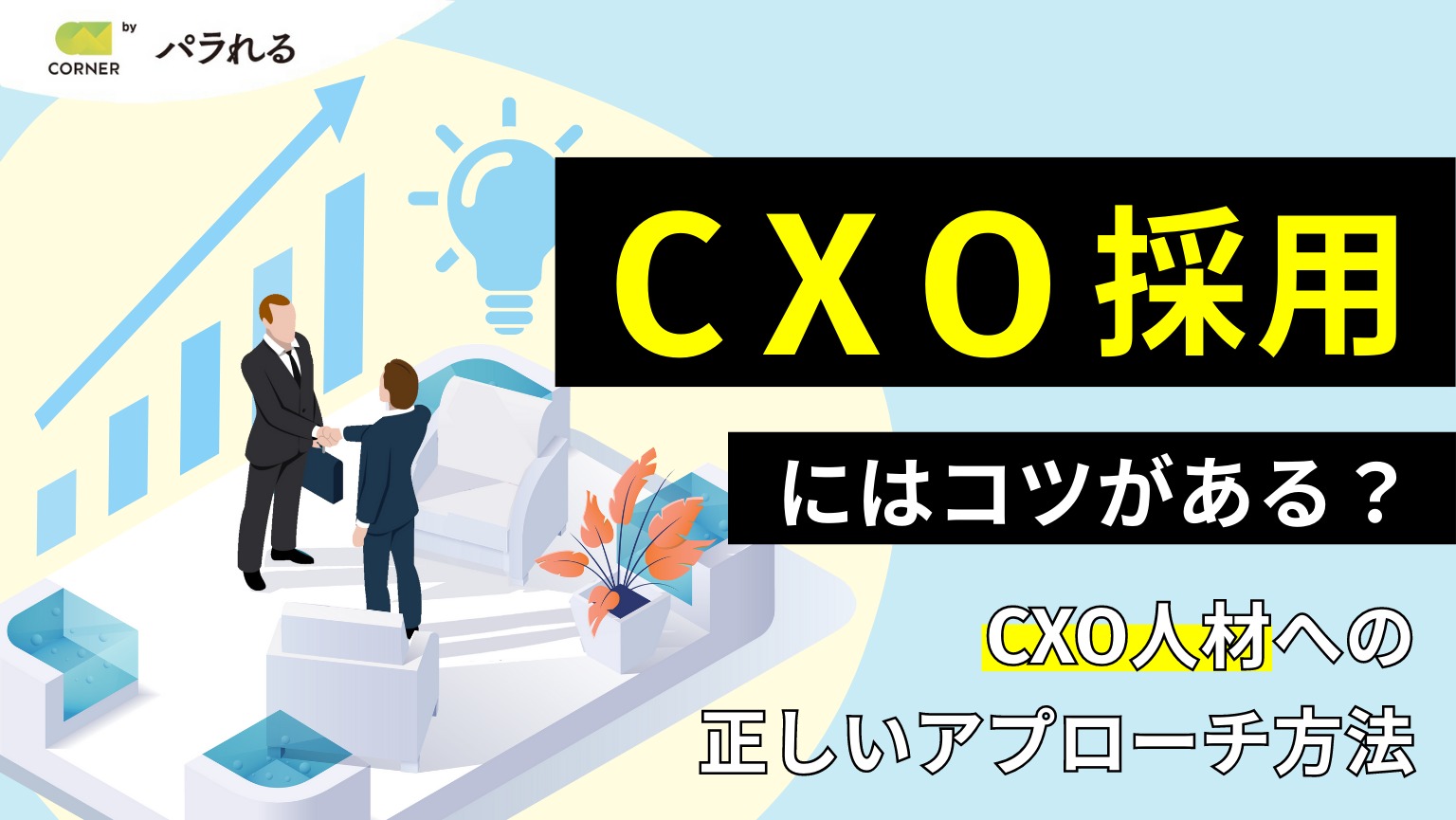
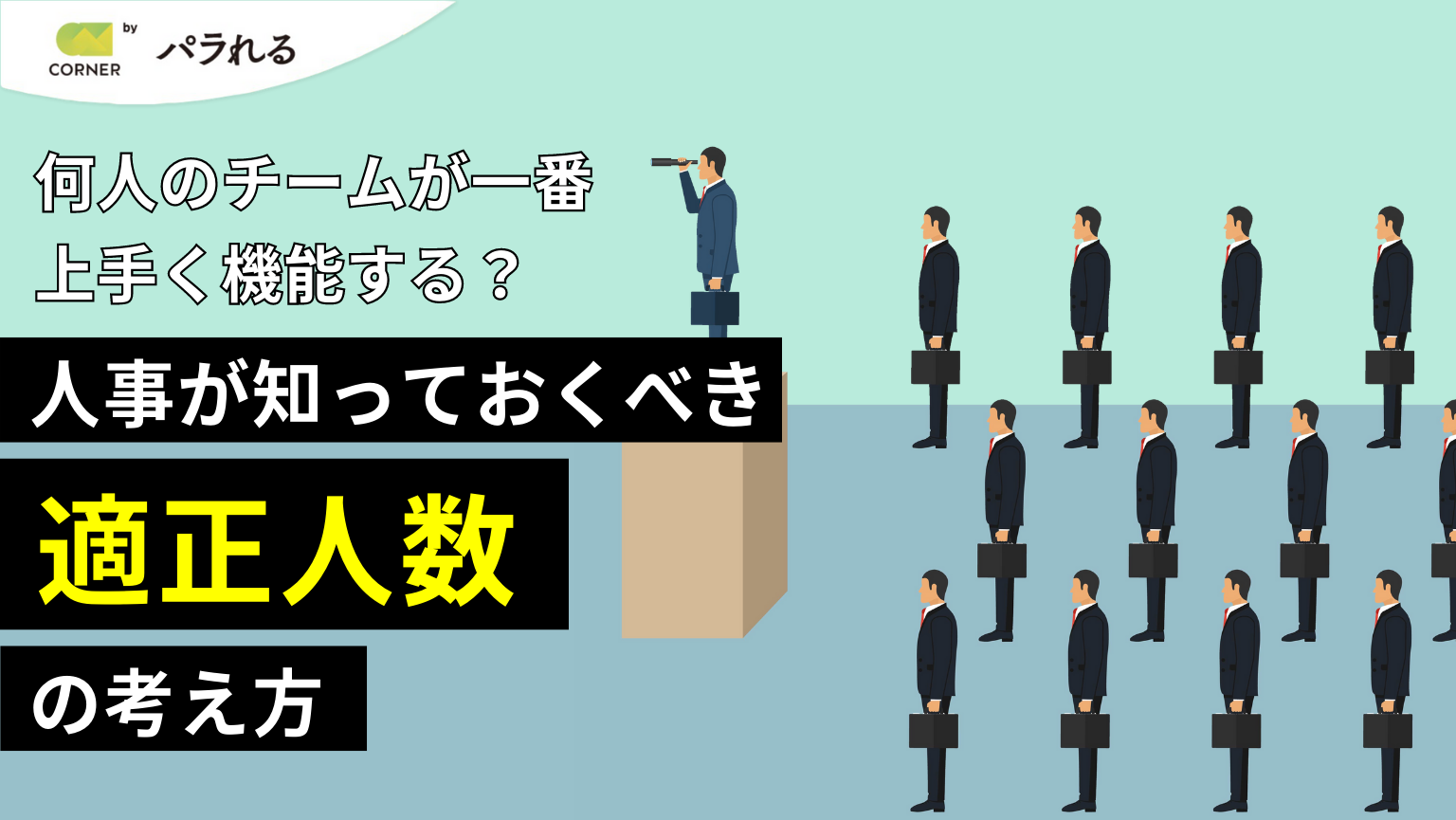
何人のチームが一番上手く機能する?人事が知っておくべき「適正人数」の考え方
マネージャー(上司)が直接管理できる人数を定義する考え方を「スパン・オブ・コントロール」と言います。 米Amaz
2020.11.10
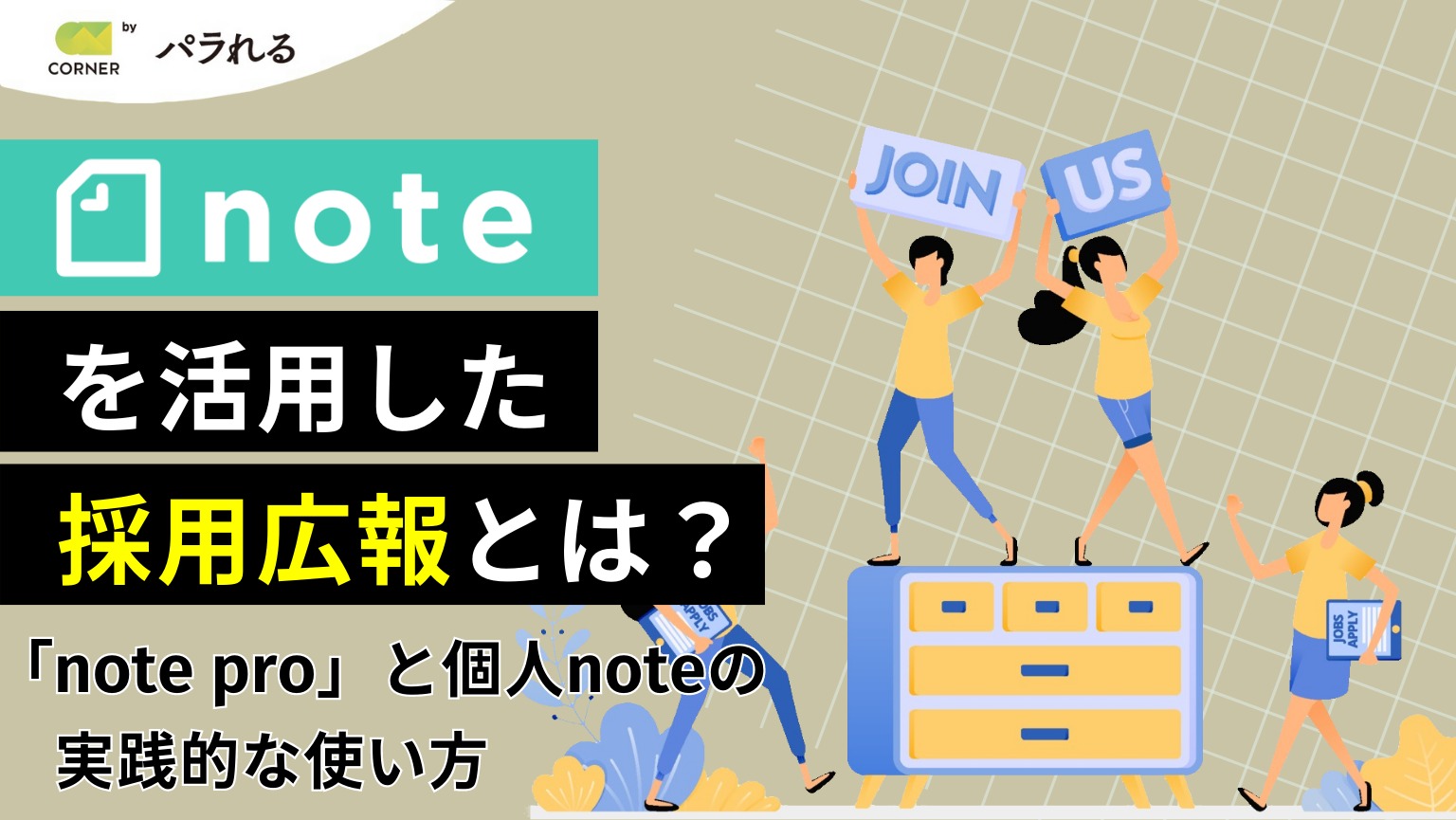
noteを活用した採用広報とは?「note pro」と個人noteの実践的な使い方。
採用広報と言えば一昔前まではHPが一般的でしたが、最近ではnoteやWantedlyなどSNSを活用して発信を行
2020.10.29

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)とは?作り方と効果の具体例
皆さんは、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)と聞いて何を思い浮かべますか?「うちの会社にもあるけど、誰も覚
2020.10.13


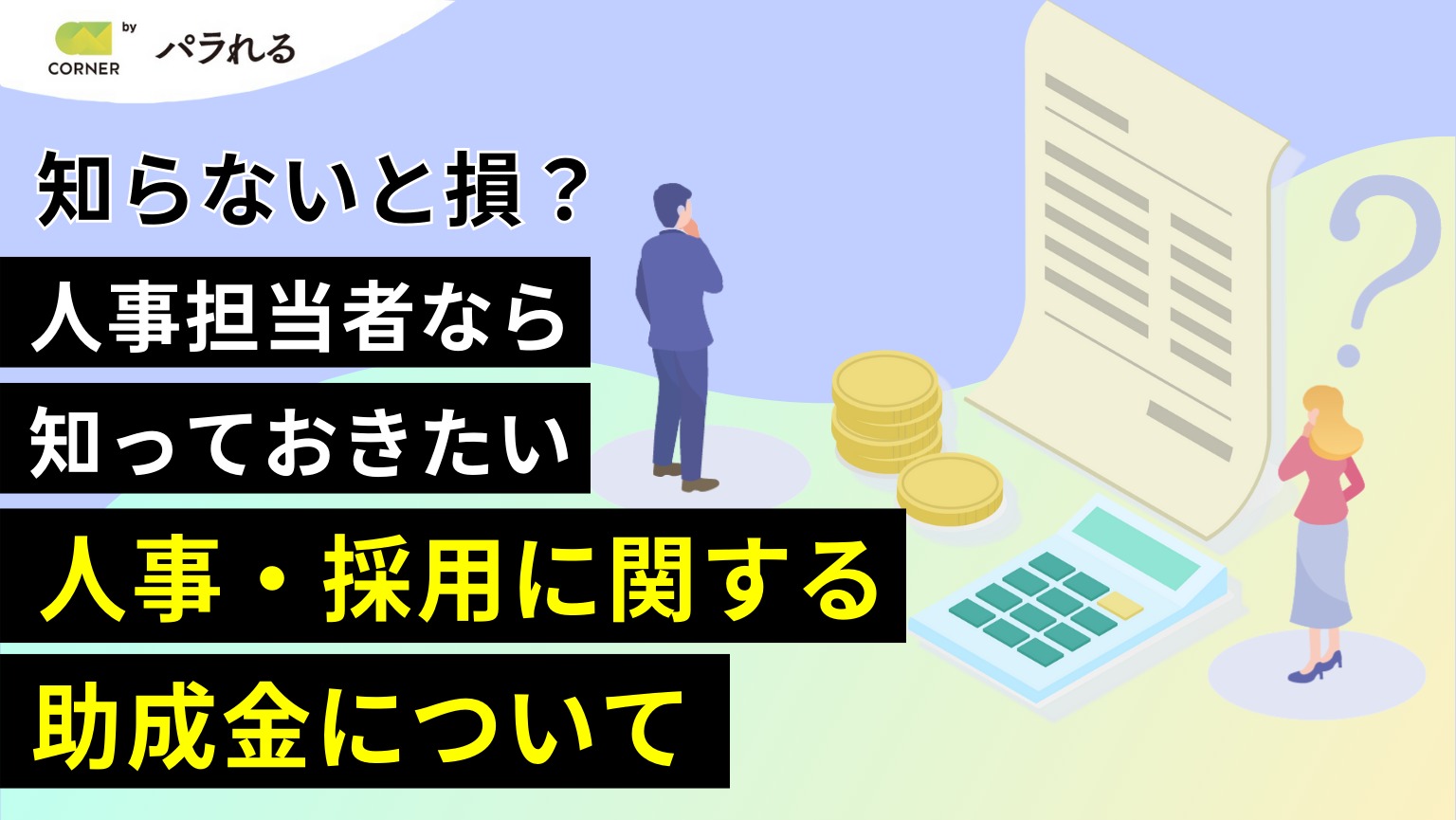
知らないと損?人事担当者なら知っておきたい「人事・採用に関する助成金について」
「雇用の促進・維持」や「人材確保」に積極的な取り組みをする企業に対して、国はさまざまな助成制度を用意し、資金面で
2020.09.17

その1on1ミーティング、本当に効果がありますか?効果的な運用と事例紹介
1on1ミーティングとは上司と部下が1対1で行う面談のことで、人材育成を目的としています。1on1と略されること
2020.09.10



「ピープルアナリティクス」の実践内容を知り、KKD(勘・経験・度胸)だけの人事から卒業するには
データを使って仕事の成果を高める流れは一般的になりつつありますが、人事領域に関しては、「ヒト」という感情や身体な
2020.09.01

戦略的な採用マーケティングとは?採用CX(候補者体験)から考える実践方法
採用活動をマーケティングとして捉え、データやテクノロジーを活用することで候補者との適切なコミュニケーションを設計
2020.08.18

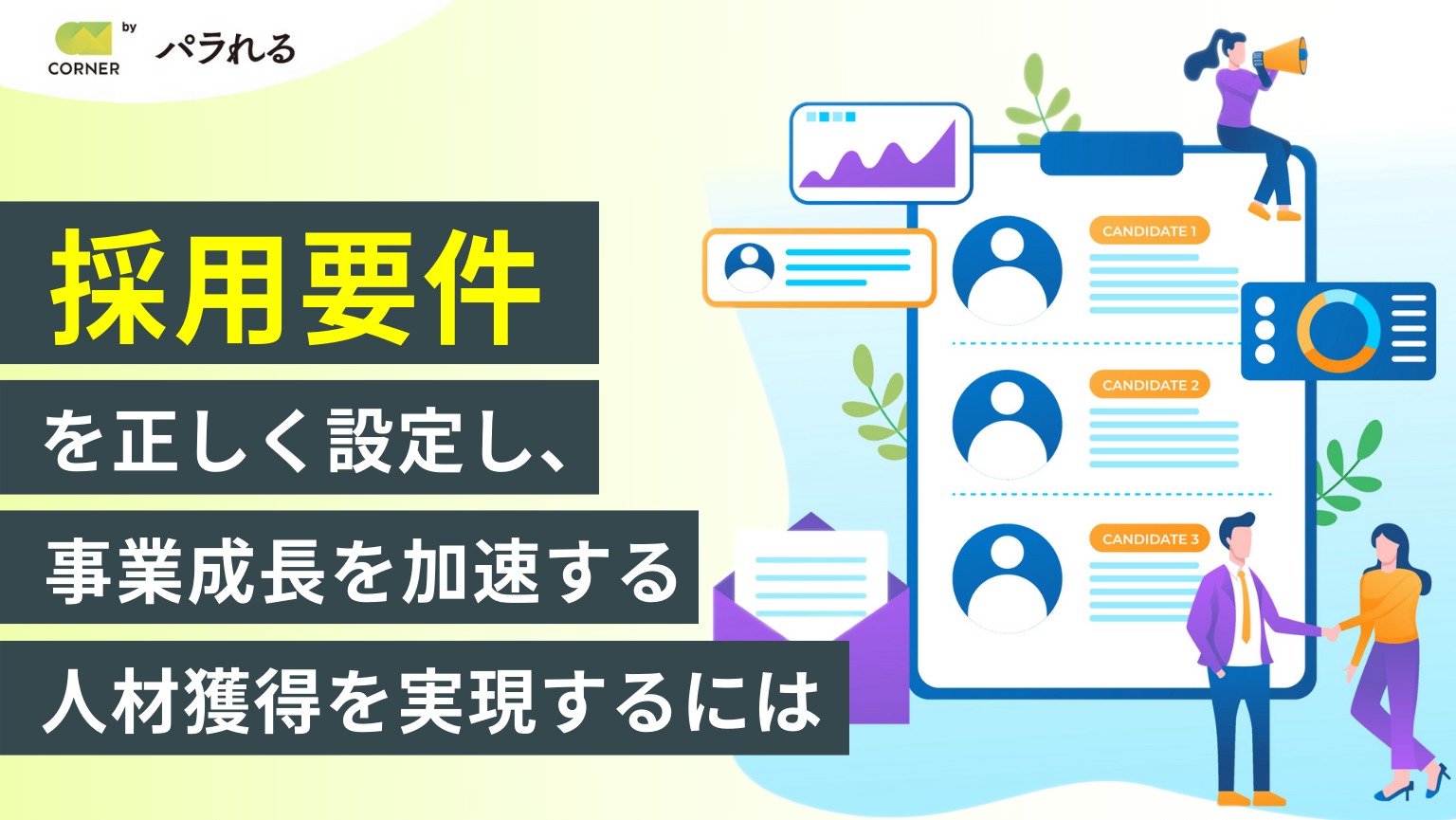
「採用要件」を正しく設定し、事業成長を加速する人材獲得を実現するには?
経営や現場側からの「こんな人を採用したい!」と要望を元に採用活動をスタートしたものの、思うような人材を採用できな
2020.08.04
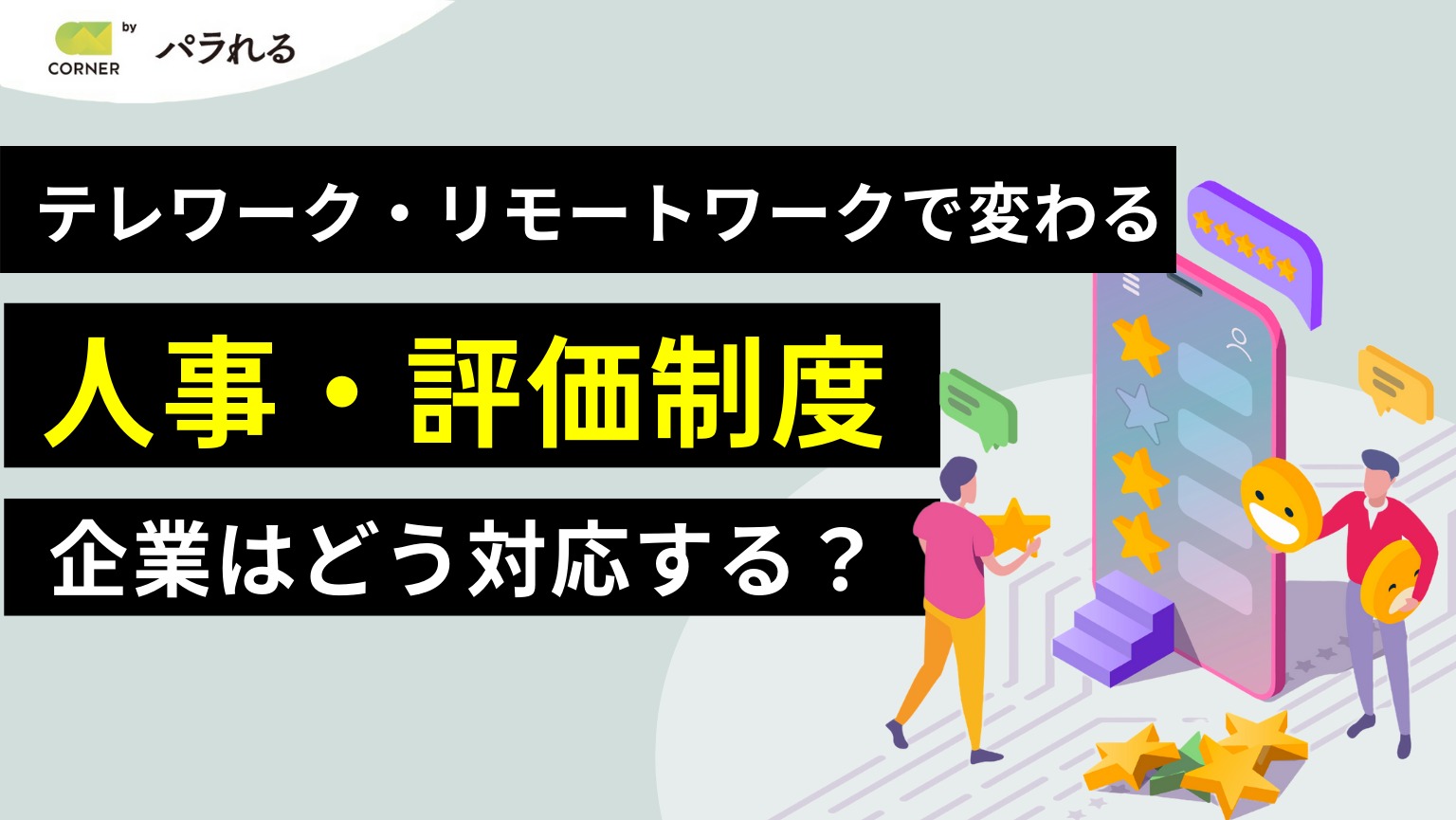
テレワーク・リモートワークで変わる人事評価制度。企業はどう対応する?
緊急事態宣言が発令・解除を繰り返す中、各社では働き方が大きく変化しており、その一つがテレワーク・リモートワークへ
2020.07.30
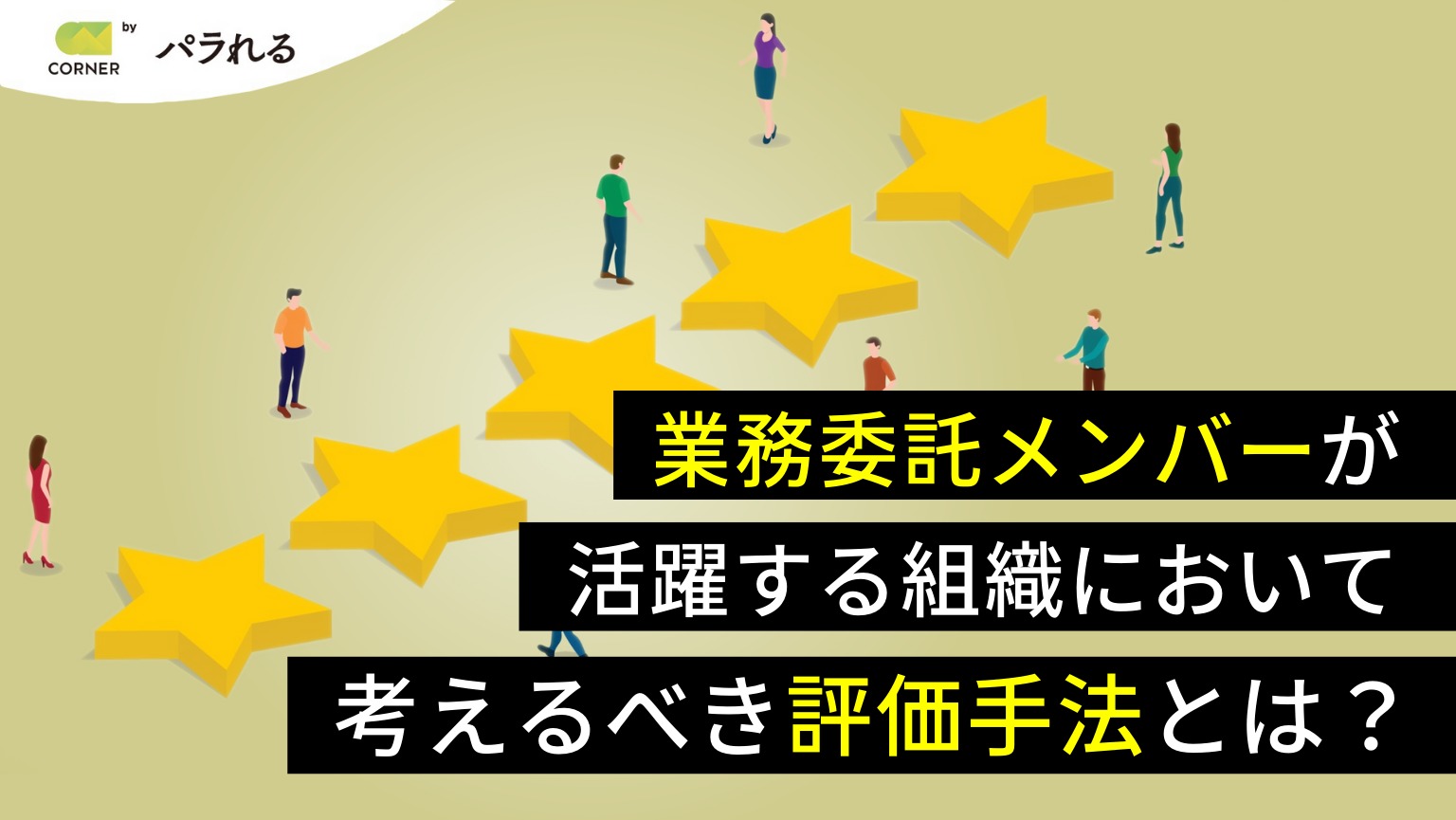

オンボーディング成功のポイントは「ユーザー視点」。押さえるべき点と事例紹介
新たに採用したメンバーが早期に活躍できるよう、組織としてサポートする「オンボーディング」。もともとは船や飛行機に
2020.07.21
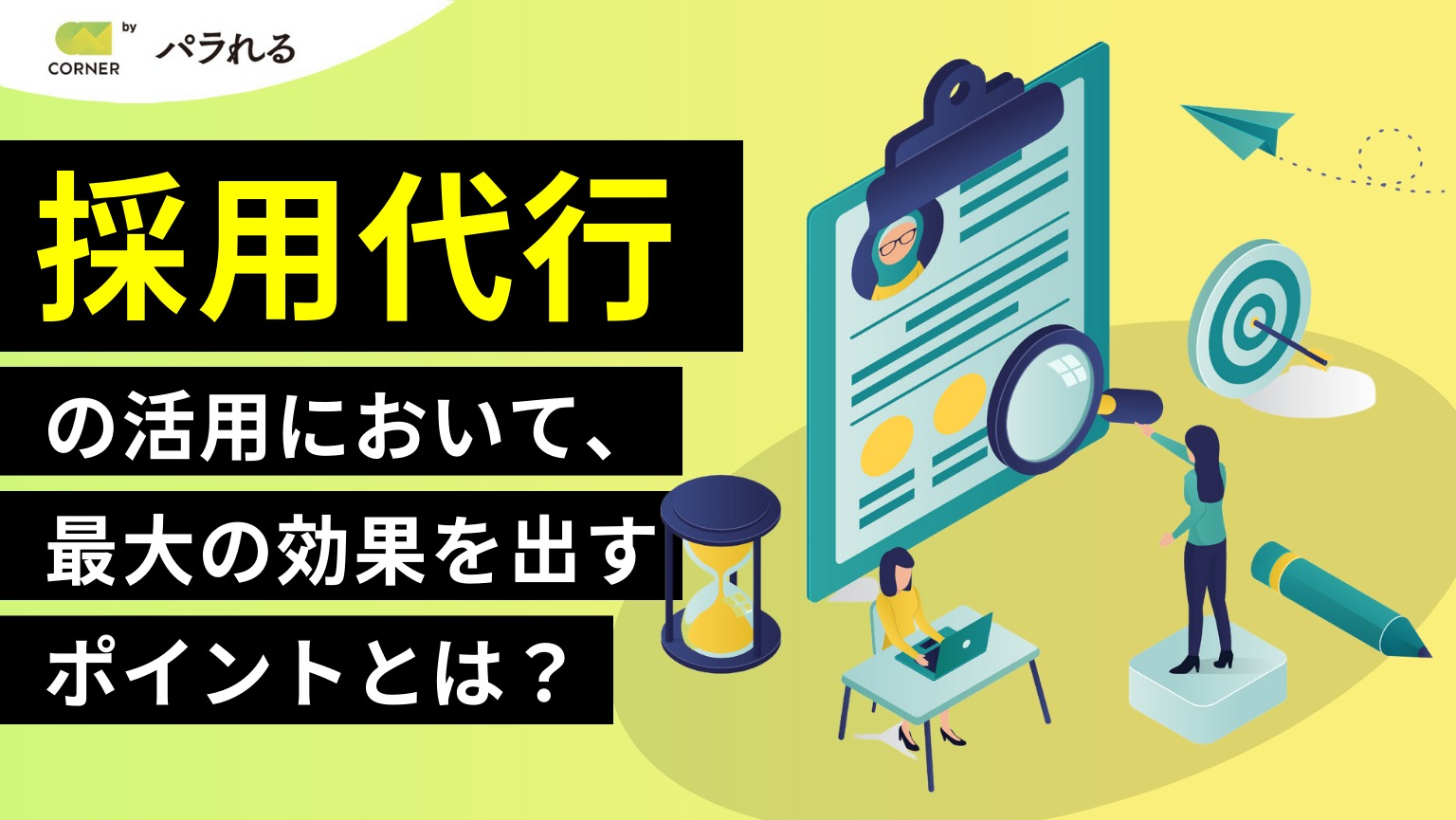
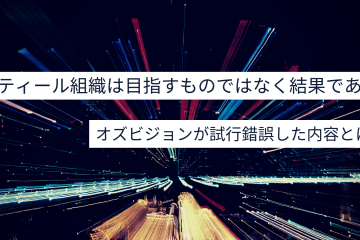
「ティール組織は目指すものではなく結果である」オズビジョンが試行錯誤した内容とは?
※2021年1月9日更新 ティール組織とは、個々の社員が意思を持ち、組織目的の達成に向けて変化し続けることができ
2020.07.14


「チームビルディング」をテレワーク・リモートワーク下で成功させるために必要なこと
新型コロナウィルスによる緊急事態宣言をきっかけに、テレワーク・リモートワークを導入する企業が増えました。また、S
2020.06.30

「OKR最大の効果は、対話型組織の開発にある!?」実践者に聞いた、OKR導入・運用の心構えと実例
GoogleやFacebookといった世界的企業をはじめ、国内でもメルカリなどが積極的に取り入れて注目を集めるO
2020.06.25

HRBPの具体的な実践内容を理解し、経営と事業のパートナーになるには?
※2021年4月9日更新 海外企業から広がり、国内ではYahooやDeNAなどのインターネット系企業でも推進され
2020.06.23
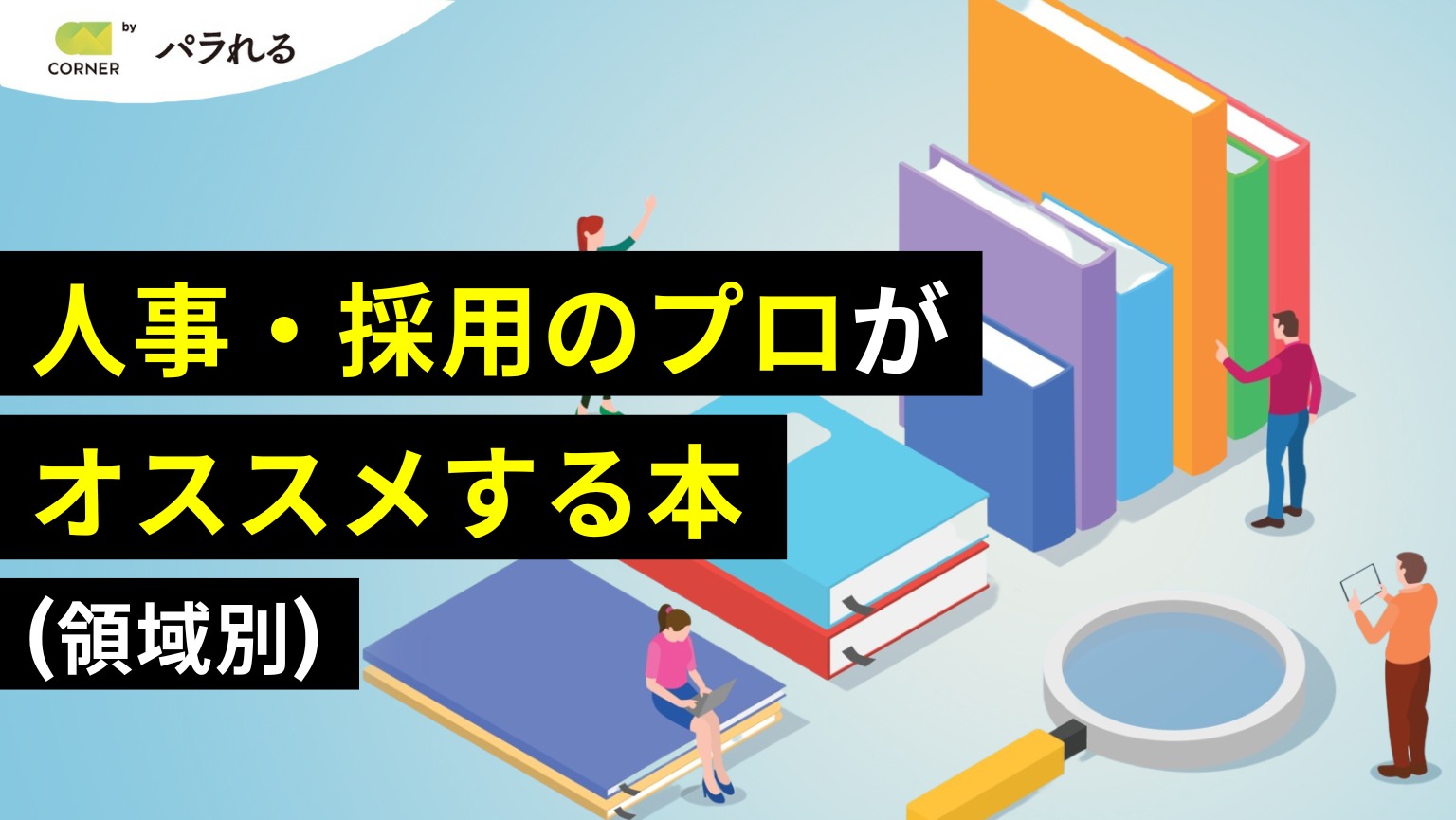
【2023年良書41冊】人事・採用のプロがオススメする本(領域別)
ヒト・モノ・カネなど経営資源の中でも、「ヒト」を一番の経営課題として捉える企業も増えてきた昨今。人事部門が担う役
2019.12.26
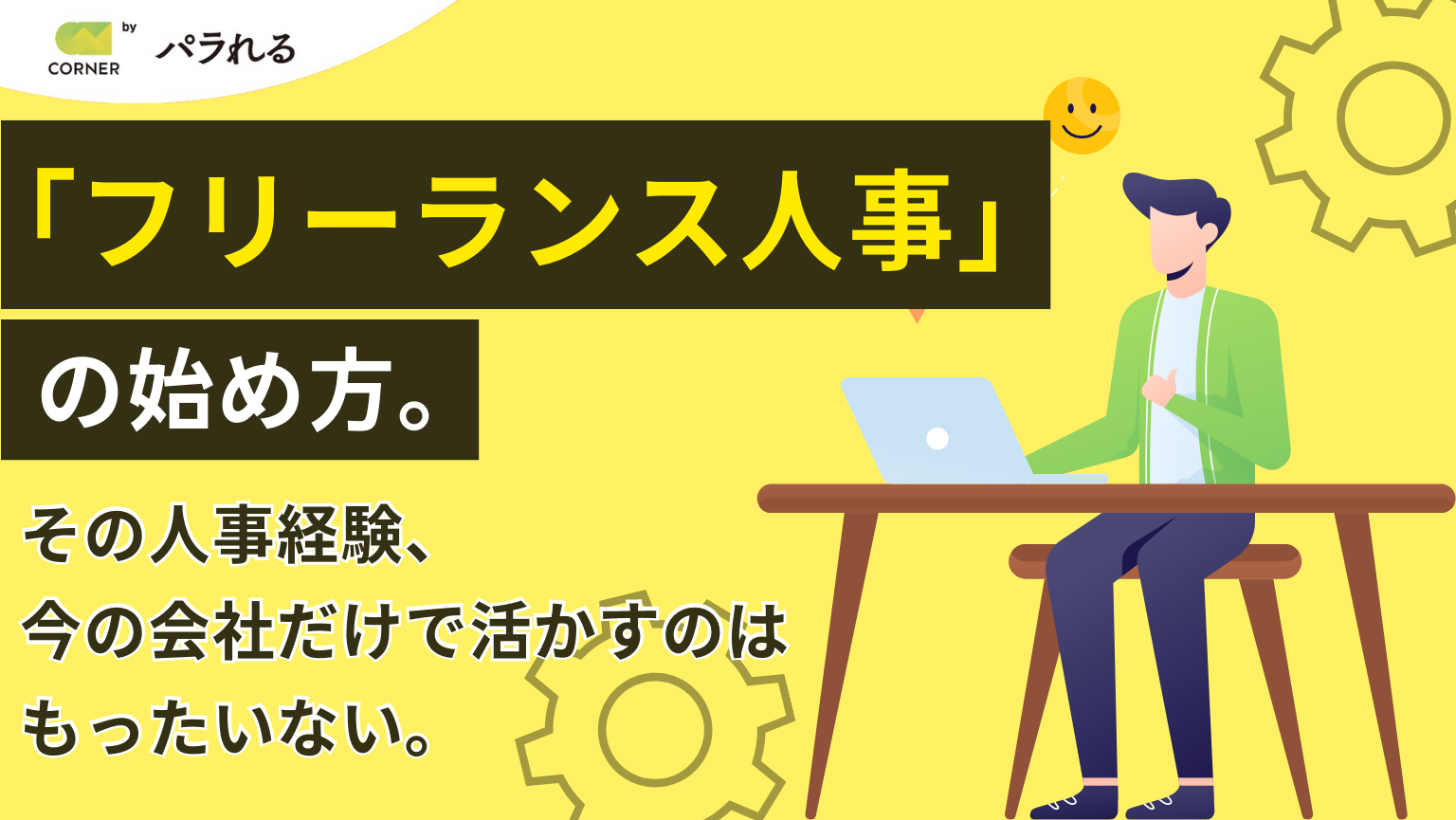
「フリーランス人事」の始め方。その人事経験、今の会社だけで活かすのはもったいない。
※更新:2023年10月6日 人事・採用の複業ならコーナー:登録はこちらからhttps://pws.corner
2019.11.22

大量のルーティン業務にサヨナラ。「採用代行」のうまい活用方法と選び方
売り手市場が続く中、採用担当者の業務範囲や量は増え続ける一方です。 そんな中注目されているのが「採用代行」。採用
2019.10.25

目的や専門性に合わせて選ぶ、「専門副業(複業)マッチングサービス5選」
近年、副業(複業)をテーマとしたニュースが増えてきました。実際に、副業(複業)で本業以上の稼ぎを得ていたり、3~
2019.10.04

求人広告や人材紹介だけに頼らない。自社採用力を高める「採用マーケティング」の始め方
最近、「求人広告や人材紹介だけでは採用が難しくなってきた」という話をよく聞くようになりました。 今やネットを検索
2019.09.26