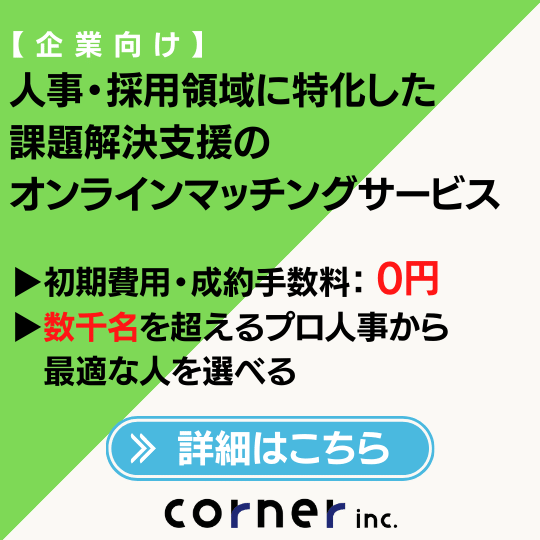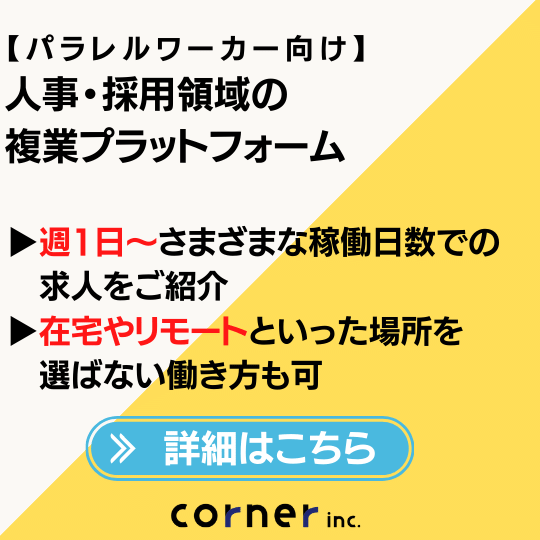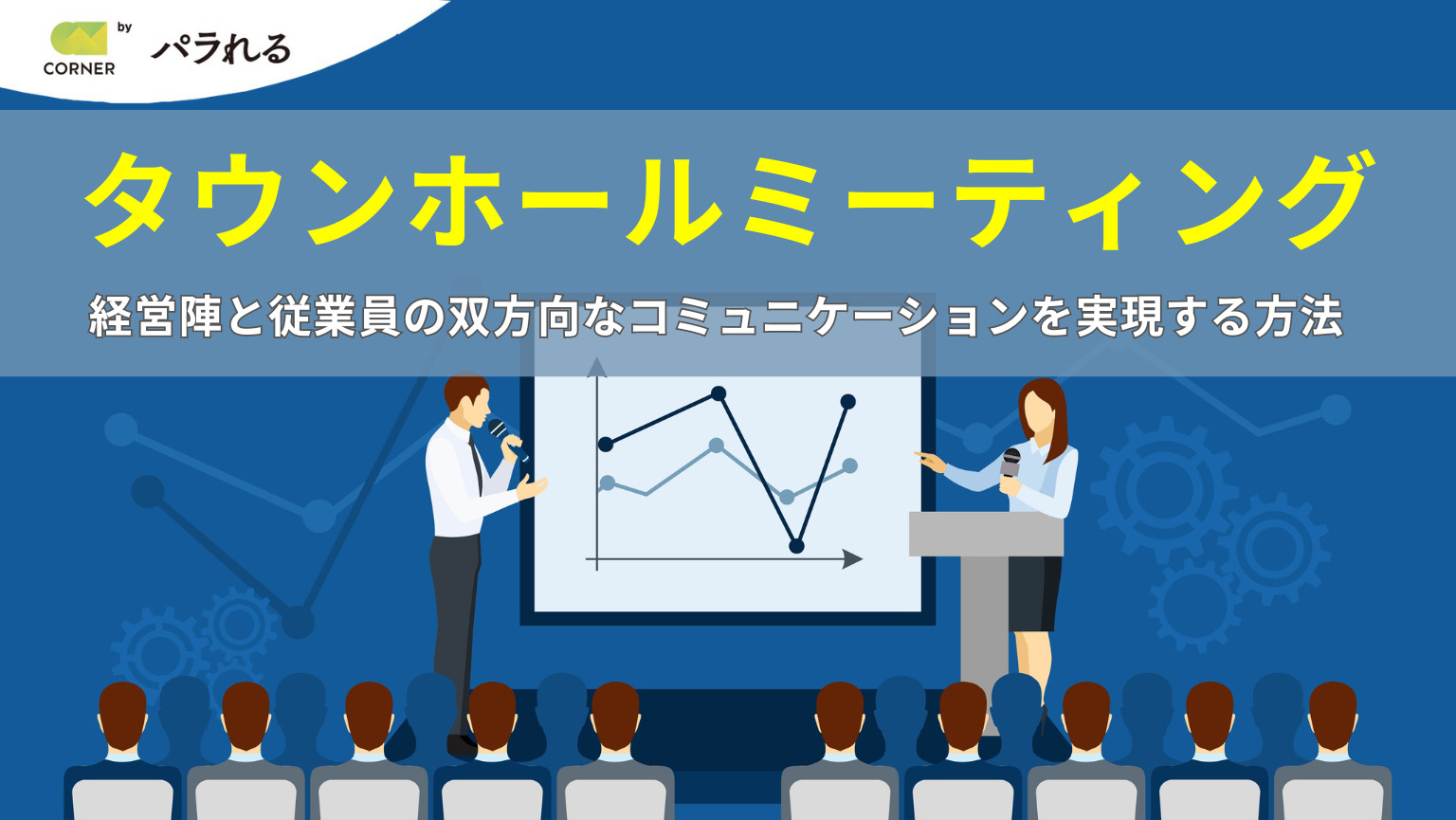“課題解決に直結する” あるべき採用KPIの設計・運用方法とは

KPI(Key Performance Indicator)を掲げ、採用管理に活用する企業が増えています。すでに一般化しているとも言えるほど浸透しているKPIですが、採用活動の成果に直結していると自信を持って言える採用担当者はそれほど多くないのではないでしょうか。むしろ、誤ったKPIマネジメントにより採用活動に支障を及ぼしているケースもあるようです。
そこで今回は、これまでインターネット系企業の人事部の立ち上げや、IPOに向けた人員強化をしているベンチャー企業など、組織拡大フェーズにおける採用戦略に関わってこられた三井祐典さんに、適切にKPIを機能させ、採用をドライブさせるために必要なポイントをお話いただきました。
<プロフィール>
三井祐典
人材エージェントを経て、人事コンサルタントとして活躍したのち、インターネット系ベンチャーの人事部へ常駐。一人目の人事として新規事業責任者からコーポレートの部長候補まで幅広い採用課題と組織課題の解決に貢献。その後、東証一部上場企業の人事マネージャーを経て、人事コンサルとして現職に参画。急成長中のエンタメ企業の業務改善PMと人事部門の立ち上げ、採用までを一貫して担当。
▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
採用戦略におけるKPIの効果とは
────採用戦略のPDCAを回すにあたり、KPIはどのように役立つでしょうか?
まず大切なこととして、KPIだけを設定しても役には立ちません。最初にKGIを明確にしてこそ、KPIを設定する意味が生まれます。
KGIとは、Key Goal Indicator(キー ゴール インジケーター)の略。「経営目標達成指標」と訳され、企業の経営戦略やビジネス戦略の最終目標が達成されているかを計測するための指標のことです。
例えば、100名以下のベンチャー企業で採用戦略を考える時に置くべきKGIは、「課題解決のために、求めた人材が入社し、定着し、パフォーマンスが発揮できている」状態と考えます。
仮に応募者数や入社数などのKPIが達成していたとしても、KGIに近づいていなければ、そもそも課題解決に結びつきません。
ちなみに私の経験上、だいたいKGIに対しては80%位が着地点になることが多いです。もちろん100%が最高であり、それを求められるのですが、なかなか難しいのも事実です。
────KGI→KPIの順番が大事ということですね?
その通りです。KGIを決めたうえでKPIを考えていかないと「経営、事業運営の課題にコミットできていない、上辺だけの結果につながらない採用戦略」になってしまいます。
また、採用単体ではなく組織全体の課題を抽出し、それに対して人事の観点からKGIを設定する「全体を俯瞰する姿勢」も必要です。
KGIを明確にすれば、”課題解決に向けてのボトルネックがどこにあるのか”という視点でKPIを設定できるため、組織全体の課題改善の役に立ちます。
採用活動におけるKPI設計のポイント
────採用のフローにおいては、どのように考えるべきでしょうか?
採用においてKPIを置く点は、「スカウト返信、書類通過、面接調整、面接合格、内定、承諾、入社、定着、活躍」などがあります。
例えば先ほどの「課題解決のために、求めた人材が入社し、定着し、パフォーマンスが発揮できている」状態をKGIとした場合に、上記点のどこがボトルネックになっているかを調査し、そこを重要KPIにします。
そして、重要KPIに置いたポイントの改善点を分析していきます。例えば以下のような形です。
1:スカウトの応募率
ここがボトルネックになっている場合、風評被害や広報に問題の可能性がある。
2:内定承諾
選考辞退が多い場合、面接官の面接方法や事業理解に問題の可能性/ESの不足(従業員の不満が外部に漏れている)の可能性がある。
3:活躍
パフォーマンスが上がらない社員が多い場合、採用ミスマッチの可能性/マネジメントに問題の可能性がある(その場合、組織バランスを考え、ペルソナを書き換えたほうが良いかもしれません。)
4:定着
早期離職が多い場合、目標設定や受け入れ体制に問題の可能性がある(せっかく入社した大事なメンバーを放置してしまっているかもしれません。)
上記は一般的な例の一部でしかありませんが、ポイントは問題を把握した上で、課題の解決に向けてプロジェクトを組むような他部署を巻き込む動きを取ることです。
採用活動におけるKPIを改善するための具体的な施策

────改善が必要な場合の打ち手・施策としては、どのようなことを行うべきでしょうか。
課題を発見し、解決に向けてアクションを取っているにも関わらず、数値に変化がないor悪化している場合は、アクションが間違っているということです。
気をつけるべきは、原因の発見は”事実に基づいて多方面から行う”ことです。
例えば面接場面での不合格が多い場合、担当面接官は「応募者が自社の風土やレベルにマッチしない」という反応をしますが、それは事実でしょうか。
検証をせずに安易に「求める応募者のレベルを上げる」ことに取り組んでも、課題解決には結びつかない可能性が高いと言えます。
この場合は少なくとも以下の3パターンは想定できると思います。
①経営が考える事業部の問題と事業現場が求める問題がぶれているかもしれない。(経営と現場のコミュニケーション、感じている課題の違い)
②担当面接官の視座の不足かもしれない。(使いやすい部下を取りたいという思考の切り替え=マネジメント育成)
③レジュメや応募者の質問が深堀りできず、スキルの見極めができていないだけかもしれない(面接官トレーニングや構造化面接)
思考や立場、時には利害や政治なども関係しているケースもありますので、根気よく原因を探しながら解決に向けてPDCAを回していくことが重要です。
プロが実践する採用KPIの管理・運用事例
────これまで実践されたことがある、採用におけるKPIの管理・運用方法について具体的に教えてください。
採用戦略を考える時、既存社員の昇格・異動は必ず考えなければなりません。
・人を採用した方が良いのか
・昇格させた方が良いのか
・異動させた方が良いのか
事業現場に何が足りないかを考え常に情報を集めておく必要があり、その考えに基づいて以下のような運用を行うことが多いです。
1.採用管理システムからCSVをダウンロードし、社員管理のスプレッドシートシートやシステムと連携
・母集団形成〜内定承諾までの数値、選考日数、採用コスト管理
・中途入社と昇給を踏まえての人件費(原資)を見積もった人件費管理
2.スプレッドシートを使って見える化
・組織図と定期的な面談の議事録を使い、定着とES、パフォーマンスの見える化
ツールに関わらず重要な点は、採用におけるKPIだけでなく、既存社員のデータと合わせて運用することです。
また本来は、内定承諾時から日々の業務を経て社員の能力や思考(志向)がどう変わっているのか、入社前〜入社後の変化を一連で蓄積できる状態が理想と考えています。
例えば定期的に1on1を実施している企業であれば、活用している面談シートに課題とビジョン、志向などを記入する欄を用意し、その推移を追いかけていくような事が考えられます。
しかしスピードが早いベンチャー企業では年単位でキャリアビジョンの変化を追うことが難しく、この点については、まだまだ私自身試行錯誤中です。
採用活動におけるKPIについて学べるお薦め本
────採用KPIについて学びたいと思っているHRパーソンに向けて、お薦めの書籍があれば教えてください。
戦略参謀の仕事/稲田 将人(著)
原因の分からない課題に直面をしてモヤモヤした時に読み直すと、モヤモヤの理由が「ああ、これこれ。」と見つかる時があります。参謀としての立場で何を見つけ、どう考えて動き、何を低減するか。インプットだけではなく、アウトプットをする際にも大変参考になります。

あなたがデキる人か否かを決めるのは、人事部です。/三冨 圭(著)
少し昔の書籍(2012年初版)ですが、人事としてのフレームを見直す時や立場を忘れそうになった時など、今でも定期的に読み直しています。
小説風に書かれており、フィクションです。(少し背筋が寒くなる内容です)
組織人事として何を問題として捉えるか、どう考えるか、どのように解決するか。経験した仕事が増える度に、違った捉え方や理解ができて参考になります。
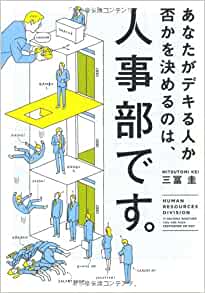
■合わせて読みたい「採用手法・ノウハウ」関連記事
>>>「採用代行」の活用において、最大の効果を出すポイントとは?
>>>「採用要件」を正しく設定し、事業成長を加速する人材獲得を実現するには?
>>>戦略的な採用マーケティングとは?採用CX(候補者体験)から考える実践方法
>>>SNSを活用したタレントプール形成・採用力強化の方法
>>>CXO採用にはコツがある?CXO人材への正しいアプローチ方法
>>>難しいエンジニア採用、動向と手法を解説。エンジニア採用に強い媒体12サービスも紹介。
>>>「アルムナイ制度」の導入・運用ポイント。自社理解も外部知見もある即戦力人材の採用
>>>スタートアップでの採用を限られた経営資源の中で進めるための採用戦略・手法
>>>グローバルで戦える企業へ。「高度外国人材」採用のメリットと活躍・定着へのポイントとは
>>>Z世代の採用手法は違う?Z世代人事に聞く、採用やオンボーディングに活かす方法
>>>オンライン化するだけではダメ。ニューノーマル時代の「オンラインインターンシップ」とは
>>>「ジョブディスクリプション」の導入・運用実態と事例について
>>>「外部登用」をうまく活用して組織力を高めるためには
>>>「通年採用」がこれからのスタンダードに?行政の動きからメリット・デメリットまで解説
編集後記
KPIは数値管理のイメージが強くありましたが、三井さんは「何が課題かを常に意識し考えながら、事業現場の理解と共感、意見をすることが大切」と強調されていました。
KPI=「机上で数値を追いかける」という認識ではKPIマネジメントの落とし穴にはまってしまう危険が高そうです。そうならないためにも、組織全体を俯瞰したうえで課題を抽出し、KGIを設定することが採用KPIを始める第一歩と言えそうです。
自社のKPIに関して、もう一度上記の観点で見直しをしてみてはいかがでしょうか。