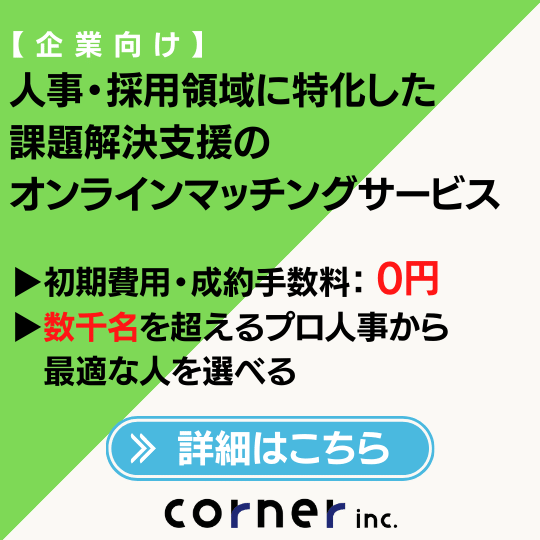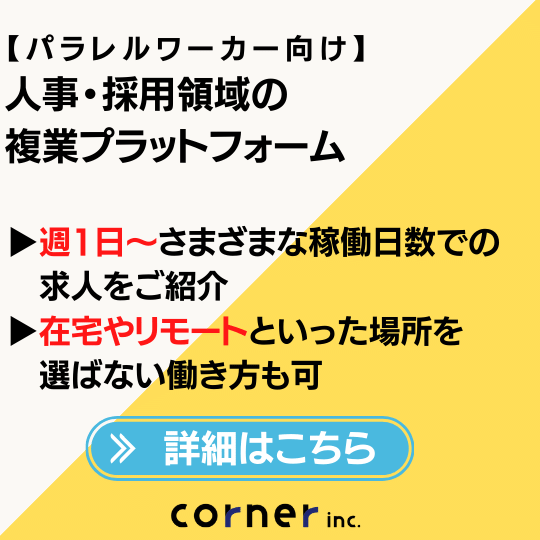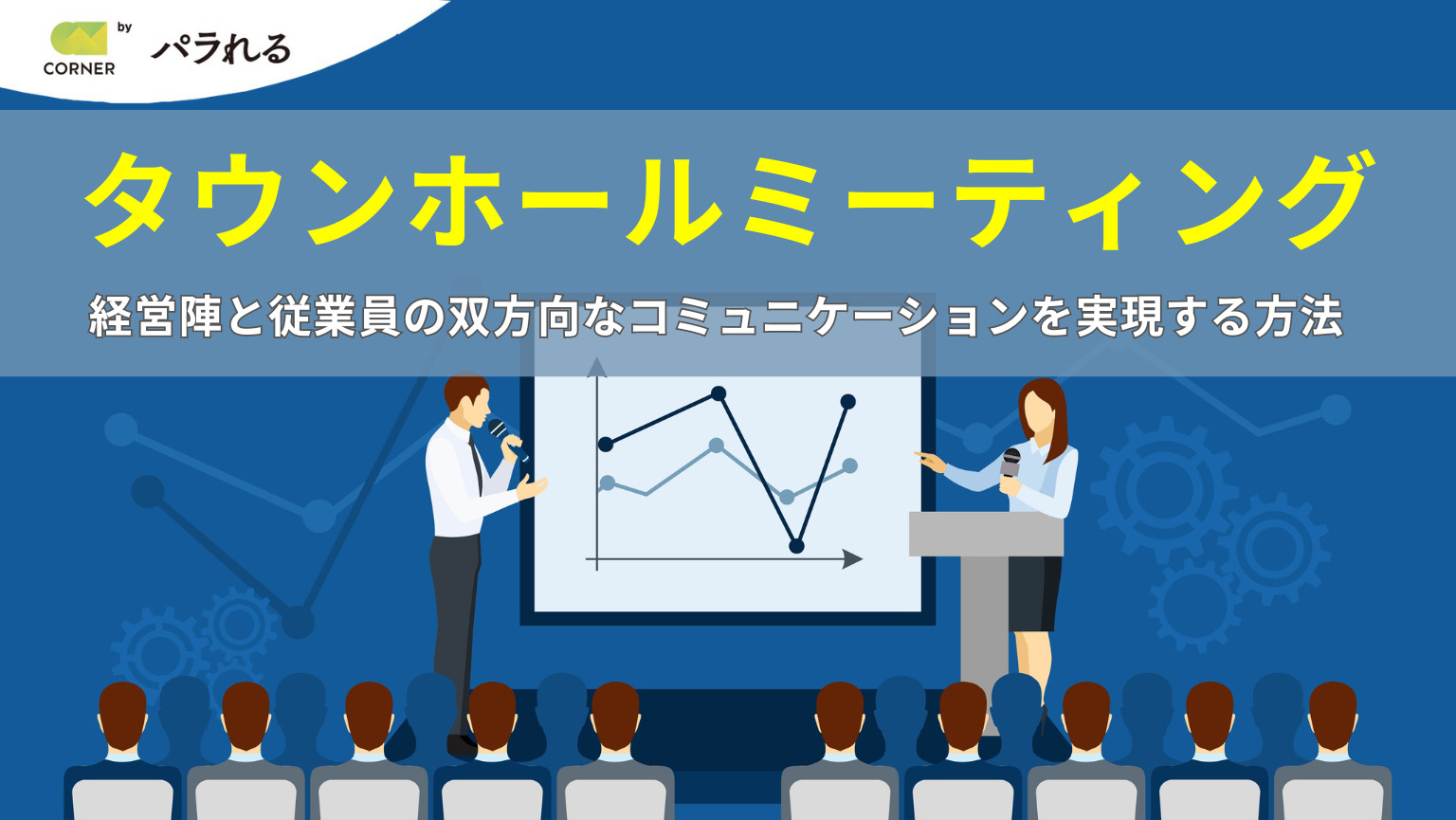社員の能力を最大限引き出す、オンライン/オフラインでの階層別研修の在り方

「新入社員研修」や「管理職研修」など多くの企業で導入されている階層別研修ですが、本来の目的やメリット・デメリットを正しく理解し、効果的に運用できている企業はごく一部ではないでしょうか。特に、中堅社員や管理職向けの研修は「やっても効果が薄い」と考えて優先度を下げてしまっている会社も多いのではと思います。
さらに昨今のコロナウイルス影響下では、研修の予算・対象者の見直し、オンラインでの研修実施などの抜本的な変更も起きており、対応しきれていないケースも見られます。
そこで今回は、日系・外資系金融企業、グローバル企業において、常務取締役CHRO、人事部長など、企業人事を24年以上経験し、現在は組織変革・人事コンサルティングを専門とするアルボーレ株式会社の代表取締役である吉野匡毅さんに、効果的な運用方法や実際の事例などを含めてお話をお聞きしました。
<プロフィール>
吉野匡毅
日系・外資系金融企業、グローバル企業において、常務取締役CHRO、人事部長等、企業人事を24年以上経験。現在は日英2ヶ国語による組織変革・人事コンサルティングを専門とするアルボーレ株式会社を創業、代表取締役。日系・外資系の多様な業種の中小企業、コンサルティング会社、IT・メディア企業、グローバル企業等を支援し、組織変革・風土改革、グローバル化、人材開発・育成制度設計、従業員エンゲージメント向上、人事制度・戦略改善、人事機能全般改善、評価・給与報酬制度改革、テレワーク導入、人事システム導入、メンタルヘルス対策導入に関するコンサルティングを提供している。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
階層別研修の概要・目的
───階層別研修とは改めてのどういったものか、定義やお考えを教えて下さい。
企業における人材育成・能力開発を目的とする研修は、一般的には以下の4種類に分類されます。
1.階層別研修
2.職種別研修
3.目的別または選抜研修
4.全社研修
このうち「階層別研修」は、対象を階層(役職、職位、等級、勤続年数など)で分けて実施される研修です。
それに対し、「職種別研修」は対象を職種(営業職、開発職、管理部門職など)で分け、「目的別または選抜研修」はプロジェクトの参加メンバーや、階層と職種で特定された社員の能力開発、特定の業務内容やスキルの向上などの目的別に対象者を選びます。「全社研修」は文字通り、全社員が対象です。
───階層別研修を行う目的にはどういった点が挙げられるでしょうか。
階層別研修は、広く一般的に行われており、対象を階層で一律に捉え、会社主導で義務的に同一内容の教育する手法が多く用いられます。社員のレベルを横並びで向上させることが目的で、「全体底上げ教育」とも呼ばれます。
階層別研修は決して万能ではありませんが、近年その重要性が再認識され、改めて注目を集めています。労働人口の減少傾向が続く中、多くの企業は人材不足を乗り切るために組織を強化し成果を拡大させることが必要になり、全社的な人材育成・能力開発手法の一つである階層別研修も、企業組織のMVV(Mission、Vision、Values)を浸透させ、全社戦略を推進する組織体制をつくり、競争力や成長力を増大させる有効な要素の一つと考えられています。
また、高度な企業統治やコンプライアンスの強化が求められる時代に伴い、さらなる社内階層の強化や組織の効率化などが必要となっています。
階層別研修の種類
───階層別研修にはどのような研修があるのか教えて下さい。またそれぞれの研修の目的、内容などの詳細も教えて下さい。
階層別研修の目的として代表的なものを3点挙げてみましょう。
1.企業のMVVを実現させる人材の育成
2.各階層での業務を適切に遂行するための必須要件を理解し、身につける
3.各階層で期待される能力やスキルの向上・成長を促す
企業は経営目的を効率的に果たすために階層を作りますが、各階層に応じて果たすべき役割が存在します。
階層別研修は、各々がその階層での仕事への姿勢や考え方などを自覚し、職務を適切に遂行する上で必要な一定スキルや能力を身につけ、チーム全体、ひいては組織全体のレベル底上げをすることが目的です。さらに、それを継続して実施することで、企業のMVV実現に向けた戦略的・中長期的な人材育成につながります。
種類と内容
| 目的 | 内容 | |
| 新入社員研修 | 長期にわたり活躍し続けられる 土台を形成し、新入社員のスムーズな組織参画を図る |
社会人として基本的に必要なスキル・知識・行動・姿勢・法律、 効果的な人間関係やチーム構築などを学ぶ |
| 若手社員研修 | 定型業務に加え、応用的な業務で成果を発揮できる人材の育成 | 社員、チームメンバーとしての確実な業務遂行、チーム全体のパフォーマンスを高める主体的・協力的な動きを学ぶ |
| 中堅社員研修 | 組織の中核として後輩の指導や支援を行える人材の育成。チームの効果を高め、後輩となるメンバーのフォロワーシップを醸成することができる状態を目指す | チーム・リーダー・サブリーダーとしての役割を認識し、チームの目標達成・業務効率化の主導や、チームメンバーとのコミュニケーション技術を学ぶ |
| 管理職 研修 |
組織パフォーマンスの向上を任せられる人材の育成。計画立案・実行力、人材育成・管理能力を向上する | 管理職としての必要な心構え・知識・スキルを学ぶ |
| 取締役・役員研修 | 経営のリーダーシップをとり、未知の課題発見、事業拡大・開発、戦略策定、組織改善、他幹部とのチームワーク醸成などができる人材の育成 | 取締役・役員として必要な法律(会社法、労働法、商法、下請法など)やコーポレートガバナンスの知識、企業倫理、経営分析や経営戦略立案の手法などを学ぶ |
なお、管理職研修や取締役・役員研修は、研修を企画して実施できる社内人材がいないことが多いため、社外の教育・研修機関や専門家を見つけ、相談・依頼すると良いでしょう。
階層別研修のメリット・デメリット
───階層別研修自体のメリット・デメリットを教えてください。
<メリット>
・階層別に、必要なスキルや知識が身につく
・意識や自覚が高まり、客観的な自己分析ができる
・視野を広げ、本来の仕事に対する目的意識を再認識することができる
<デメリット>
・義務的な印象への抵抗感
・業務時間の都合等で参加者が少ない
・職種によっては業務に活かせる部分が少ない場合がある
・実業務での成果にはすぐに繋がらない場合がある
───これらのデメリットをカバーし、研修効果を上げるためにはどうすれば良いでしょうか。
多くの企業では、新入社員や新任管理職が対象の階層別研修は行われていても、時間とコストの問題から、より上階層の社員を対象とした研修があまり実施されていないのが現状です。しかし、社会や経営環境が激しく変化する中、それに柔軟に対応するためには、中堅社員や管理職、取締役・役員も重要な階層として戦略的に研修を行って育成し、企業全体の組織力向上とモチベーション・アップを図ることが企業の成長にとってカギとなります。
階層別研修は「横並びの研修」で、同じ階層で関係性も近い対象者同士の慣れ合いが生じたり、義務感が前面に出やすい傾向があるため、「研修の目的」、「階層毎に期待される役割」、「対象者の実務(業務)との関連性」の3つを事前に明確に説明し、対象者の理解と参加意欲を促すことが重要です。
また、階層別研修の終了後、「研修内容が実践に繋がらない」という事態が起こることもありますが、これは、対象者の立場になって研修内容を構成することで予防が可能です。
この場合も、人事が一方的に研修内容を決定するのではなく、対象者と事前に研修内容・構成について検討し、綿密な連携を取りながら研修を設計することが研修の効果を高めるポイントになります。
階層別研修の設計の仕方

───それでは、具体的にどのように実践すれば良いのでしょうか。設計から実施までのフローを教えて下さい。
設計〜実施までは、以下のように進めます。
1.組織の現状を踏まえて、明確なコンセプトを打ち出す
(「研修前と研修後で何が異なるべきか」を設定する)
2.コンセプト実現のための研修・育成ゴールを書き出す
(「対象者に期待する具体的な特性・思考・行動」を設定する)
3.具体的な研修内容・形式を構成する
(講義、演習、またはその組み合わせ等を決定する)
4.コンセプト、研修内容・形式、研修効果を十分に検討・合意する
(人事と対象者双方にとって納得感と意義があるかを丁寧にすり合わせる)
5.対象階層、コスト、日時・場所、回数、研修後のフォローアップなどを決定する
具体的に、過去に私が上記に沿って設計した階層別研修の事例を共有します。
<事例:組織・風土変革を主題とした階層別研修>
1.コンセプト(研修前と研修後で何が異なるべきか)
研修前の状態(現状や課題):
・MVVは、業務で実践されていない
・過半数の社員は収益の安定を最重要と捉え、現状維持が主目的であり、価値創造や業務拡大は無理・無意味であるとしている
研修後にあるべき状態(効果):
・MVVは会社の現状に見合う内容に更新・改善していくものという認識に変わった
・MVVを業務で実践的に体現する意味や方法を学べた
・質の良いチームワークを向上し、組織に貢献していくための能力開発スキルが形成された
・主体的に価値を創造・向上し、進化する組織体質に変わった
2.研修・育成目的(コンセプトを実現する為に必要な、「あるべき姿の組織・社員が持つ具体的な特性・思考・行動など」は何か)
・企業価値の発見・創造・形成という、主体的な習慣やプロセスが定着している
・自らの内的動機(自分を揺り動かす源泉)を発見できる
・主体的な発言をし、期待・役割に対する提供価値を自らの言葉で紡ぎ出すことができる
・チームワークの質を向上させ、組織に貢献していく為の能力開発スキルを持つ
3.研修内容・形式(講義、演習、またはその組み合わせ)
・経営幹部や管理職層といったトップ層から研修をはじめ、中堅社員層→若手社員層→新人社員層へと進める
・中堅社員以降の研修に関しては、「なぜ組織が変わるべきなのか」についてトップ層からのメッセージを聞く(十分な質疑応答・対話を含む)
・外部講師・専門家から、トップ層のメッセージに関連する経営環境、市場環境、社会情勢、テクノロジーの変化などについて学ぶ
・現在の評価制度の基準をどのように変えるべきかの講義(ディスカッションを含む)を受け、研修内で評価制度の一部を自分たちで考案する
・個人演習ではなく、集団によるディスカッションやロールプレイを中心とした演習を行う
・習慣づけることを目的として、研修後に複数のチームを形成し現実のミニプロジェクトを実行する
・各ミニプロジェクトに、ロールモデルとなる社員(具体的な特性・思考・行動を持つ社員)を、リーダーやサブリーダーとして配置する
・高い評価を得たミニプロジェクトは、実際に事業化も検討していく
・研修で優秀な結果を残した社員は、他の階層研修の内容構成など、組織変革に優先的に参加させる
4.コンセプト、研修内容・形式、研修効果の検討・合意(現場と企画側双方にとって納得感と意義のある研修か)
人事部と研修対象者の間で、以下の点を十分に検討した。
・MVVの関連性が明確になっているか
・期待される組織、風土、人材像を理解することができるか
・研修の目的・内容は経営環境や社会情勢に合わせて進化しているか
・知りたい情報があるか
・業務に活かせる内容か、職務遂行能力の具体的向上に役立つか
・社員の中長期的なモチベーションの向上につながるか
・チームワークが向上し、業績向上につながるか
この研修では、結果として設定したコンセプトに沿った効果を得ることができました。人事と対象者の間で、研修実施前に内容やゴールを丁寧にすり合わせたことが成果につながった事例の一つと言えます。
オンラインでの対応について
───現状研修はなかなか対面では難しくなってきたかと思いますが、オンラインでの実施の違いを教えて下さい。また、対面とオンラインの良し悪しなど比較の面もお聞かせください。
<メリット>
・遠隔地でも研修を受けられる
・人員不足や多忙が理由で現場から移動できない場合でも、参加が可能
・研修を録画することで、随時・繰り返し視聴が可能
<デメリット>
・ディスカッションや人のマネジメントなど実習・演習型の研修は難しい場合がある
・受講者同士の交流が限られる
・大規模な社員数が研修対象の場合、本当に参加しているのか、また、意欲的に参加しているのかが分かりにくい
階層別研修は義務的な内容のものが多いため、特に現場を空けたくない(空けにくい)場合などで、参加率が問題になる傾向があります。より効果的な研修を行うためには、オンライン研修を一部組み合わせて動画配信し、個人の都合に合わせた動画学習を可能にすることも、解決策の一つといえるでしょう。また、動画学習を活用し、事前に業務に関する知識をインプットすることで、効果的に集合研修やOJTに臨むことができます。
開発、経理、事務、総務などの実務に必要なスキルを身につける「職種別研修」では、オンライン研修がより効率・効果的な場合があります。また、リスク管理、語学、法律、プレゼンテーション、プログラミングなど、その時々で身につけたい目的・テーマによって受ける「目的・テーマ別研修」も、オンランインでの実施が増えています。
ただし、チーム・マネジメント研修、ネゴシエーション・スキル研修のように、人間関係、感情、態度、ボディーランゲージなど、様々な細かい要素やニュアンスを把握・理解する必要のある研修では、オンラインのみでは十分な効果を得ることが難しく、必要に応じてオフライン研修とオンライン研修を工夫して組み合わせることで、研修効果・効率を向上させることが必要です。
編集後記
階層別研修は馴染みがある分、その目的があいまいになり、運用も何となく進めているケースが多いのではないでしょうか。今回吉野さんに階層別研修の目的や運用方法、メリット・デメリットを整理いただきましたが、正しい設計で研修を構築できれば企業のMVV実現に向けた戦略的・中長期的な人材育成が可能になるなど、その効果を再認識できました。
また、これまでうまく機能している場合でも、それをそのままオンラインで運用してもうまくいかないケースは多いでしょう。オンライン・オフラインの違いを意識するなど、一度原点に立ち返って運用を見直してみると良いかもしれません。