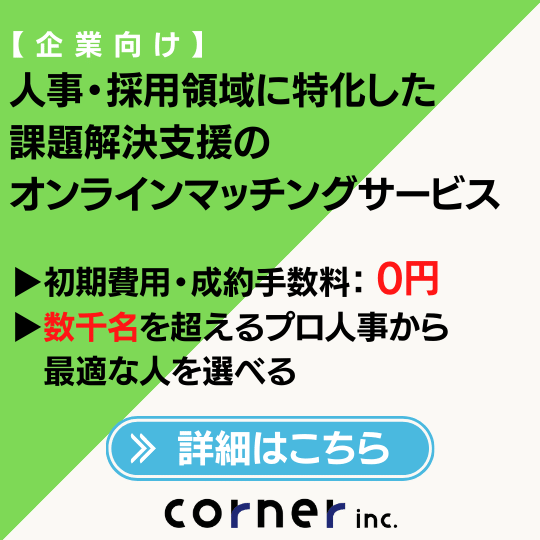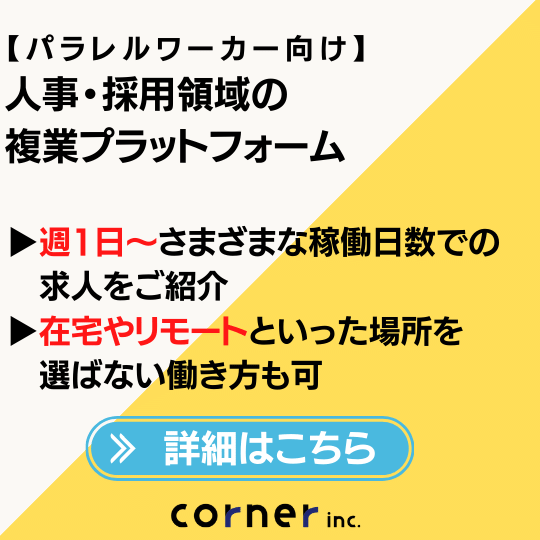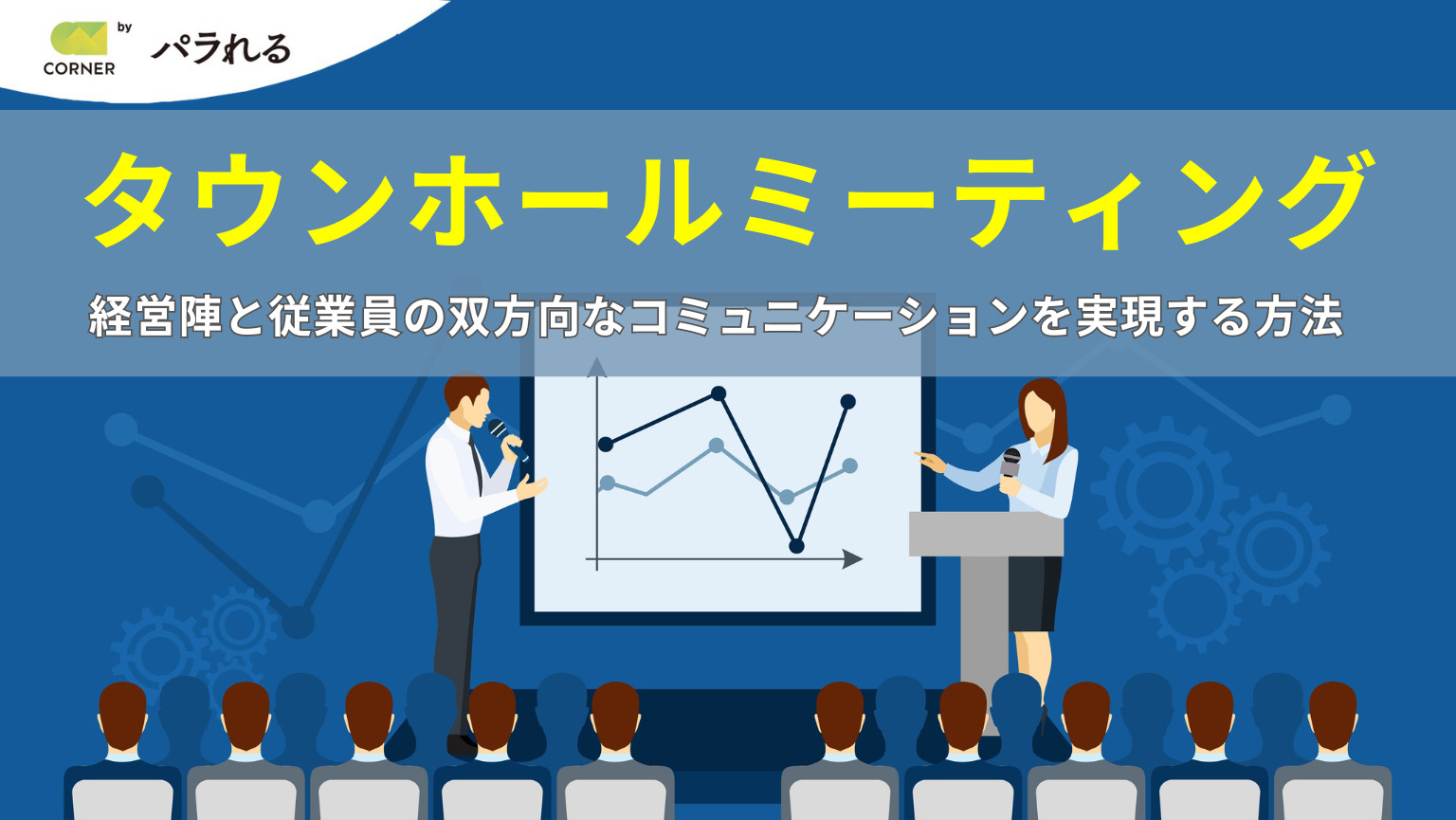「ハイブリッド型人事制度」で、ジョブ型とメンバーシップ型の良いとこどり!具体的な導入方法とは?
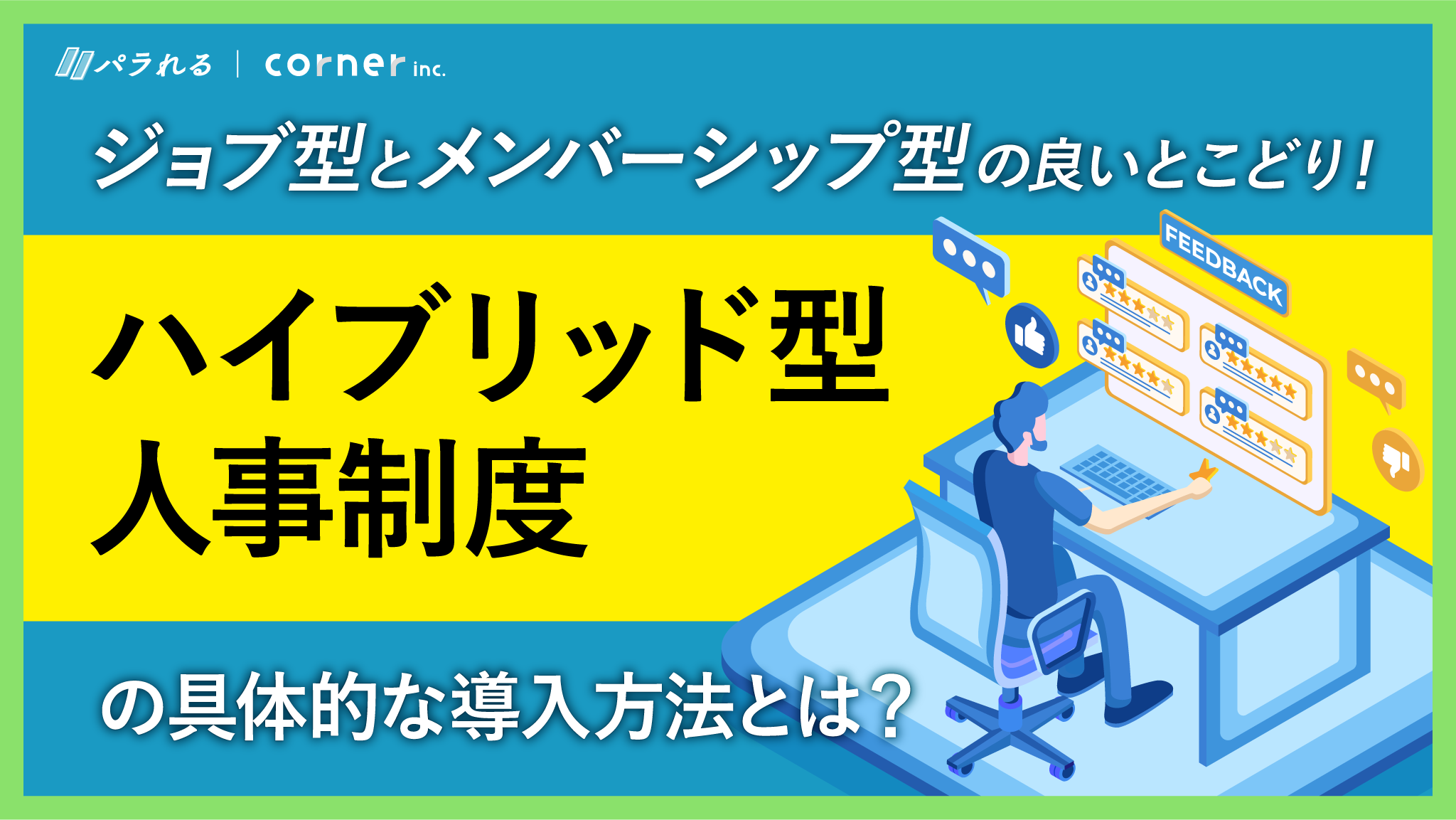
これまで多くの日本企業が導入してきた、新卒一括採用・年功序列をベースとした「メンバーシップ型」雇用から、昨今のリモートワーク増加など働き方の変化を受け、職務内容などを明確に定義して人材採用を行う「ジョブ型」雇用への関心が高まったのは記憶に新しいところです。
メンバーシップ型とジョブ型、この二元論で語られることも多いテーマですが、一部の先進企業ではそれぞれの良い部分を取り入れた「ハイブリッド型人事制度」の導入を進めているようです。
そこで今回は、外資系を含む多くの企業で組織改革プロジェクトをリードした経験を持つ株式会社士心 代表取締役 井本 一志さんに、ハイブリッド型人事制度についてお話を伺いました。
<プロフィール>
井本 一志(いもと かずゆき)/株式会社士心 代表取締役
学校法人の理事として経営に携わった後、複数の外資系企業で経営職を歴任。急拡大フェーズやM&A企業など、多くの組織改革プロジェクトをリードする。現在は、教育事業を営むかたわら、グローバル企業へ英語バイリンガルコンサルティングを提供。企業の柱である人材をどのような組織体制の元でいかにして確保し、また既存人材をいかにしてコア人材として育成するか、会社業績向上視点での施策から実行までをサポートしている。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
ジョブ型・メンバーシップ型・ハイブリッド型の人事制度とは
──ジョブ型・メンバーシップ型・ハイブリッド型とはなんでしょうか?それぞれの人事制度について、まず概要から教えてください。
まず、「ジョブ型」と「メンバーシップ型」について整理しましょう。それぞれをシンプルに表現すると、以下のような形になります。
ジョブ型(仕事に人を当てはめる型)
外資系企業に多い人事制度です。どの部署のどの仕事に、どんなスキル設定の人材が、どれくらい必要か、の考え方をベースに人が当てはめられていくため、その仕事ができる前提で人員がアサインされていきます。
メンバーシップ型(人に仕事を当てはめる型)
従来型の日本企業に多い人事制度です。従業員の配属先や仕事内容が変わることは珍しくなく、転勤で縁もゆかりもない遠方へ行くといった話もよく耳にします。
現代のグローバル社会においては、外資系企業が日本で展開することはもちろん、日本企業が海外で事業展開することも当たり前になりました。この時代の流れや変化に沿う形で、人事制度も「ジョブ型とメンバーシップ型のハイブリッド化」が広がっています。
これこそが「ハイブリッド型」と呼ばれる新しい人事制度の形であり、「ハイブリッド型人事制度=ジョブ型・メンバーシップ型双方の思想を取り入れた人事制度」なのです。
それぞれの人事制度におけるメリット・デメリット
──それでは、ジョブ型・メンバーシップ型それぞれのメリット・デメリットについて、企業と従業員双方の観点から教えてください。
企業側の観点

<ジョブ型のメリット>
①必要なポジションをピンポイントで埋めることができる
ジョブ型ではジョブディスクリプション(職務記述書)が存在します。そこには組織上のタイトル、職務内容、必要スキル、必要経験、待遇まで全てが網羅されているため、人材を探す際はピンポイントで探していくことができます。
②優秀な人材を雇用・育成しやすい
専門分野に絞って雇用ができるため、その分野における優秀な人材と巡り合える可能性が高まります。また若手から育成する場合でも分野を限定できるため、雇用リスクを大きく抑えることができます。
<ジョブ型のデメリット>
①ジョブディスクリプションから外れたことは仕事依頼ができない
あくまでも職務内容はジョブディスクリプションに明記されており、それを前提で入社してもらうため、それ以外の仕事を頼むことは基本的にはできません。
②ジョブディスクリプションを作り込む必要がある
ジョブディスクリプションが明確でないと、そこにマッチする人材と出会うことはできません。しかし、そのジョブディスクリプションが本当に会社の現状に即したものになっているかどうかを人事部だけで行うことは不可能です。部門長とやりとりをするだけでも不十分。現場レベルの仕事においては管理職にはわからない実態もあるため、階層関係なく会社全体を巻き込んだ取り組みが必要となります。また、ミスマッチを防ぐためには、現場の変化のスピードに合わせて常に最新の情報にアップデートしておく必要があります。継続的に会社全体の状態を把握し、現状に即したものに変更することも重要でしょう。
<メンバーシップ型のメリット>
①新卒など、ゼロベースから育成できる
専門性で雇用するわけではないため、幅広い可能性を持って育成に努めることが可能です。その後は会社側の考える方向性に従って適材適所で配属させることができます。
②会社都合で職務変更を行うことができる
会社の状況に合わせて部署の統廃合などは起こり得るもの。そういった場合でも職務変更を柔軟に行いやすくなります。
<メンバーシップ型のデメリット>
①スキルギャップが発生しやすい
育成の中で次々に能力を上げていく人材もいれば、全く成長していけない人材もいます。給与体系が勤続年数ベースになっていると、スキルレベルに関わらず年齢だけで給与が高くなっているケースも多々見受けられます。
②簡単に解雇ができない
何らかの事情で人員のスリム化を図りたいと考えても、会社側は簡単にそれを実行に移すことはできません。そのため辞めさせるのではなく、部署や職務変更などさまざまな観点から活かす道筋を探す必要があります。
従業員側の観点

<ジョブ型のメリット>
①得意分野で働くことができる
これまでの人生で習得してきた専門性を活かすことができるため、自分自身の特性を最大限活かすことが可能です。
②やりがいアップにつなげることができる
やりたくない仕事や人に決められた仕事ではなく、自分自身の得意分野に絞って働くことができます。そのため専門以外の仕事を押しつけられることはなく、モチベーションも高い状態を維持できます。
<ジョブ型のデメリット>
①専門性がすべてになる
ジョブディスクリプションに示された職務能力がないと判断されてしまうと、「入社前の申告が虚偽だった」と見なされて解雇されることもあります。
②時代と共に能力を磨かなければならない
いくら現状の専門性があると言っても、時代と共にその専門性もアップデートされていくもの。特にIT業界などでは次々と新しい技術が世に送り込まれるため、それに合わせて常に能力を磨く必要があります。
<メンバーシップ型のメリット>
①育成環境に身を置くことができる
ジョブ型では専門性や即戦力を求められるのに対し、メンバーシップ型では専門性がない状態でも育成環境が存在するので、そこでスキルアップに取り組むことができます。
②解雇のリスクが低い
ジョブ型では求められるスキルに到達していなければ解雇になるリスクがありましたが、メンバーシップ型ではそういったリスクは非常に低くなります。仮にスキルやパフォーマンスが低くても、部署異動などで会社側が対応しようとするためです。
<メンバーシップ型のデメリット>
①会社都合での変更に従わなければならない
ジョブ型のように、厳密に業務内容が定められているわけではありません。そのため会社都合での部署異動、職務内容変更、残業、転勤など、あらゆる指示に従う必要があります。
②給与が勤続年数ベースになってしまうことがある
いわゆる「年功序列モデル」で、どれだけ成果を出しても年齢や勤続年数によって給与が決まるケースです。メンバーシップ型の組織でも、専門性や成果に応じて給与レベルを設定している企業であれば問題ありませんが、年功序列モデルが採択されている場合は、従業員側がデメリットを感じることがあります。
ハイブリッド型の人事制度は、ジョブ型・メンバーシップ型を掛け合わせることで、以下のようなメリットを生むことができます。
<ハイブリッド型のメリット(企業側)>
■専門職と総合職の両軸でバランスが取れる
会社には2通りの人材が存在します。それは「専門性を持った人材」と「専門性を持った人材を束ねる人材」です。この2通りの人材に求める内容や評価基準は同一のものでは測ることができません。例えば、専門職であればジョブ型で縦軸のモノサシを作ることはできますが、さまざまな専門職をまとめるマネジメント人材には幅広い経験や知識といった横軸のモノサシが必要だからです。
<ハイブリッド型のメリット(従業員側)>
■評価に対する不公平感がなくなる
専門職人材も、社内を横断的に動く必要があるマネジメント系の人材も、どちらも不公平感なく評価を受けることができるようになります。
こうしたメリット・デメリットを踏まえてどの人事制度にするかを検討していくことになり、組織構成・職種ごとの人数バランス、社風・カルチャーなども加味した上で総合的に判断していきます。そのため「こんな企業はジョブ型にするべきだ」とか「ハイブリッド型にしておけば間違いない」などと一概に決めつけることはできません。
しかし、それぞれの性質とマッチしやすい形態はあります。例えば、ジョブ型は自社でエンジニアを多く抱える組織や、中途採用で即戦力者をどんどん採用する組織に向いています。一方、メンバーシップ型は開発領域に関しては外注メインで進める組織や、新卒採用・育成を重視して家族的な組織づくりをしたい企業に向いています。
そのように多様な視点で自組織にマッチした人事制度を検討する中で、ジョブ型・メンバーシップ型の双方の特徴を必要とする場合にハイブリッド型が選択されることになります。

ハイブリッド型人事制度導入に向けた「14ステップ」
──「ハイブリッド型人事制度を導入したい」と考えた経営者や人事担当者は、どのようなステップ・方法で制度導入を進めて行くのが良いでしょうか。
導入の際は、以下の14ステップの順で進めていきます。
<現状把握フェーズ>
①現状の実態(組織図)を描く。
↓
②その組織図に業務内容・必要人員数・必要スキル・必要経験・資格を記載していく。
↓
③各部門長に②と同様のものを作成してもらう。
↓
④全従業員との個別面談を実施し、それぞれの業務内容や実態、必要スキル、経験・資格等を明らかにする。
<実態調査フェーズ>
⑤各部門長と全従業員の実態認識を照らし合わせ、どこがマッチしており、どこが異なっているのかを明確にする。
↓
⑥経営陣と実態調査を共有する。その上でどのレイヤーの従業員も同じ実態認識になるように各部門と調整会議を繰り返し、一つのジョブディスクリプションを作り上げていく。
↓
⑦ここまでのアクションを全部署全ポジション分行う。
<設計フェーズ>
⑧ジョブディスクリプションによって明確になった職務内容を、会社が必要とするレイヤーに分けていく。(例)専門職1、専門職2、総合職1、総合職2など
↓
⑨どのレイヤーがどのような評価制度にするのか、どのような給与制度にするのか、を設計していく。
↓
⑩組織や人事に関するデータを網羅的・合理的に分析して、現在の問題を明確にし、今後の組織や人事基盤整備に必要な施策を提示する(スキルギャップアナリシス)
<実行フェーズ>
⑪作成したジョブディスクリプションに当てはまらない人材をどのように処遇していくかを検討する。
↓
⑫人材育成制度や採用計画を定める。
↓
⑬経営陣とのすり合わせが終わった後、部門長への教育を実施する。
↓
⑭部門長への教育が終わった後、全社員への教育を実施する。
この14ステップを進めていく上での注意点は挙げるとキリがありませんが、①〜④の<現状把握フェーズ>が骨の折れる最難関ポイントになるはずです。
というのも「人事が描いた①」と「各部門長が描いた③」と「従業員のヒヤリングによる④」は当たり前のようにズレます。なぜなら、それぞれにとって都合が良い形で進言してくることが人間心理としても“あるある”だから。そうなることを前提として、何が真実で実態はどうなのかの判断を1つひとつ行っていくこと──それが最も難しく、注意が必要な点だと言えます。
その最も現実的で効果的な解決方法は「第三者である外部の専門家に委託すること」です。どうしても内部人材で行いたいのであれば、全社を横断的かつ公平な視点で見ることができ、経営陣が信頼を寄せる人物を選ぶ必要があります。仮に人事がその役割を担う場合は、人事もまた雇われている従業員の1人であることをしっかりと認識した上で判断しなければなりません。
──これまでに井本さんが関わった企業の中で、実際にハイブリッド型人事制度を導入した事例について可能な範囲で教えてください。
私自身、過去にハイブリッド型人事制度へ移行し、数年で売上が急拡大した会社に関わったことがあります。
その時は、元々人事制度がまったく用意されておらず、給与基準が曖昧であることに現場の不満が多かったため、現状の従業員の不平不満を聞くことで実態を知ることが第一だと考え、最初に「全社員との面談」を実施しました。
その上で前述した「14の導入ステップ」を踏む形で、全役職者・経営者を巻き込み制度導入を進めていきました。
中にはスキルギャップで肩を叩かれ、退職した方もいましたが、「会社が成長するためには人事制度の整備が必要不可欠」という社長のゆるぎない決心のもと粘り強く導入を進めていった結果、少しずつ社員の理解も得られるようになりました。
最終的には、「なぜこの給与なのか」「どのように成長すればどれだけの評価を受け昇給できるのか」「どのような教育制度や福利厚生があるのか」──そういったものが明確になったことで、従業員の会社に対するロイヤリティレベルが向上しました。
さらに副次的な効果として、かさんでいた人件費の適性化、新しい売上構築に向けた人材投資計画も設計できるようになり、より正確な予算組みが可能となりました。
編集後記
「年功序列が崩れた今、もはやメンバーシップ型は時代遅れだ」「今のトレンドはジョブ型。当社も導入するべきだ」など、目的への解像度が低い状態で検討を進められることも多い人事制度。しかし最も大切なのは、「なぜ制度改革が必要か」を考え抜くことだと思います。
ジョブ型・メンバーシップ型というのはあくまで「手段」。自社で起こっている問題に合わせて、それぞれ適する型からヒントを得て制度設計を進めて行くと、結果的に「ハイブリッド型」に行きつくのだと感じました。かなり地道なアクションが必要ではありますが、それだけの工数を掛ける価値のある分野なのではないでしょうか。