「ポストオフ」制度を活用して、かけがえのない人的資本を最大限に活かす方法とは
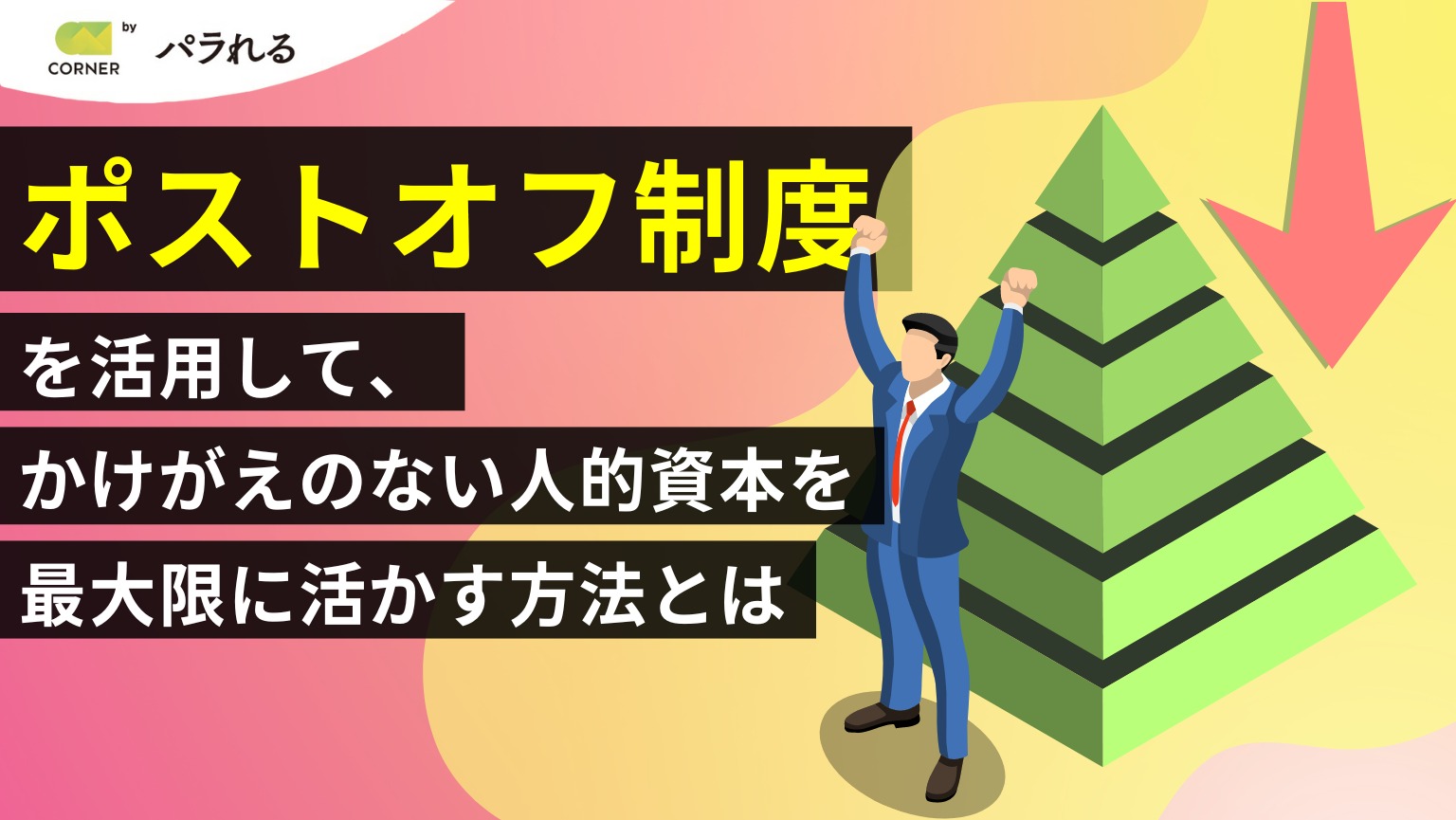
組織活性化と若手人材の起用戦略のひとつである「ポストオフ」制度。近年ではミドル・シニア人材活用の観点からもその有用性が議論されています。
そこで今回は、多くの企業で経営戦略立案・実行に携わってきた植田拓也さんに「ポストオフ」の日本企業における現状やメリット、起こりうる課題と対策に至るまでお話を伺いました。
<プロフィール>
植田 拓也(うえだ たくや)/日本たばこ産業株式会社 HR Director
東京大学大学院在籍中に人材系ビジネスにて人事責任者を経験したのち、ビジネスサイドの経験を積むため日本マクドナルド社に入社。マーケティング本部、財務本部を経て人事へキャアを戻すことを決意し、外資系人事コンサルティングファームであるヘイコンサルティンググループに参画。経営戦略と人事戦略の連動を得意領域としてコンサルティングサービスに従事し、その後は事業会社の人事へ転身。BATJ社にてHRBP(ビジネスパートナー)、日本たばこ産業社にて全社プロジェクト及び役員人事・報酬業務を担い、スイスのジュネーブにて統合プロジェクトを担当後、現在は帰任して人事システム統合プロジェクトを率いている。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「ポストオフ」とは
──「ポストオフ」の概要や定義について、日本企業における実態や活用状況と合わせて教えてください。
「ポストオフ」とは、課長や部長などの役職(=ポスト)から外れる(=オフ)制度のことです。会社が定めた年齢に達した時点で当該役職から外れ、非管理職として別のミッションを持ち働き続けます。
日系企業にも『役職定年』という似た制度がありますが、「ポストオフ」とは違って当該役職から外れると同時に会社も辞める形をとる企業も多いようです。年功序列的な考え方が広まっていた日系企業では、役職から外れた年配社員が部下に就くという構造に違和感があったためだと考えています。
ちなみに、私がこれまでにご支援した会社や在籍中の企業においては、以下のように整理していました。一口に役職定年といっても、企業によって役職から外れた後の設計に違いがあるということです。
・役職定年……役職から外れると同時に退職
・ポストオフ……役職から外れても会社残留
『人生100年時代』という言葉にも表れている通り、まだまだ働ける年齢で組織から去ることに対する企業の社会的責任を問う声は年々増えてきています。また、ジョブ型に代表される『年齢に依存しない組織マネジメント手法』が一般的になる中で、例え役職から外れたとしても貢献し続けてくれるのであれば組織に残ってもいいのではないかと考える企業が増えたことでポストオフ制度がより注目を集めています。
ポストオフ制度導入のメリット
──「ポストオフ制度」を導入すると、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
成熟企業になればなるほど、優秀な若年層が上位役職の空き待ちになりがちです。同時に、企業としてもまだまだ戦力としてシニア社員の力が欠かせない場面も多く、ついつい上位役職者をシニア社員で固定してしまう傾向にあります。結果、優秀な若手から会社を辞めていってしまい、業績悪化や組織力低下といった事態を招いてしまうのです。
ポストオフ制度の最大のメリットは、そうした悪いスパイラルを断ち切ることができる点にあります。一定年齢に達した役職者が下の世代に役職を譲ることで世代交代を実現できることはもちろん、後継者育成にも積極的になれるという副次的な効果も期待できます。
また、ポストオフされた従業員が組織に残ることで、上位役職者が持つ知識・スキル・経験を組織に留め置きながら後継者育成ができる点も企業側の大きなメリットです。従業員側にとっても若年層の昇進モチベーション向上に繋がりますし、シニア社員も来るべき「ポストオフ」に向けて事前準備ができるなどポジティブな部分が多くあります。
さらに、『ポストオフした後も働きなれた組織で継続して働くことができる』という事実が従業員の心理的安全性を高めるといった効果もあるようです。

ポストオフ制度に起こりがちな課題
──ポストオフ制度を導入・運用する上で起こりがちな課題を教えてください。
導入・運用時に一番気を付けなければならないのは、『短期的に業績悪化や組織力低下が起こる可能性がある』という点です。これまで知識・スキル・経験が豊富なシニア社員に上位役職を任せていたところに、経験の浅い若手社員を上位役職に配置するわけですから、パフォーマンスが一時的に低下するということは往々にして起こりえます。
なお、役職を退いたシニア社員がそのまま組織に滞留するため、後任である若手社員がそのシニア社員(元上司)との関係性構築や対応に苦慮するケースも散見されます。シニア社員が役職を退いたあとも実態的な意思決定権を持とうとすることも多く、そうなると制度そのものの効果を大きく損ねるばかりか、後任となった若手社員の退職を招く事態にも発展しかねません。
また、ポストオフの対象社員も仕事のやりがいを失ったり、自らの能力や希望とマッチしない業務を任されてパフォーマンスが低下したりするなどの影響も念頭に置いておく必要があります。
「ポストオフ」制度を円滑に進めるための対策・ポイント

──先ほどご紹介いただいたような課題を解決するには、どういった対策をするのが良いでしょうか。
『しっかりとした後継者計画策定と育成実施』が、制度をスムーズに運用していく上で最大のポイントです。
ただ、これは何もポストオフ制度に限った話ではありません。高パフォーマンスの上位役職者の退職や、何らかの理由で働けなくなってしまう事態をあらかじめ想定し、先手を打って後継者の目途を立てておくことは持続的な組織運営には欠かせないものだからです。
高いパフォーマンスを発揮されている役職者ほど、その自負から後継者計画策定を避ける傾向があります。しかし、自身に何かあったときのことを前もって想定して強い後継者を育てられる役職者こそ『真の高業績者』と言えます。そうした考えを会社としても発信し、強い覚悟で後継者計画策定・育成に取り組んでいくことが重要です。
一方で、「ポストオフ」の対象社員に対しては前段階からその制度の意味や狙いを丁寧に説明しておきましょう。ポストオフにより発生する組織内の役割変更、ワークからライフにシフトするにあたっての意識醸成を目的とした研修を実施するなどのサポートも必要不可欠です。合わせて対象社員のポストオフ後の役割・責任を明確に定義しておくことで、本人が引き続き組織内で必要とされている実感を得ると共に、これまでの役割や役職に固執しない体制を構築することができるようになります。
また、ポストオフの年齢は役職別・段階的に設定しておくとより持続的な組織運営が可能になります。例えば、一律50歳でポストオフするのではなく、課長は50歳、部長は55歳といった形で当該役職に達するために必要な就業年数と照らし合わせながら段階的に設定すると良いでしょう。万が一『余人をもって代えがたい』ケースが発生した際には、社長決裁などのガバナンスを担保した上で例外を許容するバッファを設けておくとさらにスムーズに運用していけると思います。
制度導入後になるべくスムーズな移行を目指すという観点でいえば、前後でのキャリア支援として、ポストオフ後にどのようなキャリアを築きたいのかについて考えるワークショップを数回にわたり開催すると効果的でしょう。重要なのは、ワークショップの開催時期を制度を導入する直前ではなく、その数年前から行うことです。
私の場合、こうしたワークショップを通じて、まず受講者にポストオフ後について考える機会、そしてポストオフ後の自身の優先順位について明確にしていくとともに、ポストオフ後の現実について統計データを用いてイメージを膨らませてもらうようにしています。またポストオフ後に関しては、転職支援事業会社と連携し、転職先の斡旋を試みるとともに、自グループ内でもポジションが無いかのサーチをサポートしています。
課題を乗り越えポストオフ制度を導入した具体例
──植田さんがこれまでご経験された「ポストオフ制度の導入例」について、導入前の状態・課題や導入後の結果・効果など可能な範囲で教えてください。
以前私がご支援した創業20年を超える企業では、シニア社員で上位役職が固定化されてしまっており、下の世代が育たない、育っても辞めてしまうといった課題を抱えていました。そこで前述した『後継者計画の策定』と合わせてポストオフ制度を導入し、会社として次の世代へ会社経営をシフトしていく旨のメッセージを発信することにしたのです。
もちろん、導入に際しては従業員からさまざまな意見が寄せられました。ポジティブな意見としては「若手への経営・権限の委譲が進む」「従業員がそれぞれが自身のキャリアを考え直したり、軌道修正する機会にできる」などが出ました。一方でネガティブな意見としては「会社から一方的に決められてポストオフするなど不遇ではないか」「会社として経験やスキルがきちんと受け継がれなくなるのではないか」「ポストオフした元上司が部下になることでマネジメントが難しくなるのでは」など、個人由来のものから会社運営に関するものまでさまざまでした。
そこでポストオフ制度の導入にあたり、まずはこの制度の導入目的や、狙い・実際にどのような運用になるのかなどを現場へ地道に説明。金銭的メリットをしっかり提示しながら、その前後でのキャリア支援を充実するように努めました。
このように金銭的メリットを提示する場合でしたら、ポストオフ後も報酬水準を現状維持するという形ですとか、あるいは退職を伴う場合であれば、制度導入以前の定年退職までを前提とした報酬を補填しうる「割増退職金制度」などの設計が望ましいでしょう。それが難しい場合は、ポストオフ後の平均収入との差分を埋める理論金額に基づいて支払うなどのオプションもあるかと思います。
上記のように説明を続けながら、少しずつ現場の理解を獲得。結果的には次世代の経営者や上位役職者が育ち、順次引き継いでいくことができるようになりました。加えて組織診断の結果も「将来のキャリア展望」といった項目においてスコアが改善するなど、とても効果のあった制度導入となりました。
なお、昨今は『ジョブ型組織』へ移行した企業にポストオフ制度の導入支援をさせていただく機会が増えてきました。 ジョブ型組織では年齢に依らず、ポジション(=役職)の要件を満たせば誰でも上位役職に就くことが可能になる反面、専門性やパフォーマンスが高い従業員ほど長く同じポジションに滞留する傾向があります。そうして人材の新陳代謝が促されず硬直化してしまう組織課題に対しても、ポストオフ制度は大きな効果を発揮してくれます。
編集後記
『人生100年時代』というキーワードが出ていたように、これからの時代はシニア社員の活用がさらに重要なテーマとなってきます。長年の経験に裏打ちされた技術や知恵は、事業・組織運営においても大きな力となってくれるはずです。かけがえのない人的資本を最大限に活かすためにも、ポストオフ制度への理解を深めて導入・運用を進めてみてはいかがでしょうか。






