「静かな退職」に気づき、適切に対処するためには
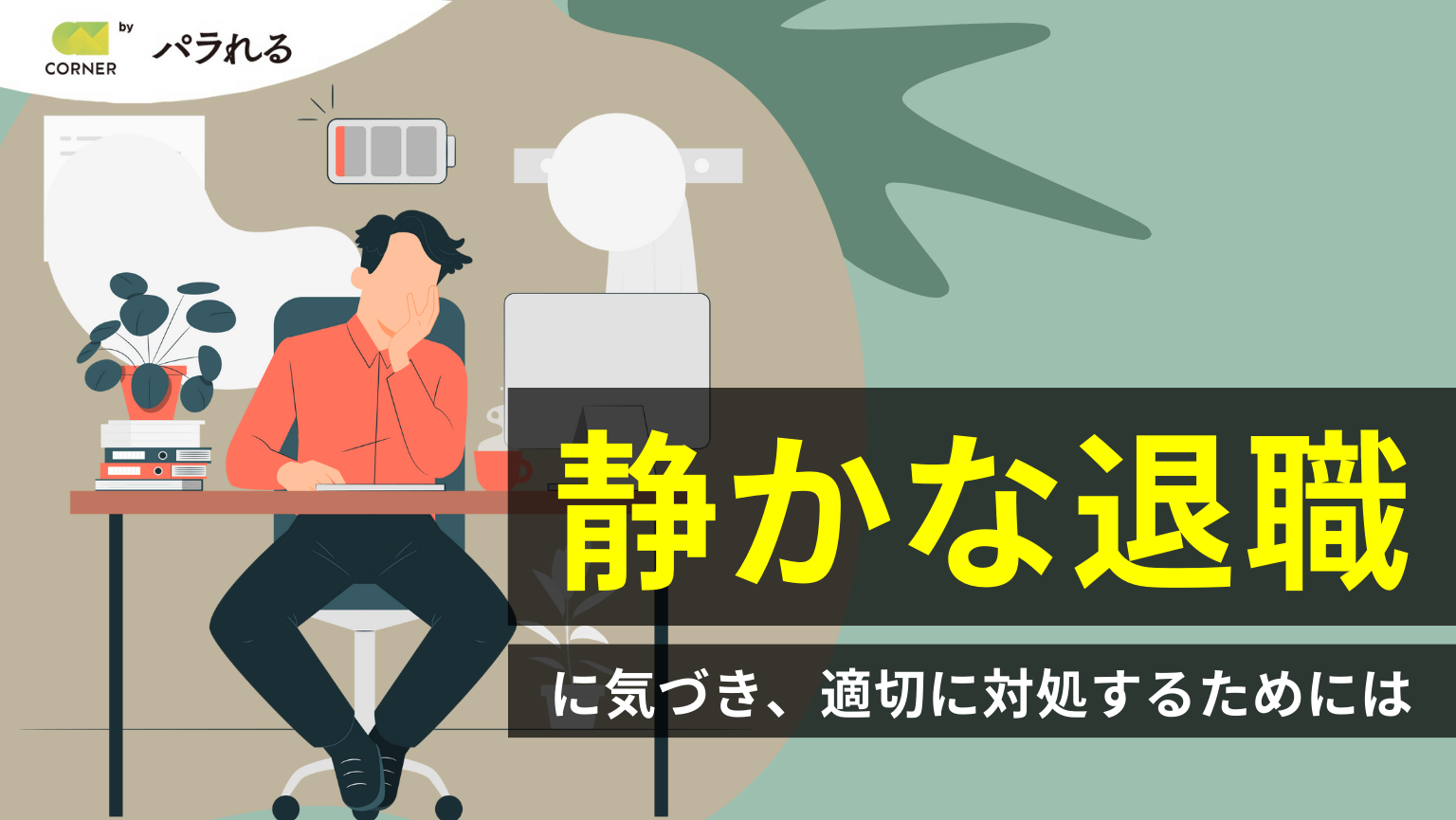
「静かな退職(Quiet Quitting/クワイエットクイッティング)」という言葉をご存じでしょうか。2022年頃より米国で話題になったもので、最近日本でも注目されているワードです。
今回は、1級キャリアコンサルティング技能士のfinest 代表の米津 幸絵さんに、「静かな退職」の概要と現状、その影響と対策に至るまでお話を伺いました。
<プロフィール>
米津 幸絵(よねつ ゆきえ)/finest 代表、1級キャリアコンサルティング技能士
組織と個人のキャリア開発の専門家。組織の外から組織のキャリア開発をサポート。民間企業で人材育成、人材開発に携わり、現在は各組織に合わせた従業員の成長に関わるサポート業務(キャリア開発、メンタルヘルス、コミュニケーションなど)に関わる研修・講演を行う。新入社員研修、管理職研修、コミュニケーション研修、メンタルヘルス研修などから、1on1導入、ダイバーシティ推進支援、キャリア開発の内製化支援、キャリアカウンセリングも実施。これまでの研修・講演は、登壇回数3000回以上、約10000名以上。国家資格キャリアコンサルタント養成講座の認定講師、更新講習講師、関西圏の大学にて非常勤講師としても活動中。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「静かな退職」とは
──「静かな退職」の概要について教えてください。
「静かな退職」とは、仕事に対するやりがいや熱意はなく、淡々と必要最低限の仕事をこなす働き方のことです。実際に退職はしないものの、退職が決まった従業員のような余裕をもった精神状態で働くことをイメージしてもらえると分かりやすいでしょう。仕事とプライベートの境界をしっかり分けるワークライフバランスを重視する働き方をしている方が多い傾向です。日本ではまだまだ聞きなれない言葉ですが、米国ではキャリアコーチであるブライアン・クリーリー氏が自らのTikTokで発信したことをきっかけに、主にZ世代(※1)の間で話題となりました。これはミレニアル世代(※2)や団塊世代ジュニア(※3)のハッスルカルチャー(仕事を人生の最重要項目とする考え方)への反発心がベースにあると考えられています。
また、米調査会社ギャラップ社が行った『2023 State of the Global Workplace』という、2022年~2023年に160カ国以上・15歳以上の従業員12万2416人を対象にした調査によると、世界の労働者の約59%が「静かな退職」状態にあると指摘しています。
※1:Z世代とは、1990年代半ばから2010年代序盤に生まれた世代のこと。デジタルネイティブ、SNSネイティブとも呼ばれ、タイパ(タイムパフォーマンス)重視の効率主義、強い仲間志向、仕事よりプライベート重視、多様性を重んじるなど、従来の若者以上に特徴的な価値観を持っている世代だと言われています。
※2:ミレニアル世代とは、1980年、もしくは1981年〜1990年代半ばごろまでに生まれた世代のこと。世界人口全体の約6割を占める最も人口の多い世代で、日本でも約4割に迫っており、2035年には過半数を占めると予測されていることから、社会に対する影響力は大きく、マーケティングの分野などでも注目されています。
※3:団塊世代ジュニアとは、1971年から1974年の間に生まれた世代のこと。日本の高度経済成長の中で幼少期〜10代を過ごした世代であり、就職氷河期などの厳しい社会を生きてきたため、現実的思考を持つ人が多い傾向があるとされています。
「静かな退職」が広まる背景と現状
──世界の労働者の約59%が「静かな退職」状態にあるということは驚くべき調査結果ですが、その背景と現状を米津さんはどう捉えていますか。
「静かな退職」が広まった背景には、大きく以下4つの背景があると考えています。
(1)パンデミックによる経済混乱で働き方が変化する中、仕事と私生活の境界が曖昧になり、仕事に対する価値観や関わり方が変わったこと
(2)ハッスルカルチャー(仕事を人生の最重要項目とする考え方)への反発心や、そんな考えを持つ上司や先輩を見て『がむしゃらに働いても報われるかどうかわからない』と疑問を持ったこと
(3)働き方の多様化、特にウェルビーイング推進の加速を受けて、キャリアアップや昇進などに重きを置かないキャリア観を持つ方が増えてきていること
(4)組織に依存せず自身でキャリア形成を模索する方が増えたこと(特にZ世代や若年層)
SNSをきっかけにZ世代中心に広まったとされる「静かな退職」ですが、実はZ世代以外にも該当者が広がっていることがさまざまな調査で指摘されています。驚くことに日本においては40代〜60代のミドルシニア世代にも「静かな退職」者が多いと言われています。その理由は複数ありますが、大きくは以下4つです。
(1)職業人生の長期化
(2)ワークライフバランスを重視化傾向
(3)家庭や子育て、介護などのライフイベントが重なる時期
(4)マルチステージへの変化
その背景にあるのは、『人生100年時代』とも呼ばれる社会環境の変化です。現代において組織は従業員の雇用延長をせざるを得ない状況となっており、給与削減、役職定年、出向転籍、早期退職などを余儀なくされています。そんな中、ミドルシニア世代は大きな変化の真っただ中に位置しており、急激な変化への適応もままならない方も少なくありません。その結果、これまでの経験を活かして淡々と仕事をこなすことで、生活の変化全般に対応しようとする動きが見られるのです。他の世代と比較しても仕事へのモチベーションやキャリア自律の意識は低く、「静かな退職」状態になりやすいのが現状です。
「静かな退職」がもたらす影響
──この「静かな退職」が組織や企業に対してもたらす影響にはどういったものがあるのでしょうか。
「静かな退職」状態を放置していると、組織にとって中長期的な悪影響が発生する恐れがあります。具体的には以下3つです。
(1)生産性低下
(2)職場環境の悪化
(3)人材流出
(1)生産性低下
「静かな退職」により会社への帰属意識が薄くなり、個々の従業員の生産性が低下し、組織全体の生産性も減少します。また、仕事に対する関与感やコミットメント・熱意が低い状態では、イノベーションや新しい価値、アイデアの創造性も低くなります。
(2)職場環境の悪化
「静かな退職」により最低限の業務しか取り組まない従業員がいると、職場全体のモチベーションが低下していく原因となります。また、その分の業務は周囲のメンバーが負担しなければならず、不満が溜まりやすい状況が生じます。特に、トラブルが発生時などは業務負担が急増し、チーム全体のモチベーションが低下して職場の雰囲気が悪化する可能性があります。
(3)人材流出
「静かな退職」が増えると元々意欲のある従業員のモチベーションまでも低下するリスクがあります。そうなれば、組織に対する不満を抱く量が増え、「静かな退職」状態に陥っている従業員だけでなく、それ以外の優秀な人材の流出や、新たな「静かな退職」社員を生み出してしまうことにもつながりかねません。
一方で、「静かな退職」でワークライフバランスを重視した生活を送ることにより、メンタルが安定したりバーンアウト(=燃え尽き症候群)になりにくかったりなどのメリットもあります。しかし、その状態が続けば仕事に対する充実感や成長実感が次第になくなり、ストレスや不安を感じるなどウェルビーイングに悪影響を及ぼします。私自身も多くの企業でキャリアコンサルティングを実施してきましたが、「静かな退職」状態に陥っている方々は、それを自身で選択しているようで、実はさまざまな不安や葛藤を抱えていることを実感しています。
このように、「静かな退職」状態が続く従業員が増えれば、組織・従業員の双方にデメリットが大きくなります。社会の発展観点でも良い状態だとは言えないため、危機感を持って早急に対策を立てる必要があるテーマです。

「静かな退職」該当者の発見方法
──自組織の誰が「静かな退職」を選択したり陥っているのかを見極めるには、どのような方法があるのでしょうか。
離職者が増えているなど分かりやすい兆候もありますが、実際は現場の状況・状態、個人の心理状況を把握することで「静かな退職」に該当するかを判断します。具体的には、以下のような兆候がないかを確認する形で調査を行います。
現場での状況・状態
・最低限の業務しか取り組まず、新たなことに挑戦しない
・仕事に積極的に取り組む意欲が低い
・ミーティングなどでほとんど発言が見られない
・コミュニケーションを取ることに消極的な傾向が見られる
・他者への影響が出ている(例:他メンバーや他部署の業務量が明らかに多くなっている)
個人の心理状態
・仕事に熱意を失い、やりがいや成長実感も見つけられず、モチベーションも上がらない
・組織に不満や不安もあるが、信頼や尊敬できる上司もいない
・仕事に自分の居場所がなかったり、自信を失い評価や報酬も期待できず、この仕事に価値を見出せない
・自分に対する責任や誇りもなく、貢献実感が得られない。このままここで働いていていいのか悩む
「静かな退職」への対策
──「静かな退職」に意図せず陥っている方を早期に発見できた場合、彼らの下がった生産性やモチベーションをどのように上げていけば良いのでしょうか。
「静かな退職」の解消、つまり従業員のワークエンゲージメント向上に効果的なアクションには組織・個人の両方への働きかけがあります。具体的には、以下のようなアクションが効果的だと考えています。
組織側
・仕事の負担や悪影響を緩和し、モチベーションを高めること
・従業員の職務や期待役割を明確にし、パフォーマンスに対する適正な評価と報酬を行うこと
・従業員の声に耳を傾けつつ、上司や同僚からのフィードバックやサポートを提供すること(信頼関係、心理的安全性のある環境づくり)
・環境要因(衛星要因)に問題があれば改善していくこと
上記のキーマンとなるのは上司である管理職メンバーです。部下へその仕事の重要さ・価値・期待役割を伝えること、仕事における裁量権の見直し、自己成長実感が得られる目標設定・評価・承認(叱る、褒める、感謝するを正しく使い分ける)など、マネジメント側で取り組むべきものがたくさんあります。少なくとも、部下に対して関心を持ち、マネジメントをする立場にある自覚・意識醸成は欠かせません。
個人側
・心理的なストレスを減らしたり、仕事に対する意欲、意味付けやモチベーションを上げたりする動機付要因を明確にすること
・自分の仕事に対する目標や価値観を見直し、自己肯定感・効力感・レジリエンスを高め、キャリア自律を醸成すること
従業員エンゲージメントの調査、キャリア研修、セルフキャリアドック、キャリアコンサルティングの導入などがこうしたアクションをサポートする上で効果的です。その上で、信頼できる相手に安心して相談できる体制づくりを行います。そこで現在の業務内容や環境に不満があるとヒアリングできた場合は、改善の可能性や提案へつなげていきます。
従業員エンゲージメントの調査
定期的な調査を通じて現状把握や従業員の声を聞くことで、組織内の課題や改善点を特定しやすくなります。従業員の意見を取り入れることで、組織全体の雰囲気や満足度向上も期待できます。
キャリア研修
従業員にキャリア自律や成長機会を提供することは、モチベーションやスキル向上に繋がります。また、組織が従業員の成長を支援する姿勢を示すことで、従業員はより忠誠心を抱く可能性もあります。
セルフキャリアドック
従業員自身で目標設定・自己評価(キャリアの自己点検)をすることで、強みや成長ポイントを理解しやすくなり、適応力も高まります。これは個々のワークエンゲージメント向上にも寄与します。
▶セルフ・キャリアドックで従業員のキャリア自律を促進し、組織成長につなげる方法についてはこちら
キャリアコンサルティング
従業員に対してキャリアに関する相談やアドバイスを提供することで、個々のニーズや目標に合わせたサポートが可能になります。これにより、従業員は組織に対してより深い関与を感じるでしょう。
これらのような個人向けのサポートは後回しにされてしまうことも少なくありません。しかし、優先的にこれらの施策を進めることで、従業員が組織に対してより満足度を感じ、信頼感が生まれる可能性が高まります。その結果として、ワークエンゲージメントや生産性向上につながるはずです。
また、コミュニケーション活性化の取り組みやコミュニケーション能力を高める研修機会を作ることも重要です。職場の同僚はもちろん、友人など仕事以外の人間関係も大切にしてコミュニケーション機会を増やすことより、仕事の悩みやストレスを共有したり、励まし合ったりすることができるようになります。
近年、私の下にもワークエンゲージメントやモチベーション向上に向けた取り組み推進の依頼・相談が多く、課題を感じている組織が増えていることを実感しています。しかし、ウェルビーイング推進が進む中で働きがいよりも働きやすさを追求し過ぎると、その居心地の良さから「静かな退職」社員が生まれやすくなり、意図せず増えてしまう悪循環に陥ることもありますから、そのバランスを保つことは大きな組織課題の1つと言えるでしょう。『働きがい』と『働きやすさ』の施策を整理し、バランスを保ちながら『働きがい』『ワークエンゲージメント』『キャリアの自律』を高める施策に取り組むことが重要な時代だと言えるのではないでしょうか。
■合わせて読みたい「人事・労務課題」に関する記事
>>>「不活性人材」を生まない組織の在り方と、具体的な人事施策について
>>>人や組織の「バーンアウト」を防ぐために、企業や人事ができる予防・対策とは
>>>「インポスター症候群」を知り、人事の観点からできる対処法を学ぶ
>>>「不正のトライアングル」を理解して、組織の不正を未然に防ぐ方法とは
>>>「労務トラブル」を未然に防ぐ方法と起こってしまった際の対応策
>>>「30人の壁・50人の壁・100人の壁」を越える組織づくりとは
>>>「非生産的職務行動」を減らして、公正性ある組織を作るには
>>>「ストライキ」の日本における現状と、予防・対処法について解説
>>>「ステルス残業」の発生要因を理解し、未然に防ぐ方法
編集後記
「静かな退職」と聞いた当初はネガティブな内容をイメージしていましたが、必ずしもそうではない(多様な働き方の1つである)ことは大きな発見でした。しかしながら、短期的にはメリットがあっても、長期的には組織・個人の双方に悪影響があることを考えると、企業としても早いうちから現状把握・改善に努める必要があるものだと感じます。まずは自組織において該当者がどれくらいいるかを把握し、『働きがい』とのバランスがうまく取れているかを見直すところから始めてみてはいかがでしょうか。






