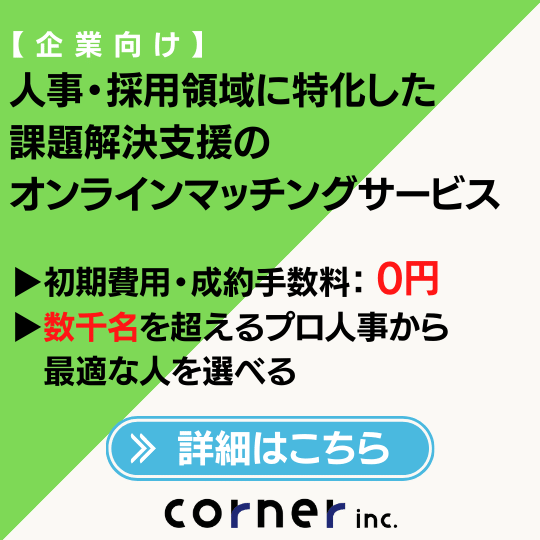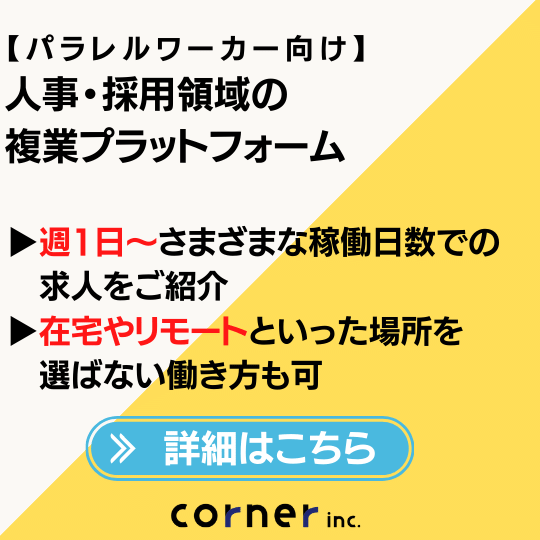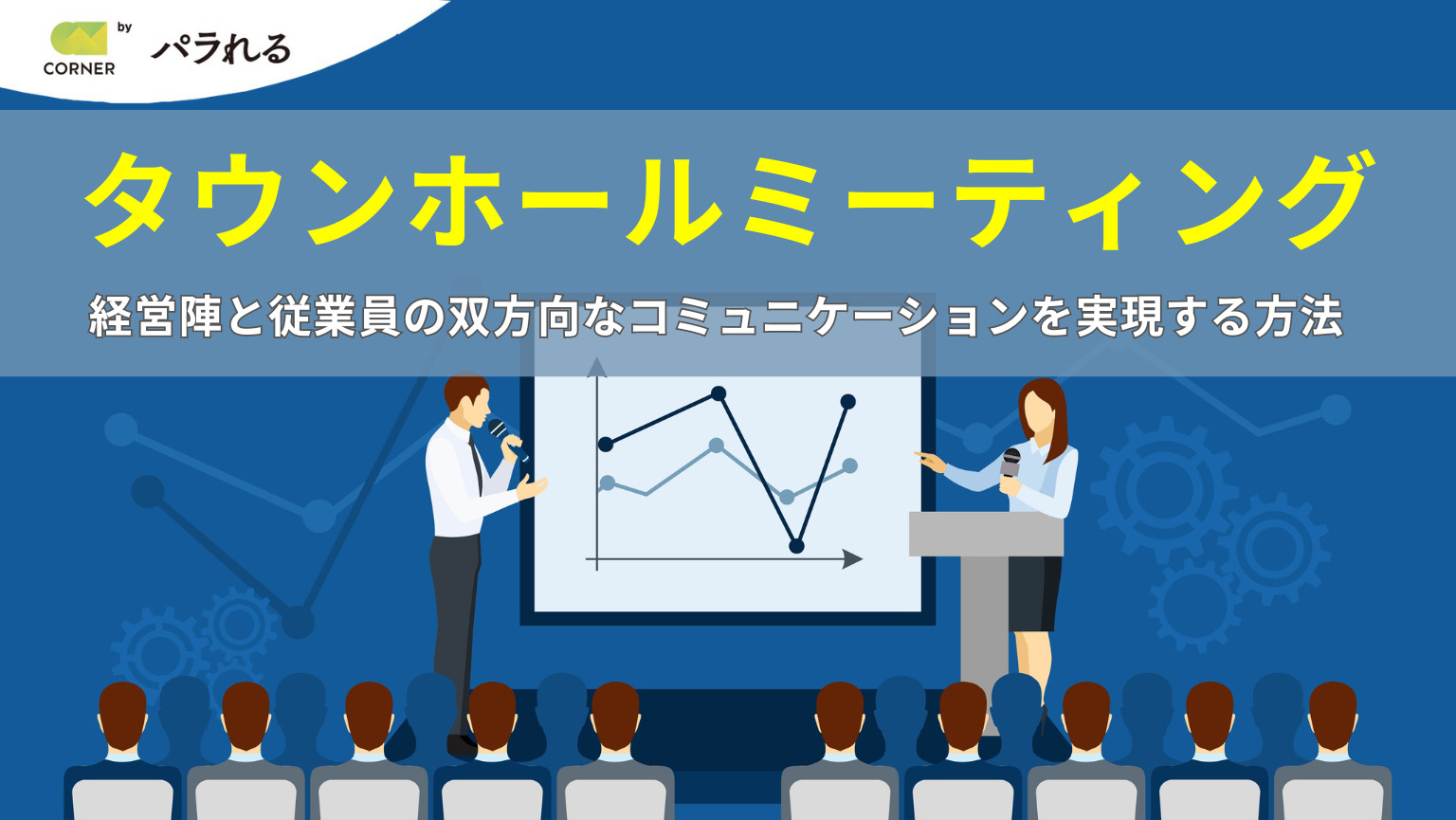「定性評価」をうまく取り入れて、組織や個人の能力を最大限に引き出す方法
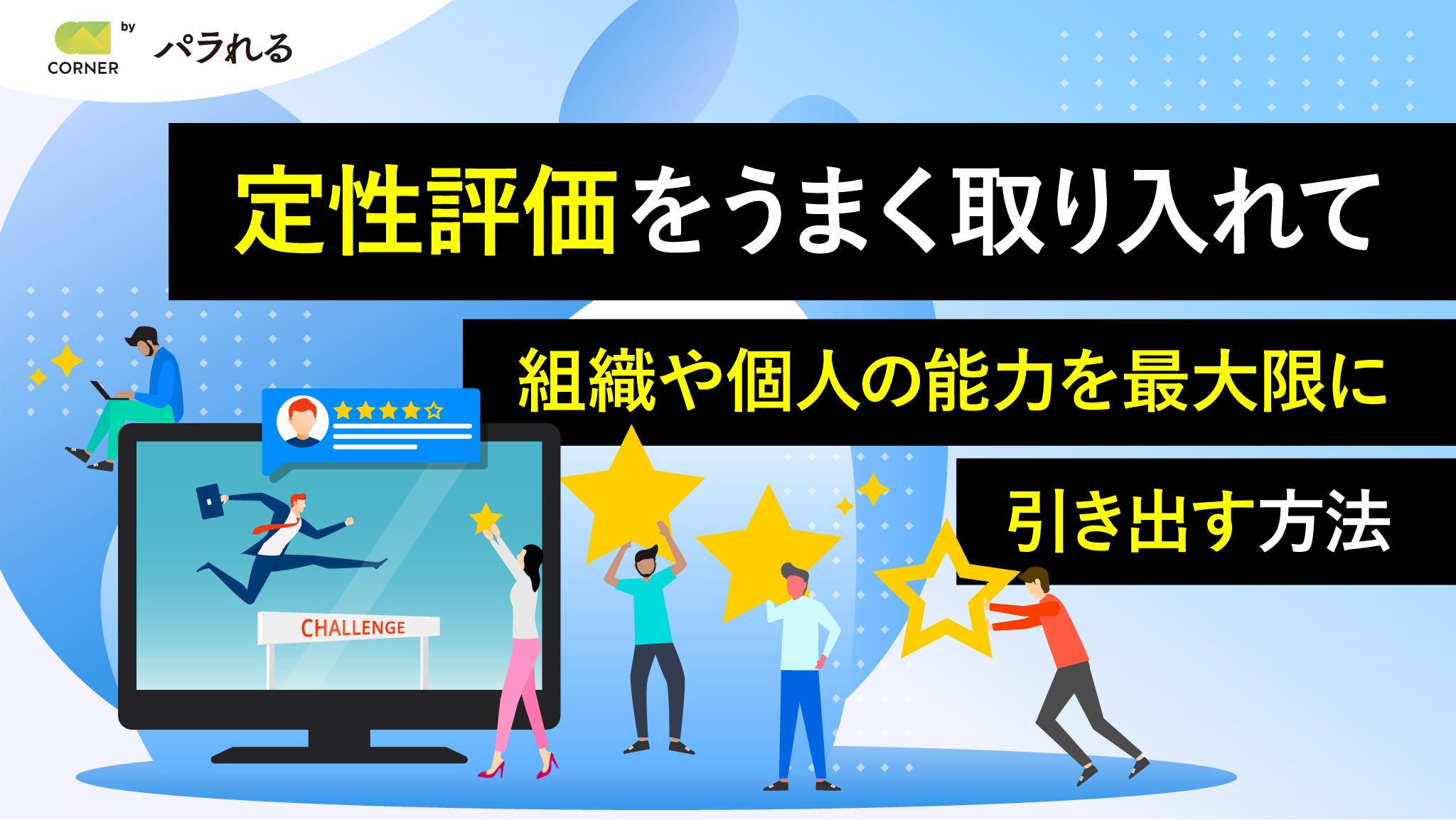
組織への貢献度合いや個人の能力を待遇に反映する人事評価。うまく活用することができれば、組織・個人の成長促進に繋がります。その評価観点において比較的設定・評価しやすい定量評価だけではなく、「定性評価」を取り入れている企業も多いようです。
しかしながら定量評価とは違い、「定性評価」は明確な評価基準が設けられていないことがほとんどのため、運用方法に苦慮している企業も少なくないようです。そこで今回は、労務や人事制度設計の領域で活躍されているパラレルワーカーの方に、「定性評価」の活用方法についてお話を伺いました。
▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「定性評価」を企業が取り入れる背景
──まず「定性評価」についてや、定量評価との違いも含めて教えて下さい。
定量評価が『数値で表せるものに対する評価』であるのに対して、「定性評価」は『数値では表せないものに対する評価』となります。それぞれの例えを挙げると以下です。
定量評価例
・売上金額
・顧客獲得件数
・目標達成率
・コスト削減率
など
※成果を○円・○件・○%などと、数値などで表すことが可能なもの。目標に達しているかどうかなどをYES or NOで判別できるもの。
定性評価例
・業務に対する姿勢や意識
・目標達成に向けた工夫
・組織にとってあるべき行動姿勢
など
※判断基準を数値に置き換えることが難しいもの。
──定量評価は多くの企業で馴染みがあるものですが、一方「定性評価」は企業によって扱い方が大きく異なります。また定量評価だけではなく「定性評価」を併せて取り入れる企業が多いと感じますが、その背景や理由はどのようなものだとお考えでしょうか?
その背景を語る前に、少し前提の話からさせてください。そもそも評価制度は、目標設定・管理とセットで考えるものです。なぜ目標を設定・管理して評価をするのかといえば、中長期的に業績を上げる組織にするため、人を育成するため、ですよね。
では、何を基準に評価するのでしょうか。それは等級制度の有無で考え方は変わります。等級制度がない場合、期初に目標を設定し、それに対して期待する成果を達成できているかどうかを測るのが一般的です。一方で等級制度がある場合にも期初に目標設定を行いますが、等級(グレード)ごとの基準に準じる必要があります。また成果評価、能力評価、意欲・情意評価の中から何を評価するのかによっても変わってきます。
なお、「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」を明確化している企業の場合は、それに沿って評価項目を決定します。会社として何を目指し、そのために社員にどうあって欲しいのか、というメッセージが人事評価制度に繋がるためです。実際には、MVV → 経営戦略・人事ポリシー →組織デザイン→人事評価制度、というような順番で決定されます。
▶MVVの作り方と効果に関しての記事はこちら
上記の前提の上で、定量評価が偏重されていた時代を考えてみましょう。その時代とは、大手製造業界などに代表される高度経済成長期の大量生産時代と重なります。世界的にも日本企業が大きな成果を上げており、『早く・正確な反復作業ができること』の価値が高かった時代です。
しかし現代はそうした作業的な時代から、第四次産業革命(AIやビッグデータを用いた技術革新など)とも呼ばれるイノベーションの時代に突入しました。より個々のクリエイティビティが価値を発揮する時代に変わったことが「定性評価」の重要性や注目度を高めていると考えています。
評価設計・運用時のポイントや注意点
──評価方法を設計・運用する際のポイントや注意点について、定性・定量の観点も踏まえて教えてください。
先ほど『評価制度は目標設定・管理とセットで考えるもの』とお話しした通り、評価方法を設計・運用する際には目標設定・管理をどう行うかも合わせて検討する必要があります。それぞれについてポイントを整理してお伝えします。
目標設定時のポイント
・明確な達成時期とセットで設定すること
・定量目標と定性目標は職種や役割に応じて使い分けること
・簡単な目標ではなく、ストレッチのある目標であること
・定性目標はDO目標ではなくBE目標であること(行動ではなく状態)
例えば、『~~の変革をする』という目標はDO目標になってしまうので、『~~な状態にする』というBE目標にすることが望ましいです。
評価時のポイント
・自己評価や振り返りをする機会を設け、促すこと
・伝えづらいことを先に単刀直入に伝えること
・サプライズ(びっくり)評価にならないこと
例えば、予め達成基準を明確にしておき、毎月1on1ミーティングで進捗をフォローするなど、評価者と被評価者の認識を共通にしておく工夫が必要です。
前述のとおり、現代は変化のスピードが速い時代です。半年もしくは1年ごとに目標を立てても、数カ月間で状況が一変してしまった、なんてことは多々あるのではないでしょうか。そんな時には毎月の評価フォローミーティング(前述の1on1ミーティングなど)で定期的にメンテナンスをしましょう。
なお、そのミーティングを進捗確認だけで終わらせてはいけません。目標達成に向けた支援や、目標修正の必要性の有無などを確認することも合わせて行いましょう。

「定性評価」の制度をつくるステップ
──「定性評価」を活用した評価制度をつくるためには、どのようなステップを踏むのが良いでしょうか。
まず大事なことは、『目先の成果だけを追わず、チーム・組織として能力を伸ばすこと』です。目先の成果(目標数値の達成度など)だけで測る制度をつくってしまうと、中長期的な組織力は向上していきません。また、個々人の能力についても合わせて評価していくことが大切です。
それを踏まえた上で、各組織の人事ポリシーに基づいて以下の順序で検討していきます。
(1)現制度の課題を洗い出し、経営課題と照らし合わせる
(2)経営・人事にて方針を定める
(3)評価項目を決める
(4)評価方法の組み合わせを決める
| 定量 | 定性 | 備考 | |
| 成果評価 | 〇 | 〇 | 目標設定必須 |
| 能力評価 | 〇 | 〇 | グレード基準により評価 目標設定無しでも評価可 |
| 意欲・情意評価 | × | 〇 | グレード基準により評価 目標設定無しでも評価可 |
なお、評価項目や方法については、現状の課題と目指す組織像を踏まえて、以下から組み合わせて選択していきます。
・評価項目
成果評価、能力評価、意欲・情意評価
・評価方法
目標管理制度(MBO)、コンピテンシー評価、360度評価、OKR、ノーレイティングなど
・種類
絶対評価、相対評価
また実際に評価制度をつくる際には、実際に評価者となるマネージャーなどの管理職に向けてその評価制度に必要な視点のレクチャーや、ワークショップを通じてフィードバックのトレーニングなども実施します。もし360度評価を実施する場合は、評価者として参加するメンバーにも研修やキャリブレーション(すり合わせ会)を実施することもあります。
「定性評価」を正しく運用するために
──「定性評価」を正しく運用するためには、どのような点に特に留意すべきでしょうか?また、実際にどのような施策を実施するのが効果的でしょうか?
「定性評価」を実施する上で、制度そのものだけでなく日々のコミュニケーションが非常に重要で、特に最も注意が必要なのは、前述した『サプライズ(びっくり)評価にならないようなコミュニケーションをとる』という点です。
評価制度は組織や個人の成長やモチベーションをアップさせるためのもの。だからこそ、被評価者が『こんな低い評価になるとは思ってなかった』『もっと早く言って欲しかった』『なぜ途中で言ってくれないのか』と肩を落とすような結果だけは避けなければなりません。それらを避けるためにも、月に1度は1on1ミーティングをするようにしましょう。

この評価進捗1on1ミーティングでフォローすべきことは、主に以下4つです。
(1)期初(目標設定時)の目標を理解し取り組めているか
⇒ 目標の再認識
(2)目標内容が、予定通りに進捗しているか
⇒ 進捗状況の認識すり合わせ
(3)目標に対して意欲的に取り組むことが出来ているか
⇒ モチベーションの確認
(4)目標の内容を変更する必要はないか(市況変化など)
⇒ 修正の必要性の有無
組織規模によっては評価者(マネージャーなど)と被評価者のレイヤーが2階層以上離れているなど、日頃の仕事ぶりが把握できていない中で進捗のみを追ってしまうケースもよく見られます。そういったことにならないよう、リーダー層との情報連携はもちろん、1on1ミーティング以外でも日頃からコミュニケーションをとって信頼関係を構築しておくことが大切です。
「定性評価」制度の導入事例
──これまでに「定性評価」制度を策定・導入されたご経験について、具体的な事例を教えてください。
これまで成果に紐づく定量評価がメインだった企業に、プロセス目標や状態目標(定性目標)を導入した事例をご紹介します。
<導入背景>
成果と市場価値を踏まえた評価がメインだったことで個人のキャリア意識は高まったものの、組織の中長期的な成長が見込めないという課題がありました。具体的には個人の能力面、組織に対するロイヤリティ面の課題などです。
個人の能力に関しては、それぞれの業務の振り返りを軽視してしまい再現性がなく、マネジメント側も目下の数字を上げるための施策に注力してしまい、中長期的に継続的な成果を出せる能力開発を後回しにしてしまっていたという課題がある状態でした。また、インサイドセールスから確度の高い見込み客をパスしてもらえるように『社内営業』に注力してしまったりと、本質的ではないアクションを優先してしまうという事が発生してしまったりしていました。
組織に対するロイヤリティに関しては、MVVへの共感を得られてはいたものの、業績がなかなかうまく上がらなかった時に成長が感じられず、組織に所属している意義を感じてもらえないなどの課題がある状態でした。
<改善に向けた行動>
目下の成果を追うだけでなく、成長につながるプロセス評価を導入することを決定しました。それに伴って、状態目標(定性目標)を明文化したガイドラインも合わせて用意し、基準の公平性が担保できるようにしました。なお、このガイドラインには目標設定の事例や、等級(グレード)ごとに求められる基準・レベル感を各部門ですり合わせた内容などが含まれています。
<結果>
これまでは会社の求める定量目標や数値目標から逆算して、個人の目標を決めるメンバーが大半でしたが、プロセス目標や状態目標などを導入したことによって『組織の目標達成に向けて何をするべきなのか』という観点で、メンバーそれぞれが自発的に考えられるようになりました。
ただ、難しいのはこれらを継続することです。またこういった制度が定着して効果として実感することができるようになるまでには時間も掛かってしまいます。正解がない世界でもあるため、常に工夫し続けることが必要な領域──それが「定性評価」を含む評価制度だと思います。
編集後記
定性評価はいわば目に見えないものを評価する方法のため、「どんな基準を設けるか」がこの制度運用のカギを握ります。人事の手腕が試される領域であり、風土改革や離職率の低減など大きな成果にも繋がる領域です。「正解がない世界でもあるため、常に工夫し続けることが必要」というお話が最後にあったように、ぜひ粘り強く取り組んでみてはいかがでしょうか。