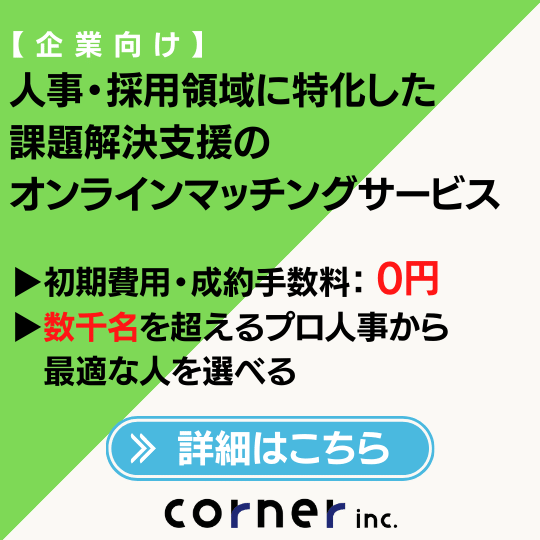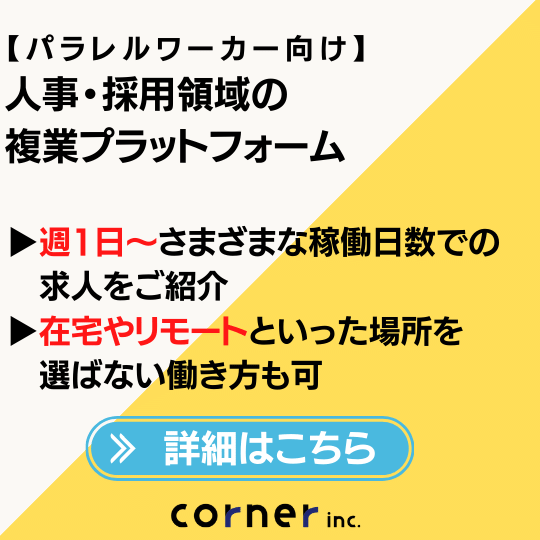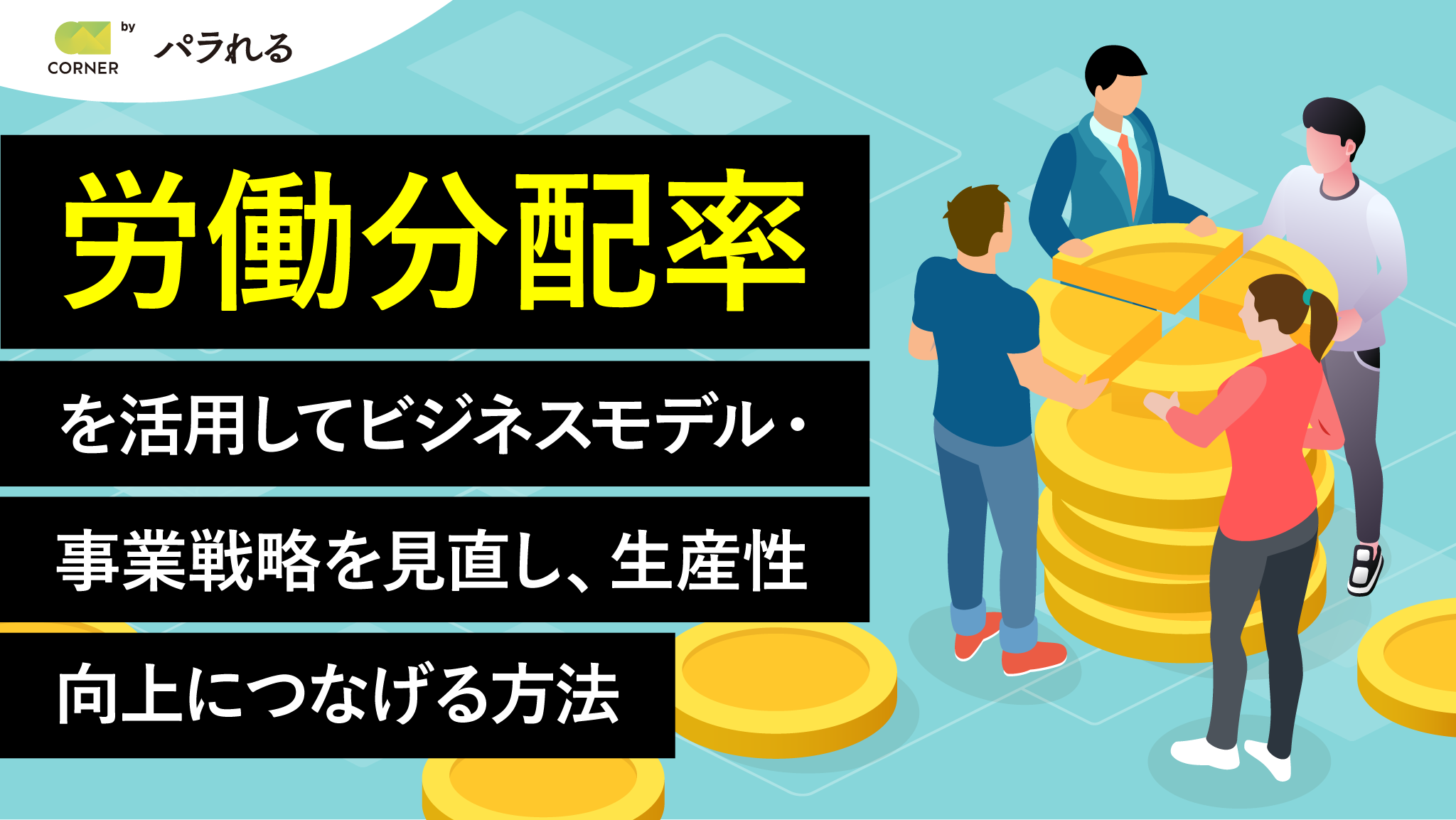グローバル企業が多く導入する「職務等級制度」がハマる組織とハマらない組織

以前、このパラれるのメディアにて「等級制度」についての記事を掲載しました。
前回の記事はこちら
「普遍性とフレキシブルさを持ち合わせた「等級制度」のつくり方」
ただ等級制度と一口に言っても、「職務等級制度」「職能等級制度」「役割等級制度」など様々なものがあります。そこで今回は、その等級制度の中でも近年徐々に導入が進んでいる「職務等級制度」についてより深掘りするべく、大企業・成長企業それぞれにおいて経営戦略と連動した人事制度改革の実績を持つパラレルワーカーの方に再びお話を伺いました。
▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
職務等級制度とは
──「職務等級制度」とはどのようなものなのでしょうか。職能等級制度や役割等級制度などとの違いも踏まえて教えてください。
等級制度とは、「企業が従業員の給与を決める上での格付けを、数字やアルファベットなどで表したもの」です。それらが「何をモノサシとして設計されるか」によってその分類が変わり、能力・職務・役割などによって区分・序列化されるのが一般的です。
代表的なものとして以下3つがあります。
①職務等級制度
②職能等級制度
③役割等級制度
職務等級制度
昨今よく目にすることの多いジョブ型は職務(仕事)をモノサシとして等級を定義するものであり、日本ではこれを「職務等級制度」と呼んでいます。元々は外資系企業に多く見られたもので、グローバルで共通のモノサシを用いながら職務価値を測定します。
会社ビジョンを実現する上で必要となる組織(仕事)のアカウンタビリティ(説明責任・義務)を基に、その価値をいくつかの観点から評価していき、その総合点によってポジション毎の等級が定められることが多いです。
職能等級制度
日本では従来から等級制度のモノサシが人に着目される傾向があり、ケイパビリティ(能力)の観点から等級を定義することが試みられてきました。これが「職能資格制度」と呼ばれ、ケイパビリティ(能力)の中でもマインド(意欲)を重視するのかスキル(技能)を重視するのかなどで等級の定義が微妙に異なってきます。
役割等級制度
マインドやスキルは在籍年数によって変動する面があり、必然的に年功序列になりやすいという弊害が語られるようになりました。それを受け日本でも成果主義やコンピテンシーがトレンドとなり、併せて職務と職能の折衷のような「役割等級制度」の検討が進んできました。この「折衷」がポイントなのですが、
「職能等級制度よりの役割等級制度なのか」
「職務等級制度よりの役割等級制度なのか」
によってその定義方法や運用方法が変わるなど、各社各様となる混乱が見られたこともありました。そのため「役割等級制度」と「職務等級制度」の厳密な定義の違いは曖昧さが残るところです。
なぜ今、職務等級制度が日本国内で広がっているのか

──先ほど挙げていただいた等級制度の中でも、「職務等級制度」が関心を集めている背景や理由にはどういったものがあるのでしょうか。
職務等級制度の考え方自体は、元を正せば欧米の人事システムが発祥です。グローバルレベルで展開するいくつかの人事系コンサルティングファームが職務価値評価の手法を提供しており、これを導入する企業が多く見られてきました。
日本でもこれらが導入されていったのは、特に製造業を中心としたグローバル展開がきっかけです。グローバルレベルでの報酬体系を検討する必要に迫られたことで、職務等級制度を導入せざるを得なくなったというのが実際のところでしょう。
一方、国内が主要なビジネスドメインとなる企業においては職務型等級制度を導入するきっかけが弱く、その運用の難しさも手伝って当初は導入が進みませんでした。しかしながら近年になって「ジョブ型」というキーワードと共に職務等級制度が着目されるようになり、導入検討が進み始めています。
その背景には終身雇用がいよいよ難しくなってきたこと、社内・社外での適材適所の配置を進めざるを得なくなってきたことの影響が大きいです。VUCAと呼ばれる先の予測ができない時代では、企業における職務内容や技能も安定的なものではなくなり、個人のキャリアも1社に限定するものではなくなってきています。これらの変化に柔軟に対応できる制度として、職務等級制度に注目が集まっているというのが現状です。

職務等級制度が有効な組織とは
──「職務等級制度」はどんな企業や組織だと特に活用しやすい制度なのでしょうか。企業フェーズ・規模・社風など、特徴や共通点などがあれば教えてください。
ようやく日本でも職務等級制度への関心が以前より高くなったのですが、やはり合う企業・合わない企業は依然としてあります。その判断軸としては「企業文化との整合性」にあることが多く、その結果次第では職務等級制度をカスタマイズしていく必要があります。
【例】企業文化としてスキル(技能)が重要な場合、スキル認定のレベルを職務価値評価のモノサシとして組み入れる、など
特に海外市場のウェイトが大きい企業(製造業など)は最も親和性が高く、反対に国内市場中心かつ1人ひとりをじっくりと育てることを重視する企業は親和性が低いと言えます。先ほど「職務等級制度と役割等級制度は厳密に区分しにくい」とお伝えしましたが、本来の職務等級制度をどこまで取り入れるかで変わってきます。
①グローバルで報酬設計を行うケース
②外部報酬水準や職務価値評価の観点との整合は取るものの、個別ポジション毎の厳密な職務価値評価は行わずに役割等級に近い設計に止めるケース
③職務価値評価を行わずに純粋に役割定義だけを行うケース
日本企業の場合②に落ち着くことが多い印象があります。シード~アーリーステージ段階(商品やサービスのリリースに向けて準備をしている段階)の企業などは③でも十分なことが多いです。
職務等級制度を導入している企業事例
──職務等級制度の導入事例を、その目的や結果なども踏まえて具体的に教えてください。
①グローバルで報酬設計を行うケース
②外部報酬水準や職務価値評価の観点との整合は取るものの、個別ポジション毎の厳密な職務価値評価は行わずに役割等級に近い設計に止めるケース
③職務価値評価を行わずに純粋に役割定義だけを行うケース
今回は前述した3つのケースから、②のケースについてご紹介します。
導入企業
・国内が主要なビジネスドメイン
・レイターステージ(事業が成長を経て安定し、株式上場やM&Aなども視野に入る段階)に位置する企業
・新卒採用者も増えつつ、様々な企業から入社する中途採用のメンバーが加速度的に増えてきた状態
導入目的(課題)
・元々の制度は「職能等級制度」に近い非常に簡素なもので、年功序列的な運用になっていた
・それにより新たに入ってきたメンバーから「どうすれば等級が上がるのか」「スピード感がないのではないか」といった疑問の声が多く挙がり、人事制度の再構築の必要性が高まった
導入内容
・職務等級制度の考え方と、職務価値評価フレームワークを活用した「役割等級制度」
・等級毎の標準的な期待役割を定め、職務価値評価の点数により同じ等級内でもある程度上下動可能なものとして運用しやすい形で設計した
結果
・職務価値によって等級が決まる点から若手登用が行いやすくなり、組織のフレッシュさを維持できるようになった
・一方で等級が下がるケースも必然的に生じるため、慎重な運用が求められた。当然人事部だけで運用できるものではなく、ミドルマネジメントとの協調が必要不可欠に。ただそれにより人事とミドルマネジメント間のコミュニケーションが活発化したのは副次的な効果だった
■合わせて読みたい「等級制度」に関する記事
>>>等級制度のつくり方。普遍性とフレキシブルさを持ち合わせた設計とは?
編集後記
等級制度、評価制度、報酬制度。これら人事制度を構成する3本柱の中でも、特に等級制度はその企業が求める人材や作りたい企業文化に大きな影響を及ぼすため、慎重に検討を進める必要があります。
「これからはジョブ型だ。だからこそ職務等級制度だ」と短絡的かつ限定的に考えるのではなく、自社との整合性も鑑みた上であえて役割等級制度に近いものを取り入れるなど、あらゆる可能性を検討した上で運用していくことが成果につなげる上でも重要なのだと感じました。