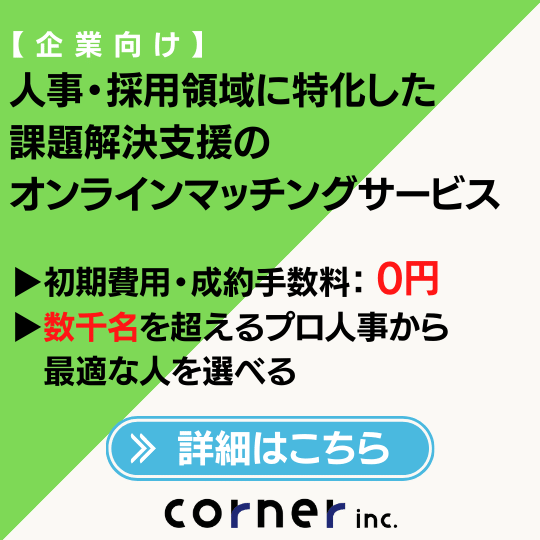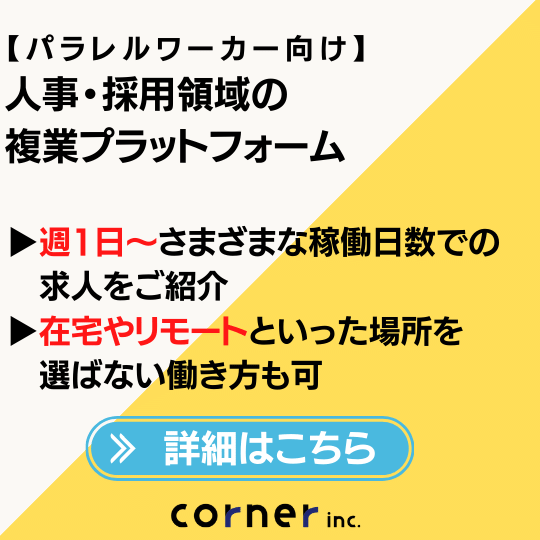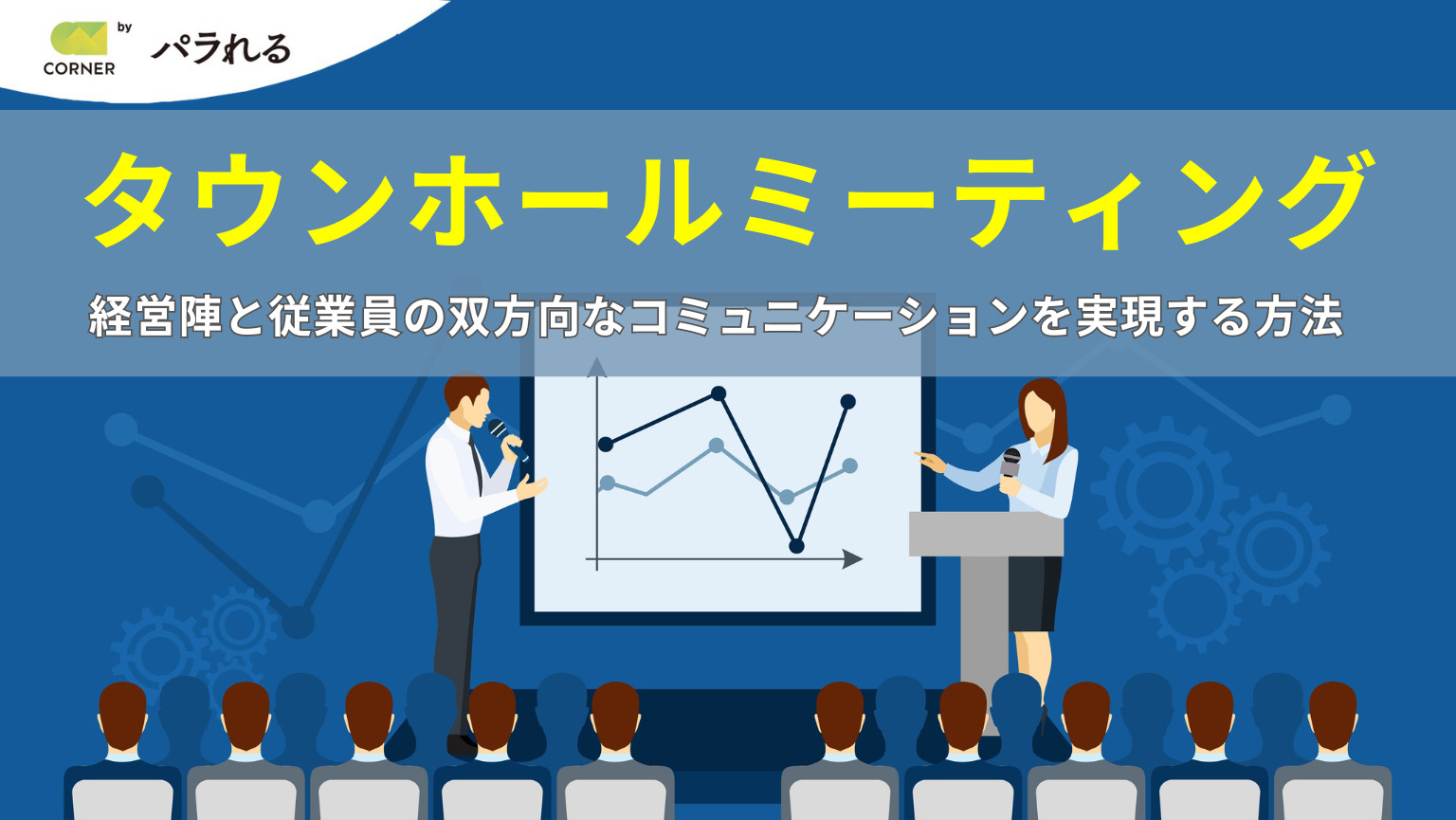「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定背景と、企業・人事が注意するべきポイント

2021年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(以下フリーランスガイドライン)」が策定されました。その名の通り、これまで弱い立場にあったフリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的に、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにしつつ、これらの法令に基づく問題行為の明確化に向け、実効性・一覧性のあるガイドラインとなっています。
今回は、このガイドラインの内容と、企業や人事担当者が特に注意するべきポイントについてご紹介します。
目次
フリーランスガイドラインの策定背景
──「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定された背景には、どのような世の中の動きがあるのでしょうか?
フリーランス人口の増加と、 2016年頃から掲げられた「一億総活躍」「人生100年時代」というスローガンを踏まえ、日本政府は経済産業省(中小企業庁)、厚生労働省、公正取引委員会等を中心にフリーランスの支援や保護といった環境整備を積極的に進めてきました。
また2018年1月には「副業・兼業ガイドライン」が策定され、その後2020年9月の改定を受け企業の副業解禁が待ったなしの状態に。さらに2020年冒頭より始まったコロナ禍で、副業・兼業を始める個人の方が急増したことを受け、一般的に「立場が弱い」とされてきたフリーランスを守るための環境整備としてこの「フリーランスガイドライン」を策定した、というのが大きな流れです。
内閣官房の試算によると、日本国内における2020年の広義のフリーランス人口は462万人とされています。一方で「フリーランス側の立場が弱すぎる」という問題は今に始まった話ではなく、手厚く守られる雇用契約とは違い、業務委託契約では残業や最低賃金などの概念もありません。
もうすぐ労働人口の10%にもなるであろうフリーランスを取り巻く環境がこのままで良いはずがなく、国としてもこの事実を重くとらえているのだと思います。
とはいえ、現状フリーランスを活用できている企業は少数派のため、どちらかといえば企業よりもフリーランス本人の方が自身を守るためにこのガイドラインを読んでいるような気がします。
私たちは人事に関する領域で事業をやっているため、周囲にはこの分野に敏感な方々が多い環境にいますが、一般的な感覚で言うとフリーランスガイドラインの内容はおろか、その存在すら認知していない企業が大半なのではないでしょうか。
独占禁止法・下請法・労働関係法の適用関係
──今回のガイドラインで定められている独占禁止法、下請法(下請代金支払遅延等防止法)、労働関係法とは、フリーランスで働く人とどのような関係があるのでしょうか?
フリーランスが事業者と取引する際には、その取引全般に「独占禁止法」が適用されます。また、相手の事業者の資本金が1,000万円を超えている場合は「下請法」も同時に適用される形です。
併せて、全ての取引において、業務実態などから判断して「労働関係法」が適用される可能性があります。
独占禁止法・下請法とは
前述の通り、一般的にフリーランスは弱者的地位に立ちやすいため、優越的地位にある事業者から不当な不利益を与えられることを防ぐために、独占禁止法・下請法で規制をしています。具体的には以下のような行為です。
また、直接的にフリーランスへ発注を行う事業者だけでなく、事業者とフリーランスをマッチングする「仲介事業者」に対してもガイドラインが定められています。
例えば以下のように、仲介事業者が一方的に規約を変更し、フリーランスへ不当に不利益を与えることについても、優越的地位の濫用として問題となります。
・フリーランスから仲介事業者に支払われる手数料が引き上げられる。
・フリーランスに対し、新しいサービスの利用を義務化してその利用手数料を設定する。
・発注事業者からフリーランスに支払われる報酬が減る。
労働関係法とは
業務実態などから判断して「労働者」と認められる場合は、「労働関係法令」が適用されます。具体的には、以下のような業務実態が対象となります。
※「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要版)」15ページより引用
見かけ上は雇用関係になくとも、仕事の進め方や時間まで事細かく指示されたり、そもそもその仕事を受けるかどうかをフリーランス自身が決められなかったりするケースは、労働者性が認められて労働関係法令(労働基準法・労働組合法)の保護を受けることができます。

企業や人事担当者が特に注意するべきポイント
──それでは今回のガイドラインを踏まえて、企業や人事担当者が特に注意するべきポイントはどんなところでしょうか。
フリーランスガイドラインの概要版で紹介されているような問題ケース(※)については、見ていただければどれも注意しなくてはいけないなと感じるはずです。しかしながら、事業者・フリーランスの両者が「悪気なく」かつ「良かれと思って」この問題行為を行ってしまうケースはよくあります。
1つ例を挙げて説明しましょう。
ある企業の面接日程調整を業務委託で行っているフリーランスの方がいました。
普段の面接は東京の事務所で実施していましたが、ある時北海道から応募者があり、面接者もちょうど同タイミングで北海道へ出張することが発覚。
「私が北海道で面接場所を探しますよ!」とフリーランスの方が気を利かしてホテルのロビーや会議室を調べて予約してくれた結果、面接者も「助かるよ、ありがとう!」と喜び、スムーズに選考が進みました。
この例を見てどう思いますか?お互いに「良かれ」と思って動いているため、何ら問題ないように見えるかもしれません。でも、この業務は業務委託契約書には書かれていないので、まさに「契約の範囲外のサービス提供」にあたります。
しかし「業務委託契約書通りに全部進めるのがベストか」というと、決してそんなことはありません。あまりにきっちり線引きし過ぎると、事業者側もフリーランス側も大きなストレスとなってしまうからです。
アウトソーシング的な仕事であれば「正しくこなす」ことが求められるので、業務の線引きもしやすいものです。しかし「知的労働者」として成果責任が求められる場合、フリーランス側があえて契約範囲を超えてサービス提供をしたり、コミットメント度合いを大幅に増やしたりすることも多々あります。早期に企業の信頼を獲得し、その後をスムーズに進めるためです。契約書記載の業務に限定することにより、そうしたフリーランスの可能性を狭めてしまうことにも繋がりかねないのです。
とはいえ「両者が良いと思っていればOK」ということにはなりません。なぜならそうした行為により、フリーランス側の実質的な仕事の単価が下がってしまうからです。また、その両者の間では「良かれと思って」の関係で済んでも、他のフリーランスを受け入れた際に「いつもこれでやってもらっているから」と押し付ける形になってしまうことも考えられます。
このフリーランスガイドラインに書かれていることを守るのは大前提として、上記のように互いに“悪気なく”やってしまっていることに対して、本当にこれで良いのか、もっと視座を高めてより良い形はないのか、などを今後さらに検討していかなければならないと感じています。
■合わせて読みたい「人事労務関連の法改正とルール」に関する記事
>>>弁護士に聞いた「副業/兼業ガイドライン」の改訂背景と、人事が注意するべきポイント
>>>2021年4月施行「高年齢者雇用安定法」の改正ポイントと、企業における努力義務などの具体的内容とは
>>>「同一労働同一賃金」は“人材育成”に効く⁉︎ 中小企業が制度をうまく活用するポイントとは
>>>「女性活躍推進法改正」で2022年4月から対象企業が拡大。その改正ポイントと対応方法について
>>>「パワハラ防止法」が2022年4月からすべての企業で義務化。そのポイント・対策の解説
>>>年金制度改正法が2022年4月から順次施行。そのポイントを解説
>>>「改正育児・介護休業法」(2022年4月1日より順次施行)の内容と対応ポイント解説
>>>【弁護士監修】複業・副業制度を導入する場合、注意すべきルール一覧
>>>「働き方改革関連法」の概要と、2023年4月施行の法定割増賃金率引上げのポイントを解説
>>>「フリーランス保護新法」が成立。概要や対策など最新情報を解説します。
>>>「2024年問題」で物流業界に何が起こる?影響と対策について学ぶ
編集後記
強い立場にある事業者に悪意があり、弱者であるフリーランス側が不当に不利益を被るケースばかりが注目されがちですが、「互いに悪気がないケース」にもフリーランス活用の落とし穴があるのだということを今回のインタビューを通じて理解することができました。
このフリーランスガイドラインを読み込み、「当社は問題ない」と感じていたとしても、どこかでその落とし穴にハマってしまっているかもしれません。そうならないような環境整備を進めることが外部人材からも選ばれる会社の条件であり、より柔軟に組織を作っていくために必要なことなのだと思います。