「2024年問題」で物流業界に何が起こる?影響と対策について学ぶ

物流業界における「2024年問題」についての報道や警鐘が鳴らされてしばらく経ちますが、いよいよその引き金となる働き方改革関連法の施行時期が2024年4月1日に迫ってきました。
今回は、物流領域での豊富な知識と経験を持つパラレルワーカーに「2024年問題」の概要から影響・対策方法に至るまで幅広くお話を伺いました。
▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
物流業界における「2024年問題」とは
──物流業界における「2024年問題」について、法改正の内容も踏まえて教えてください。
2018年6月に法改正され、2019年4月1日から順次施行されてきた働き方改革関連法の中に『時間外労働の上限規制』があります。自動車運転業務・建設事業・医師については施行日が遅く設定されていましたが、いよいよ2024年4月1日より法施行がなされ、時間外労働・拘束時間の2つの上限規制が行われます。
具体的には、それぞれ以下のように変更されます。
(1)時間外労働規制
変更前:規制なし
変更後:上限年960時間(休日労働含まず)
(2)拘束時間規制
<1日あたり>
変更前:原則13時間以内・最大16時間以内、かつ15時間超は1週間2回以内
変更後:原則13時間以内・最大15時間以内、 かつ長距離運行は週2回まで16時間(14時間超は1週間2回以内)
<1か月あたり>
変更前:原則293時間以内。ただし、労使協定により年3,516時間を超えない範囲内で320時間まで延長可
変更後:原則年3,300時間、284時間以内。ただし、労使協定により年3,400時間を超えない範囲内で310時間まで延長可
なお、(1)に違反した事業者は労働基準法違反として『6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金』が科せられる可能性があります。
「2024年問題」による影響
──この「2024年問題」により発生すると想定されている影響にはどのようなものがありますか。
「2024年問題」により発生が想定される影響について、物流企業・発荷主(荷物を出荷する事業者)・着荷主(荷物を受け取る事業者)・一般消費者の各視点から解説します。
物流企業
・時間外労働規制の厳格化により、運転手の労務管理についても厳格化が必要となり、総労務費が上昇するおそれがある
・これまで運転手1名で輸送していた長距離区間の一部について、交代要員を確保する必要があり、コスト増となるおそれがある
・交代要員を確保する代わりに、目的地までの中間地点でトレーラーヘッド部のみを交代し、引き継いで輸送する『中継輸送』を行う必要があり、コスト増となるおそれがある
・労務費の高騰や従業員の確保がままならず、倒産・廃業する中小運送事業者が増えるおそれがある
発荷主(荷物を出荷する事業者)
・法施行に対応するため、後述する着荷主との間で取引条件見直しに当たっての交渉を要するおそれがある
・荷物の引き渡しを速やかに行わず、2時間を超える待ち時間を発生させた場合、運送事業者からの訴えにより監督官庁からの罰則・警告を受けるおそれがある
着荷主(荷物を受け取る事業者)
・荷物の受取を速やかに行わず、2時間を超える待ち時間を発生させた場合、運送事業者または発荷主からの訴えにより監督官庁からの罰則・警告を受けるおそれがある
一般消費者
・遠隔地(例:首都圏~九州間など)から輸送されている生鮮食品・水産品について、輸送費の上昇により販売価格の上昇や入手性の低下が発生するおそれがある
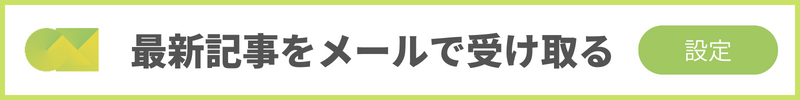
物流企業側の対策観点
──先ほど解説いただいた影響への対応として、物流企業側で行っている対策にはどのようなものがありますか?
大きく以下5つの観点で対策を行っている企業が多いです。それぞれご紹介します。
(1)労務管理
・デジタルタコグラフ(※)を活用して業務記録および運行記録を電子データで管理することにより、運転手による自己申告を前提とした労務管理から脱却
・法施行に基づく労働時間に見合った輸送ルートおよび配車計画の再設計
(※)デジタルタコグラフとは、自動車運転時の速度・走行時間・走行距離などの情報をメモリーカード等に記録するデジタル式の運行記録計のこと。通称『デジタコ』。
(2)人員増強
・運転手の採用(同業他社からの引き抜きや転職がメイン)
・管理部門人材の採用(労務管理強化に伴う、コンプライアンス遵守を前提としたもの)
・営業人員の採用(昔から荷主側が強い業界・商慣行があるため、それを打開すべく条件交渉をする人材として)
(3)DX推進
業界全体でDX化は遅れているものの、下記システムなどの導入により効率化を目指すことがポイントとなります。
・(大前提としての)デジタルタコグラフ実装率の向上
・商品が物流センターから出荷された後から届け先までの輸配送を包括的に管理する輸送管理システム(TMS:Transport Management System)の導入
・荷物の積卸しのために車両を停車する場所と時間の予約管理をするバース予約システムの導入
・ルート最適化システムの導入
(4)設備投資
・トラックの増車
・拠点の移転または新設
・サーバーやPCなどIT関連投資の実施
(5)M&A
中小の運送事業者が大多数を占めることもあり、(1)~(4)の対策が困難な物流企業については大手企業の傘下入りなど同業他社による買収を受け入れることで法施行に対応するケースも多々あります。
特に、運転手に対してはこれまでの労務管理方法では対応が難しいため、労使共に対応が必要です。その際、会社・運転手側双方の意識改革が欠かせません。異なる立場の関係者に向けて意識改革を促しつつ、正しい労務知識を伝えて理解してもらうことが人事のミッションです。
さらに、業界全体で不足している運転手をどのように採用するのか、他社との違いをどう打ち出していくのかまで考え抜くことも重要です。運転手以外にも、荷主に対して交渉を行える営業人材や、人材不足をITで補うためにDXを推進していく人材の採用・育成なども同様です。これまで以上に物流業会でも人事に期待される役割は大きくなっていくと考えられます。
荷主企業側の対策観点
──同じく、荷主企業側の視点での対策事例についても教えてください。
荷主企業側の視点では、以下4つの観点で対策を行っている企業が多いです。それぞれご紹介します。
(1)納品スケジュール管理
・発荷主として着荷主との取引条件の交渉を行うことで、受注から納品までのリードタイム延長を実現し、自社が利用している運送事業者へのサービス要求水準を緩和させること
・発荷主として、法施行に基づく労働時間に見合った輸送ルートおよび配車計画の再設計
(2)プロセス管理
・荷待ちの『2時間ルール』を超過しないよう、工場・物流センターでの荷待ち時間を発生させないための業務プロセスの見直しおよび人員増強の実施
(3)DX推進
・事前出荷通知(ASN:Advanced Shipping Notice)の送受信を可能とする情報システムの導入
・自社が利用する運送事業者のデジタコ実装率の向上支援
・商品が物流センターから出荷された後から届け先までの輸配送を包括的に管理する輸送管理システム(TMS:Transport Management System)の導入
・荷物の積卸しのために車両を停車する場所と時間の予約管理をするバース予約システムの導入
・ルート最適化システムの導入
(4)設備投資
・物流センターの移転または新設
・物流センター内の自動化推進にあたってのマテハン機器(物流業務を効率化するために仕様される作業機械の総称)や、倉庫管理システム(WMS:Warehouse Management System)をはじめとする情報システムの導入
・事前出荷通知の送受信実現に当たってのサーバーやPCなどのIT機器の導入
荷主企業においても物流企業同様、運転手不足による配送力低下を補うためには上記のような対応が必須です。そのためにもより一層のDX化に加え、採用や既存社員の育成を進めることが急務と言えます。
■合わせて読みたい「人事労務関連の法改正とルール」に関する記事
>>>弁護士に聞いた「副業/兼業ガイドライン」の改訂背景と、人事が注意するべきポイント
>>>2021年4月施行「高年齢者雇用安定法」の改正ポイントと、企業における努力義務などの具体的内容とは
>>>「同一労働同一賃金」は“人材育成”に効く⁉︎ 中小企業が制度をうまく活用するポイントとは
>>>「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定背景と、企業・人事が注意するべきポイント
>>>「女性活躍推進法改正」で2022年4月から対象企業が拡大。その改正ポイントと対応方法について
>>>「パワハラ防止法」が2022年4月からすべての企業で義務化。そのポイント・対策の解説
>>>年金制度改正法が2022年4月から順次施行。そのポイントを解説
>>>「改正育児・介護休業法」(2022年4月1日より順次施行)の内容と対応ポイント解説
>>>【弁護士監修】複業・副業制度を導入する場合、注意すべきルール一覧
>>>「働き方改革関連法」の概要と、2023年4月施行の法定割増賃金率引上げのポイントを解説
>>>「フリーランス保護新法」が成立。概要や対策など最新情報を解説します。
編集後記
いよいよ目の前に迫った「2024年問題」。物流業界のみならず多方面に大きな影響を与えることが予想されていますが、これを前向きに捉えれば『物流業界全体の生産性向上にもつながるチャンス』とも考えることができます。物流業界に在籍している方はもちろん、関連業界への人事的な支援を行っている方もこの「2024年問題」については正しく理解して対策を講じていきたいものです。






