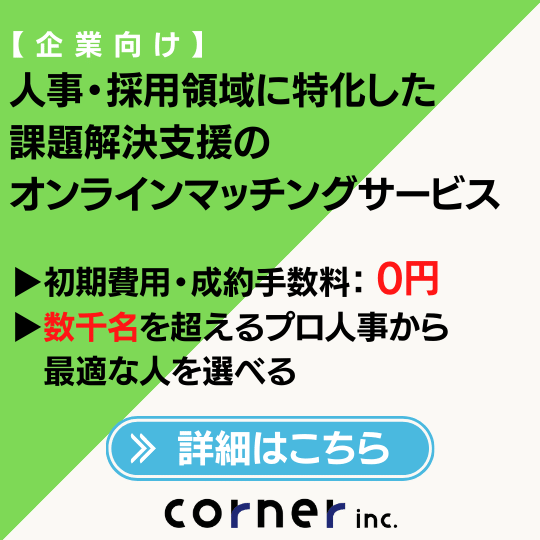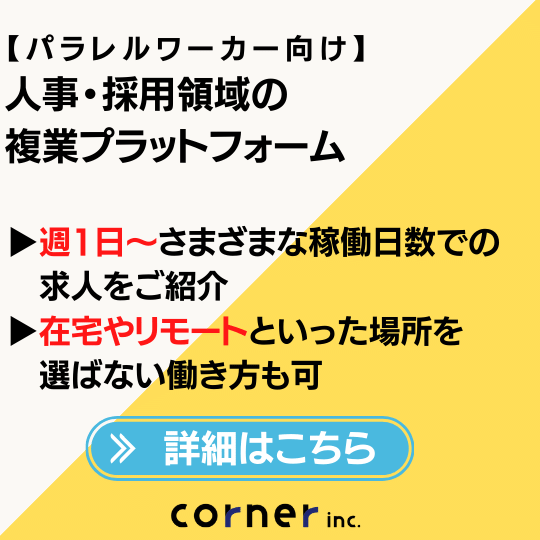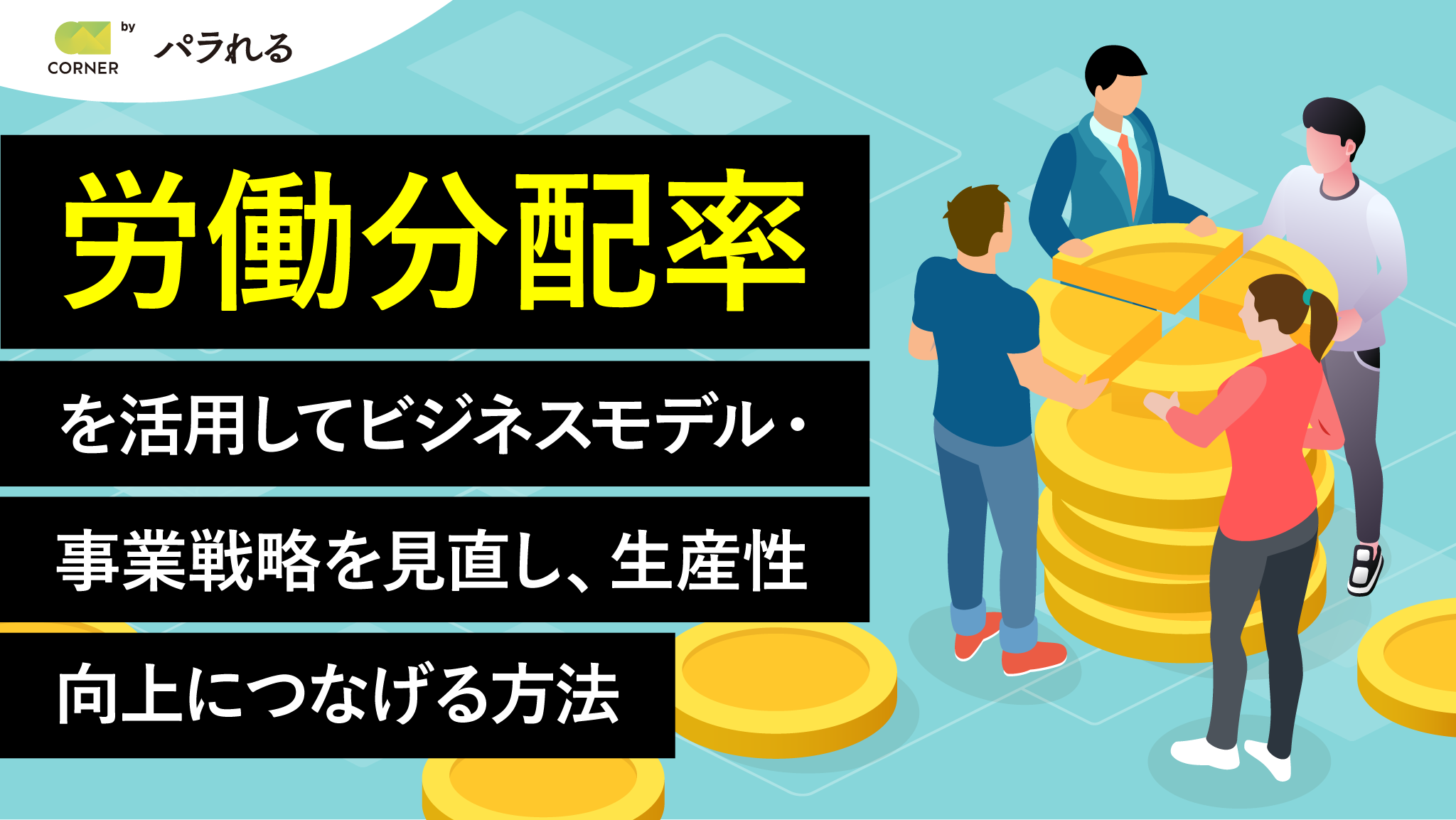「越境学習」の本質は葛藤にあり!?企業の人材育成に活かす上で抑えるべき本質とポイントとは
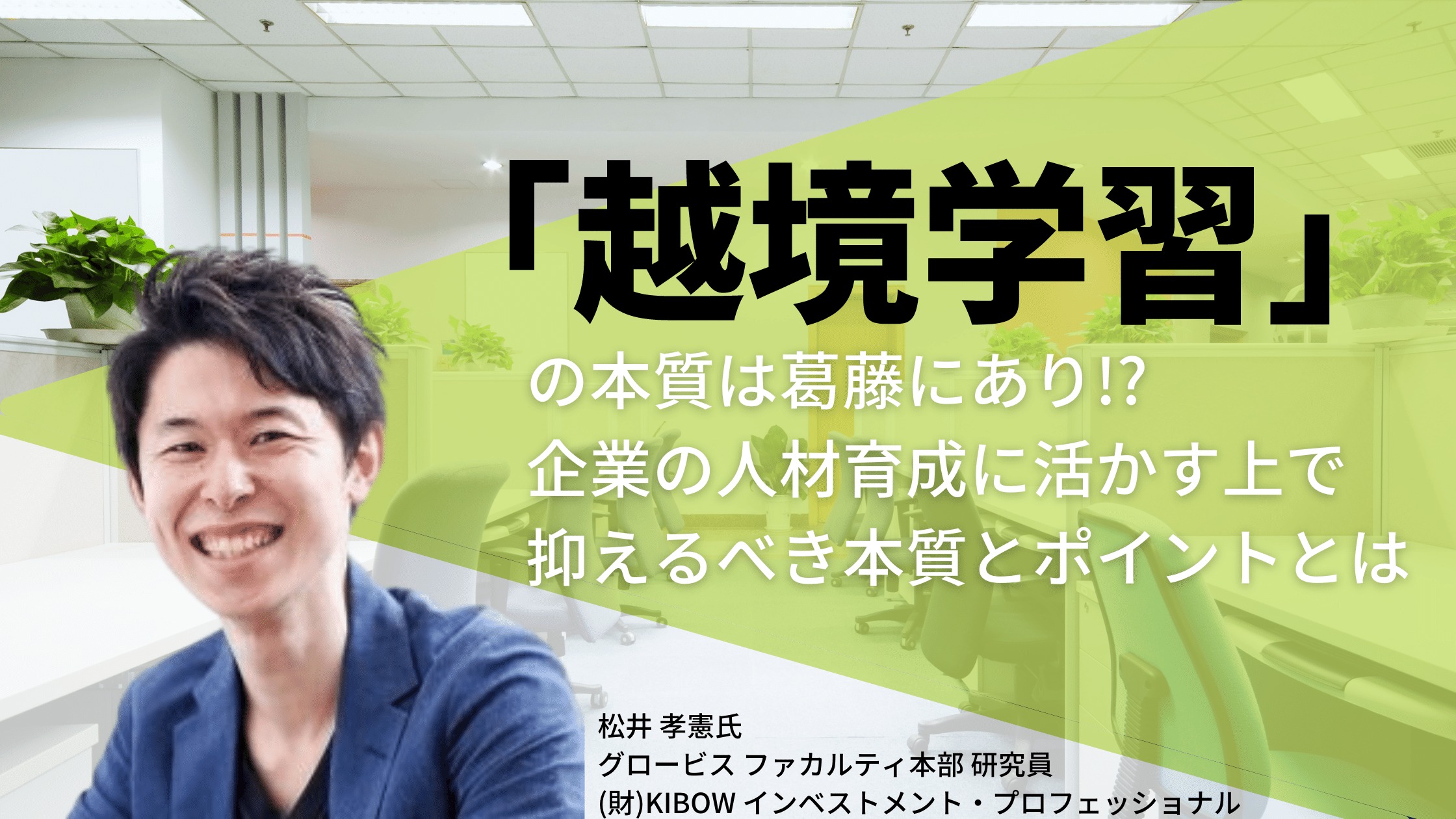
終身雇用が崩れ、キャリア自立をより求められる環境になったことから、ビジネスパーソン個人が職場以外に学びの場を求める機会が増えてきました。
また企業側も社員のキャリア開発やイノベーションへの寄与を期待して、組織的に社員を外部へ“越境”させる「越境学習」を人材育成の一環として導入する企業も増加しています。
しかし、「越境学習」は少しアカデミックな分野であることもあってか、世間一般の理解と研究者・専門家側の理解には少しギャップがあるようです。
そこで今回は、この「越境学習」をテーマに実践と研究に取り組む松井 孝憲さんに、その定義と企業へ導入する際のポイント等をお聞きしました。
<プロフィール>
松井 孝憲(まつい たかのり)/グロービス ファカルティ本部 研究員、(財)KIBOW インベストメント・プロフェッショナル
一橋大学法学部卒業、早稲田大学大学院政治学研究科修了後、(株)シグマクシスにて、新規事業立案、人事・人材開発プロジェクト等に従事。その後、並行して2011年にNPO法人二枚目の名刺に参画、2015-16年に常務理事。企業とNPOの協働プロジェクトを運営する。現在、グロービス ファカルティグループにて副(複)業・パラレルキャリア・越境学習の研究活動しつつ、(財)KIBOWの社会インパクト投資にも従事。
目次
越境学習とは
──まず「越境学習」の定義について教えてください。
一般的には「ビジネスパーソン等が組織の枠を越えて今までとは違う新しい視点を培うという学習スタイル」のことを指すことが多いと思います。
例えば、社会人大学院やビジネススクール、地方課題の解決ワークショップ参加、社外留学、ワーケーション、プロボノなどがあり、パラレルワークなどもその一種と言えます。
この定義はもちろん正しいものですが、もう一歩踏み込んで考えてみると、「越境学習」についてより立体的な捉え方ができます。
言葉を「越境」と「学習」に分けてそれぞれ考えてみると、以下の通りです。
「越境」について
越境学習における「越境」とは、物理的な境界(組織や地域など)だけではありません。“心理的な境界”もそこに含まれます。
越境学習の研究をされている法政大学の石山教授は、本人の捉え方にホーム・アウェイという感覚が生じていたら、そこには境界があると考えられると指摘しています。
例えば同じ「アメリカ旅行」であっても、人によっては「越境」になる場合とそうではない場合があります。
初めて渡米する方であれば「越境」になり得ますが、元々海外留学の経験があったり英語が堪能であったりする場合には必ずしもアウェイだとは言えず、本人が「越境」と捉えないケースもあります。
もっと身近な例を挙げると、同一の職場の中でも心理的な境界を越えている(すなわち「越境」している)ケースはあります。
反対に、組織を飛び出して他の企業や地域で働いても、本人がアウェイな環境だと認識してなければそれは「越境」とは言わないかもしれません。
「学習」について
一方、学習については、一般的にスキルや情報のインプットがイメージされがちですが、より広義に捉えることも可能です。
何かしらのスキルを習得することに留まらず、自分の世の中における“位置取り”が変わることで「自分は何者なのか」という認知の変化が起こることを「学習」と捉えることもできます。
例えば、今の職場では自分のスキルなんてまだまだだと感じていた人でも、別の環境ではそのスキルが賞賛されたり人の役に立てたりすることも多々あります。
すると「この経験って意外と活きるんだ」「自分にはこんな一面があったんだ」と自分に対しての見方が変わり、世の中における位置取りにも変化が出てきます。まさにこの変化が「学習」なのです。
近年、「越境学習」の機会をつくる企業が増えたように感じます。
企業としては、例えば外部協働によるイノベーションや多様性の実現を、個人としては組織によらない学習機会や自律的なキャリアの構築を目的としていることが多いようです。
また、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが急増したことから、副業・複業(パラレルワーク)を始めるなど、組織の枠を飛び出して活動する個人も同様に増加しています。
でも、「ビジネスパーソンが社外へ出る=多様性やイノベーションの実現・個人の成長」と捉えるのは早計です。
上述の通り、越境学習には「境界を越えている」という本人の認知が欠かせません。
例えばパラレルワークを実践していても、自分が得意とするいわばホーム領域だけで展開している場合には、越境とは言えない場合もあります。
「越境学習は外形的なものだけではなく、心理的な要素を含んだもの」
こう捉えていただくと、これ以降の内容もご理解いただきやすいと思います。
越境学習は人材育成に有効なのか
── 一般的な理解だけでない越境学習の捉え方があるとのことですが、越境学習は人材育成に有効なのでしょうか?
私自身、「越境学習は人材育成に役立つ」と主張してきた立場の人間であり、その価値を身を持って経験しています。
しかしながら、先ほどお伝えしたような「越境」「学習」についての捉え方を捨象してしまうとその価値を実感する機会を逃してしまったり、そもそも「越境学習」というものへ期待する効果が本来とは異なるポイントに置かれてしまったりということが発生しがちです。
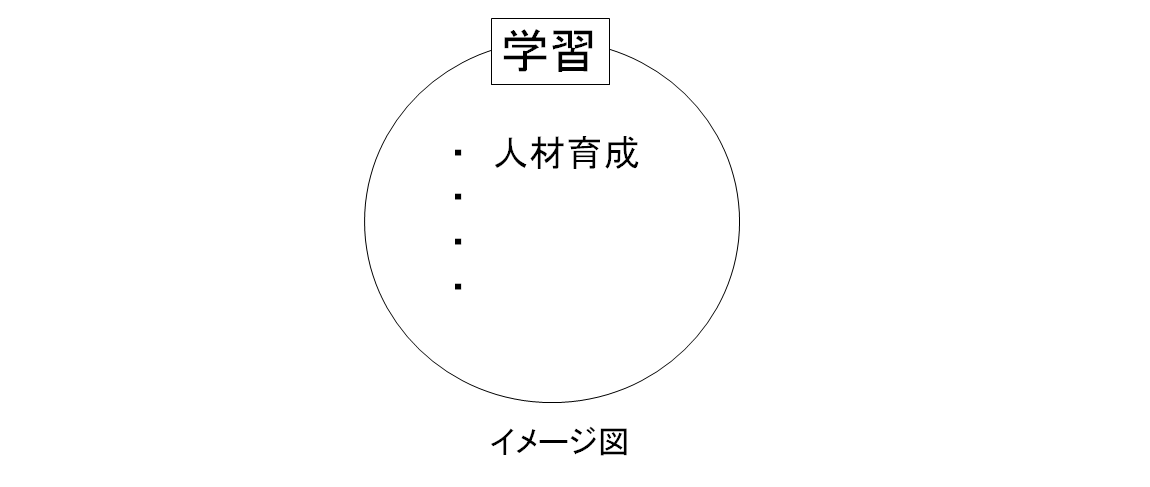
そもそも人材育成とは、企業などの経営組織が、社員に狙った通りに狙った形で学習してもらう、組織の都合に焦点を合わせた考え方です。
もちろん組織が人材を育成すること自体は悪いことではありませんし、むしろ経営活動の中でとても重要なものです。
しかし、越境学習における学習とは、必ずしも人材育成だけに限定される範囲のものだけではありません。
なので、「人材育成の範疇だけで越境学習を捉えると、その価値を取り違えてしまう」と、よく伝えています。
越境学習は組織の枠を越えるものであるため、そこから生まれる変化が、ある単体の組織にだけ都合の良いものではなくなってくることは当然考えられます。
つまり、越境学習を、組織の都合にだけ合わせた人材育成として役立てようとすると、大きなギャップが生まれてしまうことになります。
ここは今回の話の中でも特にお伝えしたいことです。
企業が越境学習を導入する際のポイント

──ここまでお話しいただいた「越境学習の本質」を理解した上で、企業はどのように越境学習を組織に活かしていくべきでしょうか。そのポイントや注意するべき点なども教えてください。
最大のポイントは、「いかに本人が“自発的”に越境できるか」にあります。
よく越境学習について議論する際、「組織からの指示がきっかけで越境する、というのは形容矛盾(*)では?」という話が出ます。
(*)形容矛盾とは、論理学である語をその語のもつ性質に矛盾する語で形容すること。「三角な円形」とか「ゴム製の鉄板」などがその例。
企業都合で越境学習させようとすると、本人が「越境」をどう捉えているか不明なまま行われることも多く、期待した効果や本来の価値が実感できない事態につながりやすい。
そもそも自発的に境界を越えていくからこその「越境」であって、経営者や人事に言われたからするものではない、という意見もあります。
その考えも一理ありますが、個人的には「企業のイニシアチブやプログラムの中で越境学習が行われることにも意義がある」と考えています。
その理由は、組織から越境のきっかけを作ることが、個人の行動につながる側面があるからです。
では、企業において越境学習を実践する際に留意するべき点を、越境者、またそれを受け入れる組織の2つの側面から説明します。
越境者側のポイント
越境学習の価値をどこで測るか。これについて、最近の調査では「異質なものと出会ってどれだけ葛藤できているかどうか」がポイントになることが分かってきました。
この葛藤と出会わなかったり、もしくは回避してしまったりすると、越境学習の醍醐味を味わえていないということになります。
(調査引用元:越境体験ルーブリック & スタートアップ出向モデル契約書)
越境して異質なものと出会いモノの見方が変わる──これはビジネスパーソンにとって大きな痛みを伴うものです。時には過去の自分を卑下するような気分になるかもしれません。
その葛藤から逃げずに向き合いこれまでの自身の行動や思考を見つめ直せるかどうか。これこそが越境を通じて変化(学習)を生むポイントです。
また、その越境者が自組織に戻ってきたときにも同じく葛藤が起こります。
モノの見方や自身の位置づけに対する認知が変わった状態で自組織に戻ることで、元の組織を見て、「何だこれは」と愕然とし葛藤が起こるのです。
ただ、そこで「ウチの組織はダメだ」と排除するのではなく、「なぜ自分はダメだと思ったんだろう」と向き合い葛藤することで、越境者はさらに自身の認知を変化させます。
上述の石山教授は、「越境者は二度死ぬ」という言い方をされています。
越境を通じて、「死ぬ」という喩えで表現されるような葛藤、その量こそが学習・変化の源泉になるのです。
越境者を取り巻く組織側のポイント
越境者だけでなく、その上司や人事も同じく越境学習の本質を理解していることがとても重要です。
よくあるのは、「外から新しい情報や人脈を持ち込んで、すぐに組織に伝播して成果を上げてくれるんでしょ?」といった期待を上司や人事が持っていることで、越境学習の価値を見逃してしまうというケースです。
ただ単に新しい情報を持ち込むだけなら、インターネットやSNSで情報を眺めているのと大差ありません。
そういったインフォメーションとは違い、知恵(ナレッジ)は越境者が、異質なものと向き合い葛藤を乗り越えて生まれてくるもの。
それを組織の中で活かすには、同様の葛藤が組織メンバーに生じる可能性があります。
そのことを、越境者本人だけでなく、その上司や人事側も認識を揃えておかなければそもそも越境学習は機能しないということを理解しておく必要があります。つまり、越境学習を実践する上では、組織側でもそれなりの「覚悟」が必要だということです。
まれに、「とりあえず社員を外に出せばいいんでしょ?」と言われることもありますが、そういったスタンスでは絶対にうまくいかないことがここまでの話でご理解いただけるかと思います。
──「越境学習の本質」を上司や人事または受け入れ組織全体が理解することは、簡単なことではないように感じます。どうすれば組織の理解が得られやすいでしょうか。
理想は、経営層や上司・人事が実際に越境し、「葛藤と向き合うってどういうことなのか」を体感することだと思います。
通常業務を抱える中で越境することは容易ではありません。立場が上の人であればなおさらです。
またそういった方々はこれまでの実務での蓄積があるが故に、居場所が変わってもホームはホームのままということは往々にしてありますし、葛藤を受け入れる心理的な障壁も高くなりやすいものです。
上司や人事が越境することが難しいのであれば、せめて越境学習における成果やKPIを「即物的な業績やメリットではないところに比重をおくことができるか」を考えていくのが良いでしょう。
そもそも越境学習がもたらす変化は組織風土やメンバー間の関係性の変化にあるため、売上などの定量目標とは因果関係が遠いものです。
しかし、遠いからといって影響しないわけではなく、そういった変化を受け入れられる風土や関係性をつくることは必ずゆくゆくの目に見えた成果につながってきます。
越境学習を短期的なものではなく、中長期的な施策として認識してもらうこと。
またそれに合わせた定性目標を策定してもらうことが組織において重要だと考えます。
──他にも人事が関与する上で、越境学習の効果を高めるためにできることはありますか?
社員が「この経験は越境なんだ」と気づけるような支援を行うことでしょうか。
越境学習と聞くと、なにかプログラムを受けたり物理的に移動したりするイメージが先行しますが、実は越境はより身近なところでも日常的に発生しています。
例えば職場と家庭との違いや、子どもの学校でのPTA活動に参加することなどもその1つです。
前述した通り、本人がホーム・アウェイを認識していればその時点で越境になります。
「自分は今、越境している」ということに気づくことができれば、その中で起こる葛藤に向き合い、モノの見方や位置づけを変えていくことにつなげられ、結果的に自分の在り方、ものの見方を変えられる可能性が出てきます。
つまり、第三者の立場から定期的に「今まさに越境してるよね」と認知を促すことは、周囲ができる最初の支援と言えるでしょう。
例えば人事評価のタイミングなどで定期的に行動を棚卸し、認知や内省を促すことで越境学習の効果を日常的に感じることは十分に可能です。
こういったアクションを組織内のマネジメントラインにインストールしていくと、越境学習の効果をより実感しやすくなるはずです。
越境学習が効果的な企業・そうではない企業
──そもそも、どんな企業であれば越境学習が効果的に働くのでしょうか。
「イノベーションが必要な大企業こそ越境学習は必要だ」とよく言われますが、必ずしも企業規模だけで判断するものではありません。
それぞれの企業が置かれた「フェーズ」により、越境学習が効果的かどうかが分かれると考えています。
そもそも越境学習は、これまでの予定調和を崩し、組織の適応性を高めたり新たなイノベーションを生んだりすることに寄与するものです。
その効果から、一般的に硬直しているといわれる大企業にこそ必要だと言われやすいのですが、投資家として様々なベンチャー企業に触れてきて感じるのは、ベンチャーはベンチャーであるがゆえに非常に硬直的な面もあったりします。
なぜならベンチャーには大企業のように組織的な余剰資源や余白がないことも多く、リーンな組織運営を目指すことで余分なものを極力排除するといった組織文化になりやすいからです。
もちろんそれが一概に悪いというわけではありません。事業の立ち上げや新しいサービスローンチのフェーズにおいては、無駄なことに資源を使わず、目標達成のために集中していくことが必要なタイミングが必ずあります。
一方、よりフェーズが進んで、より多くのメンバーを受け入れるなど、組織の硬直をほぐして、新しい組織文化を作っていくことが必要なフェーズであれば、社員の越境学習は効果的かもしれません。
だからこそ越境学習は、大企業かベンチャーかといった企業規模ではなく、自分たちの組織課題や事業フェーズに合わせて導入を検討するべきものなのです。
【事例紹介】越境学習により社員のセルフリーダーシップ力を高めたパーソルキャリア(株)
──松井さんが実際に関わった企業で、越境学習を導入して成果を上げた企業の事例を教えてください。
人材サービスを手掛けるパーソルキャリア株式会社(旧:インテリジェンス)の事例をご紹介します。
私が関わった当初、パーソルキャリアはベンチャー気質の大きい営業組織として現場主導の風土がありました。
一体感や推進力といった意味では強い組織でしたが、同時に昇進してもマネジメントとして管理する人数だけが増えていき、社員の役割内容が大きく変わらないというキャリア課題も抱えていたのです。
この「予定調和」的なキャリアを打ち破りたい。社員のセルフリーダーシップを高めたい。
当時の人事責任者がそんな明確な目的を持っていたこともあり、これなら越境学習が効果的であろうと組織に導入することを決定しました。
ただしながら前述した通り、組織に「予定調和を破れ」と言われたから、そうするように越境しに来ました、ということでは、本人の中に「予定調和では無かった感を出す」という予定調和が生まれてしまい、越境学習の価値が見逃されてしまう可能性が高くなります。
そこで取り組んだのが、「いかに社員に強制せず、自発的に越境学習に取り組んでもらうか」という点です。
まず、越境希望者は指名ではなく自推してもらう形をとりました。
その中で「なぜこの越境学習プロジェクトに参加するのか」ということをエントリーの際に必ず明記してもらうようにしたのです。
幸いにも毎回定員を超える応募があり、その中からより目的が明確なメンバーを選ぶことでより自発性を担保できました。
参加目的が明確だと、参加メンバーがいざ越境し葛藤が生まれた際に、立ち戻る場所として活用できます。この目的がなければ、耐えられなかった葛藤もあったでしょう。
それだけ辛いシーンにぶち当たっても、当初の目的に立ち戻り、「自分はなんのために、これをやっているのか」を忘れずにいることで葛藤から逃げずに向き合い続けることができたのです。
またこの目的意識は、越境後、自組織に戻ってきてからも活きてきます。
外で見てきた世界をどう元の職場で活かすかという目的意識が明確であれば、ブレることなく行動に移すことができるからです。
また周囲の方も、その人がどんな目的で越境学習に臨んだかが分かり、新しい要素を受け入れやすい風土を作ることができたように思います。
数々の越境者と関わってきた中で、特に印象に残っている方の言葉を紹介します。
「これまでは自分が自らやって見せること、背中を見せることでマネジメントしてきました。でもそのやり方にも限界が来て、もっと違う方法はないかという思いで越境学習のプログラムに参加しました。
そこで出会ったのは “見守るマネジメント”というもの。これはパーソルキャリアの中ではあまり見られなかったマネジメント方法であり、その引き出しを自分の中に持つことができたのはとても大きな収穫でした。」
これまで、マネージャーとして部下と共に自分も一緒に手を動かしていた人が、その方法を手放して“見守る”ことは、大きな不安を伴ったはずです。
しかし、越境学習によってこれまでのやり方が上手くいかなかった経験や、そこから生じた葛藤と向き合い、自分のモノの見方や位置づけが新たになったことにより、これまでとは違うやり方を自分の中へ取り入れることができた。これこそがまさに越境学習の価値です。
■合わせて読みたい「社員育成プログラム」関連記事
>>>オンボーディング成功のポイントは「ユーザー視点」。押さえるべき点と事例紹介
>>>オンライン環境で失敗しない、オンボーディングの3ステップ
>>>社員の能力を最大限引き出す、オンライン/オフラインでの階層別研修の在り方
>>>研修効果測定で研修から組織の成果へとつなげる方法。
>>>「OJD」で長期的・計画的にマネジメント人材を育成する方法
>>>「企業内大学」を立ち上げ、持続的な人材育成を実現する方法とは
>>>「ブレンディッドラーニング」を取り入れて研修効果を高めるには
>>>「人材育成体系」はどう見直す?タイミングやポイントを解説
編集後記
「今日話した内容は、一般的に求められている話とは違うかもしれません。越境によってオープンイノベーションが生まれる云々といった話は、越境学習においての本質ではないと考えているので」と謙遜しながら話してくれた松井さん。
確かに今回お聞きした内容は、これまでに聞いたことのない視点からの話ばかりでしたが、どれも認識しておくべき本質的なものだとすぐに理解できました。
またこれは越境学習だけに限った話ではありませんが、人事担当としては目の前の組織課題に対してどうしても分かりやすい“定量的”な解決策を求めてしまいがちです。
しかしそこに“定性的”なアクションを持ち込み、自組織の変化を促すこと──これがまさに「越境学習」なのかもしれないなと、今回の話を通じて感じました。