「企業内大学」を立ち上げ、持続的な人材育成を実現する方法とは

社員の学ぶ場として企業が社内に設置する「企業内大学」。カリキュラムを自由に選択できるなど、自主的な学びを深める制度の1つとして大企業を中心に導入が進んでいます。
今回は、「企業内大学」を実際に導入・運用した経験を持つ人事パラレルワーカー 大内 礼子さんに、企業内大学を効果的に運用するために必要なプロセスや要素について伺いました。
<プロフィール>
大内 礼子(おおうち れいこ)/人事パラレルワーカー
ソフトバンク社にて10年以上人事として活躍し、採⽤・⼈材開発を担当。ヤフー社では組織開発・ダイバーシティ推進の領域を経験。特に人材開発の領域に強みを持ち、ソフトバンクの社内大学や、グループ会社であるヤフーでの管理職育成では企画・導入・運用を一貫して経験。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「企業内大学」とは
──「企業内大学」の概要について、社内研修との違いも含めて教えてください。
「企業内大学」とは、その名の通り企業内の人材育成機関のことです。企業理念・経営戦略・カルチャーに基づいた教育機関としてのコンセプトを掲げ、複数のプログラムを設けて社員が能動的に学び合う環境を提供します。大学と名前がついていますが公的なものではなく、企業の人材育成制度の一種に分類されます。その運用目的は大きく以下2つです。
(1)次世代リーダーの育成
(2)社員の自己啓発・能力開発
「企業内大学」と従来の社内研修の違いは、その目的と時間軸にあります。
「企業内大学」は、中長期的な育成視点から体系立てて組み立てられます。一方、一般的な社内研修は短期的かつ単発的なスキルアップを目的としたものが多く、目の前の業務遂行のために必要な情報提供がメインです。また、研修対象を一部の階層・部門・職種に限定したり、研修内容も企業独自のものではなく普遍的なスキル習得を優先したりします。これはどちらが良い・悪いではなく、あくまで在り方が別だという話です。
なお、「企業内大学」のはじまりは、アメリカのゼネラル・エレクトリック(GE)社が1956年に開設した「ジョン・F・ウェルチ・リーダーシップ開発研究所(通称:クロトンビル)」です。これは組織マネジメントの習得を目的とした世界初の企業内ビジネススクールで、ここでのリーダー育成成功事例がきっかけとなりアメリカ全土に「企業内大学」が広まっていきました。その後、日本においても大企業を中心に「企業内大学」を設立する企業が増えていきました。
昨今、人的資本経営(人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上を目指すもの)が日本でも話題に挙がるようになりましたが、この文脈においても「企業内大学」は人材戦略の1つとして注目されています。「企業内大学」を人事制度や現場マネジメントと連携させることで、企業の独自性を活かした人材育成・組織づくりに繋げることができるからです。
「企業内大学」運用に必要な体制
──「企業内大学」を運用する上で最低限必要になる体制や規模感、また運用を継続するためのポイントについて教えてください。
「企業内大学」を立ち上げる際に必要な体制や規模感は、目的によっても大きく異なるため明言が難しいところです。基本的なところだけお伝えすると、以下のような項目を実現するための人員確保と時間が必要になります。
・企業理念、経営戦略、カルチャーに基づき教育機関としてのコンセプトの策定
・人材育成を行う上での現状分析、課題整理
・経営や現場マネジメントメンバーの巻き込み
・中長期的な育成視点を持をもった、プログラムの全体設計
・社員が能動的に学び合う場のデザイン
・他の施策や制度との連携検討
また、「企業内大学」スタート後も以下のようなポイントを押さえて運用を継続・改善していく必要があります。
・プログラム管理(募集・実施・評価・改善/新規開発の検討など)
・受講者管理(誰が・いつ・何を受講する/したなど)
・講師管理(誰が・いつ・何を提供する/したなど)
このような基本的なオペレーションが発生するため、立ち上げ当初はプログラム数を無理に増やし過ぎず、継続運用を優先して設計していくことをおすすめします。その際、緊急性の高いプログラムからスモールスタートして基本的なオペレーションを回しながら最適な運用方法を見出しつつ、プログラムを段階的に拡大をさせていくのが現実的でしょう。
──「企業内大学」を中小企業で導入するのは難易度が高いものでしょうか?
中小企業でも人材育成課題を明確にしてスモールスタートすれば「企業内大学」の導入・運用は十分に可能です。中小企業でよく見られる人材育成課題には、以下のようなものがあります。
・人材育成が一部に偏ってしまう(新卒育成のみで管理職育成までリソースが回らないなど)
・現場OJTによる育成がメインで、体系立った育成が難しい(属人的、個別差がある、経営視点を持った次世代リーダーが育ちづらいなど)
・マネジメント手法も個別差があり、会社としてもスタンダードなマネジメントが定まらない(浸透しない)
・その他(生産性向上、技術力継承、新しい技術へのシフトチェンジなど)
こうした人材育成課題に対しては、以下のようなポイントを抑えることでうまく「企業内大学」の導入・運用を進めることができます。
・中長期的に投資するべき人材育成の課題を特定する
・中長期視点を持って辛抱強く継続することを経営陣と合意する
・フォーカスした人材育成課題を解決するために、誰に対して何を行うべきかを検討し優先順位をつける
なお、よく心配される運用体制ですが、仮に運用専任の方がいなかったとしても必要な時期に優先度高く業務に取り組める方がいれば運用は回せます。ただし、企画・運用・コンテンツ開発・登壇などの全工程を1人で担うのは大変なので、目的に応じて誰を巻き込むのかは事前に考えておくのがベターです。(登壇者として社長・経営陣・あるいは専門性の高い社員・外部ベンダーなど)
「企業内大学」の設計プロセス
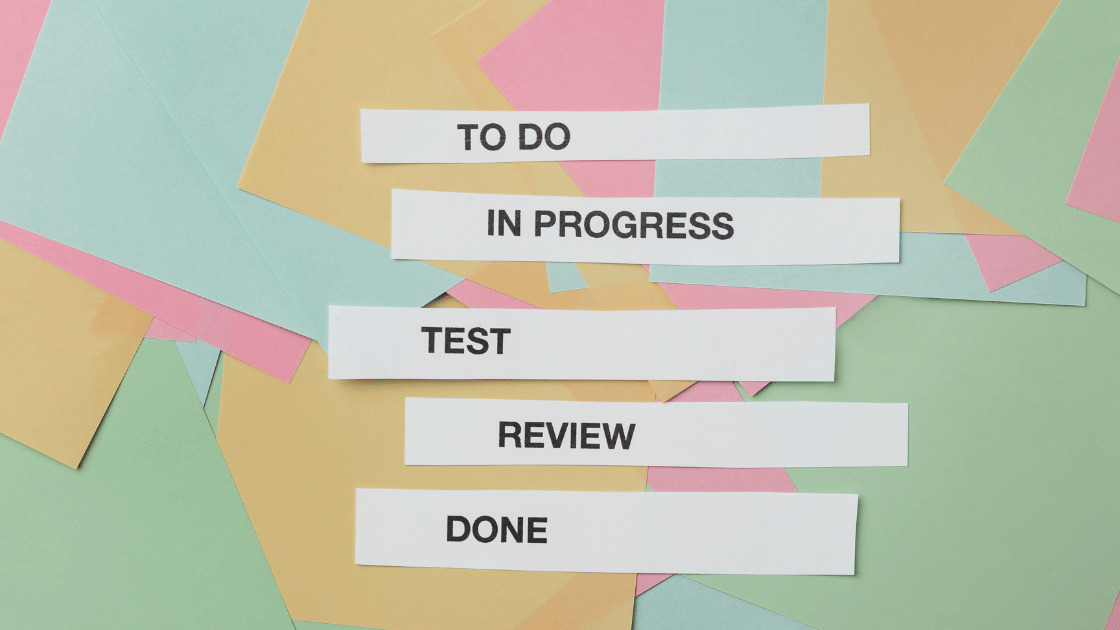
──これから「企業内大学」を導入検討しようと考えている人事担当者に向けて、具体的な設計方法やプロセスをお伝えいただけますか?
各企業の導入目的によっても内容は変わってきますが、一般的な「企業内大学」の設計プロセスには以下9つがあります。
(1)人材育成に関する現状分析(会社・社員・人事それぞれの視点から)
(2)あるべき姿と課題の特定
(3)企業内大学の位置付けの整理
(4)企業内大学のコンセプト決定
(5)プログラムの設計・開発
(6)運用の設計
(7)社員への周知
(8)実施
(9)効果測定
上記9つの中でも特に重要なのが(1)〜(3)のプロセスです。現状と課題を整理した上で本当に「企業内大学」がその改善策として効果的なのかどうかを検討せずに『他社もやっているから・流行っているから』などの理由で導入を進めてしまえば、必ず失敗します。
また、「企業内大学」で提供するプログラムだけで人材育成が完結することはあり得ないことを認識しておく必要があります。『成長を支援する仕組み』と『現場で発揮する/評価される仕組み』は本来セットであるべきものであり、「企業内大学」は前者の1つに過ぎないからです。既存の人事施策・評価制度・現場のマネジメントと「企業内大学」がぶつ切りにならず連携している全体像を描くためにも、(1)~(3)のプロセス内で集中的に議論をしておきましょう。こうして人事制度や現場のマネジメントと「企業内大学」を連携させるプロセスを経て、各企業の独自性を活かした人材育成・組織づくりの実現に繋がります。
──この設計プロセスを進めていく上で、人事以外のメンバーを巻き込むのはどのタイミングが良いでしょうか?
なるべく早い段階から巻き込めるのが理想です。人事(人材開発担当者)は考えを生み出すよりも、経営や現場の状況を鑑みて組み立てるイメージに近い役割だからです。また、「企業内大学」の検討は社内のあらゆる人と『人材開発』について対話できる機会でもあります。その結果、社内キーパーソンと繋がり、育成への想いや考え、目指すべき方向性や課題感の共通言語ができるようになります。
中でも(1)のタイミングは、周囲を巻き込める絶好の機会です。具体的には、以下のようなコミュニケーションを取ることができます。
社長、経営層へインタビュー
人材育成に対してどのような思いや課題感を持っているのか。
人材育成がうまく機能している組織へインタビュー
どのような方針で何をしているのか、思いなど。機能しているかどうかは、ES調査など組織診断結果や業績、社内での定性的な評価などから判断。
マネジメント層/専門性の高いプロフェッショナル層へインタビュー
人材育成に注力をしている方、課題感をお持ちの方に思いを聞く。
さまざまな人材育成施策の担当者へインタビュー
制度、アワード、研修、独自の勉強会開催など、人事に限らずさまざまな施策の担当者へ実情と課題感を聞く。
注意点としては、1回聞いて終わりにするのではなく、継続的な接点を持ち続けることです。特に、社長・経営層・マネジメント層・プロフェッショナル層などは、「企業内大学」導入後に登壇してもらったり、あるいはメッセージをもらったりと、施策を後押ししてもらう可能性が高い人物です。他にも、既存の人材施策と社内競合が起きないよう、初期から関係性の構築や情報収集はしておきましょう。
ちなみに、社内講師には思いと専門性のある人材を巻き込むのも重要です。例えば、社長や経営陣を巻き込めればパーパス・MVVなどを効果的に伝えることができるようになります。マネジメントの考え方・在り方などは、現役のマネジャーから経験談や失敗談を発信してもらってもいいでしょう。企業のバリューを体現している社員が講師として参画することで、外部講師にはできない自社独自の人材育成が成り立ちます。
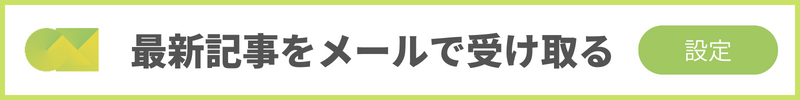
「企業内大学」の運用ポイント
──「企業内大学」を導入した後、継続的に運用していくためのポイントがあれば教えてください。
細かい点まで挙げればポイントはいくつもありますが、今回はその中でも重要度の高い点を3つお伝えします。
(1)プログラムの目的を言語化する
『誰に・何を・いつまでに・どうしたい』の観点を事前に言語化しておくと、プログラムを企画する際も、その後の運用で迷った際も立ち戻って考えることができるようになります。
一般的に研修プログラムを考えるときには『何を』が先行して検討されがちです。しかし、残りの『誰に・いつまでに・どうしたい』の内容次第でプログラム内容がまったく別モノになるケースは多々あります。例えば、『何を=マネジメントスキル』と定めたとしても、『新任マネジャーに管理職の役割を理解してもらう』のと『ベテランマネジャーに自身の課題を自覚してもらい改善アクションを促す』では、必要なプログラムはまったく違います。
(2)『何を』には“独自性”を意識する
「企業内大学」を自社 ”ならでは” の人材育成機関とするためには、『何を』の部分にこだわって考えるのがおすすめです。冒頭でお伝えした通り、「企業内大学」は企業理念・経営戦略・カルチャーに基づいた教育機関としてのコンセプトを掲げるものです。ただ個人が知識やスキルを学ぶだけではなく、以下のような『どのように学ぶ場を作るか』という観点も大切になってきます。
・経営理念やバリューなど大切にしたい価値観の共有/醸成の場
・社員の専門性やノウハウを相互交換する場
・職種や部門を超えた横断的な社員ネットワーキングの場
「企業内大学」は、経営に紐づいた戦略的な人材育成の場であるからこそ、その中にはリーダー育成・ビジネス基礎スキルの底上げなどといった複数のテーマが並列し、それぞれに細かいプログラム内容が紐づくこともあり得ます。
全てのプログラムを一気に運用するのは工数もかかります。今、会社として注力できるものをちゃんと見極めた上で、優先順位を設けてプログラム開発をすることが大切です。
(3)効果測定
人材育成の効果は、売上や利益などのわかりやすい数値で表すことが難しいものです。中長期的な人的投資の1つとして捉え、目に見えた成果がなくとも意志を持って継続することが欠かせない取り組みだと言えます。
とはいえ、何も効果測定を行わなくて良いわけではありません。「企業内大学」を設立した当初に掲げた人材育成課題解決がどれだけ進んでいるかを、何らかの方法で“見える化”してウォッチしていく必要があります。例えば、従業員満足度調査・組織サーベイ・離職率などの評価ポイントやコメントなどから変化を感じ取ることはできるはずです。
1つひとつのプログラムを評価する上では『受講後アンケート』が効果的です。プログラムそのものの質を確認する際は受講直後に、実務での実践度を確認する際は受講から数カ月経過してからアンケートを取得します。また、受講者本人ではなく、受講者の上司・部下へヒアリングすることで本人の変化を調査する方法もあります。どの方法を選択するにしても、プログラムの目的にマッチした効果測定を考えることが肝要です。
「企業内大学」にありがちな失敗例

──「企業内大学」を運営する中で、陥りがちな失敗例やポイントはありますでしょうか。
ありがちな失敗例として、ここでは3つほどご紹介します。
(1)導入目的が定まらないままスタートしてしまう
設計プロセスの項目でもお伝えしましたが、どのような施策であってもその目的が定まっていなければ期待した効果は得られません。『他社がやっているからうちもやろう』と考える企業は少なくありませんが、いずれもうまく運用できず終わっています。導入目的はあくまで自社の課題解決にあるべきですし、その中で「企業内大学」がどんな位置づけを担うのかを俯瞰して検討することが重要です。
(2)従来の研修スタイルに囚われて内容を設計してしまう
冒頭でもお伝えした通り、従来の社内研修と「企業内大学」ではそもそも在り方が異なります。それゆえ目的も学び方も変わってくるはずなのですが、どうしても過去に実施していた社内研修との比較ベースでプログラム設計がなされてしまうことが多々あります。
例えば、これまでは半日間の研修がベースになっていたとしても、これからは1時間の対話を複数回開催したほうが効果的かもしれません。また、e-learning形式で行われていたものも講演会動画を配信する形式に変更することで、より好奇心を掻き立てることができるようになるかもしれません。
これまでに恒例開催されていた研修で、その効果が一定の水準を超えていたとしても、そのままの内容で今後も継続するかどうかについては改めて議論するべきです。なぜなら、最適な学びは時代によって変わるものだから。目的を達成するためにその時々でもっとも効果のある手法を選択し試す意識を持つことが重要です。
(3)社員を講師として巻き込む際に、環境整備ができていない
「企業内大学」では、社内の専門性の高い社員を社内講師としてアサインすることがあります。誰かに教える経験は当人の学びにも繋がるため非常に良い発想と言えますが、一方で運用面の難しさが見過ごされがちです。分かりやすい部分で言えば『業務量の増加』でしょう。講師業が本来の業務にただただプラスオンされるだけの環境では、本業が回らなくなることはもちろん、上司や同僚からの理解も得られません。結果的にネガティブなサイクルに陥ってしまい、誰も講師を買って出てくれなくなってしまいます。
それを防ぐには、社内講師を担当してくれる当人が安心して講師業に協力できるような環境整備が必要です。例えば、以下のようなアクションが効果的だと考えます。
・上司や組織の理解を得るために必要な情報や懸念点を洗い出し、関係者内で擦り合わせる。
・社内講師に依頼する内容、工数、時期などはあらかじめ関係者間に伝達し握っておく。
・社内講師の業務状況に応じたサポートを行う。
・社内講師の登壇スキルを高めるための支援をする。
・上司に対しての定期的なインプットをする。 など
プログラム数の増加に伴って社内講師数が増えるほどこうしたオペレーション工数も増えていきますので、継続的な運用を実現するためにも設計時からバランスを検討しておきたいところです。
編集後記
「企業内大学」のネーミングの通り、学校としての形はなくとも中身は非常に大きく充実したものであることが大内さんのお話からも理解できました。これだけの施策を導入・運用していくためには、生半可な覚悟と目的ではうまくいかないでしょう。ただ、その分うまく運用できた際の効果は大きなものとなるはず。ぜひ本格的に検討を進める際は、本記事にある設計プロセスやポイントを参考にしてみてください。






