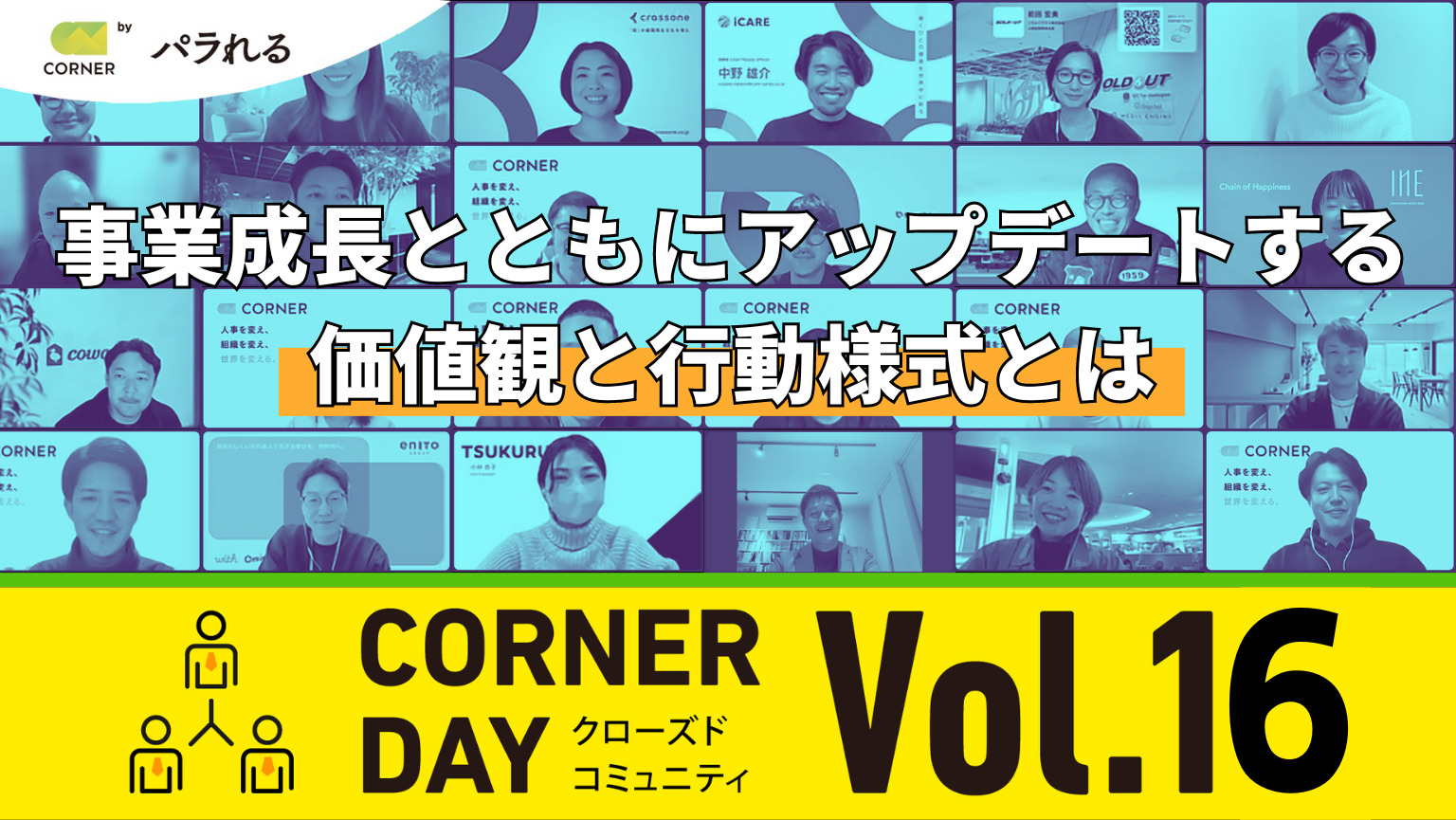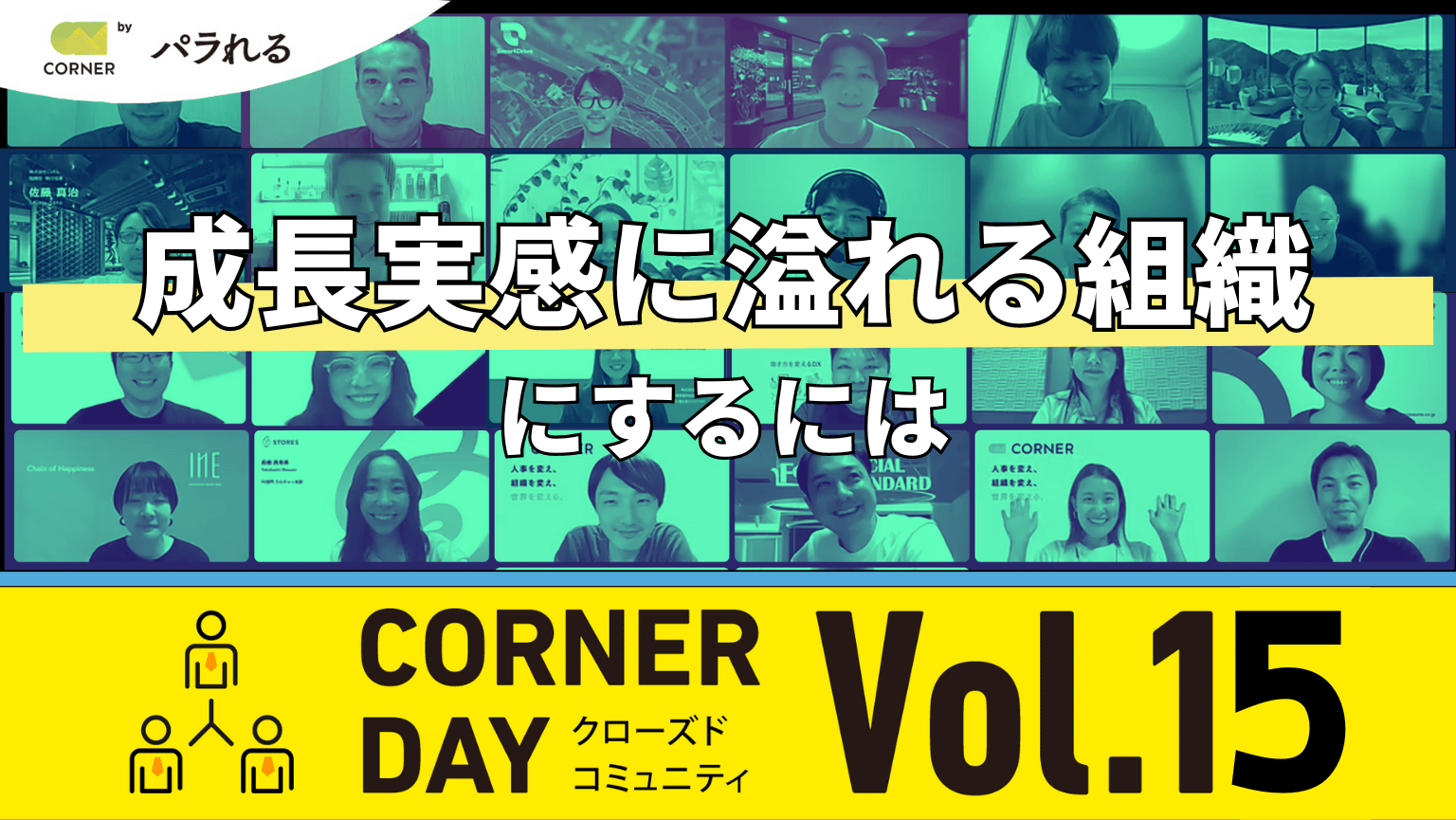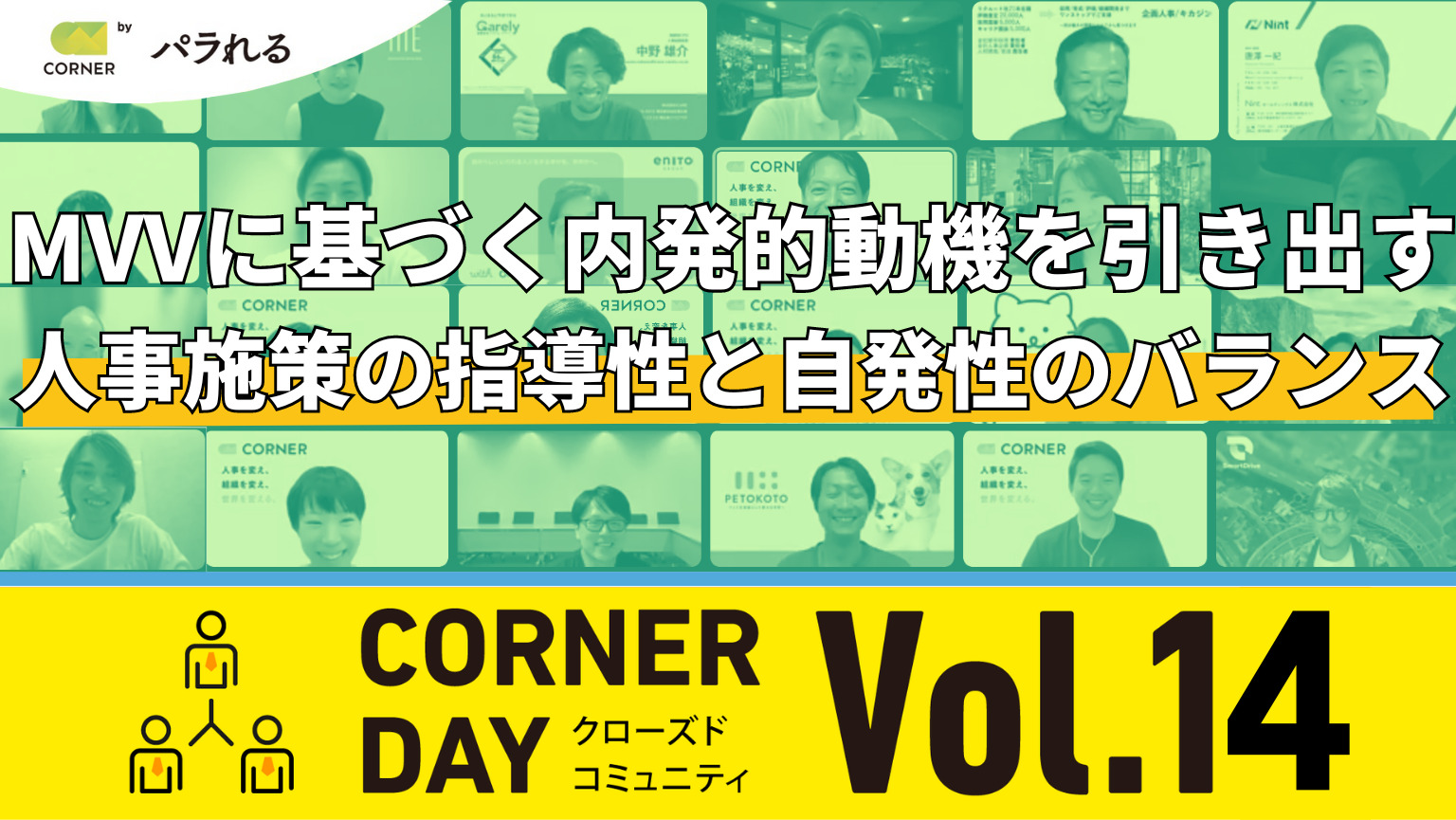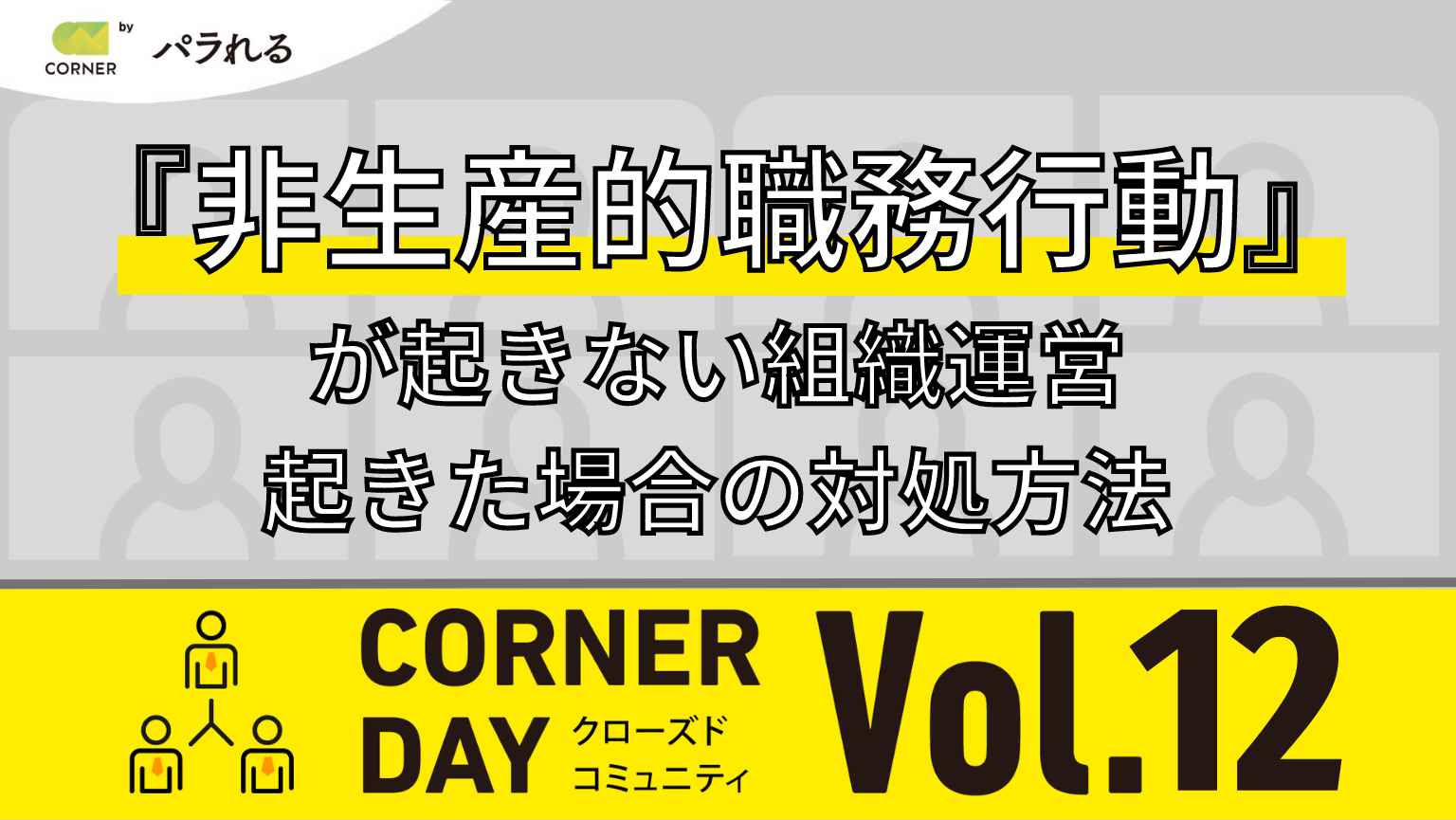【イベントレポート】次世代リーダーが直面する課題と解決に必要な経験・スキル/CORNER DAY Vol. 13
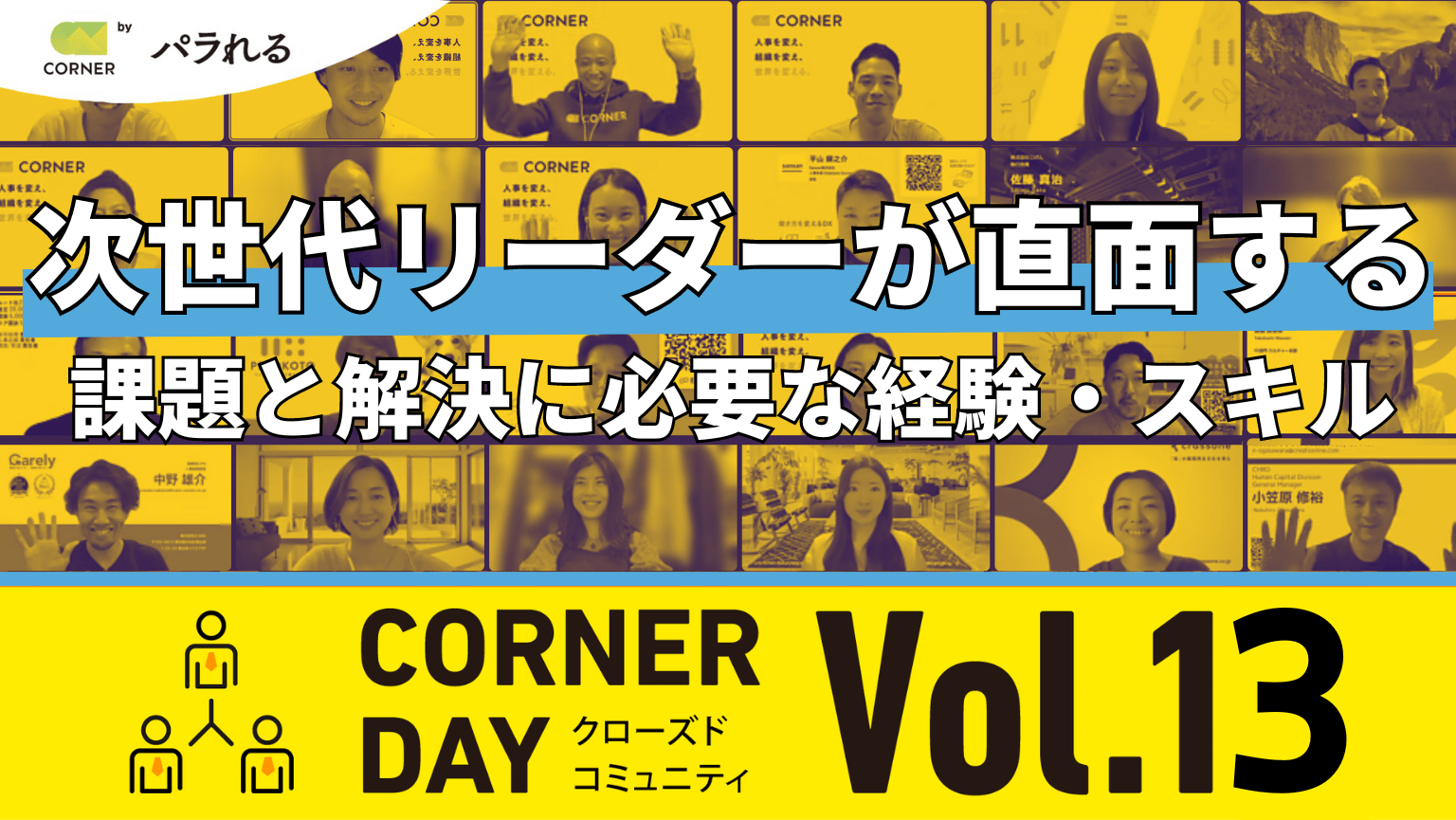
将来の経営人材として期待される次世代リーダー。そうした人材を計画的に輩出していくことは、人事にとっても優先順位の高い取り組みです。
そこで、CORNER DAY Vol.13(2023年5月24日実施)では『次世代リーダーが直面する課題と解決に必要な経験・スキル』をテーマに、参加者は4つのグループに分かれて以下3つの問いについて議論しました。
<問い>
(1)次世代リーダーの「定義」とその「理由」
(2)次世代リーダーが直面している各社固有の「問題・課題」
(3)課題解決に向けて次世代リーダーに求められる「スキル・経験」
今回は、本イベントに参加した人事責任者・担当者・スタートアップ経営者(計20名)のディスカッションのハイライト、各社の取組事例などをご紹介します。
目次
次世代リーダーの「定義」
まず、各社が次世代リーダーとして考える候補者の定義について共有が行われました。議論チームは、あらかじめ事前アンケートで次世代リーダーの定義を伺っていたことから、その定義の近しい参加者同士としました。それぞれのディスカッションチームごとで規模感やフェーズもさまざまだったことから、その定義も多様なものとなりました。
■チームリーダー(主任)〜マネジャー(課長)クラス
戦略推進のキープレイヤーとして活躍しているこの層に対し、今後は戦略立案や組織運営も任せたいと考える企業が多いようです。
「環境やミッション次第で伸びしろが大きい層」という意見もあり、中には経営会議への参加や経営陣の海外出張に同行させるなどで経験を積ませている企業もありました。他にも、マネジメント関連の研修や抜擢人事などの取り組みも多く聞かれ、この層に対する期待の大きさを感じました。
■部長クラス
経営メンバーの一段手前であり権限委譲先でもあることから、部長クラスを次世代リーダーと捉えている企業もありました。現経営メンバーとのOJTやオフライン合宿などを通じて必要な機会を提供しているとのこと。また、一口に部長といっても採用や組織開発には関わっていない“マネジャー寄り”の部長職となっている企業もあるようで、役職に求められるミッションも三者三様であることが垣間見えました。
■事業部長、執行役員クラス
CxOの直下メンバーとも言えるこの層を次世代リーダーとして捉えている企業も多く見られました。この層には集団研修だけでなく、エグゼクティブコーチングや360度評価など個別要素の高い取り組みを通じて能力開発をサポートしている企業が多い印象です。
なお、上記のように役職などで次世代リーダー候補者を選定しつつも、そのスキルやコンピテンシーまでは明確に定義できていない企業も少なくないようです。それに伴いレイヤーを上げる際の基準や定義作りが今後の課題だという意見には、多くの共感が寄せられていました。
次世代リーダーが直面している各社固有の「問題・課題」
次世代リーダーの定義に加え、各社が今抱えている「問題・課題」についてもシェアされました。当初の問いにある次世代リーダー自身だけでなく、組織・人事側にも議論が波及していた点が印象的でした。
■リーダー・マネジャー希望者が少ない
比較的多くの企業から挙がっていたのがこの課題です。特に女性については顕著なようで、ライフイベント関連やロールモデルの不在などが理由として挙がっていました。ただ、ロールモデルになりうる女性経営メンバーがいたとしても、現場メンバーからはインパクトが強く見えてしまい「あんな風にはなれない」と感じてしまう方も少なくないようです。
また、副業・複業が以前よりも一般的になり、社内以外のキャリア選択肢が広がってきていることも要因として挙がっていました。特に、役職に応じて給与や待遇を上げていくことが難しいスタートアップなどではこの問題を認識しているものの、解決に向け魅力的なポジションや待遇を用意するだけの余力がない実状もあるようです。副業・複業の広がりは多くの人事担当者が歓迎する一方、そのやり方次第ではスキルや時間の切り売りになってしまうリスクについても議論されていました。経験からスキルをアップデートでき、かつ適切な報酬を得られる副業・複業のあり方を人事としてデザインする余地がありそうです。
反対に、「マネジャー志望者が比較的多くいる」と話す企業もありました。ポイントは「個人の意思を気にしすぎないこと」だと言います。昇格前に「マネジャーになる意欲はあるか」と問うケースは一定あると思いますが、実際に経験する前のものに対してすべての人がポジティブなイメージを持っているとは限りません。「canから生まれるwillもある」という意見には、発見も多かったようです。
■スキル面
次世代リーダーの役割を担う上では、テクニカルスキルだけでなくヒューマンスキル(人柄・性格など)も重要です。マネジャーなど決められた戦略を的確に推進していく上ではテクニカルスキルをメインに乗り越えていくことができますが、それ以上の役割に関しては超えていける人とそうでない人に分かれるのではないかという意見もありました。それに付随して、ピープルマネジメントまでカバーできる人材の希少性についても話題が集まっていました。
■経営陣との目線合わせ
人事としてはサクセッションプラン(後継者育成計画)について対策が必要だと感じているものの、経営陣が同じ温度感でこのテーマを扱わないケースも少なくないようです。特に、創業社長がいる場合は優先順位がどうしても上がりきらずに具体的な取り組みまで落とし込みにくい傾向があるとのこと。創業者はこれまで壮絶な経験を積んできており求心力を持っていることも多く、自然と優秀な人材が集まってくる経験をしているので無理もないかもしれません。
しかし、次世代リーダーは経営者と同じような景色を見れるわけではありません。その中でどう人が集まる組織を作って成果を出していくかを考えなければならないため、そうした人材をいかに育てていけるかについては人事も常に頭を悩ませている様子が見て取れました。
■事業フェーズ
次世代リーダーが経営を担う頃には、事業も次のフェーズへと進んでいることが予想されます。すると、前リーダー時代とは違う形の組織づくりが必要となるため、そのフェーズにマッチした人材のアサイン・育成が必要となります。
ただ、特にスタートアップなどではそのフェーズの経験者が社内にいないため、どうしても外部採用に頼らざるを得ない状況があるようです。また、そうしたフェーズ移行を考慮せずに次世代リーダーの定義やコンピテンシーを決めてしまうことも少なくないようで、定義やコンピテンシーをフェーズや時代に応じて変えていく必要性についても議論されていました。
■次世代リーダー育成につながるポジションの準備
「子会社の社長を任せるのは次世代リーダー育成の鉄板」との意見から、子会社社長・新規事業責任者などのポジションを活用した育成課題についても話が展開されていました。これらが育成に有効であることは概ね同意されていましたが、一方で「子会社や事業が外的要因でうまくいかなかった場合、次世代リーダー候補者へ与える影響は大きい」といったリスク面の話も。ポジションがあればどんな状態でも良いわけではなく、勝ち筋が見える・経営課題に直結している事業など組織的な後ろ盾・サポートが手厚いポジションでなければ、うまく育成に繋がっていかないなどの指摘もありました。
課題解決に向けて次世代リーダーに求められる「スキル・経験」
最後に、どんなスキルや経験を次世代リーダーに求めているか、またどんな観点から育成を検討・実施しているかについてディスカッションが行われました。
■修羅場経験
より多くの意見が集まったのがこのテーマです。正解のない意思決定を求められるポジションのため、実際にそうしたシーンに直面した際に修羅場経験がないと的確にアクションできないと言います。特に、抜擢人事などで慣れない意思決定を迫られるとパニックに陥ってしまうことも。そうならないように事前に経験や体験を積んでおけるよう、各社さまざまな取り組みを行っている様子がシェアされていました。
また、こうした修羅場を乗り越えるためには「なぜ次世代リーダーを目指すのか」といった役割意識や内発的な動機が欠かせないという意見も。責任あるポジションにつく上で、そうした意識・動機をどう持ってもらうか・引き出すかは人事としても関わり方があるように感じます。
■視座の高さ
次世代リーダーに必要なスキルとして多くの企業が挙げたものに「視座の高さ」があります。ここを高めてもらうために、経営会議への出席や経営陣とのOJTなどへの取り組みを進めている企業も多い様子でした。
また、同じ次世代リーダー候補者同士の「横のつながり」を作ることで視座を高めようとしている企業もあるようです。半年〜1年に1回オフラインで集まり、戦略背景のインプットやグループディスカッションなどを行うことで事業を自分ゴト化してもらうことが目的とのこと。ただしながら、運用方法を工夫しなければ横のつながりが生まれていかないどころか、ネガティブな交流が生まれてしまうリスクについても言及されていました。
■事業上必要なスキル・経験
ここは各社それぞれ違う印象です。例えば、海外展開をこれから控えている企業については次世代リーダー候補者にも登竜門的に海外赴任を経験させるなどがわかりやすい例です。ここは事業内容やフェーズ、時代変化によっても変わっていくものであるため、常に定義を見直しブラッシュアップしていく必要性について話し合われていました。
また、そうしたスキル・経験を得る機会を社外からも求める思想を持つ重要性についても意見が上がりました。副業・複業などをうまく活用することは、個人だけでなく組織にとっても大きな意味を持つようです。
■ヒューマンスキル
自分から手を上げられるか、機会をもらった時に挑戦できるか、そもそも機会をどう捉えているか──こうしたスタンス・マインド面についても多くの意見が集まりました。こうした主体性・ポジティブさに加え、「自身の弱さや嫌なことと向き合う力」が必要だという意見も。理由は、これまでの成功経験や固有スキルをアンラーニングする・コンプレックスと向き合うことがなければ本質的な変容に向かわないため。こうして自らの弱さを認め、成功体験を過去に置いていけることがキャリア開発に置いても重要なようです。
イベント参加者の声
『事業内容・規模・フェーズによってもまったく考え方が違うことがこのイベントでよく理解できた。個別性が高く、正解もない世界。次世代リーダー育成はネット検索しても出てこないテーマなので、常に自組織に当てはめて考え続けることが必要だと感じた。』
『次世代リーダーという言葉ひとつとっても、会社ごとにそのポジションに求められるスキルや経験はまったく違う。それだけに、この領域は探求する価値があるものだと思った。自社らしさをうまく活かしながら、リーダーが育つカルチャー作りを進めていきたい。』
『経営陣の理解・協力なしに次世代リーダー育成は進めることができないと改めて感じた。重要だと思うことは、諦めずに人事から経営に提言し続けていかなければ。経営陣をどう動かすかに人事の手腕が問われる。』
まとめ
事業規模やフェーズが異なる方々が同じチームとして議論をしたことにより、いつもと違う視点や角度の発見も多くあったようです。また、イベント実施後には他チームの議事録も全体共有され、より多くの学びに繋がっていました。
当社は、今後もCORNER DAYを通じて先駆的な人事課題を解決するきっかけを作り、事業と組織の連動性の向上に貢献していきます。
<CORNER DAYとは>
“経営と人事のレジリエンス”を探究するコミュニティイベントとして、株式会社コーナーが定期開催しているイベントです。第一線で駆け抜けている経営者や人事の方に多く参加いただき、毎回白熱した議論が交わされています。
<CORNER DAY Vol. 13:参加者一覧)※50音順
飯田 竜一氏(フリーランス)
伊藤 允晴氏(株式会社PETOKOTO)
小笠原 修裕氏(クリエーションライン株式会社)
小倉 将氏(株式会社アカツキ)
佐藤 真治氏(株式会社じげん)
高橋 真寿美氏(STORES株式会社)
高村 美穂氏(株式会社マネーフォワード)
永井 雄一郎氏(株式会社スマートドライブ)
中野 雄介氏(株式会社iCARE)
林 英治郎氏(LINE株式会社)
平山鋼之介氏(Sansan株式会社)
藤田 大洋氏(株式会社ツクルバ)
前田 宏美氏(カルビー株式会社)
宮田 ゆかり氏(株式会社クラッソーネ)
吉川 彩加氏(READYFOR株式会社)
他2名
<過去イベントレポート>
corner day vol.1 :レジリエンスを高める組織・制度とは?
corner day vol.2 :MVVをベースとした自律的な組織の作り方
corner day vol.3 :人的関係資産が薄れる中でのミドルマネジメントの人材開発
corner day vol.4 :採用後の早期戦力化
corner day vol.5 :経営・事業に貢献する最適なエンゲージント施策の効果測定
corner day vol.7 :コロナ禍におけるミドルマネジメントの新たな課題と可能性を探る
corner day vol.8:リモートワーク環境下のメンタルヘルス不調を未然に防ぐために
CORNER DAY vol.9:人的資本経営にも大きく影響する「ミドルマネジメント」の人材開発とは
CORNER DAY vol.10:経営戦略・事業戦略に基づいたタレントマネジメントとは
CORNER DAY vol.11:「権限委譲」による管理職育成と環境整備
CORNER DAY vol.12:「非生産的職務行動」が起きない組織運営、起きた場合の対処方法