「従業員データ」の収集・管理の重要性と、そのメリット・注意点について解説
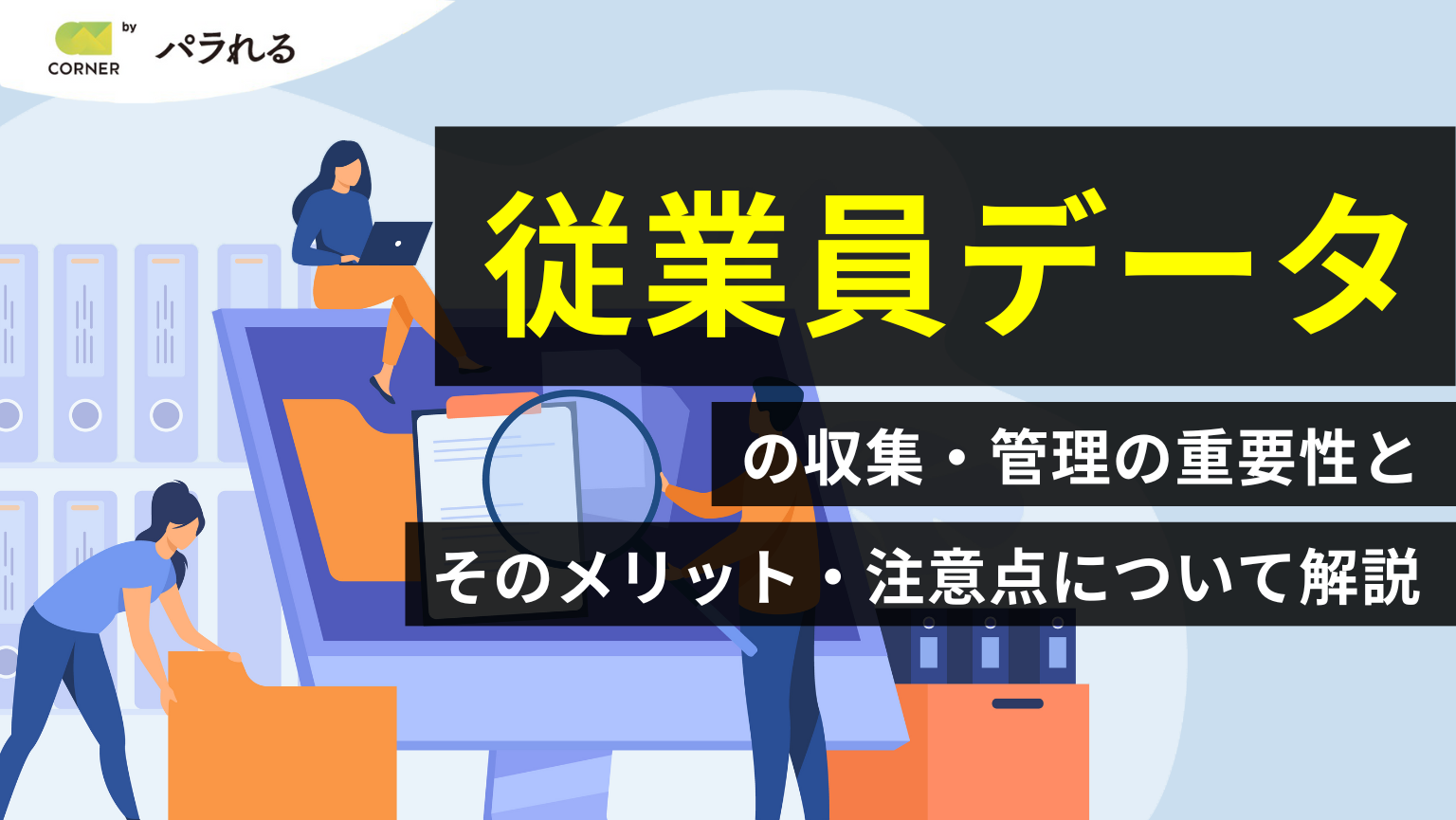
あらゆる人事施策をデータドリブンに進めるためにも、「従業員データ」の収集・管理は人事にとって非常に重要なミッションです。
今回は、さまざまなフェーズの企業の人事として豊富な経験を持つ株式会社Spectee 人事総務マネージャーの田中 豪一さんに、「従業員データ」の重要性から収集・管理方法に至るまでお話を伺いました。
<プロフィール>
田中 豪一(たなか こういち)/株式会社Spectee 人事総務マネージャー
防衛省航空自衛隊にてキャリアをスタート。その後、ゼネコン・PRエージェンシー・ITとカラーの異なる企業で人事業務キャリアを構築。東証一部(現プライム)上場企業での勤務経験、IPO準備、M&A対応などさまざまなフェーズを経験し、現職であるSpecteeに人事総務マネージャーとして参画。労務・人事制度領域に強みを持ち、人事領域のDX化など幅広く従事。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「従業員データ」とは
──「従業員データ」の概要(種類や管理方法)について教えてください。
「従業員データ」とは、人事業務に用いる従業員や関連従業員のあらゆるデータを指します。本記事内では人事業務を大きく労務・採用・人材/組織開発の3つの要素に分けて説明します。それぞれの観点から該当する代表的な「従業員データ」は以下の通りです。
労務
氏名・生年月日・住所・電話番号のほか、配偶者・扶養者・それぞれの扶養の有無・給与の振込口座・住民税の税額などが挙げられます。これらは、従業員の社会保険手続きや給与計算の際に利用し、各種の処理を正しく実行するために利用します。
採用
学歴・入社経路(媒体・エージェント・リファラルなど)・雇用区分変更履歴(アルバイトから従業員など)などが挙げられます。これらは自社の採用戦略を見直す際や、自社にいる従業員属性を分析する際などに利用します。
人材・組織開発
現状の役職・役職に就いた期間・公的資格の保有状況・受講履歴などが挙げられます。これらは、人事異動案を作成する際や、次世代の管理職を検討する場合などに利用します。
なお、これらの情報はExcelやスプレッドシートなどを用いて管理するケースが多い印象がありますが、予算に余裕があればシステムやBIツールを導入した方が、より効率的で安全性高く管理できます。例えば、Excel管理だと更新タイミングや上書き前のデータがわからなくなってしまいますが、システムであればその問題点もクリアできるなどの利点があります。編集・閲覧権限を個人や部門別に柔軟に設定できる機能があるものがほとんどなので、権限設定を自由度高く行える点もシステムの利点です。また、昨今その重要度が再認識されているように、人事資本を管理したり活用することができる点も利点のひとつです。代表的なシステム・ツール例にはSmartHR、オフィスステーション、Workdayなどがあります。
「従業員データ」の収集・管理はなぜ重要か

──「従業員データ」を収集・管理の目的や重要性については一定認識があると思いますが、改めてその重要性について教えてもらえますか?
労務・採用・人材/組織開発の3つの観点から、その重要性について解説します。
労務
労務面において「従業員データ」を収集するタイミングは、大きく以下2パターンです。
(1)入社時
(2)情報が変更になった時
(1)は社会保険の手続きや給与計算に必須となる情報のため、ある程度ルーティン化しているはずです。ただし、(2)のタイミングは従業員側からの申し出次第なので管理側は掌握しようがありません。そのために見落としがちであり、これを怠ることでさまざまな影響が出てしまいます(例:住所が古いままであったため給与支払報告書が違う自治体に提出されてしまった、扶養家族が増えていることを知らず税金を取り過ぎていた、など)。こうした収集漏れを防ぐためにも、適切なタイミングで情報を収集・更新していくことが大事です。
また、「従業員データ」には住所・家族・給与などの個人情報なども多分に含まれるため、データの取り扱いには細心の注意が必要です。基本は人事メンバーだけがアクセスできる環境・場所で情報を管理し、必要に応じて情報が必要な役員などに閲覧権限を付与するという方法で運用していく形が一般的です。一例を挙げると、私の普段の運用では以下の権限設定をベースにしています。
・人事→全データの『閲覧+編集権限』
・代表→全データの『閲覧権限』※給与含む
・役員→①自分が管掌する部門データの『閲覧権限』※給与含む
②他部門のベーシックなパーソナルデータの『閲覧権限』※氏名・年齢・住所など
・部長→自部門の限定したパーソナルデータの『閲覧権限』※氏名・年齢のみ
通常時は上記のような設定をベースにしておきながら、採用業務においては部長クラスにも一部の給与データを閲覧できるようにするケースもあります。オファー年収を設定するため、部内の他のメンバーや市場価値との均衡を評価するために例外的に付与する形です。
なお、給与情報の取り扱い方法は企業によっても様々です。私たちの会社では役員以上のみが知る情報として取り扱っていますが、採用時に一部公開したり、企業によっては部長クラスにも通常公開されているケースもあります。
採用
新卒採用と中途採用でそれぞれ重要視するデータは変わってきますが、以下3つの観点は採用戦略を検討する際によく用いるため、新卒採用・中途採用両方に共通して重要なデータだと言えるでしょう。
(1)どんな人が入社しているのか
(2)どんな人が入社後活躍しているか
(3)どんな人が会社を去っているか
共通しないデータに関しては、新卒採用であれば出身大学や適性検査の傾向など、中途採用であれば採用経路やスキルセットや経験値なども活用すべき重要なデータです。
人材/組織開発
人材/組織開発に関する制度設計もしくは制度の運用にあたり重要となるデータは非常に広範囲なものとなります。職種・職位・保有資格・スキルなど、自社に存在するもしくは今後導入しようとする制度に必要なデータを多角的に収集する必要があり、そのどれもが制度設計や運用のためのパーツとなるため重要性が高いです。
また、人事異動などの社内の配置転換に「従業員データ」を活用するケースが多いと考えています。企業規模が大きくなるにつれて、誰が・どのようなスキルを持っているかを把握することは難しくなります。そのため、これまでの業務や経験スキルと、今後貢献できそうな領域のすり合わせなどをする際にはこれまで蓄積した多くのデータを元に判断していくことになります。そういった際に、最新のデータが集約されている人事マスターデータがあるかどうかは重要なポイントになります。
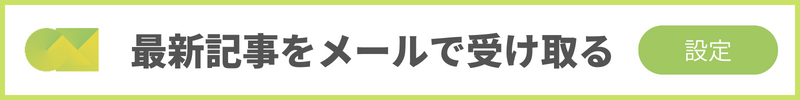
「従業員データ」収集・管理の在り方を見直す企業が増えている理由
──昨今、「従業員データ」の収集・管理方法を再検討している企業も多いと聞きます。その背景や理由について田中さんはどう考えていますか?
コロナ禍の影響で在宅ワークやフレックスタイム制など多種多様な働き方が世に浸透してきたことを受け、管理部門の働き方も以前よりは柔軟になりました。その中で、より従業員と人事が直接顔を合わせることなく業務が進む仕組み作りが求められるようになり、「従業員データ」の収集・管理方法も合わせて変化が求められている印象です。例えば、コロナ禍以前は入社時に「従業員データ」を紙に書かせて書面で回収する企業もあったようです。紙ベースで管理する場合、会社にいればすぐ内容を確認できますが、会社にいない場合は情報にアクセスする術がありません。また、字が汚くて読めない、紙が痛んで読めない、などの不具合も絶えず発生します。これらをデジタル上のデータ管理に変更することで、いつでも・どこでも正しい情報を確認できるようになります。外部環境の変化もあり、必要に迫られてデータ管理への移行を再検討する企業も増えているはずです。
さらに、近年では『人的資本経営(※)』の重要性が増し、データドリブンな人事施策が課題になっている傾向があります。「従業員データ」へいつでも・どこでもアクセスできることは当然として、常に最新の状態で管理できているかどうかが社内外から問われる時代になってきているのです。
(※)人的資本経営とは、人材を『資本』として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方のこと
人的資本経営はまずは現状分析から始まるものだと考えています。その中で、新たに取得が必要なデータが出てくれば回収・更新を行い、自社にとって有意義な経営判断のできるデータを構築していく、というように都度軌道修正をする形が現実的ではないでしょうか。
例えば、以下のような情報を回収・蓄積することで有意義に活用できるのではないかと考えています。
退職
退職者それぞれの退職理由ごとの分類や、そこから想定できる会社の問題点をまとめた情報。このデータを把握できていれば、以降の組織改善に対して施策を立てたり改善をすることが可能です。人的資本の7分野19項目と照らしあわせると、『流動性』を主としつつ、内容により『健康・安全』もしくは『コンプライアンス』に該当する項目になります。
採用経路
獲得できた媒体やエージェント、在職年数などの情報。このデータが蓄積できていれば、ポジションごとに相性の良い媒体やエージェントの選定ができたり、採用の精度向上に繋がります。人的資本の7分野19項目と照らしあわせると、『流動性』に該当する項目になります。
保有資格やスキル
エンジニア職が分かりやすいと思いますが、従業員が保有している資格やスキル、会社として従業員に伸ばして欲しいと考えているスキルなどの情報。これらを再確認することで、教育や研修の方向性を検討したり見直す際に利用できます。人的資本の7分野19項目と照らしあわせると、『人材育成』と一部『流動性』に該当する項目になります。
なお、これらのデータを把握・管理する際には開示に向けてデータを集めることだけが目的にならないよう留意しましょう。上場企業では人的資本の開示義務が発生するため、その義務を果たすためだけにデータを集める形になる傾向があります。しかし、このデータをそれだけに留めるのではなく、『経営戦略を後押しする人事戦略のためのデータ』だという認識を念頭に置いておくことが重要だと考えます。また、人材育成・エンゲージメント・流動性・ダイバーシティ・健康・安全・労働慣行などの項目は企業目標に応じた取り組みが必要になります。これらも踏まえて開示の方向性を検討し、必要となるデータの枠組みを決めて、現有データのアップデートを進めていくプロセスを重ねていく必要があります。
<人的資本開示に関連する過去記事はこちら>
▶「人的資本の情報開示」の世界情勢と「ISO 30414」出版に伴う日本企業の対策と未来
▶人的資本開示の本質を捉え推進する、三井化学のデータドリブン人的資本マネジメントとは
▶【事例インタビュー】人的資本の情報開示を契機に人事データ基盤を構築。多角的な視点で自社の人材戦略を再考する
「従業員データ」収集・管理時の注意点

──人事担当者が「従業員データ」を収集・管理する時に気を付けるべきポイントについて教えてください。
私が「従業員データ」を収集・管理する際は、いつも以下3つの点を重視して取り扱っています。
(1)何のために利用するのか
(2)いつ時点のものか
(3)正確な情報かどうか
今回は『住所』を例に挙げて、上記3つのポイントについて解説します。
(1)何のために利用するのか
この目的次第で住所データの登録方法を検討する必要があります。例えば、都道府県別の分布を調べたい場合、『〇〇県△△市◇◇町』と入力するよりも『〇〇県』と『△△市◇◇町』を分けて入力する方が分析は楽になります。
(2)いつ時点のものか
住所が変わった日付によって、給与支払報告書の提出先に変更が発生します。
(3)正確な情報かどうか
従業員から届け出のあった住所が正しいものなのか、申告間違いがないかなどを必ずチェックします。その際、住民票などと付け合わせて確認しないと誤ったデータを登録してしまうこともあり、その後の分析などに影響が出る恐れがあります。
データ収集の目的により、その適切な登録方法は異なります。この目的が固まり切る前に「従業員データ」を収集・管理する場合は、できるだけ細かく区切ったデータで登録・運用を進めると後々もアレンジしやすく便利です(特に、Excelで運用する際は後々でデータを分けるには手間が掛かるため)。
なお、こうしたデータの収集や更新はできるだけリアルタイムに行うことがベストです。しかし、人事側ではそう思っていても、従業員側からすれば『どの情報を・どこまで詳細に・いつまでに人事に伝えるべきなのか』がいまいちわからなかったり、その重要性について理解しづらかったりすることがあります。そうした従業員側の迷いを解消するためにも定期的なアナウンスが重要です。よって、各種データ収集や更新に際して定期的なアナウンスをする際、『なぜ人事データが重要なのか』についても合わせて広報を行って従業員側の理解促進に努めることも重要です。これらを繰り返すことで『何かあれば人事に報告しよう』というカルチャーを根付かせることが、正確でタイムリーなデータ収集の第一歩だと考えています。
ちなみに、私は定期的な全社向けのアナウンスの際に以下3点をお伝えし、厳重に管理していることの理解を得られるようにしています。
・データの利用目的
・データを閲覧できる者の範囲
・管理方法
その際は問い合わせ先も明記し、個別対応が発生した際はミーティングや対面でのやり取りをして心理的安全性の確保にも努めています。
■合わせて読みたい「人事データ・人的資本情報」に関する記事
>>>「ピープルアナリティクス」の実践内容を知り、KKD(勘・経験・度胸)だけの人事から卒業するには
>>>「人的資本の情報開示」の世界情勢と「ISO 30414」出版に伴う日本企業の対策と未来
>>>「データドリブン人事(HR)」人事データを取得・活用して採用や配置に活かす方法とは
>>>的資本開示の本質を捉え推進する、三井化学のデータドリブン人的資本マネジメントとは
>>>「労働分配率」を活用してビジネスモデル・事業戦略を見直し、生産性向上につなげる方法
編集後記
人事の仕事は、オールド3K(記憶・勘・経験)からニュー3K(記録・客観性・傾向値)に変化してきており、データ面から人事を捉えていくことはもはや避けられない流れです。改めてその重要性を理解した上で、自社にマッチした運用方法を考えていくことが人事にも求められているのではないでしょうか。






