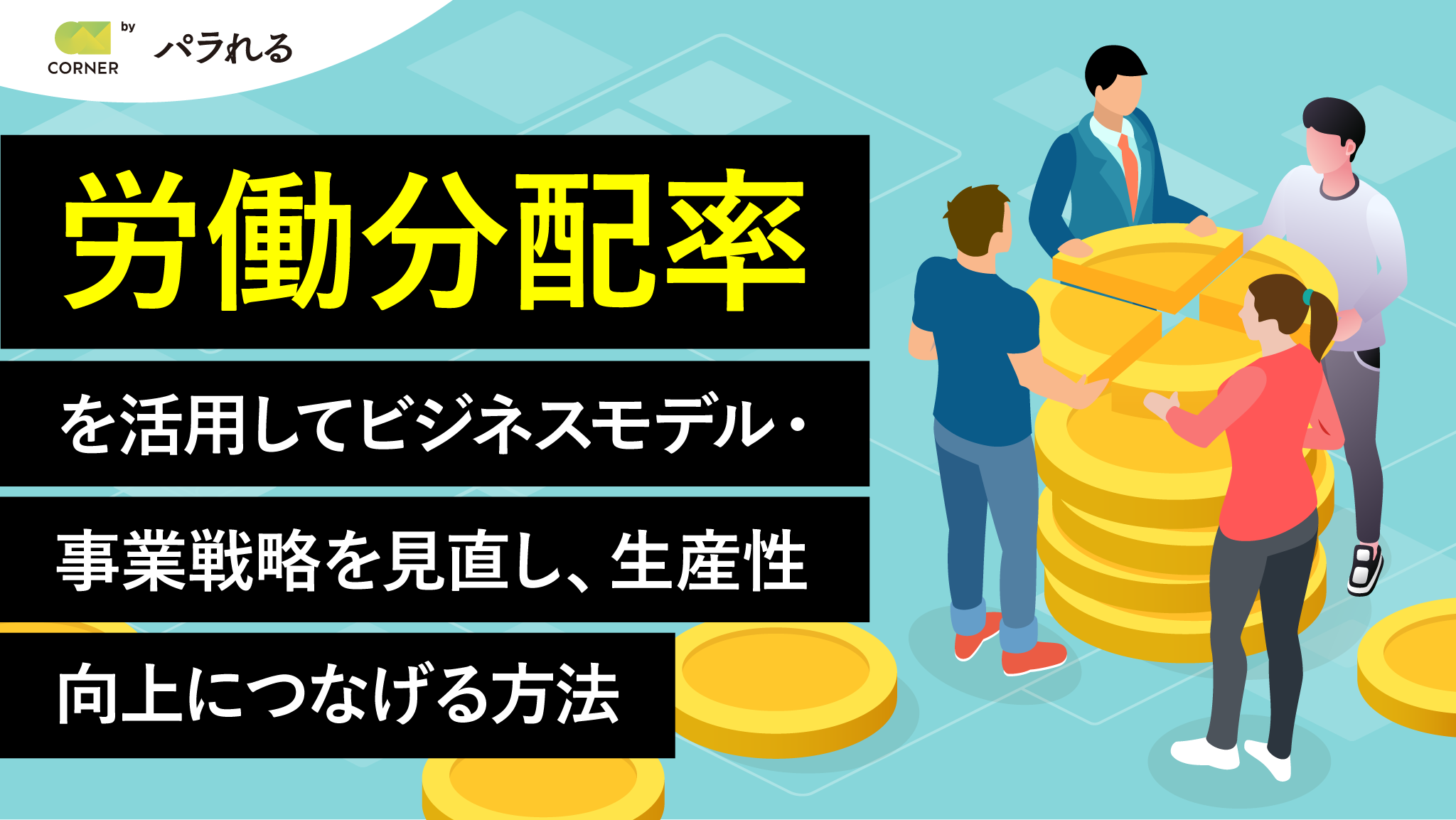「ケアハラスメント」に対する行政の動きと、予防・対処法について解説

高齢化で介護を必要とする方が年々増加していることを受け、介護と仕事の両立が組織・個人の課題となっています。その中で問題視されているのが「ケアハラスメント」です。
今回は、大手~中小企業まで幅広く人事経験を持つ磯野 篤紀さんに、「ケアハラスメント」の概要から予防・対処法に至るまでお話を伺いました。
<プロフィール>
磯野 篤紀(いその あつのり)/大手教育系企業 HRBP
中小事業会社で人事総務業務を幅広く担当、その後ヤフー株式会社で人事担当を12年半経て、200名規模のIT企業で人事担当。現在は大手教育系企業にてHRBPを担当している。これまで人事領域では、給与・労務系、人財育成、組織開発、組織活性、HRBPを経験。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「ケアハラスメント」とは
──「ケアハラスメント」の概要について、具体例と合わせて教えてください。
「ケアハラスメント」とは、働きながら介護をする人に向けたハラスメント行為のことです(通称:ケアハラ)。嫌がらせや不快な発言・行為だけでなく、介護をする人に向けた制度の利用を阻害する行為も含まれます。また、介護職の人がサービス利用者やその家族から暴力や嫌がらせを受ける場合も「ケアハラスメント」に該当します。
この「ケアハラスメント」は勤務先の上司や同僚から受ける場合が多く、仕事と介護の両立を阻む深刻な問題となっています。介護休業を取る従業員が不当に扱われるだけでなく、その従業員の心身・健康に悪影響を及ぼす可能性すらあります。少子高齢化問題も叫ばれ続けている日本では、要介護認定者数も毎年増加(以下図参照)しており、「ケアハラスメント」の解消が日本社会全体の課題と言っても過言ではありません。
※引用:令和3年度 介護保険事業状況報告(年報)/厚生労働省
なお、「ケアハラスメント」には以下のような行為・言動が該当します。
・不快に思う言動や不当な発言をされる
(例)奥さんにやってもらえばいい、親御さんを介護している人に重要な仕事は任せられない、残業をしなくて済むからうらやましい、業務を増やされて周りはいい迷惑、自分ならそんな休暇は取らない、など
・介護休業制度や短時間勤務などの取得を妨げる
・通常業務で雑務のみをアサインされる
・本人の承諾や希望なしに異動をさせる
・人事評価を不当に低くつける
・正社員から契約社員やパートタイムに雇用形態を変更する
・契約社員の雇い止め(雇用契約更新拒絶)をする
・機密情報などへのアクセス権の剥奪
・復帰後の不当な業務負担
「ケアハラスメント」が起きてしまう背景・理由
──この「ケアハラスメント」の発生要因や背景にはどのようなものがあるのでしょうか。
一般企業において「ケアハラスメント」が発生してしまう背景や要因は複雑で多岐に渡るため、一概には説明が難しいところがあります。ただ、その例としては以下のようなものがあります。
【組織要因】
制度運用の準備不足
会社として就業規則などで必要最低限の整備は行ったものの、細かな運用や社内ルールの整備までされていないことはよくあります。いざ介護休業を取得したい従業員が発生しても、本人のみならずその上司・同僚もどう対応したら良いのかわからない状態になり、それが「ケアハラスメント」を誘引してしまっている可能性があります。
組織文化とリーダーシップ
組織内の文化やリーダーシップスタイルが「ケアハラスメント」の発生に影響を与えることがあります。例えば、ワークライフバランスを重視するカルチャー・価値観が欠如している組織では、長時間労働が奨励され、従業員は休みを取ることが難しいと感じるようになります。
業務のしわ寄せ
周囲の社員にとっては、介護で休む人がいる分だけ業務のしわ寄せが発生する可能性があります。特に繁忙期などに半ば押し付けるように仕事を割り振られてしまえば、不満が溜まるのもムリはありません。
ストレスと業務負担
従業員が高いストレスや業務負担にさらされている場合、感情的に不安定になり、他の人に対して不適切な行動を取る可能性が高まります。これにより人格的な尊厳を傷つけてしまうことにつながり、「ケアハラスメント」に限らず何らかのハラスメントにつながる可能性があります。
日常のコミュニケーション不足
適切なコミュニケーションの欠如は誤解や不信感を生む可能性があり、それが「ケアハラスメント」の要因となることがあります。従業員間や上司と部下、部門間でのコミュニケーションの不足が問題をエスカレートさせることもあります。
【個人要因】
認識不足と意識の低さ
ハラスメント対策を進めている会社は多くありますが、ハラスメントの種類は30個以上あると言われており、そのすべてを理解・認識することは簡単ではありません。そのため、「ケアハラスメント」の概念や重要性に対する認識が低いことも問題の一因となっています。
会社・従業員が「ケアハラスメント」について正確な知識を持たない場合、問題の早期発見や防止が難しくなります。また、介護を理由とした会社からの支援は確立がされてないことも多く、それが「ケアハラスメント」を誘引してしまっている可能性があります。
介護に対する固定概念
近年では女性の社会進出が加速し、夫婦共働きの世帯も増加しました。政府も男女平等社会の実現に向けてさまざまな取り組みを行っています。しかし、それでもなお日本社会には『介護は女性が行うもの』という固定概念が今も残っています。こうした男女の役割における社会通念・慣習は、まだ根強く残っているのが現状です。そのため、男性が介護休業を取ることに違和感を覚えたり、介護を女性に押しつけようとしたりする人も一定数存在します。
個人的な偏見と差別
前述した固定概念にも通じる部分ですが、従業員の中に性別・人種・性的指向・宗教などの属性に対する偏見や差別的な信念を持つ方がいる場合、それが「ケアハラスメント」の要因となります
「ケアハラスメント」に対する行政の動き・サポート

──「ケアハラスメント」に対しての行政側の動きやサポートはどういったものがあるのでしょうか。
「ケアハラスメント」に対する行政の動きとしては、厚生労働省が発行している以下パンフレットに詳細がまとめられています。より詳しくは内容をご覧いただければと思いますが、本記事ではその概要について簡単に解説します。
『職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠 ・ 出産 ・ 育児休業 ・ 介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!!』(厚生労働省)
厚生労働省における「ケアハラスメント」の取り扱い内容の変遷(5ページ)
厚生労働省では、従来から男女雇用機会均等法および育児・介護休業法によって事業主による妊娠・出産、育児休業・介護休業などの申出や取得を理由とする解雇などの『不利益取扱い』を禁止してきました。
2017年1月からは、妊娠・出産、育児休業などに関する上司・同僚による就業環境を害する行為を上記の『不利益取扱い』と区別し、『職場における妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント(マタハラ・ケアハラ)』と整理し、事業主に対して防止対策を講じることを義務付けました。
厚生労働省による「ケアハラスメント」の定義(5ページ)
職場における介護休業などに関するハラスメントとは、『職場』において行われる上司・ 同僚からの嫌がらせや不快な言動によって引き起こされるものであり、介護休業制度の利用と嫌がらせ行為の間に因果関係があるものがハラスメントとしてみなさるとしています。
介護休業を認めないのは当然ながら、介護休業を取得しないよう勧める、本人の承諾なく(希望しない)異動をさせる、減給になった、などがハラスメントに該当します。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的に見て業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しないと定義しています。
「ケアハラスメント」防止に向け事業主が雇用管理上講ずべき措置(15ページ)
(1)「ケアハラスメント」への理解促進とと周知・啓発
介護休業などに関するハラスメント発生の原因や背景には、そもそも「ケアハラスメント」への理解がないことが挙げられます。例えば、業務のしわ寄せ先となったメンバーが単なる嫌味程度にした発言に対して、休んだ本人も『周囲に迷惑をかけてるから』とケアハラだと思わずに受け入れてしまっている可能性も考えられます。ハラスメントをしてしまっている側、ハラスメントを受けている当事者の双方が『どんなものがケアハラに該当するのか』を知っておくことが、「ケアハラスメント」防止の第一歩でもあります。
(2)相談へ適切に対応するために必要な体制整備
ハラスメントが発生してしまった場合、加害者に対しての罰則だけでなく、被害者のケアも重要です。相談窓口は設置するだけでは意味はなく、窓口を設置していることを全従業員に周知する・気軽に利用できるようにしておくなど、適切な運用も求められます。
(3)ハラスメントへの迅速かつ適切な対応
迅速かつ適切に対応するために、問題が生じた場合の担当部署や対応の手順などをあらかじめ明確に定めておく必要があります。
(4)「ケアハラスメント」の原因や背景になる要因を解消するための措置
介護休業を取得する従業員はもちろん、その周囲のメンバーも含めて制度などの利用ができるという知識を持つこと。また、その制度を利用をしにくい職場風土や職場内での周知が不十分でないかどうかを常に確認しておくことが重要です。また、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の状況に応じて適切に業務を遂行していく意識を持ってもらうことも、「ケアハラスメント」の原因や要因を解消する上では必要な措置です。
「ケアハラスメント」が起きてしまったら
──残念ながら「ケアハラスメント」が起きてしまった際、人事はどのように対処すれば良いでしょうか。
前提、『ケアハラスメントは他のハラスメントと比べて認識されづらい』点を人事だけでなく組織全体が理解しておく必要があると考えます。
例えば、介護には終わりが見えない不安がつきまとうもの。そのため、介護者もなかなか会社・上司・周囲に相談できずに抱え込んでしまい、周囲の理解も進まないまま業務に影響が出てしまうことが多々あります。結果、周囲から心無い言葉を言われたり嫌がらせを受けたりしても、それをケアハラだと本人も気づかず受け入れてしまうのです。
1度受け入れてしまえば、周囲も自分たちがやっていることがケアハラだと気づかずそのままの姿勢を継続してしまいます。それによりさらに介護者へのプレッシャーが強まり、結果的に負のループが強化されてしまう形になります。
これらを防ぐためにも、「ケアハラスメント」への理解を従業員全体に浸透させることは必要不可欠です。以下2つの観点での周知や啓発、情報提供を行いましょう。
(1)全従業員向けに「ケアハラスメント」を含めたあらゆるハラスメントの定期的な周知・啓発活動を徹底し認知に努める
(2)これから介護に直面しそうなタイミングの従業員に対する情報提供
(2)のタイミングは、介護保険の被保険者になる40歳・50歳あたりがポイントです。40歳の時には、介護保険の概要や社内の介護支援の仕組みなどを説明しましょう。また、親御さんが65歳を過ぎて認定を受ければ介護保険サービスを使えることも合わせて伝えると良いでしょう。50歳の時には、多くの親御さんが75歳以上になる年齢のため、再度同様の説明を行うと周知が進みます。
ここまでを踏まえた上でも、「ケアハラスメント」が起きてしまった際には厚生労働省より発行されている『職場におけるハラスメント対策マニュアル』に記載されている対処法が参考になります。その中から、今回は人事の対処法として基本となる5つの手順をご紹介します。
(1)事実関係の調査
(2)調査報告書の作成
(3)加害者への適正な措置の実施
(4)被害者に対する適正な配慮・措置の実施
(5)再発防止への取り組み措置
(1)事実関係の調査
ハラスメントの疑いがあることを知った場合は、まず被害者と行為者(加害者)とされている方を隔離するかどうか検討します。調査の担当者は客観性を担保するために複数であることが望ましく、処分の効力を争われた場合に備えて当事者の同意を得た上で録音やメモを取るなど詳細を記録します。また、場合によっては社内担当者が調査するよりも外部担当者(弁護士や社労士など)を活用して調査を行った方が中立性も高くスムーズに進行するケースも多いです。どのような体制で調査を行うかは状況に合わせて判断しましょう。
(2)調査報告書の作成
関係者からの調査内容・報告はすべて一致することはほとんどなく、被害者と行為者(加害者)の供述内容も食い違うのが一般的です。被害者と行為者(加害者)の言い分が食い違う場合、判断を誤ると関係者から訴えられることもあるため十分注意が必要です。調査完了後は事故報告書の作成を行い、諮問委員会(名称は企業により異なる)にて審議を行います。
(3)加害者への適正な措置の実施
就業規則、その他の職場における服務規律などを定めた文書、職場におけるハラスメントに関する規定などに基づき、行為者に対して『必要な懲戒その他の措置』を行います。さらに、事案の内容や状況に応じて以下のような措置も実施します。その際、行為者とともに働く従業員のフォローも忘れてはいけないポイントです。
・被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助
・被害者と行為者を引き離すための配置転換
・行為者の謝罪
など
(4)被害者に対する適正な配慮・措置の実施
調査によりハラスメント行為が認定され、行為者(加害者)の処分方向性が定まった際には、被害者に対してできるだけ具体的に理由を添えて報告する必要があります。処分妥当性についても客観的・合理的な根拠を用いて、本人に理解を促すような配慮が必要です。
被害者の心的負担は相当なものだったことが想像できますから、ケアは必須です。また、行為者の処分や被害者へのフォローは良くも悪くも周りの従業員に伝播します。つまり、会社がどう動いたかによってその後の組織パフォーマンスに大きな影響を与えるのがハラスメント対応だということです。行為者への指導はもちろん、面談などを通じて他の従業員にも寄り添うことで、『1人ひとりが働きやすい職場環境』を作ることが欠かせません。
(5)再発防止への取り組み措置
再発防止に取り組まなければ何度でもハラスメント事案は発生してしまいます。以下のような取り組みを通じて、こうしたハラスメント事案が発生しないよう取り組むことは何より重要です。
・全体研修の実施
・啓発や周知の実施
・相談窓口の増設
・規則類や対応マニュアルの整備(拡充)
・専門家(弁護士や社労士など)との顧問契約
「ケアハラスメント」の予防方法
──「ケアハラスメント」の再発防止策について先ほど少し触れてもらいましたが、ここについてもう少し具体的に教えてください。
先ほどは再発防止策についてご紹介しましたが、正直なところハラスメントは“問題が起こってから対処するのではもう遅い”と思っています。実際にハラスメントが起きてしまえば、それにより精神的なダメージを受けてしまう方がいるからです。
そのため、理想としては『いかにハラスメントを未然に防ぐか』について問題が起きる前から全力で検討し取り組むことが重要だと考えています。具体的には、以下5つの観点から取り組みを進めて行くと良いでしょう。
(1)明確な方針の策定と周知
(2)ガイドラインの策定と周知
(3)適切な報告チャネルの提供
(4)教育とトレーニングの提供
(5)内部監査体制の強化や定期的なアンケート
(1)明確な方針の策定と周知
「ケアハラスメント」を禁止する明確な方針を策定し、すべての従業員に周知させます。会社のトップ層が『職場から「ケアハラスメント」をなくす』とハッキリ意思表示を行うことが重要です。なぜなら、トップ層が「ケアハラスメント」を黙認してしまうと、改善どころか『役員は気づいているけど何も言わないから大丈夫だ』と誤った考え方が広まる原因にも繋がるからです。
(2)ガイドラインの策定と周知
ハラスメントを行ったものに対して対処するという方針を策定し、具体的な懲戒処分を定めたガイドラインを作成します。処罰を周知しておくことで「ケアハラスメント」発生を抑制する効果があります。また、万が一「ケアハラスメント」が発生してしまった際にも迅速に行動できるようになり、被害を最小限に抑えられます。
(3)適切な報告チャネルの提供
従業員がハラスメントを報告しやすい環境を整え、報告者が報復を受けないように保護します。具体的には、信頼性のある報告チャネル(個別の担当者、ホットライン、オンラインフォームなど)を提供します。
(4)教育とトレーニングの提供
従業員に「ケアハラスメント」の定義や種類、組織のポリシーを教育し、意識を高めるためのトレーニングを実施します。具体的には、育児介護休業の仕組みや権利、どんなことが「ケアハラスメント」に該当するのか、などの知識や意識を浸透させる内容を実施します。これらは1回実施したら終わりではなく、定期的に内容を確認するなど浸透度をチェックする仕組みづくりも合わせて必要です。
(5)内部監査体制の強化や定期的なアンケート
内部監査の強化はもちろん、半年も~1年に1回の定期的なアンケート調査・ヒアリングなどの仕組みづくりを進めていきます。定期的に実施されることで予防や理解も徐々に深まります。
これらハラスメントの予防施策は、組織全体が取り組む必要のあるものです。その中でも人事部門は中心的な役割を果たします。組織のリーダーシップやカルチャーの在り方次第でもハラスメントの予防につなげられるため、人事部門が果たす役割は非常に大きいと考えています。
■合わせて読みたい「ハラスメント・コンプライアンス」に関する記事
>>>「マタハラ防止対策」が2022年4月よりさらに強化。その内容と対策を解説
>>>社員の「コンプライアンス教育」を進める上で必要な知識と考え方
>>>「時短ハラスメント」の原因や背景を知り、未然に防ぐ方法とは
>>>「セカンドハラスメント」の種類・発生原因・適切な対処方法を解説
編集後記
「ケアハラスメント」問題は、単に組織パフォーマンスを下げるだけではありません。介護などで体力的・精神的負担を感じている従業員へさらなる追い打ちをかけるような出来事であり、さらには高齢化社会である日本全体の問題でもあります。いつ・誰もが当事者になってもおかしくないと考え、何かが起こる前に対策を進めておきましょう。