【対談インタビュー】創業期のスタートアップにおける採用土台づくりに外部人材を活用した事例
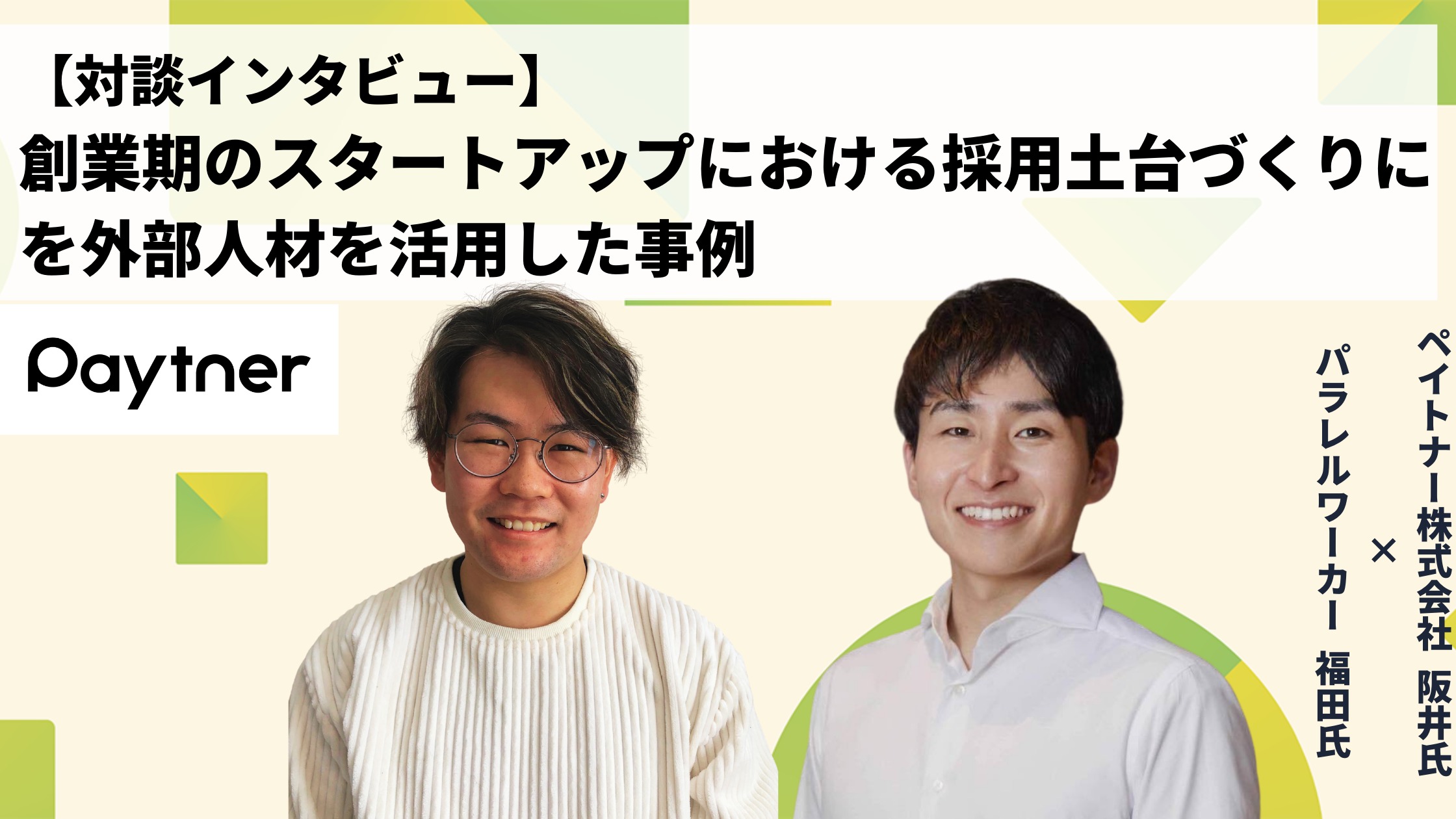
コーナーへのご依頼やお問い合わせはこちら。
人事パラレルワーカーを社外から受け入れ、事業推進を行った企業にインタビューをする「対談インタビュー企画」。今回ご紹介するのは、2019年2月からBtoB決済サービスを展開し急成長を遂げているペイトナー株式会社が、1人目の外部人事として人事パラレルワーカーを迎え入れた事例です。その経緯やプロセスについて、今回はペイトナー株式会社 代表取締役社長の阪井 優さん、そしてパラレルワーカーの福田 友樹さんにお話を伺いました。
■この事例のポイント
・採用業務がほぼ未経験のボードメンバーに変わり、創業当初の採用土台作りを「1人目人事」としてジョインした外部人材が担うことで実現した。
・人材を外部・内部で区別することなく同じ粒度でコミュニケーションすることで、パラレルワーカーの専門性や知見に任せ、プロの力を最大限に引き出した。
<プロフィール>
■阪井 優(さかい ゆう)/ペイトナー株式会社 代表取締役社長
1989年、大阪府堺市生まれ。智辯学園高等学校、大阪教育大学を卒業後、NTTドコモを経て、コイニー(現:STORES 株式会社)に入社、事業開発として地域金融機関との提携、テンセントの決済サービス「WeChat Pay」に関する業務に従事。2019年2月にペイトナーを設立、「TechCrunch Tokyo 2019」ファイナリスト、「Forbes JAPAN 100」に選出される。
■福田 友樹(ふくだ ゆうき)/人事パラレルワーカー
大手求人メディアの営業職としてHR領域のキャリアをスタートし、その後IT企業の1人目人事としてバックオフィス部門の立ち上げや、採用広報などを担当。現在は人事パラレルワーカーとして、主にエンジニア採用のダイレクトリクルーティングや戦略立案~実行までの一連に携わる。
目次
「外部人事」の参画が、組織の成長スピードを加速させる
──つい先日(2022年12月15日)にも総額約19億円の資金調達を実施した件がニュースになっていましたね。まさに破竹の勢いで成長を続けるペイトナーですが、その創業背景はどのようなものだったのでしょうか。
阪井さん:ペイトナーは「成長する全てのビジネスの、お金のストレスをなくす」をミッションに掲げて、スモールビジネスの資金繰りや資金管理を簡単にするサービスを提供している会社です。その創業のきっかけは、前職でベンチャー企業に在籍していた時の原体験。多くの個人や中小企業のお客様が資金繰りや管理で悩む様子を目の当たりにし、「本来の業務に集中できる環境を作りたい」という想いからペイトナーを立ち上げました。
そんな僕らも、創業後は「お金面」でかなり頭を悩まされました。スタート時に出資いただいた資金にも限りがあるので、他にも銀行から借り入れを行ったり、何度も投資家にプレゼンして資金調達を進めたりと、お金集めには相当苦労したのを覚えています。創業から約2年で売上が大きく伸び、サービスを利用いただいているお客様からも「資金繰りにとても助かっている」「毎月月末に2~3時間かかっていた請求書の時間と手間、ストレスが軽減された」といった声をもらえるようになりました。
もう1つ大変だったのは「仲間集め」です。創業当初は正社員採用にかける力がなかったこともあり、前職の同僚や友人に副業(業務委託)で入ってもらって、サービスを作り上げていきました。そんな背景もあって、今でも一緒に働くメンバーの契約形態については、そこまでこだわりはないですね。それよりも「自社のビジョンやミッションに共感してもらえるかどうか」を第一に考えて仲間集めを行っています。

──コーナーにお声がけいただき、福田さんをお迎えしたのは2021年の末頃でしたね。なぜ人事領域においても外部人材を活用しようと思われたのでしょうか?
阪井さん:エンジニア採用はそれまで別の副業・複業マッチングプラットフォームを使っていたのですが、そこでお世話になっている担当者の方に「そろそろ採用専任の方が欲しい」と相談したところ、コーナーをオススメしてもらったんです。
実は、私自身も含め、創業メンバーの中に採用経験がある人がおらず、当時は採用ツールもフローもほとんど整備されていない状態でした。一応採用管理システムは入れてみたものの運用しきれず、スプレッドシートやSlackで対応していたくらい。そんな環境下で採用に関する一連の流れや仕組みを整えたい──そんな要望をコーナーにお伝えし、福田さんとつなげてもらった形です。
福田さん:ペイトナーは「社会の負を解消する」という点でとても素敵な事業をやっていると感じますし、何より代表である阪井さんの人格が魅力的。阪井さん自身が自分のできること・できないことをよくわかっているというか、できないことも「助けて」と飾らず言ってくれるので、周りが助けようという気持ちになるんですよね。ペイトナーの事業もメンバーも好きなので、こぼれているボールやタスクがあるなら自分から取りにいこうと思えるほどです。
あとは、採用に妥協しないスタンスも私自身の考えと近しいものがありました。ただ単にヘッドカウントを揃えるためではなく、事業の「未来の在り方」と「現在地」のギャップを埋めるための手法としての採用という考えが一致していたので、スムーズに支援を行うことができたと思います。
私が普段企業を支援する上で大事にしているのは「期待値を超える」こと。そのため、通常であれば業務委託が入ってから活躍するまでには時間が掛かるのが一般的といわれているところを、今回はその通説を跳ね除けるために圧倒的なスピードで準備を進めました。2021年12月の年末にジョインして、年内にはボードメンバーから採用業務を巻き取り、年明けには事業進捗やフェーズを考えながら採用の武器や強みを見つけていく業務もスタートさせました。早く戦力にならないと!と思うあまり、大晦日当日にも1人でスカウト配信をしてたくらいです(笑)。
阪井さん:大晦日まで仕事させてしまったのは申し訳ないのですが(笑)、ジョイン後の凄まじいアクションを目の当たりにして、「人事のプロってこういう人のことを言うんだ」と実感しました。福田さんはすごく実直かつ真面目に自分たちがやれていないタスクを積極的に拾って推進してくれます。ジョブディスクリプションなどもイチから作ってくれましたし、適切な媒体の選定や、エージェントとコミュニケーション取ってくれたりと、いいカタチでスタートも切れたと感じます。
自分たちだけで進めていたときは、普段のタスクに忙殺されて、つい採用業務は後回し……となりがちでした。しかし、福田さんが必要業務を洗い出してスケジュールを切ってバリバリと推進してくれるので、お尻を叩かれている気分でありがたかったです。
──福田さんがジョインされてから、どのようなことに取り組まれてきましたか?
福田さん:エンジニア採用を設計する上で、まず「母集団を作る」ことが重要だと考えました。というのも、ペイトナーでは採用リソースが少なくトライ&エラーが足りていないと感じたからです。だからこそ、ジョイン後はスカウトや媒体露出など採用全体における行動量を増やすことを先決にアクションを開始。その後、「そもそもエンジニア組織って何に困っているんだっけ?」という未来を描くための話をCTOと共にキャッチアップ&ブラッシュアップしていきました。
ここまで1年近く一緒にやってきましたが、その中でかなり行動量を伸ばすことができたかなと。あと、社内で採用に関して興味を持ってくれる人が増えたようにも感じています。今では各方面から「ここで困っているんだけれど、採用をどうすれば良い?」と相談をもらえるようになったからです。ペイトナーはもともと「走りながら学習する」カルチャーを持っているので、自分を起点として組織全体に採用ノウハウをインプットすることができれば、もっと早い速度で成長していけるような気がします。
阪井さん:福田さんのジョイン後、まず面接数が圧倒的に増えましたね。自分たちだけで採用を進めていた時は面接1つ設定するにも大仕事で、1件組めたら「おぉ、やっと設定できた」と思うくらい。今では面接がどんどん組まれ、内定までキレイに流れていくんです。採用に知見のないボードメンバーが四苦八苦していた業務を福田さんがどんどん巻き取ってくれた上で、採用ツールを選定し、ジョブディスクリプションの作成、面接設定、求職者コミュニケーション、内定通知と、採用のために必要なスケジュールが上から実行されていく。昔とは大違いです。
あと、福田さんの客観的な視点からのフィードバックなどもあって、自社の採用における強みなども理解できるようになりました。行動指針のひとつに「全員で最高のチームを作る」というものがあるのですが、みんなで良いチームを作っていくことに意識が向いている点が特徴であり強みにもなっているようです。
結果、わずか1年の取り組みにも関わらず、最近では巷で有名なスタートアップ企業などで活躍しているエンジニアの方とも選考を通じて会えるようになりました。これは自分たちだけで採用活動を進めていたらきっと到達できていなかった領域だと思います。

外部人材が活躍できる「場」の作り方
──外部人材を活用する上で工夫されていることはありますか?
阪井さん:「外部人材だから」と区別をしていない点でしょうか。例えば、社内の情報に関しても給料などのセンシティブな情報以外はすべてアクセスできるようにしており、情報の粒度はまったく分けていません。雇用や契約形態で何かを分けてしまうと会社全体で見たときにパフォーマンスが下がると思っていて。そこを区別することなく、同じ粒度でコミュニケーションをできるようにすることが外部人材活用の環境面における最も大事なことなのではないでしょうか。
あと、何かしらペイトナーの成長に関わってくれた人には、金銭的な報酬以外にも良いものを返したいなと考えています。うちに関わる期間は人生の中でもそう長くないだろうけれども、その中で良い経験や思い出ができたと感じてもらえたら嬉しいですね。そこに雇用形態や関わり方は関係ありません。
福田さん:ペイトナーと協働しやすい要因として、「任せてもらっている感」が挙げられると思います。よく上司・部下のマネジメントでもあるのが、自分の気になるところだけフィードバックをもらうマイクロマネジメント的なコミュニケーション。これだとただの作業員として見られているような気がするのですが、ペイトナーは「全部任せた!」と言い切ってくれるので、手足としてではなく仲間として見てくれている気がしますね。リソースをアウトソースするための人材ではなく、この領域のプロとして認めてもらっているので、結果で返さないとという気持ちになるんです。
阪井さん:福田さんのことをプロだと認めているし、お任せしていますが、全部丸投げになってしまってはダメだとも思っていて。現状、業務委託メンバーの割合がかなり多い(60名ほど)ので、マネジメントスキルを高める必要性をヒシヒシと感じています。
実際、これまでにもお互いの期待値がずれていたことが要因でうまく成果を出せないことがありました。こちらが期待しすぎてもうまく行かないし、反対に外部人材の方が張り切りすぎてあれもこれもとなってはポイントが絞れず結果が出ない。そうした失敗からも学びを得て、工夫・改善を行っているところです。
今後のビジネス成長と組織拡大に向けて考えていること
──福田さんと一緒に採用を前に進めてきた1年でしたが、今後はどんなことに取り組みたいと考えていますか?
阪井さん:5年後の上場を目指して、その時には100名近い組織を作っていたいなと考えています。今は業務委託のメンバーが中心となって組織の土台づくりを行っていますが、ゆくゆくは正社員割合を7~8割くらいまで伸ばしてより開発ドリブンな会社にしたい。2022年9月に新しくサービスも出したので、その立ち上がり具合によってはもっと人が必要になるかもしれません。
あと、メンバーの副業をもっと推進してさらなる多様性を持った組織にしていきたいなと。副業先で学んだスキルや知識を社内に持ち帰ってもらうことはもちろんですが、我々が創業期からそうだったようにこれから伸びる会社をうちのメンバーが副業で支援することで他のスタートアップが伸びていくきっかけになればいいなと思っていて。なので、「副業OK」ではなく「副業推進」と言い切って取り組んでいます。
福田さん:今後組織をさらに拡大させていく中で直面しそうな課題として、「ビジョンの発信」があります。現状、ペイトナーが発信できているのはミッションやプロダクトといったビジョンを実現するためのスタンスや手段についてが多く、「こういう未来に向けてこんな組織にしていきたい」というビジョン発信はまだまだできていません。こうした発信を増やすためにも、各領域や広報・マーケティングで採用の話をするときには「どんな未来を描いていきたいか」についてできるだけ話をするようにしています。そうした積み重ねがこれからは重要になってくるのかなと。
あともう1つ重要なのは、「採用基準のさらなる明確化」。この1年伴走してきた中で、ペイトナーで活躍できる人材には大きく2つの側面があると感じています。1つは「学習しながら走れる人かどうか」。ペイトナーのメンバーには知的好奇心が高い人が多く、Slackで各々タイムチャンネルを作って自分たちが何をやっているかを平日・休日問わず吸収している人が多いんです。もう1つは「社会に対する負を解消したい気持ち」。代表の阪井さんがそうだったように、メンバーでもそうした社会の負に対して想いを持っている方が多いと考えています。この2軸が揃っているからこそ、目指している世界のために切磋琢磨できるんだろうなと思っているので、今後採用基準にしっかり落とし込んでいきたいと考えています。
──これから外部人材を活用したいと考える会社へ、アドバイスがあれば教えてください。
阪井さん:当社がそうだったように、契約形態で分けずにとにかくオープンな環境を作ることが最も大事だと思います。昨今はまだまだ対面でコミュニケーションを取りづらい面もありますが、できる限りカジュアルに交流できる場も作って、経営陣がしっかりと意思疎通を行いコミットするべきなのかなと。
あともう1つは、「外部人材をリソースとして見ない」こと。こちらで切り出したタスクベースで依頼してしまうと、それ以上の成果を得ることは難しくなりますし、何よりもプロの力を最大限発揮してもらえなくなってしまいます。福田さんのようにプロとして自走できる方であれば、我々が気づけないポイントや取りこぼしている業務も拾って前に進めてくれるので、私たちにできるのは福田さんが動きやすくなるように環境を整えるくらいなのかなと。そのためにもマネジメントスキルは必要になってくると思っています。
福田さん:外部人事側も「自分に対して期待されているものは何か」を考えることはすごく大切で、その上で企業とも期待値やミッションを握っておく必要があります。私自身、過去に失敗をしたのもここがボトルネックでして、合意形成がしっかり取れていないと、タスクベースで「これだけやっていればOK」みたいな状況になってしまい、そこから広がることがありません。渡されていないタスク以外にもやれることはあるはずなので、どこに期待値や目標を置くかについては事前に企業側とコミュニケーションし合意を取っておくと良いと思います。
編集後記
スタートアップの1人目人事として外部人材にジョインしてもらい、ほぼゼロから採用の土台を作り上げた今回の事例。阪井さん・福田さんの関係性が「依頼者と作業者」ではなく、1人の人間として信頼し合い、同じ方向を向いて進んでいる様子が取材からも垣間見えました。
外部人材だからと区別しない──このスタンスこそが外部人材活用において最も大切なことだと認識すると共に、プロ人材が「この会社と一緒に働きたい」と思える組織・人間的魅力こそが優秀な外部人材を惹きつけるポイントなのだと感じました。






