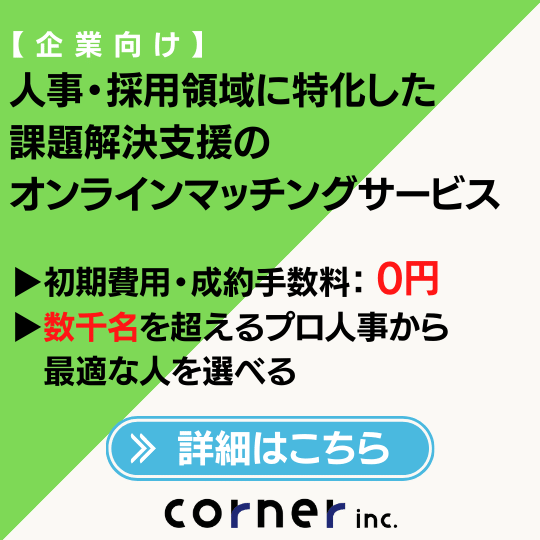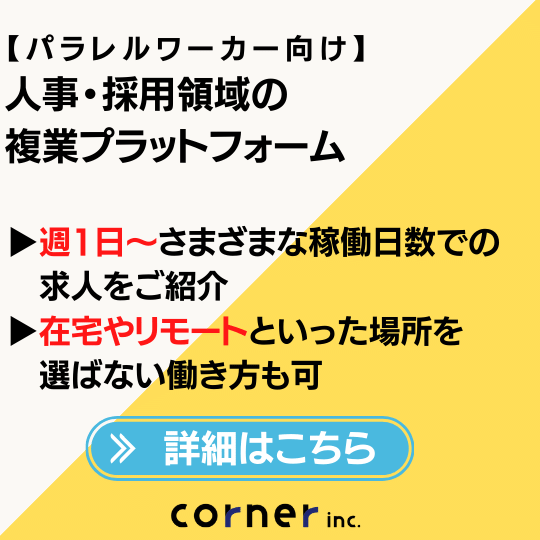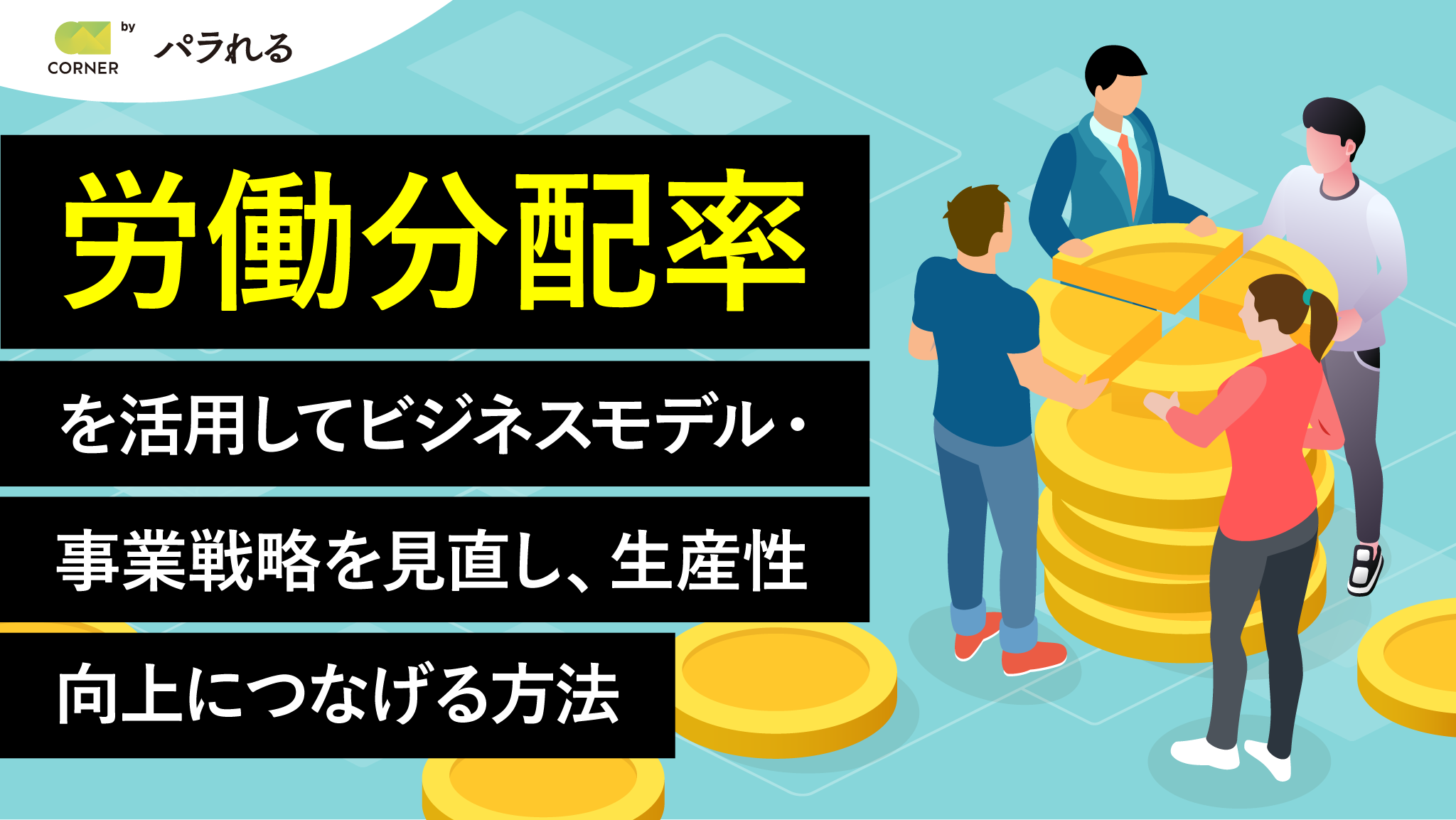メンバーの「EQ(感情知性)」を向上させ、組織パフォーマンスを高める方法【前編】
」を向上させ、組織パフォーマンスを高める方法【前編】.jpg)
「感情を表に出さないことがビジネスパーソンにとって正しい」という考え方があるように、仕事において「感情」に目を向ける必要はないと考えてきた方も少なくないでしょう。しかし「感情」はすべての人間が必ず持っているもの。抑え込むのではなく、自分の感情も他者の感情も上手く扱うスキルを身につけることが重要です。
このスキルは、IQ(知能指数)と並べて「EQ(感情知性)」と定義されています。EQの高さは天性のコミュニケーションスキルや性格だけによるものではなく、後天的に鍛えることができます。今回は、2011年からこの「EQ」について実践と研究を進めてきたEQトレーナーの池照佳代さんに、その定義と組織への活かし方などをお聞きしました。
<プロフィール>
池照 佳代/株式会社アイズプラス 代表取締役
マースジャパン、フォードジャパン、アディダスジャパン、ファイザーなどで一貫して人事職を担当。人事制度設計・運用やタレントマネジメント、ダイバーシティ、女性活躍推進プログラムの企画実行など、人事業務全般に携る。出産後、法政大学経営大学院在学中にアイズプラスを設立。主に企業向けの人事支援に携わり、コーチング、マネジメントスキル講師としても活躍。最近では、女性活躍支援のための制度・職場づくりにも関わり、人事職で培ったスキルと、EQトレーナーならではのコミュニケーション・ファシリテーションスキルを兼ね備えたIC(インディペンデント・コントラクター)として、高い評価を得ている。2021年4月から山野美容芸術短期大学 特任教授。著書に『感情マネジメント ~自分とチームの「気持ち」を知り最高の成果を生みだす』(ダイヤモンド社)など。
目次
EQ(感情知性)とは
──まず「EQ(感情知性)」の定義について教えてください。
EQ(Emotional Intelligence Quotient)とは、「自分の感情や思考をマネジメントして、成果に向けて動かす力」のことを指します。
EQについて世界で初めて語られたのは、1990年に出されたアメリカの学術論文の中でのことでした。心理学者たちが「こんなにIQも学歴も高い人たちが会社をマネジメントしているのに、組織ををつぶしてしまうリーダーがいるのはなぜだろう」と疑問を持って調査を開始したところ、「IQよりもエモーショナルな部分が組織に影響している」という研究結果を導き出しました。
その後1995年にジャーナリストであったダニエル・ゴールマン氏が「EQ こころの知能指数」を出版。一般人にもEQを分かりやすく解説したこの本がベストセラーになり、その概念が世界中に知れ渡りました。
EQは、その言葉のイメージからメンタルやスピリチュアルに関する新しい概念だと思われがちです。しかし、そもそも感情は赤ちゃんから老人まで人間に標準装備されているもの。そこに着目し、感情を人生やキャリアにどう活かして“発揮”していくのかというのがEQの根底にある考え方です。
人を動かす原動力は「感情」にあります。知識やスキルで人を説得することはできても、心から共感・理解をして動いてもらうことはできません。
そのため、EQとは他のすべてのスキルの土台となるものになります。自分と他人の感情に目を向け、感情をマネジメントし活用することができれば、大きな成果や成長に繋げることができます。
──日本でEQという言葉が認知されたのはいつ頃だったのでしょうか?
2016年のダボス会議において、EQが世界のビジネスパーソンに必要なスキルTOP10に挙げられたことが大きな転換ポイントになりました。
私自身がEQについて学び始めたのは2011年頃のこと。ずっと人事畑で採用、評価、アセスメント、サクセッションプラン(事業後継者の育成施策)などに取り組んできた中で、「メンバーも優秀で、必要な知識もあるのになぜか成果が上がらない」という場面に何度も遭遇しました。そんな時に改めてEQの概念に触れ、「まさに今の組織に足りないのはこれだ!」と直感したことがEQに関わり始めたきっかけだったのです。
しかし、当時はまったくと言っていいほどEQは理解されませんでした。組織開発や経営支援の手段としてEQの話をしても、「仕事において感情とかは関係ないから」と一蹴されることもしばしば。それどころか「あれだけバリバリ働いてた池照さんでも、お子さんができると(感情がどうとか)そうなっちゃうんだね」と言われることもあって。
でも、ダボス会議後は状況が一変。「池照さんが言ってたのはこれだったんだね」と理解してくれる方も増え、問い合わせが急増したんです。
とはいえ、まだまだEQは十分に理解されていないと思っています。EQとメンタルヘルスに関する本は日本でもよく目にしますが、EQを組織の力に変えていくという考え方は一般的ではありません。また組織開発や人材育成についてもリーダーシップ論やコーチングといった手法が先行し、「感情」という概念が抜け落ちていることが多いように感じます。
なぜEQが重要だと言われ始めたのか
──日本でも、アンガーマネジメントなどEQを重要だと考える風潮は強くなってきているように思います。その背景は何でしょうか?
「知能から知性の時代へ」ダボス会議でも言われた変化が、要因としてあるでしょう。
従来の組織はトップダウンが中心で、社員はリーダーの言うとおりにオペレーションを回していれば一定の成果が出せる時代でした。社員に求める能力も、正解がある問いに対して素早く正確な形へたどり着く力(=知能)がメインであり、似たような人材を集める傾向がありました。
しかし、これから迎える第四次産業社会では、顧客ニーズは多様化し、より正解のない世界へと入っていきます。それに対応するかの如く、リーダーの在り方もトップダウン型からサーバント型や協働型など多様に変わってきており、アメーバ型・ネットワーク型の組織も多く見られるようになりました。人材要件も正解がないものに対して答えを探求する力(知性)がより求められるようになり、その知性の中には感情を扱うEQの要素も多分に含まれています。
こう説明をすると「これからはIQではなくてEQの時代ですね!」と言われたりするのですが、決してそういう訳でもありません。今までがIQに偏りすぎていただけであり、パフォーマンスを上げるためにはIQもEQも必要なのです。
新型コロナウイルスにより「知能から知性」への変化が急激に加速したことも、EQの重要性を大きく高めました。特にリモートワークが普及したことにより、現場のリーダーからは「部下の気持ちが分からない」「信頼関係が築けない」といった悩みをよく聞きます。その原因がすべてリモートワークにあるとは思いませんが、「気持ち」や「感情」というキーワードに着目しやすくなった時代背景も、EQの理解促進に寄与していると感じます。
EQで個人・組織パフォーマンスは上げられる
」を向上させ、組織パフォーマンスを高める方法【前編】.jpg)
──自身の感情をマネジメントすることで個人がより良い状態になることはイメージできるのですが、それがパフォーマンスとどうつながっていくのでしょうか?
それを考える上で、まずパフォーマンスが何から構成されているかを考えてみましょう。
「パフォーマンスにつながる要素を洗い出してみてください」と色んな企業に質問すると、おおよそ以下3つの要素に集約されます。
① IQ(知能/情報収集力・ロジカルシンキングなど)
② ナレッジ(業務を推進する上で必要な知識・知見など)
③ アクション(行動量)
しかし、この3つがあれば必ず成果につながるかと言えば、そういうわけにもいかない時代になってきたのは前述の通りです。では何が足りないか。そこで登場するのがEQです。
先ほどもお伝えした通り、人が動く原動力は、知識やスキルではなく感情です。
そのため、自分や他人の感情をマネジメントするEQは、パソコンで例えるなら「OS」のようなものです。これがなくてはどれだけ良いアプリケーションがあってもアプリケーションはその力を発揮することはできません。つまり、いくらIQが高いメンバーが集まり、質の高いナレッジを保有し、行動力を確保したとしても、その土台となるEQがうまく発揮されていなければ、個人のパフォーマンスを最大化できないのです。また、個人のパフォーマンスが感情を土台にすることと同様に、組織の感情状態は組織パフォーマンスに大きく影響します。
私が各企業の支援をさせていただく際も同様の質問からスタートすることが多いのですが、そこで大半の企業がEQの視点が抜け落ちていることに気づきます。「やるべきことはすべてやってるはずなのに、なぜか成果につながらない」そんな企業の課題は、意外にもEQで説明できることが多いのです。
とはいえ定性的な話も多くなるため、ここまでお話をしてもまだその必要性に気づいてもらえないこともあります。そんな時は定量的な数字で出ている課題についてヒアリングをします。どこの企業も定着率・離職率・メンタル不全の問題は抱えていて、人事としては何とか解決したいと考えているもの。その要因を一緒に考えていくことで、結果的にEQが足りないことに行きつき、理解を得られることが少なくありません。
その後半年~1年かけてEQの概念を組織に取り入れ、EQを高めるためのトレーニングを社内で行うことにより、これまでに出せなかった成果が出るようになります(もちろんIQやナレッジなどその他足りないところも同時並行で補いながら)。
──EQの概念を組織に導入し、成果が出た企業の事例を具体的に教えてください。
以前ご支援したある会社は、「顧客との関係性」が最も売上インパクトの高い要素になっている企業でした。そのためこれまでもコミュニケーションや関係性構築をテーマとした研修や勉強会を日々行ってきましたが、一向に成果が上がらなかったと言います。相手の目を見て話そうとか、傾聴しようとか、そういった技術的な話ですね。
繰り返しになりますが、優れたスキルやテクニックを知っていたとしても、それらの効果を発揮する上でOSとなるEQの概念は欠かせません。自分や相手の感情を理解した上で、目指すべき成果に対してどんな方法を選択すればよいかを考える。このスタンスなしにテクニックばかりに走っても、成果につながりにくいことは想像いただけるでしょう。
この組織においても半年〜1年ほどかけてEQの概念を浸透させることで、成果を2倍に伸ばすことができました。元々持っていたIQ・ナレッジ・アクションにEQが加わることで、これだけの成果を創出できるようになったのです。
もちろんEQは「顧客との関係性」だけでなく「社内の関係性」にも有効です。
例えばチームマネジメントをする中で1on1をやる企業も増えたと思いますが、その1on1の場で自分や部下の感情がどんな状態かをいつも記録している人ってほとんどいないですよね。大半がその時進めている仕事の進捗とか、困っていることに対するアドバイスに終始しているはずです。
でも、その1on1の中で「今日はどんな気分ですか?」と問いかけてみると、たちまち景色は変わってきます。初めはどう答えたらいいか分からないメンバーも多いかもしれません。でも慣れてくると、「子どもの食事の準備もあっていつも焦っています」とか「雨でなんとなく気分が上がりません」とか、徐々に感情を話してくれるようになります。これらの感情を無視して正論や仕事の指示をぶつけていても、メンバーは上司の言っていることを素直に受け止めることはできないでしょう。
昨今の変化を受け、一番頭を悩ませているのがマネジメントを担うリーダーの方々です。そのリーダーがEQを理解しうまく活用することができれば、その影響力はとても大きいものになります。これまで感情を一切抜きにしてマネジメントしていた方はいないと思いますが、もっと意図的に感情に重きをおいてマネジメントしてみてはどうか。これは私が特に伝えていきたいことの1つです。
後編もお楽しみに!
ここまでのお話で、EQとは何か・EQが組織において重要な理由について理解することができました。後編では、具体的に「EQを後天的に鍛える方法」についてご紹介していきます。お楽しみに!
後半の記事はこちら
■合わせて読みたい「コンピテンシー」関連記事
>>>「コンピテンシー」に基づく人材開発で組織のパフォーマンスを高める方法
>>>「シェアドリーダーシップ」でメンバーの主体性を高め、変化に対応できる組織をつくる方法