「レイオフ」を正しく理解するために知っておきたい世界動向と国内事例

一時解雇を意味する言葉の「レイオフ」。日本と比較すると海外では用いられることも多い取り組みですが、日本ではまだ実施されるケースはほとんどありません。しかし、最近アメリカの大手IT企業が行った大規模な「レイオフ」に日本法人従業員も対象として含まれていたことなどから注目度が高まっているワードと言えます。
そこで今回は、上場企業からベンチャーまで幅広く経営課題に向き合ってきた村井 庸介さんに、「レイオフ」の概要から事例、留意すべきポイントに至るまでお話を伺いました。
<プロフィール>
村井 庸介(むらい ようすけ)/人事パラレルワーカー
中小企業の社外番頭として、人事制度のみならず新規事業開発・DXと企業の経営課題を横断的に眺めながら企業成長を支援。独立前は野村総合研究所・リクルート・グリー・IBMなど合計8社で就業し、その経験からキャリアに関する本も出版。企業在籍時に培った人事制度設計・戦略コンサルティングの経験から、現在もベンチャー企業から上場企業まで幅広く人事制度設計・再構築支援に携わっている。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「レイオフ」とは
──ニュースなどでも聞くことがある「レイオフ」ですが、改めて概要について日本と海外事情の違いも含めて教えてください。
「レイオフ(layoff)」とは『一時的な解雇』を意味する言葉です。企業の財政難、事業の縮小、技術革新による作業自動化などの理由に基づき、従業員が一時的または恒久的に職を失うことを指します。また、「レイオフ」は従業員のそれまでのパフォーマンスとは無関係に行われることが一般的です。
なお、海外(特に欧米)と日本における「レイオフ」の法的規制や取り扱いには大きな違いがあります。労働市場の流動性が高い欧米では「レイオフ」はよく見られる事象です。特にアメリカでは雇用の自由が原則であり、経済・企業状況に応じて「レイオフ」を比較的容易に行うことができます。これは企業だけでなく、労働者にとっても新しいスキル習得や雇用機会を追求するインセンティブになっています。
アジアでは、国によって労働規制が大きく異なります。シンガポールのような自由経済を志向する地域では規制も比較的緩やかです。中国やインドのように労働者保護が強い国もありますが、いずれの国も労働流動性と労働者保護のバランスが重要な課題となっています。
一方、日本では従業員の権利が強く保護されているため「レイオフ」の実施自体も非常に少ないのが現状です。このように、各国・地域ごとに「レイオフ」に対する法的規制や文化的な理解が異なるため、国ごとの規制に準じた柔軟な対応が必要になっています。
リストラや解雇との違い
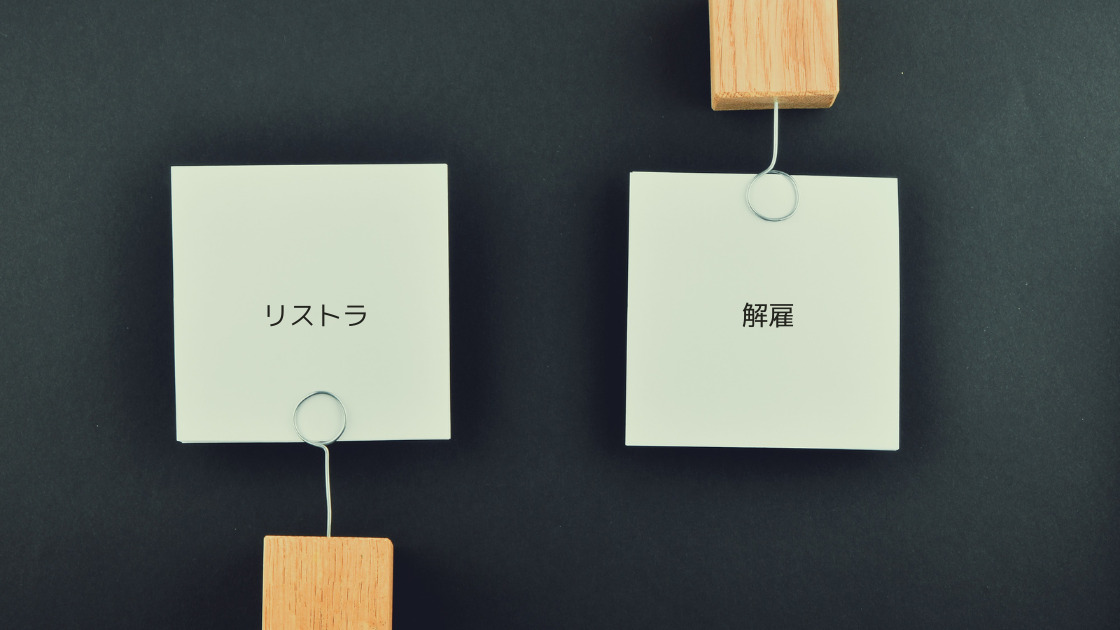
──日本においてはリストラや解雇などの方が馴染みのあるワードですが、「レイオフ」とはどう違うのでしょうか?
解雇とは、従業員との雇用契約を会社側の一方的な判断により終了させることを指します。また、解雇には普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3つがあり、「レイオフ」は整理解雇に該当する取り組みです。
リストラ(リストラクチャリング)とは、その言葉通り『再構築』を意味するものであり、そもそも人員削減や雇用契約解除を直接意味するものではありません。しかし、このリストラに合わせて希望退職制度や早期退職制度を連動させることが多いため、人員整理のイメージとセットになっているのだと考えております。
希望退職制度とは、期間を区切って企業から従業員に対して退職希望者を募り、従業員に対して退職金の割増や再就職支援を提供・受けられる制度のことです。早期退職制度とは、定年前に退職できる制度のことです。この制度を利用して申請が受理された従業員は、その企業での勤続年数に応じた通常の退職金に加え、割増退職金の付与や再就職支援サービスなどを受けられるようなこともあります。
なお、日本においては『社会通念上相当と認められない場合は従業員を一方的に解雇できない』と労働基準法第16条に定められています。また、労働基準法第20条では『企業が従業員を解雇するのには少なくとも30日以上前から解雇予告が必要』とあります。こうした情報は厚生労働省の『労働契約の終了に関するルール』(※)などから最新情報を得られるのでぜひご覧ください。
(※)参考:厚生労働省『労働契約の終了に関するルール』
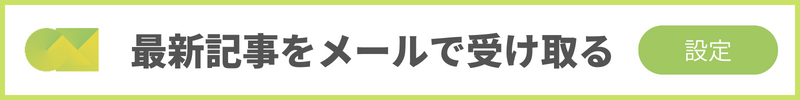
直近の「レイオフ」事例
──最近では外資系大手IT企業が大規模な「レイオフ」を行い、日本法人の従業員もその対象となったことがニュースでも大きく報道されていました。こうした「レイオフ」の事例について、国内・海外両方の観点からご紹介いただけますでしょうか。
日本で直近話題になったのはクックパッド社の事例です。2023年2月に40名の希望退職者を募集、翌3月には海外レシピサービス事業において80名の人員削減を発表しました。業績不振を背景として、特に収益貢献しづらい新規事業領域を中心に人員整理を行ったと言われています。その際、国内では退職勧奨、海外子会社では解雇を実施したようです。この実施施策の違いにも国内における「レイオフ」実施の難しさが表れていると感じます。
一方、海外ではアクセンチュアが2023年3月から18カ月間に渡って従業員の2.5%に相当する1万9000人の雇用を削減すると発表をしました。削減対象となった従業員の半数以上は間接部門の方であることから、この「レイオフ」の理由は業績不振などではなく、技術革新などによる組織の再配置・スリム化といった前向きな取り組みとなっていることが分かります。実際に投資家からも評価され、発表当日のアクセンチュア株は7.3%高で終了。一時は8.4%上昇したタイミングもあり、日中ベースで2021年12月以来の大幅高となりました。
日本ではネガティブな印象を持たれがちな「レイオフ」も、海外では未来に向けた柔軟な対応としてポジティブな評価をされることが少なくありません。ただし、これは雇用の流動性や組織への帰属意識など、元々持ち合わせたその国それぞれの文化などの影響を大きく受けているため、日本企業がそのマネをしたとしても海外企業と同じような結果になるとは限りません。日本企業が「レイオフ」を実施する際には、こうした日本の文化や認識、上述した法的な背景を正しく理解した上で慎重に判断し進めるべきだと考えています。
「レイオフ」検討時に留意すべきポイント
──もし国内企業で「レイオフ」の実施を検討しなければいけない状況になった場合、具体的にはどのような点に留意して検討を進めて行くのが良いでしょうか。
日本企業が整理解雇に該当する「レイオフ」を検討する際には、以下4つの観点からその妥当性について合意を得る必要があると考えています。
(1)人員削減の必要性
(2)解雇回避の努力
(3)人選の合理性
(4)解雇手続の妥当性
(1)人員削減の必要性
財政状況や事業環境の変化など、人員削減の必要性を明確に証明する必要があります。例えば、毎月の月次業績説明会などで業績を含めた具体的な数字を提示するなどです。その上で、いつまでにどの程度の人員削減が経営を持続するために必要かを事前に示しておくことが重要です。
(2)解雇回避の努力
解雇はあくまでも最終手段。それ以前に他の選択肢を検討・実行していく必要があります。例えば、賃金削減、週休3日制度と副業の解禁、部門間の配置転換、再教育・再訓練などが考えられます。それらの検討・実行状況を(1)と併せて説明・開示していくことが求められます。
(3)人選の合理性
「レイオフ」対象者の選定は、客観的かつ公正な基準に基づいて行われるべきです。そのためにも年齢・勤続年数・パフォーマンスなどを考慮した明確な基準を設定しておく必要があります。その際、エクセルなどに選定基準や結果を証拠として残しておきましょう。
(4)解雇手続の妥当性
企業は解雇の手続きにおいて、事前に従業員や労働組合と十分な協議を行っておく必要があります。解雇理由とプロセスを明確に伝えることはもちろん、解雇通知の期間や退職金の支払いなど解雇に際する義務も適切に遵守してください。
以上4つすべての観点において、第三者が聞いたとしても正当だと思えるだけの確認・検証が必要になってきます。また、前述した早期退職者制度などの運用も恒常的に行って組織内の不必要な滞留を無くすことができていると、いざという時に慌てずに済むようになるでしょう。
また、「レイオフ」ではなく業績を伸ばす手立てを考える方が有効な場面もあるため、「レイオフ」ありきで対処法を検討しないことも非常に重要です。一度人員削減をしてしまうと、これまでよりも少ない人員で業務を運用することになり、負荷が増大してしまう傾向があります。それが結果として売上再成長のボトルネックとなることも多いため、安易な「レイオフ」は個人的にも推奨しません。
■合わせて読みたい「離職・退職」に関する記事
>>>介護離職を事前に防ぐ。高齢化でさらに増える未来に対応するには
>>>急増する「退職者による情報漏洩」リスクと対策について
>>>退職時の「オフボーディング」で好意的な関係を築き、企業成長のヒントを得る方法
>>>「リテンションマネジメント」をから人事施策への好影響を伝播する方法とは
>>>「連鎖退職」の発生要因を知り、その防止方法を事例と共に学ぶ
編集後記
国内事例からも理解できるように、日本において「レイオフ」の実施は簡単なことではありません。ただ、将来的には解雇規制が緩和される可能性もゼロではないはずです。今のうちから「レイオフ」の概要を理解し、企業・従業員の双方がポジティブな形で実施できる方法をイメージしておけると、いざという時に慌てずに済むのではないでしょうか。






