「パフォーマンスマネジメント」とMBOの違いを理解して、人を育てる会社をつくる方法
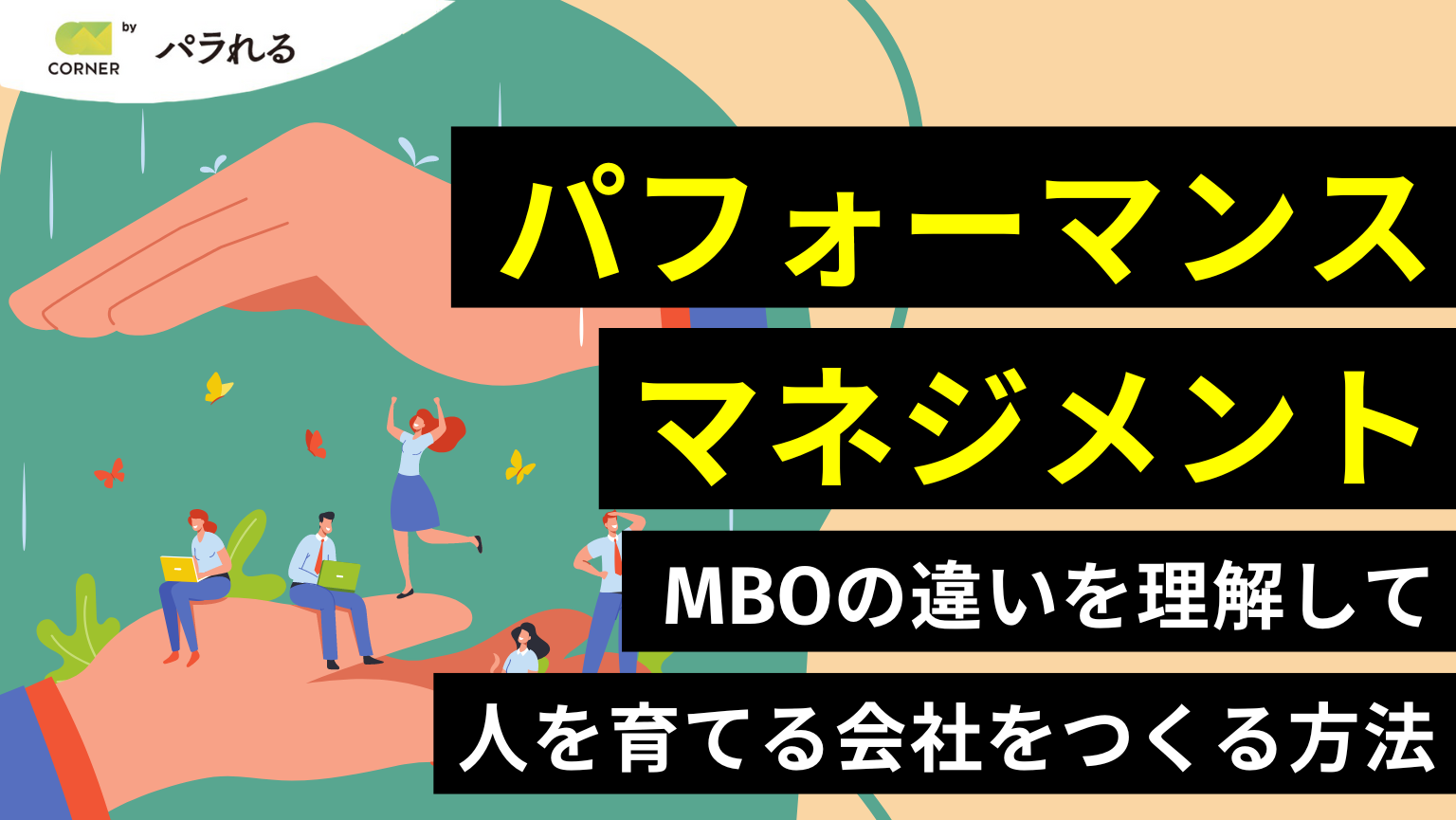
マネジメント手法の1つである「パフォーマンスマネジメント」。まだ聞き馴染みがなかったり、その定義をはっきりと理解していなかったりする方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、大手企業・スタートアップ企業双方でのご就業経験があり、「パフォーマンスマネジメント」の導入実績も豊富な北村豊さんに、その定義や事例についてお話を伺いました。
<プロフィール>
北村 豊(きたむら ゆたか)/わくわく人事WorkBe 組織成長デザイナー
滋賀大学大学院にて心理学修了後、NECグループにて20年就業。その後HRTechスタートアップ企業のCMOや組織コンサルファームでの経験を経て起業し、現在に至る。顧客企業の『第2人事部』として人材戦略策定および伴走サービスを展開。『人事の夢が形になれば会社はもっと良くなる』が信条。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「パフォーマンスマネジメント」とは
──まず、「パフォーマンスマネジメント」の概念や定義について教えてください。
「パフォーマンスマネジメント」とは、企業・個人の持続的成長を目的に、個人から最大のパフォーマンスを引き出すための一連の人材マネジメント手法を指します。従来の人事評価制度が『個人の成果に対する評価』を重視するのに対し、「パフォーマンスマネジメント」は『個人の能力やモチベーションを引き出し成長すること』、それが企業の成長に繋がるという点を重視するという違いがあります。
ちなみに、アメリカのゲーリー・M.コーキンスは著書『パフォーマンスマネジメント(2007・東洋経済新報社出版)』で「パフォーマンスマネジメントとは、マネジャーとメンバーが連動し、メンバーが事業主であるかのように振る舞える職場環境を作ることである」と述べています。
なお、「パフォーマンスマネジメント」には方法論まで特定された独自システムがあるわけではありません。そのため、存在する人材マネジメント手法(OKR、ノーレイティング、1on1など)を組み合わせて『自社に最適な形』を特定しながら統合的に構築する必要があります。
つまり、ノーレイティングなどを部分的・手段的に導入したり、「パフォーマンスマネジメント」の事例としてよく取り上げられるスターバックス社の人材マネジメント手法をそのまま転用したりしても、必ずしも機能しません。自社の特徴や事業環境に基づき、個の成長を引き出すための最適化されたプロセスを組み立てることで、「パフォーマンスマネジメント」は初めて機能します。
▶「ノーレイティング」で実績を上げている企業、フィードフォース社のインタビュー記事はこちら
評価・目標管理制度が多様化してきた歴史と背景
──評価制度はこれまでもさまざまなものが各企業で導入されてきました。それぞれどのようなものが、どんな目的で導入されてきたのでしょうか?
日本においてはさまざまな評価・目標管理制度があるわけではなく、おおむね目標管理(MBO)の派生形であると考えています。労政時報(人事部門の実務対応や課題解決をサポートする会員制のデータベースサービス)によると、多くの企業がMBO(Management by Objectivesの略。個人もしくはグループごとに設定した目標の達成度を個人で管理する方法のこと。)を導入していたようです。
MBOは、マネジメントの生みの親と言われるP.F.ドラッカー氏が著書『現代の経営(1954年)』で提唱した人材マネジメント手法です。本来は評価手法ではありませんでしたが、日本では1990年代に評価手法としての導入が急速に進みました。その背景には、1990年代のバブル崩壊後の横並びの昇格・賃金制度に対する問題意識があります。その対策として年功序列型から成果・実力主義へ転換するにあたり、MBOの概念が扱いやすかったのでしょう。
しかし、2000年代に入ると『内側から見た富士通「成果主義」の崩壊(城繁幸著・2004・光文社)』の発売にも表れるように、MBOの問題が顕在化してきました。行き過ぎた成果主義が日本本来の強みや文化を損なうきっかけになったとして、多くの企業がMBOの改善に乗り出したのです。
その結果、社員の納得度を高める評価制度の追求がトレンドとなり、プロセス重視・育成面重視・精緻な等級制度など、カラーが異なる各社各様のMBO派生形が多く生まれました。一方で、運用が難解になるなど評価制度の改悪につながったケースも残念ながら少なくないようです。
2010年代になると、今までのMBOの改善という流れではなく、人材マネジメントのあり方から根本的に考え直す取り組みが出始めました。GEやGoogleなど先進的グローバル企業を中心に、ノーレイティングやOKRなどの従来のMBOを文脈としない考え方が出てきたことにもそれは表れていると思います。そこに影響を受ける形で日本企業も『人材マネジメントの在り方から根本的に考える』兆しが見えてはきましたが、足元ではまだまだ大半の企業がMBOをベースとした派生形で留まっている印象です。
▶MBOがマッチする組織についての記事はこちら
▶OKRの導入・運用についての記事はこちら
「パフォーマンスマネジメント」がもたらす組織メリット
──「パフォーマンスマネジメント」を導入すると、組織にどんなポジティブな影響がありますか。
今までのMBOをベースとした評価制度が『他者比較/過去』であるのに対し、「パフォーマンスマネジメント」導入によって『個の成長/未来』を主眼に置くことができるようになる点が、最大のメリットです。従来の『他者比較/過去』に基づく評価では、公平性や処遇の透明性は担保できても、モチベーション・エンゲージメントなどの観点ではどうしても限界があります。例えば、成果を出せてないという自己認知のある人がその評価の低さを妥当だと感じていたとしても、エンゲージメントやロイヤリティにはつながりません。
2016年時点、アメリカでは従業員レイティングを廃止する企業がフォーチュン500(※)の20%にまで増えており、社員の人間性尊重・能力開発が今のアメリカにおける人材マネジメントの潮流となっています。日本もこれまでの大量採用時代と安定したビジネス環境が続いていれば「パフォーマンスマネジメント」もここまで注目されなかったはずです。
しかし、これからのVUCA環境や少子高齢化の環境下では、個人が成長できる企業でなければ企業としての魅力を失って淘汰されていく可能性は大いにあると感じます。
(※)フォーチュン500とは、アメリカ合衆国のフォーチュン誌が年1回編集・発行するリストの1つ。全米上位500社がその総収入に基づきランキングされる。
『成果を出した人に報いる会社か、成果を出せる人を育てる会社か』
従業員に選ばれる会社になるためにも、一度全体を俯瞰した上で人材マネジメントの在り方を考えてみることをオススメします。

従来のMBO(目標管理制度)との違い

──MBO(目標管理制度)と「パフォーマンスマネジメント」の違いについて先ほど言及がありましたが、より具体的にその違いを教えてください。
MBOと「パフォーマンスマネジメント」の違いは、その目的の違いに尽きます。
■MBOの目的:一定期間の成果を評価する
■パフォーマンスマネジメントの目的:個の成長を支援することで企業成長を実現する
上記に最適化したプロセスを構築すると、結果的に両者の違いが浮き彫りになってきます。その観点でそれぞれの違いを整理してみましょう。
| MBO | パフォーマンスマネジメント | |
| サイクル | 一定期間の評価期間が必要なため半年・1年サイクルの運用となり、半年・1年前に立てた目標が形骸化しやすい。 | フォローはリアルタイム性が必要なため、上司部下の面談が高頻度になる。 |
| 主旨 | 過去について良し悪しを伝えることがメイン。モチベーションやエンゲージメントにはつながりにくい。 | 未来について建設的な対話を行うことがメイン。モチベーションやエンゲージメントにつながりやすい。 |
| コミュニケーションスタイル | ティーチング・フィードバック中心 | 積極的傾聴・フィードフォワード中心
上司は部下の長所・短所を具体的に把握でき、部下は自己理解が深まる(役割・課題・ビジョンなど)ことで主体性が高まる |
| 個人と企業の関係性 | 適正な評価≠個人の成長≠企業の成長 | 個人の成長支援=個人の成長=企業の成長 |
ちなみに、アメリカ人事コンサルティング会社のNeuro Leadership Instituteの調査によると、「パフォーマンスマネジメント」に2年以上取り組んでいる企業の多くが『上司・部下の対話の質・量向上やエンゲージメント改善が見られており投資価値あり』と回答しています。このことからも、個人の成長支援を行うことで企業成長を目指す「パフォーマンスマネジメント」の概念が、今の時代にもフィットしていると言えるでしょう。
「パフォーマンスマネジメント」の導入事例
──北村さんが関与した「パフォーマンスマネジメント」の導入事例について教えてください。
私はこれまで4社での導入に携わりました。情報通信業や製造業など、いずれも組織化の壁(採用・退職を繰り返し、組織拡大できない)に問題意識を持つ企業です。
導入内容としては、評価制度を全面刷新するのではなく『目標設定→月次1on1による成長支援→4半期評価』といった枠組みを構築するようにしました。その理由は、人材マネジメントにかかる労力増大を避けるためです。活かせるところは活かしつつも整合を取りスリム化することで、部下の成長支援向上にフォーカスできる体制へと変えていきました。
上記の経験から感じるのは、『上司がこまめに部下の成長支援を行えるか(かつ続けられるか)』が導入の成否を分ける一番の要因だということです。これを実現するためには以下3点が重要だと考えています。
(1)会社としての自社理解
(2)上司の役割のアップデート
(3)効果測定
(1)会社としての自社理解
『どうありたいか?それは本当にやりたいことか?それでなぜ事業として成り立つのか?』など、シンプルな問いは意外と具体的に答えられないものです。しかし、パーパスやMVV(Mission、Vision、Valueの略語。日本語では使命、理念、行動指針と訳される。)、クレドなどの会社としてのアイデンティティの解像度を高め、こうした本質的な質問に答えられなければ、「パフォーマンスマネジメント」を導入しても意味がありません。
なぜなら、目指す姿が曖昧かつ魅力がない状態では、従業員の成長支援はできないからです。理想的には1人1人が自分の言葉でクリアに語れる状態になれるようにする努力が必要です。
(2)上司の役割のアップデート
MBOでは評価者でしたが、「パフォーマンスマネジメント」では部下の成長を支援することが上司の役割になります。その役割の変化を会社がサポートできないと、結局は絵に描いた餅になってしまいかねません。上司の意識改革、コーチングスキルの継続的向上、面談実施の継続性確保など、運用やサポート体制が伴ってこそ「パフォーマンスマネジメント」は機能します。
そのために、まずは上司と部下の対話を適切に機能させることが重要なので、役割認識の浸透と対話力の向上をサポートする必要があります。役割認識の浸透は研修などを通して、MBOの目的や意義、方法を具体的に共有し、グループワークなどを通して、腹落ちさせると良いと思います。対話力の向上はなかなか研修のみでは劇的に向上することが難しいので、研修と対話センシング・ロールプレイなどを組み合わせて活用したトレーニングを導入する企業が最近多いように感じます。
(3)効果測定
繰り返しになりますが「パフォーマンスマネジメント」導入には大きな労力がかかります。その労力以上の効果を周囲に示すことができなければ、なかなか持続しません。効果測定の方法としては、会話の質を可視化する対話センシング技術の導入、360度サーベイによる行動評価、パルスサーベイなど、数ある選択肢の中からニーズにあった方式で実現していけば良いでしょう。
▶エンゲージメント向上にパルスサーベイを活用する方法についての記事はこちら
編集後記
時代は変わり続けているのに、社内の制度はずっと変わらないままということはままあります。ただ、そこで焦ってすべてを刷新しようとするのではなく、現状やありたい組織像を理解した上で『活かせるところは活かす・変えるところは変える』という姿勢が大事なのだと、北村さんの話からも感じました。『成果を出せる人を育てる会社』になるためにも、「パフォーマンスマネジメント」の概念を理解した上で評価制度を見直してみてはいかがでしょうか。






