「キャリアアンカー」を組織運営に活かす方法
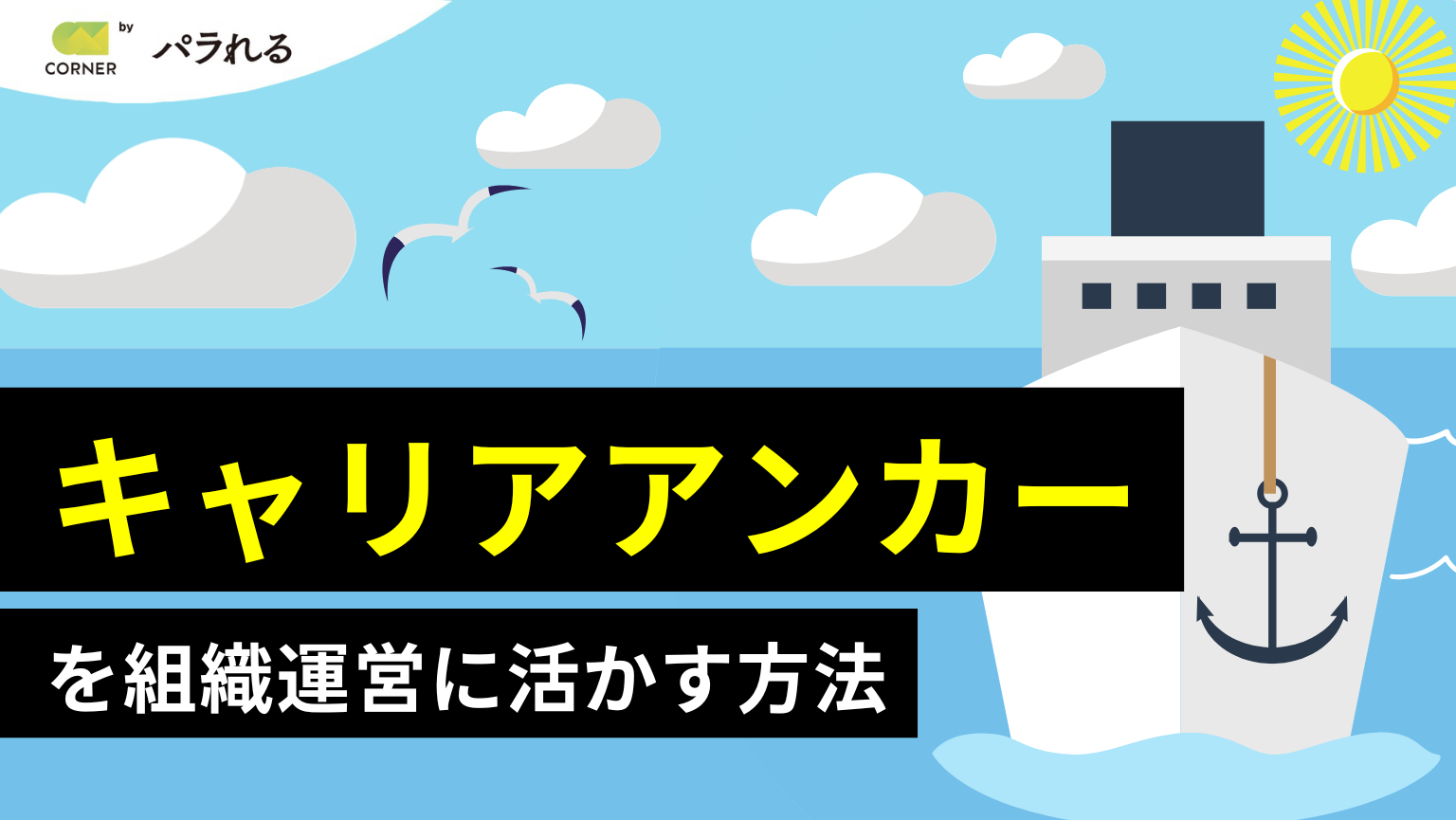
生涯に渡り自身の働き方の軸となる「キャリアアンカー」。近年一人一人のキャリア自律が重視されるようになり、その中で自分自身の「キャリアアンカー」は何なのかを個人でも探索されている方が増えており、社員の「キャリアアンカー」を支援すると同時に経営に活かす方法を探している会社もあるのではないでしょうか。
今回は、日立グループの人材育成部門で活躍し、独立後も広く能力開発に従事している株式会社THdesign 代表取締役の三森 朋宏さんに、「キャリアアンカー」の概要から企業の取り組み事例に至るまでお話を伺いました。
<プロフィール>
三森 朋宏(みつもり ともひろ)/株式会社THdesign 代表取締役
日立グループのIT系事業にてSEやプロジェクトマネジメントを経験した後、システム営業として10年間で200社以上のシステム導入に携わり、日立グループの人材育成部門に異動。EQの専門性を活かし新人からリーダー層まで幅広い層の能力開発に従事。その後、独立して一般社団法人感情活用研究会にて理事、一般社団法人日本SEL推進協会にて理事を務めながら、非認知能力であるEQやSELの普及発展に務めている。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「キャリアアンカー」とは
──「キャリアアンカー」の概要について教えてください。
「キャリアアンカー」は、一言で言うなら『どんなに難しい選択を迫られたときでも手放すことのない拠り所としての自己概念』です。そこには、自分が認識している能力・動機・価値観が複合的に組み合わさっています。
アンカーは英語で錨(いかり)という意味であり、自身の舟(キャリア)が潮目で流されてしまうことを防ぐ目的であることが語源になっています。エドガー・H・シャイン博士(マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院)による著書『キャリア・アンカー』の和訳を金井壽宏先生(神戸大学名誉教授)が出版したことをきっかけに、日本でも広く知られるようになりました。
「キャリアアンカー」は一定の実務経験とフィードバックによって発達していくものであり、自分自身で明確にしていくものでもあります。自分なりのアンカーを知っていれば、報酬や肩書きといった外部要因に惑わされることなく就職やその後のキャリアを“自分らしく”選択することができるようになります。
自身の「キャリアアンカー」は、先ほどご紹介したエドガー博士の著書内でも掲載されている『自己診断用キャリア指向質問票』により確認できます。40問の質問に対し、以下図の様に『全然そう思わない』から『いつもそう思う』までの6段階で回答し、集計表を用いて集計する形です。企業の研修などでも多くこの『自己診断用キャリア指向質問票』が用いられています。

▶三森さん作成の「キャリアアンカー」チェックシートのダウンロードはこちら
上記のサンプルイラストの様に、各設問毎にカテゴリごとに点数が反映されるようなエクセルを作ると集計が容易になります。カテゴリ欄に記載されているアルファベットは、「キャリアアンカー」の分類を略称で示しており、カテゴリー毎の点数の比較などもできるようにしています(※それぞれのカテゴリーの名称や内容については次章で解説)。こういったシートの作成はそれほど難しいものではないので、上記リンクからダウンロードするか、質問票を基にご自身で作成されてもいいかもしれないですね。
「キャリアアンカー」の8つの分類
──「キャリアアンカー」は人それぞれ違うものだと思うのですが、そこに傾向やタイプなどはあるのでしょうか。
「キャリアアンカー」には8つの分類があり、すべての人がいずれかの分類に該当します。先ほど紹介した『自己診断用キャリア指向質問票』を活用すると自身がどの分類に該当するかを知ることができます。
(1)専門・職能別(Technical/Functional Competence, TF)
仕事の種類を問わず、専門家(エキスパート)として自分の才能を発揮することに満足感を覚えます。自分の専門分野が追求できる場合に限ればマネジャーになる気持ちがないわけではなりません。自身の能力・技能を試すことができる仕事に向いています。
(2)全般管理(General Managerial Competence, GM)
ゼネラル・マネジャー(部門長)など経営管理そのものに関心を持ち、組織の中で責任ある地位につきたい、自分の努力によって組織の成果を左右してみたいという願望を持っています。重い責任を望み、挑戦的で変化に富み、リーダーシップを発揮しメンバーをまとめるような統合的な仕事を好みます。
(3)自律・独立(Autonomy/Independence, AU)
規則や手順、作業時間、服装規程など規範に束縛されることを嫌います。自分のやり方、自分の納得する仕事が基準にあり、自律的な専門職に向かっていきます。自身の専門分野の範囲内で明確に線を引き、時間を区切って仕事をすることを好みます。
(4)保障・安定(Security/Stability, SE)
安全で確実と感じられ、将来が予測でき、特に金銭的な保障が優先課題となります。終身雇用、退職後の諸制度が整い、安定している組織を探します。職務の充実や職務上の挑戦などの内発的な動機づけよりも、給与や労働条件・福利厚生などの外的環境にこだわります。
(5)起業家的創造性(Entrepreneurial Creativity, EC)
新商品・サービスを開発したり、財務上の工夫で新しい組織をつくったりと、常に新しい事業を起こしたいと考えています。自律・独立のアンカーと違いは、『自分で新しく事業を起こしたい』と熱望している点です。創造することを強く望みますが、一方で飽きっぽい傾向があります。
(6)奉仕・社会貢献(Service/Dedication to a Cause, SV)
自分の価値観によって方向づけられ、世の中をもっとよくしたいという欲求によってキャリアを選択します。例えば、ダイバーシティ施策に打ち込む人事の専門家のように、大義のために身を奉じる方です。自分の所属している組織、あるいは社会における政策に対し、自分の価値観と合う方向で影響を与えることが可能な仕事を望みます。
(7)純粋な挑戦(Pure Challenge, CH)
不可能と思えるような障害の克服、解決不能と思われている問題の解決、極めて手強い相手に勝つことを『成功』と考え、より困難な挑戦を求めます。仕事分野・所属組織・給与や昇進は二の次で、自分を絶えず試す機会がある仕事を求めます。
(8)生活様式(Lifestyle, LS)
プライベートと仕事をバランスしたいという単純なことだけでなく、個人・家族・キャリアのニーズを統合させ、人生におけるクオリティ・オブ・ライフを追求したいと考えています。労働時間が自由に調整できるフレキシブル勤務や、リモートワークと出社の併用、コワーキングスペースの利用など、働く時間や場所が自由に調整できる働き方を求めます。

「キャリアアンカー」を組織内で活用する方法
──組織に「キャリアアンカー」を導入し活用するためには、どのような方法があるのでしょうか。
エドガー博士曰く、『10年以上の実務経験とフィードバックによって能力・動機・価値観といった自己概念が発達する』と述べています。これを日本企業で働く一般的なビジネスパーソンに当てはめると、大卒の新卒入社者であれば30代前半〜半ばの方が該当します。この年代の方々は、1人で一通りの業務を遂行することができることはもちろん、社内の人間関係も広く理解できている頃合いです。だからこそ、キャリアに対して悩みがちな時期でもあったりします。社内におけるキャリアだけでなく、転職も含めて考える方も多く、積極的な方であれば転職エージェントに登録してキャリアコンサルタントに相談する方もいるでしょう。
一方、会社側はこの世代を戦力の中心として捉えていることも多く、自社内の業務においてモチベーション高く能力を発揮してもらえることを期待しています。それぞれの状況を踏まえ、うまく双方を結び付けていくために活用できるのが「キャリアアンカー」です。研修などを通じて社員の「キャリアアンカー」を明確にし、それを自社のキャリアと結び付けていくことで将来的なキャリアイメージを描くサポートを行います。
また、社員のニーズを踏まえた適正な配置を検討する重要な要素とすることも可能です。これらにより社員が十分に能力を発揮できるようになるだけでなく、優秀な人材が離職してしまうことを防ぐ効果もあります。
さらに、近年課題となっているシニア層のリスキリングやリカレントを含めたキャリア問題に対しても「キャリアアンカー」の概念は有効です。できるだけ早い段階でシニア層の「キャリアアンカー」を確認した上で、適正な配置や再雇用先などを決めることができれば、人材の流動性と活用度の向上が期待できます。
「キャリアアンカー」を活用し意識改革に成功した事例
──三森さんご自身が経験した「キャリアアンカー」の活用事例について教えてください。
とある大手製造業企業からご相談をいただいた事例をご紹介します。
その企業のある事業部では、コロナ禍の在宅勤務増加に伴い日常のコミュニケーションが減ってしまったことなどから、社員のキャリアに対する考えや方向性をキャッチアップすることが難しくなってしまったり、中堅層の離職が増えてしまったり、シニア層のモチベーション維持やリスキリングに課題を感じられていた状況でした。
そこで社員の方々に研修を実施し、参加者全員にご自身の「キャリアアンカー」を、前述の8つの分類を説明したり表を用いて確認してもらい、自己認知をしてもらうところから始めました。そして、在宅勤務が増えたことによって仕事と生活の距離が近くなったことや、世代に関係なく一人ひとりが自分のキャリアについて考えて自己形成していくこと、特にシニア層においては自発的なキャリア形成が求められることを学んでいただきました。
研修実施のあとには、社員の方々にはご自身の「キャリアアンカー」をもって上司や人事担当者と面談を行い、今後のキャリアについて共有を図り、上司と人事担当者は「キャリアアンカー」をもとに一人ひとりに最適なキャリア支援を行うようにしました。
まさにコロナ禍における施策であったことから、この施策は進行中。はっきりとした効果が確認できるまでになるのはもう少し先になると思いますが、現時点にて既に離職のリスク低減やシニア層のキャリアに対する自発性の向上は表れはじめており、一方の労働生産性もコロナ禍においても維持できているようです。
他にも、20代後半~30代にかけて「キャリアアンカー」を取り入れたキャリア研修を行うことで育成と適正配置を実現できた組織もあります。
これらの事例に共通して言えるのは、従来の日本企業のように全社員が昇進・昇給を目指して優劣を競い合うのではなく、社員それぞれの「キャリアアンカー」を明確にした上で人事担当者と共有することでよりマッチしたキャリアパスの提示ができるようなったということです。このような施策により、メンタルヘルス障害の発生も無くなり、結果的に会社に対するエンゲージメントも向上させることができました。
編集後記
多様な人材が活躍する組織を志向する上で、個人の価値観や「キャリアアンカー」を組織側が正しく理解することは欠かせないことなのだと三森さんのお話を聞いて再認識しました。この「キャリアアンカー」の概念を拠り所として個人の才能や能力を最大限に引き出せる方法を考えることができれば、人事としても迷わずに各取り組みを推進できるようになるのではないでしょうか。






