「エクスターンシップ」を理解し、効果を高める上で必要な考え方とは
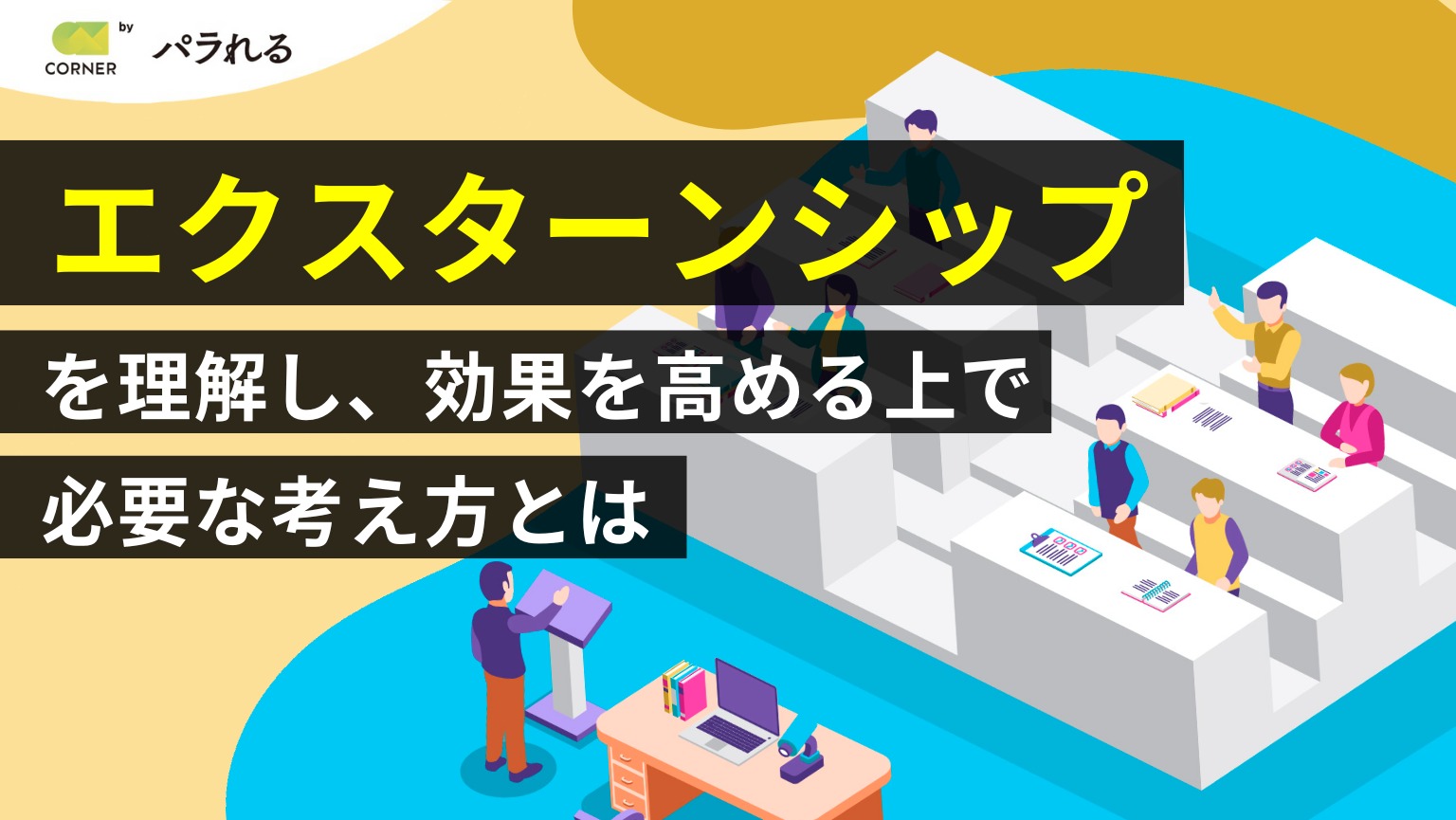
キャリア教育観点の超短期施策として取り入れられる「エクスターンシップ」。しかし、インターンシップとの明確な違いや活用方法などについては曖昧な方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、これまで数多くのインターンシップ設計・立案・実行に携わってきた経験を持つ人事パラレルワーカーの方に、「エクスターンシップ」とインターンシップの違いや活用事例についてお聞きしました。
➡️「エクスターンシップ」についてやこのパラレルワーカーへのご相談につきましてはこちらからお問い合わせください。
→ お問い合わせ
目次
「エクスターンシップ」とは
──「エクスターンシップ」について、インターンシップとの違いも含めて教えてください。
「エクスターンシップ」とは、大学低学年層を対象にキャリア教育を目的として行われる『短期就業プログラム』のことです。インターンシップとの違いは以下の点にあります。
| エクスターンシップ | インターンシップ | |
| (1)実施主体 | 大学や教育機関 | 企業 |
| (2)参加対象 | 大学低学年 | 大学高学年(就活層) |
| (3)参加効果 | 大学の単位や資格獲得に有利に働く | 就職活動に有利に働く |
| (4)目的 | キャリア教育、キャリア学習 | 採用活動の一環、企業PR活動 |
| (5)主な内容 | 最短1日~2、3週間の短期で仕事・職場を体験、見学する | 中長期で業務を経験し、必要な業務スキルを習得する |
2000年以降、日本ではインターンシップが先んじて活発に行われるようになりました。その多くの実施目的は『学生への就業理解』だと表向きには言われていますが、実際は『採用学生の見極め効率化』が主目的となっている場合があります。
その要因の1つとなっているのが『大手就職サイトが誕生して応募数が急激に増加した』ことです。面接は基本的に少数対少数で行われるため、その工数が増大。さらに『面接対策情報』がネットを通じて広がりを見せたことも手伝って、学生を本質的に見極めることの難易度が急激に高まりました。こうした課題を解消するために加速度的に広がったのがインターンシップというわけです。
一方、「エクスターンシップ」もキャリア教育を目的として大学の長期休暇期間を中心に実施されてきましたが、インターンシップほど市場で有名にはなりませんでした。「エクスターンシップ」という言葉自体に聞き馴染みがない方が多いのもそのためです。しかし、近年では優秀な人材の獲得難易度が上がり、学生との接点をなるべく早いタイミングで行いたいという企業側のニーズが高まったことを受け、エクスターンシップに対する注目度が年々増してきています。
企業と連携して学生のキャリア教育を実施できる点で、大学側にも多くのメリットがあります。そのため、企業・大学双方のニーズを満たすエクスターンシップは今後さらに社会に浸透されていくはずです。中長期的にはインターンシップとの境目も無くなっていくことでしょう。
「エクスターンシップ」の企業メリット
──「エクスターンシップ」による企業および人事のメリットにはどのようなものがあるでしょうか。注意するべき点などもあれば合わせて教えてください。
エクスターンシップ最大のメリットは、『早期に人材との接点を持てること』です。
学生が就職活動をスタートすると、一斉に複数の企業からアプローチを受けます。それが短期間で行われるため、いかに熾烈な採用競争となるかは言わずもがなです。しかし、「エクスターンシップ」であれば学生がそうしたアプローチを受ける前から接点を持つことができるため、より自社の魅力を伝えやすくなります。
また、学生のキャリア教育に寄与できる点はもちろんですが、企業の『ブランディング』という観点でも一定の効果が見込めます。2000年前半には珍しかったインターンシップも、昨今では実施していない企業の方が珍しい状況となりました。ですが、「エクスターンシップ」はまだ参画企業が少なく、『大学と連携をしている』『キャリア支援に関わっている』といった理由とも相まって、SNS上などで注目・拡散されるチャンスがあります。
ただ、『良い情報よりも悪い情報の方が広がりやすい』点には注意が必要です。そのため、話題性を優先して単に実施するのではなく、やるからにはクオリティに拘る必要があることを念頭に置いておきましょう。特に、自社の採用成功だけを目的に置いてしまうと学生にとって良い時間となりづらいものです。あくまで学生のキャリア教育の一助となるよう、参加者の視点を持って内容をつくり込むこと──それが結果的に採用につながる可能性もあるくらいに捉えるのがちょうど良いかもしれません。

「エクスターンシップ」がより効果的に働くケース

──「エクスターンシップ」とインターンシップを比較した際、それぞれに向いているケース、向いていないケースがあるかと思います。企業はどんな観点から使い分けを検討するべきでしょうか?
「エクスターンシップ」とインターンシップのどちらが適しているかを検討する上でポイントになるのは、『人材獲得への時間軸』です。
まず、インターンシップは就活層向けの中長期的な取り組みです。学生も就職活動の一環として参加するため、採用につながる確率は自然と高くなります。ただ、競合他社との熾烈な争いとなることは現状避けられず、どのような形で自社魅力を訴求して学生を惹きつけるかといった内容の工夫なしには効果を得られることはできません。
一方、「エクスターンシップ」は学生の中でいえば低学年向けに行われる短期的な取り組みです。そのため参加目的もさまざまで、ゆくゆくの就職企業の検討に活かしたい層ももちろんいますが、基本的には授業の一環として参加を検討する学生がメインのため、採用につながる確率もインターンシップに比べて低くなりやすい傾向があります。
ただし、この長期的な接点が必ずしも採用に繋がりにくいかといえばそうではありません。リクルートの就職白書2022(就職みらい研究所)によると、内定者の中にインターンシップ参加者がいたと回答した企業は80%を超えているというデータもあります。これは採用における『初恋効果』とも言われている現象で、いかに最初の接点が重要かを示唆しています。
エクスターンシップ実施企業がまだまだ少ないことを考えると、長期的に学生と接点を持っておくことがいかに効果的かご理解いただけるはずです。もし大学2年生を対象に「エクスターンシップ」を実施したとすると、インターンシップとは優に1年以上の差があることになります。
こうした効果が広く認知されていくと、インターンシップとの境目は徐々に無くなり、エクスターンシップでの接点から入社につながるケースはより増えてくると考えています。長期的な視点で学生との接点形成にコミットできる企業は、時間こそ掛かりますが結果的には優秀な人材の採用を実現できるようになるはずです。短期的な取り組みだけに縛られず、いかに長期的な取り組みを継続できるかが、今後の採用市場を勝ち抜くキーポイントであることは間違いないでしょう。
「エクスターンシップ」の導入実例
──これまでご経験された「エクスターンシップ」に関する事例を具体的に教えてください。
以前、関東・関西の有名私立大学にて、企業と連携した『低学年向けのキャリア教育プログラム』を実施しました。当時はまだ「エクスターンシップ」という呼び方はしておらず、周囲に実施していた大学や企業もそうなかったと認識しています。
当時の大学側の要望は、『学生に対して、卒業後の自律的なキャリアを歩むためのスキルや、スタンスなどを伝えてほしい』というものでした。自社のメリット(≒採用・ブランディング)だけを考えれば、1社だけで「エクスターンシップ」を行うのが自然な選択です。しかし、学生側のメリットを考えると、1社だけでなく複数企業と接点を持てた方がより多様な学びの機会を得ることができます。そこで前述した通り『学生側のメリット』を優先させ、自社以外にも複数企業に参画いただくことにしたのです。
内容としては、夏休みの5日間を利用して以下のようなプログラムを開催しました。
1日目
5日間のプログラム説明&目的設定(自社が担当)
2〜4日目
ビジネスの中で向き合う課題に対して自由に調査→議論→社員に向けてプレゼンする形のワークショップを実施(各社が担当)
5日目
プログラム全体を通じた振り返りの実施(自社が担当)
この5日間のプログラムを通じて、学生は仕事をする上で必要なスキル・スタンスを実際に活躍しているビジネスパーソンとの対話の中から学びとり、企業は自社が扱う商材やマーケット・課題間をワークショップの中で伝えて自社に対する興味・関心を高めることに成功しました。なお、採用実績に関しても私が所属していた企業だけでなく、参画した他企業でも入社者を生み出すことができました。
これ以降、夏休みの定番プログラムとして継続的に導入されており、協賛企業も年々増加。さらには形式を変えて他大学でも転用するまでに拡大しました。実際に参画した企業の人事からは、『就活時に優秀な人材の獲得競争を行うよりも、大学と連携して優秀な人材の育成・共創を行うことに価値がある』との声もいただいております。
編集後記
優秀人材の採用に大きな効果をもたらす「エクスターンシップ」。しかし、採用目的ばかりが先行してしまうと視点が短期的なものになってしまい、効果を最大化させることはできません。学生へのキャリア教育、社会貢献の視点も併せ持ち、長期的なAll Happyを目指して内容を検討・実施することが「エクスターンシップ」の本質なのだと、今回のお話を受けて理解することができました。






