「エンゲージメントツール」の効果的な運用方法とは

『従業員のエンゲージメントを高めたい』と考えている人事担当者は多いはず。しかし実際にツールを導入しても思うように活用できず、期待した結果が得られないことも少なくないと聞きます。
今回は、事業会社・コンサルの両面から人事に関わった豊富な経験を持つエス・エー・エス株式会社 HRコンサルティング部 部長の五十嵐 祐幸さんに、「エンゲージメントツール」の概要からその運用方法に至るまでお話を伺いました。
<プロフィール>
五十嵐 祐幸(いがらし ゆうこう)/エス・エー・エス株式会社 HRコンサルティング部 部長
ハウスメーカーにて営業として勤務したのち、人事の世界にキャリアチェンジ。組織人事のコンサルティングファームで人事制度設計・運用支援、人材開発を専門領域としてコンサルティングを実施。その後、事業会社の人事を複数社経験。本間ゴルフや串カツ田中ホールディングスでは人事責任者を歴任し、それぞれ人事組織の立上げから携わった。「人の心に火をつける」を信条に、現在はエス・エー・エスにてHRコンサルティング事業を立ち上げその責任者を担う。特に、中小企業の組織課題・人事課題に対して伴走型のコンサルティングサービスを提供。「組織コンサルの会」所属。プロティアンキャリア協会認定ファシリテーター。国家資格キャリアコンサルタント。▶このパラレルワーカーへのご相談はこちら
目次
「エンゲージメントツール」とは
──「エンゲージメントツール」の概要について、一般的な導入目的・背景なども含めて教えてください。
「エンゲージメントツール」とは、組織と従業員、または従業員同士の関係性を支えることを目的としたツール・サービスのことで、状態分析やコミュニケーション促進などが行えるツールのことを指します。エンゲージメントは従業員と組織の心的つながりを表す言葉であり、『従業員が自ら組織に貢献する意図を持って業務に取り組んでいる状態』をエンゲージメントが高いと表現します。このエンゲージメントを高めると、従業員のパフォーマンス向上や退職による人材流出抑制などの効果が期待できます。
この「エンゲージメントツール」を使って行うエンゲージメントサーベイは、主にエンゲージメントの高低を把握するために実施するものです。組織と個人の関係性(会社の方針への共感や上長や同僚との関係性など)に関する質問が多く、実施頻度は半年〜1年に1度くらいで実施します。一方、エンゲージメントサーベイに似たパルスサーベイは、主に本人の状態を把握するために実施するものです。本人の体調面や仕事への取組み意欲などの質問が多く、毎週あるいは毎月などの高頻度で実施します。
ただ、このように明確に分けられていない場合もあり、エンゲージメントサーベイを毎月実施する中で社員本人の体調に関する質問が含まれるような、パルスサーベイの要素を含むケースもあります。いずれのサーベイにおいても大切なのは、『どういう状態が望ましいか・それに対して何が知りたいか・どう対応するか』を明確にすることです。
この「エンゲージメントツール」の一般的な導入目的には、大きく以下2つがあります。
(1)従業員が仕事や会社にどれほど愛着を持ち、働きがいを感じているかを分析する
(2)分析結果から問題点を見つけ、改善を通じて従業員のエンゲージメントを高める
この「エンゲージメントツール」の導入背景には、各企業がエンゲージメントの重要性を強く認識していながらもその測定・向上(改善)・活用方法について具体的な手法や解を持っていないことがあると考えています。当然ながら、エンゲージメントを測定して結果を抽出するだけでは意味はありません。そこで得た結果を読み解き、どう活用するかが何より重要であり、人事部が注力するべきポイントでもあります。測定・結果出しだけで労力を使い果たしてしまった──などの本末転倒な状況もよくあることから、それを容易にする「エンゲージメントツール」が多く開発・導入されている背景があります。
ニューノーマルが変えた「エンゲージメントツール」の重要性
──ニューノーマル(新しい日常)という言葉も生まれたように、コロナ禍を経て就業環境は大きく変化しました。「エンゲージメントツール」もこの変化を受けて何か影響はあったのでしょうか。
コロナ禍を経て、企業はこれまで以上に多様な働き方を容認するようになってきました。出社を前提としない働き方(本社は東京にあるにも関わらず、住居を北海道や沖縄に構えるなど)などが代表例です。こうした新しい働き方や選択肢を企業の特徴として打ち出して優秀な人材を受け入れようという動きは、採用競争の激しいIT企業などで特に多く見られます。
一方、こうした新しい働き方を実践している従業員が常にエンゲージメントの高い状況で働けているかは別問題です。働きやすい環境の提供はエンゲージメント向上にも寄与するものの、そのすべてを担うものではありません。エンゲージメントを構成する要素は他にもあり、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や会社の方向性への共感が別軸で存在します。前述したような働き方の場合、日々のコミュニケーションがオンラインでしかできないため、一緒の空間にいるからこそ感じられる『感覚的な変化』を把握できません。それらを把握するためにも「エンゲージメントツール」の必要性がより高まっているのだと考えています。
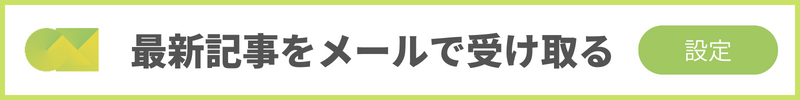
「エンゲージメントツール」運用時のよくある課題
──「エンゲージメントツール」を運用する中で陥りがちな問題や課題について教えてください。
「エンゲージメントツール」に限らない話ですが、何よりも重要なのは『運用』です。他社が導入しているから、ひとまず自社のエンゲージメントがどれほどのものか知りたいから、などの興味本位で導入を進めるケースも多くありますが、その大半は失敗しています。他の人事施策同様、ツールはあくまで手段。『何のために』『結果をどう活用するか』を導入前に検討しておかなければ、何の成果も得られません。
また、こうしたツールを入れることにより従業員は少なからず何かしらの変化を期待します。しかしながら、前述したように目的や活用方法を事前に定めないまま導入したことにより何も変化が生まれなければ、組織に対する信頼を大きく損ねることになります。これだけは絶対に避けなければなりません。ひとたび信頼を失えば、別の施策導入時にも『どうせまたやりっぱなしになるはずだ』と非協力的な従業員を生み出してしまうことになります。
なお、「エンゲージメントツール」ならではの課題には『リソース不足』があります。一部の大手企業を除き、導入企業の多くは「エンゲージメントツール」の運用に専属のスタッフを配属することはできません。よって兼務者が時間をつくって対応することになるわけですが、それにより生ものであるデータをすぐに分析・対応していくことができず、次のサーベイまでに何もアクションできていないことも往々にして起こりえます。スピード感のある「エンゲージメントツール」の活用を実現できる体制作りも重要なポイントのひとつです。
「エンゲージメントツール」運用課題への対処法

──先ほどご紹介いただいた課題への対処法について、五十嵐さんが経験された事例なども交えて教えてください。
導入前にその目的と活用・運用方法を具体化するためには、大きく以下2つの観点で検討を進めて行くと良いです。私が経験した事例と共にご紹介します。
(1)結果の公表方法
『誰に・どのタイミングで・どこまで結果を公表するか』を事前に設計しましょう。私が以前「エンゲージメントツール」導入・運用に関わった企業では、経営陣・管理職(部長と課長でも異なる)・従業員など、階層によっても伝達する内容やタイミングをそれぞれ設計していました。具体的には、
経営陣へは緊急を要するもの以外は経営会議を通じての報告とし、そこでは部署ごとの詳細や経過について共有していました。管理職へは全体の結果と自部署の結果のみを公表していました。
(2)記載ルールの設定・情報の取り扱い方法の周知
まず検討したいのは、『フリーコメントを記載できるツールであればそれをどう扱うか』ということです。エンゲージメントサーベイは一般的に匿名でコメントすることが多いものですが、私の場合は全従業員に記名式で実施してもらっていました。もちろん、記名により不利益を被ることは絶対にないとの確約をした上です。
また、誰が何を書いたかの情報は運営責任者である『私だけ』が閲覧できるようにしました。不利益を被ることはないと約束されたとしても、記載内容に誰までアクセスできるのかが不明瞭であれば不安は払しょくしきれないと考えたからです。一方、運営責任者以外も閲覧できるようにしたことはこれまでありません。なぜなら、記載内容(特にフリーコメント)の解釈は読み手によって受け取り方が大きく異なるためです。勝手な思い込みによって回答者の状態を決めつけてしまうことがないよう、運用責任者のみが閲覧できるルールとしています。
(3)結果・回答への対応方法
<個人>
フリーコメントで気になるコメントがあればオンライン面談を実施し、記載内容の事実確認と感じていること・考えていることを把握するように努めました。こうした個人の結果は、前回との比較が非常に重要です。結果が下降傾向なのか上昇傾向なのか、その上昇・下降の程度はどうかを常に把握できるように情報を加工していました。特に、大きく下降している場合は何らかの要因があるはずなので、その際はすぐに当該従業員に面談を申し込むようにしていました。
下降要因としてよくあるのが『環境の変化』です。異動や組織改変により人間関係を新たに構築しなければいけないケースや、今までの仕事の仕方が通用しなくなるケースなどが該当します。また、評価フィードバックで思ったような評価が得られなかった時にもエンゲージメントの低下(特に上司との関係性に関する項目)がよく見られます。上昇・下降の程度をどの程度のスパンで見るかについては、内容によっても異なります。時に数カ月ほど様子を見るものもありますが、良い状態から急激に悪い状態へ落ちたものについては早急に対応すべきです。もちろん、一時的な落ち込みである可能性もありますが、念には念を入れておいた方が良いでしょう。
<組織>
組織の結果をもって組織長と面談を行います。特に、下降傾向が見られる組織、あるいはフリーコメントにある不満が組織長に向いているものはピックアップして組織長に伝え、現状と事実確認を行います。内容が事実であり組織長に改善意欲がある場合は、『自分でやるか/私(人事)が介入した方が良いか』を判断してもらい、私が介入した方が良いと判断されればすぐさま該当メンバー全員と面談をします。ここで大事なのは、メンバー自身にもこの問題を自分ゴトとして捉えてもらうことです。組織長だけでなく、メンバー各自にも何ができるかを考えてもらうようにしています。
また、これらの活動は経営会議においても名前を伏せた状態で報告していきます。どのようなケースでエンゲージメントが下がっているのかを自社の事例を用いて話をすることにより、経営陣にも正しく現状を認識してもらい、改善・行動に移してもらうことを求めていきます。
こうして事例をご紹介するのは簡単ですが、これらを実際に実行するには相当な時間確保が必要です。そこまでやるのは腰が引けてしまうという方もいるかもしれませんが、エンゲージメントを向上させるとはそれだけの覚悟が必要なものだと思ってください。ツールを入れて終わりではなく、日々現場で起こっていることやそこから生まれる不安・不満にきちんと組織として向き合っていく──その結果、ようやく組織が従業員から信頼してもらえるのだと考えています。
編集後記
年々導入企業が増えている「エンゲージメントツール」。導入しやすいものも増えていることから、深く考える前に手段的に導入してしまう企業も少なくない印象です。導入検討時には改めてこの記事を読み返し、その目的と活用方法をイメージしてもらえればと思います。






